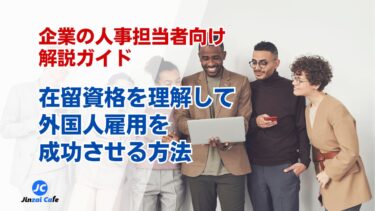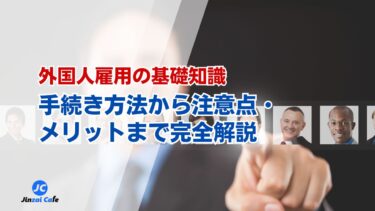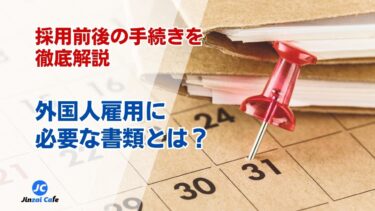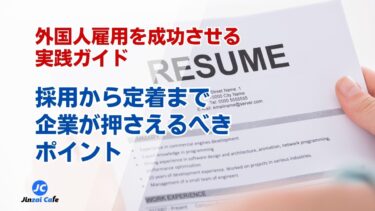「人手不足が深刻化する中、外国人材の採用を検討すべきか悩んでいる」「外国人労働者を雇用するメリットやデメリット、その理由を詳しく知りたい」。このような課題を抱える企業の人事担当者は少なくないでしょう。
厚生労働省の調査によると、2024年10月時点で日本国内の外国人労働者数は約230万人に達し、過去最高を記録しました。少子高齢化が進む日本において、外国人材の受け入れは人手不足解消の重要な手段として注目されています。しかし一方で、言語の壁や文化の違い、複雑な手続きなど、うまく対応しないと起こりうる様々な課題も存在するのが現状です。
本記事では、外国人労働者採用の4つのメリットと4つのデメリットを徹底解説し、受け入れる際の注意点から成功させるための具体的な方法まで、人事担当者が知らなければならない知識を網羅的にお伝えします。下記で紹介する内容は、外国人材の雇用を検討している企業様にとって、実践的で有益な情報となることでしょう。
外国人労働者採用の現状と背景

日本の労働市場では、構造的な人手不足が深刻な課題となっており、特に特定技能分野などでの人材需要の高まりが見られます。外国人材の受け入れが拡大している背景には、どのような要因があるのでしょうか。ここでは、現在の状況と政策の変化について詳しく見ていきましょう。
日本の人手不足の深刻化
日本の人手不足の深刻さは、各種調査からも明らかです。帝国データバンクが2025年1月に実施した調査によると、53.4%の企業が正社員不足であると感じています。また、日本商工会議所の2024年9月の調査では、人手が「不足している」と回答した企業の割合は63.0%に達しました。
実際に、多くの企業では求人募集をかけても応募が集まらず、既存従業員の負担増加や事業縮小を余儀なくされるケースが増えています。このような状況下で、外国人材の活用は企業存続のための重要な選択肢となっているのです。
参考:
帝国データバンク 人手不足に対する企業の動向調査(2025 年 1 月)
日本商工会議所 人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査
外国人労働者数の推移と動向
外国人労働者の数は年々増加の一途をたどっています。2019年には約166万人だった外国人労働者数は、コロナ禍の影響で一時的に減少したものの、2022年と比較しても大きく数字を伸ばし、2024年には230万人を超え、過去最高を記録しました。この数字は、日本の全労働者の約3.4%という割合に相当し、労働市場において無視できない存在となっています。
国籍別に見ると、ベトナム出身者が最も多く約57万人、次いで中国約41万人、フィリピン約24万人となっています。在留資格別では、専門的・技術的分野が約72万人、技能実習生が約47万人、特定技能が約20万人という内訳です。特に2019年に創設された特定技能制度の影響で、建設業や農業分野での外国人材の受け入れが急速に拡大している点が注目されます。
参考:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)
政府の外国人材受け入れ政策
政府は人手不足解消と経済成長の両立を目指し、外国人材受け入れ政策を段階的に拡充してきました。2019年4月に開始した特定技能制度は、従来の技能実習制度とは異なり、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。対象分野は介護、建設、農業など16業種に及び、これらの業界・産業では特に人手不足が深刻なため、当初5年間で最大34.5万人という上限付きの受け入れ目標が掲げられました。
さらに2023年には、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、長期就労や家族帯同が可能となりました。これにより、外国人材にとって日本での就労がより魅力的な選択肢となり、企業側も安定的な人材確保が期待できるようになっています。また、高度外国人材の受け入れ促進策も相次いで導入されており、グローバル化が進む中での人材獲得競争において日本の競争力向上を図っています。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度
出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
外国人労働者採用の4つのメリット

外国人材を採用することで、企業はどのような利益を得ることができるのでしょうか。まず知っておくべきは、多くの企業が実感している主要な4つのメリットです。ここでは、具体例を交えながら詳しく解説します。これらの利点を理解することで、外国人材活用の可能性を正しく評価できるでしょう。
メリット1:労働力不足の解消効果
外国人材の採用による最も直接的なメリットは、慢性的な人手不足の解消です。特に製造業や建設業では、日本人の応募が少ない現場作業において、外国人労働者が重要な戦力となっています。例えば、ある製造業の企業では技能実習生を受け入れることで、生産ライン停止のリスクを回避し、安定した事業運営を実現しています。
また、外国人材は比較的若い世代が多く、就労意欲も高いため、体力を要する業務にも積極的に従事してくれる傾向があります。日本人従業員の高齢化が進む中で、このような若い労働力の確保は企業の持続的成長に不可欠です。さらに、外国人材の多くは真面目で勤勉な姿勢を持っており、日本人従業員にとっても良い刺激となることが期待できます。夜勤や交代制勤務にも柔軟に対応してくれるケースが多く、24時間体制の事業所では特に重宝されています。
メリット2:多様性がもたらす組織力向上
外国人材の参加により、職場に多様性(ダイバーシティ)がもたらされ、組織全体の活性化につながります。異なる文化背景を持つメンバーが加えられることで、これまでにない視点や発想が生まれ、問題解決能力の向上が期待できるでしょう。実際に、多国籍チームを編成している企業では、創意工夫やイノベーションが生まれやすくなったという報告が数多く寄せられています。
さらに、外国人材との協働を通じて、日本人従業員のコミュニケーション能力や国際感覚が自然と向上します。英語や現地語を学習する機会も増え、グローバルな視野を持った人材の育成にもつながるでしょう。このような組織の国際化は、今後の海外事業の発展や外国企業との取引、新たなビジネスチャンスの創出においても大きなアドバンテージとなります。
メリット3:グローバル展開への足掛かり
外国人材の雇用は、企業の海外進出や国際展開への第一歩としても非常に有効です。外国人従業員は、母国の市場情報や商習慣、消費者ニーズなど、現地に根差した貴重な情報を提供してくれます。例えば、ベトナム出身の従業員を採用した食品メーカーでは、その従業員のアドバイスを基に現地向け商品を開発し、東南アジア市場への参入を成功させています。
また、外国人材は自然な形でのマーケティングリサーチャーとしても機能します。日本製品への率直な意見や改善提案を通じて、より国際競争力のある商品・サービスの開発が可能になるのです。さらに、将来的に海外支社を設立する際には、これらの外国人従業員が現地駐在員や橋渡し役として活躍することも期待できます。グローバル化が進む現代において、このような人的ネットワークの構築は企業にとって計り知れない価値を持っています。
メリット4:新しい視点とイノベーション創出
外国人材が持つ、国ごとの文化的特徴や価値観は、既存の組織に新鮮な風を吹き込みます。日本の企業文化では当たり前とされていた慣習や手法に対して、「なぜそうするのか」という素朴な疑問を投げかけることで、業務改善のきっかけが生まれることも少なくありません。ある製造業では、外国人技能実習生からの提案により作業工程を見直し、効率を20%向上させることに成功しました。
技術的な面でも、外国人材の持つスキルや知識が企業の競争力向上に貢献します。特にIT分野では、インドやベトナムなど高い技術力を持つ国出身のエンジニアが、最新の開発手法やツールを導入してくれるケースも少なくありません。このような技術移転は、日本人従業員のスキルアップにもつながり、組織全体のレベル向上を実現するでしょう。さらに、若い外国人材の柔軟な発想力は、デジタル化や業務のスリム化など、現代的な課題解決にも大いに役立ちます。
いま、多くの企業がグローバルビジネスの展開を模索しています。人口減少や国内市場の縮小に直面する中で、海外進出は日本企業にとって避けて通れない課題となっています。しかし、国際的な市場で競争力を維持するためには、多様な人材の力が必要です。[…]
外国人労働者採用の4つのデメリット

外国人材の採用には多くのメリットがある一方で、企業が直面する可能性のある課題やデメリットも存在します。これらの問題を事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。ここでは、実際に多くの企業が経験している4つの主要なデメリットについて詳しく解説します。
デメリット1:コミュニケーションの壁
外国人材採用において最も頻繁に挙げられる課題が、言語によるコミュニケーションの問題です。日本語能力が十分でない場合、業務指示の理解不足や意思疎通の齟齬が発生し、作業効率の低下や安全面での懸念が生じる可能性があります。特に製造業や建設業では、安全に関わる重要な指示が正確に伝わらないリスクがあるため、十分な注意が必要です。
また、日本人従業員側も外国語でのコミュニケーションに不慣れな場合、お互いにストレスを感じる状況が生まれがちです。特に細かなニュアンスや文化的背景が関わる話題では誤解が生じやすく、人間関係が悪化する危険性も潜んでいます。さらに、緊急時やトラブル発生時には迅速で正確な情報伝達が不可欠であり、言語の壁は事業継続における深刻なリスクと言えるでしょう。このような課題を解決するためには、時間とコストをかけた語学サポート体制の構築が不可欠です。
デメリット2:文化の違いによる摩擦
宗教観、価値観、労働観などの文化の違いは、時に職場での摩擦を引き起こします。例えば、イスラム教徒の従業員には一日5回の礼拝時間が必要であり、ラマダン期間中は日中の飲食を控えるといった配慮が求められます。また、欧米系の外国人材は個人主義的な働き方を好む傾向があり、日本特有の集団行動や長時間労働に強い違和感を覚えるかもしれません。
さらに、上下関係や年功序列に対する考え方も国によって大きく異なります。日本人には当然でも、考え方が違う外国人材にとっては理解が難しい、日本の職場特有の暗黙のルールも存在します。「報告・連絡・相談」の文化や、会議での発言の仕方などもその一例です。
休暇の取り方についても、欧米諸国では長期休暇を取ることが一般的ですが、日本の職場ではなかなか受け入れられない現状があります。これらの文化的ギャップを埋めるためには、双方の歩み寄りと相互理解が重要ですが、調整には相当な時間と労力を要するのが実情です。
デメリット3:手続きの複雑さとコスト負担
外国人材を雇用する際には、在留資格の確認、就労ビザの申請、各種届出など、日本人従業員とは異なる複雑な手続きが必要になります。特定技能や技能実習などの制度を利用する場合は、監理団体や登録支援機関との連携、定期的な報告書提出など、継続的な事務作業が発生します。
これらの業務に慣れていない企業では、手続きミスによる法的リスクや、採用にかかる直接的な金銭負担だけでなく、想定以上の費用や経費がかかることがあります。給与水準の設定も慎重に行う必要があり、コスト負担は大きな課題です。
また、外国人材のサポートには専門的な知識が必要です。社会保険労務士や行政書士などの専門職に依頼すれば費用はかかりますが、複雑な手続きに伴う人事部門の負担を軽減し、法務リスクを回避できるという大きなメリットがあります。後から想定外の請求が発生しないよう、事前に契約内容を精査することが賢明です。
住居の確保、生活サポート、研修費用なども含め、日本人従業員を採用する場合と比較して初期投資が大きくなる傾向があります。さらに、不法就労防止のためのチェック体制構築や、定期的な在留状況の確認作業なども必要であり、人事部門の負担は相当なものとなります。
人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の採用を具体的に検討される企業が増えています。しかし、実際に外国人材の受け入れを進めようとすると「あっ、一体どのくらいの費用がかかるのだろうか」という疑問が必ず浮かんでくるでしょう。採用にかかる[…]
デメリット4:労働条件や法的な注意点
外国人材の雇用においては、労働基準法をはじめとする日本の労働関連法令を遵守することはもちろん、外国人特有の法的要件についても知っておくべき知識が数多くあります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人材に単純労働をさせるなど、定められた業務範囲を逸脱した仕事をさせることは法律違反となり、企業に対する罰則や在留資格取消しのリスクがあります。
労働条件の設定においても注意が必要で、国籍による不合理な差別は固く禁じられており、日本人従業員と同等以上の待遇を保証することが法的に求められています。最低賃金の遵守はもちろん、社会保険への加入、有給休暇の付与、安全衛生管理なども適切に実施しなければなりません。
さらに、母国への送金や家族の呼び寄せなど、外国人材特有のニーズに対する理解と配慮も重要です。これらの要件を満たすためには、専門知識を持った担当者の配置や、定期的な法令改正への対応が欠かせず、コンプライアンス体制の整備に多大な努力が必要となります。
人手不足が深刻化する中で、外国人材の雇用を検討する企業が急増しています。しかし、「在留資格の確認方法がわからない」「手続きが複雑で不安」といった悩みを抱える人事担当者も少なくありません。実際に、適切な知識なく外国人を採用した結果、あっという[…]
外国人材受け入れ時の注意点

以下に挙げる3つのポイントは、トラブルを未然に防ぎ、円滑な雇用関係を築くために特に重要です。これらの注意点を事前に理解し、適切な体制を整えることが成功への第一歩となります。
在留資格の適切な確認方法
外国人の選考から内定、そして在留資格の取得・確認に至る一連の流れの中で、最も重要なのが在留資格の把握です。就労可能な在留資格を持たない外国人を雇用した場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。在留カードを確認する際は、有効期限、就労制限の有無、在留資格の種類を必ずチェックしましょう。特に「資格外活動許可」が必要な留学生などは、許可証の内容も併せて確認することが重要です。
在留カードが偽造されている可能性もあるため、出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会サイトで真正性を確認することをおすすめします。また、在留期間の更新手続きについても、企業として適切にサポートする体制を整えておくことが必要です。更新手続きを怠ると不法滞在となってしまうため、期限管理は非常に重要な業務となります。専門的な判断が必要な場合は、行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
労働条件の明確化と契約書作成
外国人材との雇用契約では、労働条件を日本人以上に明確に定めることが大切です。言語や文化の違いがあるため、あいまいな表現は後々のトラブルの原因となります。労働契約書には、業務内容、勤務時間、休日、賃金、社会保険、有給休暇などを具体的に記載し、可能であれば母国語での翻訳版も用意することをおすすめします。
特に技能実習生や特定技能外国人の場合は、制度上の要件も含めて契約内容を整備する必要があり、必要な書類も多くなります。例えば、技能実習では実習計画に基づいた業務に従事させる必要があり、計画外の作業をさせることは認められません。また、特定技能では分野別の基準に合った労働条件を設定することが求められます。労働条件通知書の交付も法的義務ですので、適切な様式で作成し、本人に確実に理解してもらうよう説明することが重要です。
不法就労防止のためのチェック体制
企業には不法就労を防止する責任があり、そのためのチェック体制構築が不可欠です。採用時の在留資格確認はもちろん、在留期間中の定期的な状況確認も重要な業務となります。在留カードの有効期限が近づいた場合は、更新手続きの進捗を確認し、必要に応じてサポートを行いましょう。また、資格外活動を行っていないかどうかの確認も定期的に実施することが推奨されます。
従業員教育も重要な要素で、人事担当者や現場の管理者が外国人雇用に関する基礎的な法知識を身につけることが必要です。政府から随時発表される最新の指針や関連資料を参考に、社内研修を実施することをおすすめします。さらに、外国人雇用状況届出についても、適切な時期に確実に提出できる体制を整えておきましょう。万が一違反が発覚した場合のリスクを考えると、事前のチェック体制整備にかかるコストは決して高いものではありません。
外国人労働者採用を成功させる方法

外国人材の採用を成功に導くためには、単に雇用するだけでなく、長期的な視点での受け入れ体制構築が重要です。ここでは、多くの企業が実践している効果的な方法と、実際の成功事例を紹介します。これらのノウハウを活用することで、外国人材が活躍できる環境を整備し、企業の成長につながるでしょう。
職場環境の整備とサポート体制
外国人材が安心して仕事に集中し、長く働いてもらうためには、職場環境の整備が不可欠です。まず重要なのは、多言語対応の体制構築です。業務マニュアルや安全手順書の翻訳、多言語での掲示物作成など、言語面でのサポートを充実させましょう。また、日本語学習の機会を提供することで、コミュニケーション能力の向上を支援することも効果的です。
生活面でのサポートも欠かせません。住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約など、日本での生活に必要な手続きを支援する体制を整えることが重要です。さらに、定期的な面接を通じて仕事や生活上の悩みを聞き取り、適切なアドバイスを提供することで、早期離職を防ぐことができます。
文化的な違いについても、日本の職場文化を丁寧に説明し、お互いの理解を深める取り組みが必要です。社内でのメンター制度や、先輩外国人従業員による新人サポート体制なども有効な手段として多くの企業で採用されています。
効果的な研修プログラムの設計
外国人材の能力を最大限に引き出すためには、体系的な研修プログラムが不可欠です。入社時の導入研修では、会社の理念や事業内容、日本の労働文化について丁寧に説明し、職場への適応を促進します。実務研修では、業務に必要な技能や知識を段階的に習得できるよう、個々のレベルに応じたカリキュラムのもとで計画的に研修が行われることが重要です。
特に技能実習生や特定技能外国人の場合は、制度の要件に沿った技能習得が求められるため、計画的な研修実施が必要です。OJT(職場内訓練)を主としつつ、Off-JT(職場外訓練)を組み合わせ、理論と実践の両面から学習できる環境を提供しましょう。
また、研修の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて内容の調整を行うことも大切です。研修記録の作成と保管も、制度上の要件として求められる場合があるため、適切な記録管理体制を整えておくことをおすすめします。
長期雇用に向けた制度づくり
外国人材の長期定着を真剣に考えるのなら、キャリア形成支援と処遇改善の仕組みづくりが重要です。日本人社員と同じ昇進・昇格基準を明確に設定し、能力や成果に応じた適正な評価を行うことで、モチベーション向上を図りましょう。また、日本語能力の向上や専門スキルの習得に応じた待遇改善制度を導入することも効果的です。要件に合えば、キャリアアップ助成金といった助成制度の活用も検討できます。
長期就労を可能とする在留資格への変更サポートも重要な要素です。技能実習から特定技能への移行や、特定技能1号から2号への変更など、制度上の移行をスムーズに行えるよう支援することで、優秀な人材の継続雇用が可能になります。また、自社のウェブサイト等で多言語の採用情報を公開し、キャリアパスを明確に示すことも、優秀な人材を惹きつける上で効果的です。
外国人材活用の成功事例
ある製造業A社では、ベトナム出身の技能実習生20名を受け入れ、3年間の実習期間後、そのうち15名が特定技能に移行して継続雇用を実現しています。成功の要因は、入社時からの手厚い日本語教育と、ベトナム人の先輩社員によるメンター制度の導入でした。現在では、これらの外国人材がリーダー的役割を担い、新たな外国人材の受け入れにも協力しています。
IT企業の事例
IT企業B社では、元々日本に留学していたインド出身の高度人材5名を採用し、AI開発プロジェクトの中核メンバーとして活用しています。同社では英語を公用語とする部署を設置し、国際的な開発環境を整備しました。その結果、日本人エンジニアの英語力向上にもつながり、海外との協業プロジェクトが大幅に増加しています。
建設業の事例
建設業C社では、フィリピン出身の特定技能外国人10名を雇用し、深刻な人手不足の解消に成功しています。同社では外国人材専用の宿舎を整備し、母国料理を提供する食堂を併設するなど、生活環境の充実に力を入れています。また、母国の家族とのビデオ通話設備も提供し、精神的なサポートも行っています。これらの取り組みにより、離職率を10%以下に抑制し、安定した事業運営を実現しています。
人手不足が深刻化する現在の日本企業において、外国人材の活用は避けて通れない課題となっています。厚生労働省が掲載する資料によると、外国人労働者数は年々増加傾向にあり、多くの企業が新たな労働力として注目しているのが現状です。しかし、外国[…]
まとめ|外国人材採用で企業成長を実現しよう

本記事では、外国人労働者採用のメリット・デメリットから受け入れ時の注意点、成功のためのポイントまで詳しく解説してきました。労働力不足の解消、組織の多様性向上、グローバル展開への足掛かり、イノベーション創出という4つの大きなメリットがある一方で、コミュニケーションの壁、文化的摩擦、手続きの複雑さ、法的要件への対応といった課題も存在します。
重要なのは、これらの課題を適切に理解し、事前に対策を講じることです。在留資格の確認、労働条件の明確化、職場環境の整備、研修制度の構築など、基本的な準備を怠らずに取り組むことで、多くの課題は解決可能です。また、成功事例に学び、自社の状況に合わせた受け入れ体制を構築することが、外国人材活用を成功に導く鍵となります。
いわゆる2025年問題も控え、人材不足がさらに深刻化する前に、多様性を活かした新たな企業文化の構築に向けて一歩を踏み出すときです。上記で触れたように、適切な準備と継続的なサポートにより、外国人材は企業にとって かけがえのない戦力となることでしょう。
外国人材の雇用で何から始めれば良いか、お困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。私たちの人材紹介サービスでは、注意すべき点をまとめた一覧や比較表などもご用意し、企業様向けに様々な職種の外国人材を紹介しています。関連資料のダウンロードも可能ですので、ぜひご覧ください。