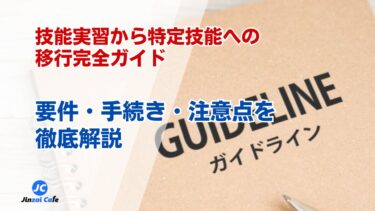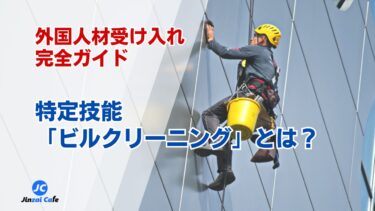少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。
こうした背景のもと、2019年4月に新たに設けられたのが「特定技能制度」です。これは、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れ、即戦力として活躍してもらうための制度であり、多くの会社・企業が注目しています。
本記事では、この特定技能制度について、その仕組みや背景、そして企業側のメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。初めて制度導入を検討する企業の担当者にも役立つ内容となるよう、専門用語も丁寧に噛み砕きながら説明します。本記事が、制度理解を深め、外国人材の受け入れを円滑に進めるための参考になれば幸いです。
- 1 特定技能制度とは何か?基本の解説
- 2 技能実習との違いと制度選択のポイント
- 3 特定技能外国人を受け入れる8つのメリット
- 4 特定技能外国人を雇用する際のデメリットと注意点
- 5 特定技能人材の受け入れを成功させるために
- 6 まとめ|特定技能制度は人材確保の有効な選択肢
特定技能制度とは何か?基本の解説

特定技能制度は、2019年4月に導入された新しい在留資格制度で、国内の人手不足が深刻な分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。特定技能は「即戦力」としての外国人労働者を対象にしており、これまでの技能実習制度とは異なり、労働力としての活躍が前提となっています。
制度の運営は出入国在留管理庁が所管し、企業が外国人を受け入れるには一定の条件を満たし、支援体制を整える必要があります。現在では16の産業分野が受け入れ対象となっており、受け入れ人数も年々増加傾向にあります。
ここでは、制度の基本をいくつかの観点から解説します。
制度創設の背景と目的
日本の労働市場における人手不足は、構造的な課題として長年にわたり指摘されてきました。特に中小企業や地方の産業では、日本人の若年労働力が確保できず、業務の継続が困難になるケースも目立っています。
こうした状況を受けて政府は、従来の「技能実習制度」に加えて、より実務的な労働力としての活躍が可能な外国人材の受け入れを可能にする「特定技能制度」を創設しました。この制度は、一定の技能を持った外国人が、日本の産業現場で即戦力として働けるように設計されています。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ在留資格の内容や在留期間、就労可能な条件が異なります。
- 特定技能1号は、試験などにより一定の技能や日本語能力の水準が認められた外国人が対象で、最長5年間の在留が可能です。ただし、家族の帯同は原則不可です。この資格を取得して、同一分野内であれば転職することも認められています。
- 特定技能2号は、より熟練した技能を有し、さらに試験をクリアした外国人が対象となります。2号では在留の更新が可能となり、家族帯同も認められるなど、長期的な雇用が前提となっています。
従来、特定技能2号は建設や造船・舶用工業など限られた分野のみ対象でしたが、2025年7月現在では、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など幅広い分野に拡大しています。今後も状況に応じて対象分野の拡大が検討されています。
対象職種と現在の対応状況
特定技能制度の対象となるのは、出入国在留管理庁が定めた以下の一覧にある16の産業分野です。これらはいずれも人手不足が深刻で、外国人材の受け入れが強く求められている領域です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造
- 造船・舶用工業
- 自動車運送業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材業
外国人がこれらの分野で従事するには、各分野ごとに実施される技能試験や日本語能力試験(JLPT N4レベル以上)に合格する必要があります。
特に介護、外食業、製造業分野では既に多数の受け入れ実績があり、企業からの評価も高まっています。
深刻な人手不足に直面する日本の企業にとって、外国人材の活用は喫緊の課題となっています。特に製造業、建設業、介護分野などでは、即戦力となる人材の確保が企業の存続に関わる重要な経営課題です。2019年4月に創設された特定技能制度は、これ[…]
技能実習との違いと制度選択のポイント

外国人材の受け入れ制度として、従来から存在する「技能実習制度」と、近年導入された「特定技能制度」。この2つは似ているようで根本的な目的や制度設計が異なります。
制度を誤って理解してしまうと、適切な人材活用ができなかったり、企業にとって不利益となるリスクも生じかねません。このセクションでは、技能実習と特定技能の主な違いと、どちらの制度を選ぶべきかを判断するためのポイントを整理します。
目的と制度の根本的な違い
技能実習制度は「国際貢献」が目的で、発展途上国の人材に日本の技術や知識を移転し、母国の発展に役立てることを主眼に置いています。そのため、実習終了後の帰国が前提となります。つまり“労働力”というより“教育”の色が強い制度です。
一方、特定技能制度は「労働力確保」が目的です。人手不足が深刻な産業において、一定のスキルを持つ外国人を即戦力として迎え入れる制度で、より実務重視の仕組みとなっています。
在留期間・家族帯同の可否の違い
技能実習制度では在留期間の上限が原則3年(条件によっては最長5年)であり、家族の帯同は認められていません。あくまで一時的な滞在と技能習得を前提としています。
対して特定技能1号は最長5年の在留が可能で、2号に移行すれば在留期間の更新ができ、家族の帯同も認められるようになります。これにより、より長期的・安定的な雇用関係を構築しやすくなります。
転職の可否とキャリアパスの違い
両制度の大きな違いの一つに「転職」の可否があります。技能実習生は、原則として実習先企業からの転職は認められていません。
一方で、特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば本人の意思で転職が可能です。これは、労働者としての権利がより尊重されていることを意味します。企業側にとっては人材流出のリスクにもなり得ますが、働き手にとってはより良い労働条件を求めてキャリアを構築できるというメリットがあります。
企業側の責任と支援体制の違い
技能実習では、監理団体を通じて受け入れるのが一般的であり、企業は技能実習計画に沿った実習を提供する義務があります。また、受け入れの際にはさまざまな報告義務が課され、制度運用上の負担も少なくありません。
一方、特定技能では、登録支援機関による生活支援や行政手続きのサポートが必須ですが、企業が直接雇用する形です。より柔軟で現場の実情に即した人材活用が可能であり、企業が主体的に制度を使いこなす意識が求められます。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
特定技能外国人を受け入れる8つのメリット

特定技能制度を通じて外国人材を受け入れることには、企業にとって多くのメリットがあります。ここでは、特に実務面や経営上の利点として顕著な具体的なメリットを紹介します。
制度を正しく理解し、適切に運用することで、単なる「人手不足の補填」ではなく、組織の活性化や生産性向上にもつなげることが可能です。
メリット1 即戦力として現場に早期投入できる
特定技能の外国人材は、受け入れ前に技能試験や日本語試験をクリアしています。そのため、現場に必要な知識・技能をすでに有しており、教育費用を抑えながら短期間で戦力化が可能です。
これまでのように一から研修する必要が少なく、即日稼働できるケースも少なくありません。特に繁忙期や欠員補充が急務の場面では、大きな力となります。
【事例】建設業界における即戦力活用ケース
建設業界で型枠大工が不足していた企業が、ベトナムで同職種の経験があり技能試験に合格した人材を受け入れました。来日後、基本的な安全教育を終えた翌日には現場に入り、図面を読みながら日本人従業員と共に作業を開始できました。これにより、未経験者を採用した場合に比べて数ヶ月単位での教育期間を短縮し、プロジェクトの遅延を防ぐことができました。
メリット2 人手不足の長期的な解消に貢献する
特定技能1号では最大5年間の就労が認められ、さらに条件を満たせば2号への移行により無期限の就労や家族帯同も可能になります。
これは、毎年のように従業員が入れ替わるアルバイトや短期契約と異なり、長期的な人材確保につながるという点で、企業にとって非常に大きな魅力です。
【事例】食品加工工場における長期的・安定的雇用ケース
地方の食品加工工場で、パート従業員の高齢化と若者の採用難に悩んでいた企業が、複数の特定技能外国人を雇用しました。彼らは5年間安定して勤務し、工場の生産ラインの中核を担う存在になりました。企業は毎年発生していた採用コストと新人教育の負担を大幅に削減でき、安定した生産体制を維持することが可能になりました。
メリット3 受け入れ可能な分野が広く業界を問わず対応可能
特定技能制度は、農業・建設・製造業・外食業など、多様な16分野が対象となっており、自社の業種に応じた外国人材の活用が可能です。
これにより、業界特有の作業にも適応できる人材を確保できるため、採用の自由度と可能性が大きく広がります。
メリット4 在留資格1号で最長5年間の安定雇用が可能
特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月単位での更新を含めて通算5年まで就労可能です。これはアルバイトや技能実習生に比べて安定的な雇用関係の構築がしやすいという利点があります。
また、期間内に実務能力が向上すれば、2号への移行によってさらなる長期雇用も視野に入ります。
メリット5 2号移行により長期的な定着・戦力化が見込める
特定技能2号に移行すれば、在留資格の更新制限がなくなり、実質的に長期の就労が可能となります。さらに、配偶者や子どもなどの家族の帯同も認められるため、生活基盤を日本に移すケースも増えています。
これにより、単なる“働き手”ではなく、地域社会に根づいた存在として定着し、企業にとっても貴重な戦力となる可能性があります。
メリット6 採用・受け入れ費用(コスト)が明確で計画が立てやすい
特定技能の採用には、試験費用やビザ申請、支援体制の整備に伴うコストが発生しますが、その金額はある程度明確で、年間の人件費計画に組み込みやすいのが特徴です。
また、登録支援機関を活用すれば、手続きや生活支援の多くを委託でき、提供されるサービスによって社内リソースの負担も最小限に抑えることが可能です。
メリット7 職場の多様性が促進され組織文化が活性化する
外国人材を受け入れることは、社内に多様な価値観や文化をもたらします。これにより、固定化された業務プロセスの見直しが進んだり、日本人従業員も含めた業務の効率化が図れるなど、副次的な効果も期待できます。
特に若手社員にとっては、異文化交流を通じて成長する機会ともなり、企業全体の風通しが良くなることもあります。
メリット8 企業の国際貢献やCSRのアピールにつながる
特定技能制度を活用することで、企業は単に労働力を確保するだけでなく、国際的な人材育成や地域との多文化共生にも貢献することができます。
こうした取り組みは、SDGsやCSR(企業の社会的責任)の観点からも評価されるポイントとなり、企業イメージの向上や採用広報にも良い影響を与えるでしょう。
日本の労働市場では深刻な人手不足が続いており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。この課題を解決する重要な選択肢として外国人材の活用に注目が集まる一方、頻繁に行われる制度変更や言語・文化の壁、複雑な手続きなど、人事担当者の悩みは尽きません[…]
特定技能外国人を雇用する際のデメリットと注意点
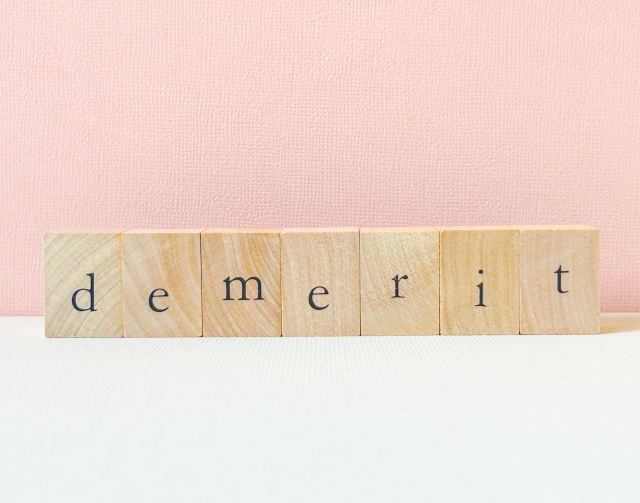
特定技能制度は多くのメリットを持つ一方で、導入に際しては慎重に検討すべき課題や企業側の負担も存在します。
制度を有効に活用するためには、こうしたデメリットや注意点を事前に把握し、適切な対策を講じることが欠かせません。ここでは、代表的な課題について解説します。
日本語能力や文化的ギャップの問題
特定技能の外国人材は、日本語能力試験(JLPT N4レベル以上)に合格することが条件となっていますが、業務上の複雑な指示を理解するのは難しい場合もあります。
例えば、専門用語の理解や現場での口頭指示のやりとりにおいて、意思疎通に時間がかかるケースもあります。また、文化や習慣の違いによる戸惑いが生じることもあり、社内の混乱を招くリスクも否定できません。
【事例】介護施設におけるコミュニケーション・ギャップのケース
介護施設で、日本人職員が「ちょっと様子を見ておいて」といった曖昧な指示を出した際、外国人材は何をすべきか具体的に分からず、ただ見守るだけで適切な対応ができませんでした。また、自分の意見をはっきり言う文化の国出身の従業員が、会議で上司の意見に率直に反論し、職場の和を乱していると誤解された例もあります。こうしたすれ違いを防ぐには、具体的で分かりやすい言葉を選び、文化的な背景を互いに理解する努力が必要です。
制度変更や在留資格更新に伴う不確実性
特定技能制度は比較的新しい制度であり、制度運用や要件が将来的に変更される可能性もあります。過去には技能実習制度で制度改正が行われた例もあり、同様の見直しが特定技能でも起こり得ます。
また、在留資格の更新時には、企業側や本人の状況によって不許可となるケースも稀に発生します。こうした不確実性がある以上、長期雇用を前提とする場合は、リスク管理が重要です。
受け入れ手続きの全体像と流れ
特定技能人材を雇用する際の全体的な流れは、煩雑に感じられることがあります。各ステップで必要な書類等が多岐にわたるため、その詳細を事前に把握しておくことが重要です。
- 採用候補者の選定と雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画書の作成
- 在留資格認定証明書交付申請(海外在住者)または在留資格変更許可申請(国内在住者)
- 在留資格の許可後、就労開始
この手続きをスムーズに進めるための方法として、専門の行政書士や登録支援機関に相談する選択肢があります。
教育・管理体制の構築負担
特定技能人材の受け入れにあたっては、企業が直接雇用の主体となるため、一定の責任が伴います。登録支援機関に生活支援を委託する場合でも、社内での教育体制や安全管理、業務の指導、相談体制の整備は不可欠です。
特に初めて外国人を受け入れる企業にとっては、管理体制の構築に時間とコストがかかる点がネックになり得ます。ただし、この体制づくりは一度構築すれば将来的な受け入れ拡大にもつながる資産になります。
【事例】外食店における教育体制の構築負担ケース
小規模な外食店が初めて特定技能人材を受け入れた際、これまでは口頭や「見て覚えろ」というスタイルで教えていた調理手順や接客ルールが全く伝わりませんでした。結果的に、写真や簡単な日本語を使った業務マニュアルをゼロから作成する必要に迫られ、店長が数週間にわたり通常業務以外の時間と労力を割くことになりました。こうした初期投資を想定しておくことが重要です。
特定技能人材の受け入れを成功させるために

特定技能制度を最大限に活用するには、単に外国人材を採用するだけでは不十分です。長期的な戦力化と定着を実現するには、企業側の受け入れ体制や支援の質が重要になります。
ここでは、受け入れを成功させるためのポイントを紹介します。これらを押さえることで、外国人材が安心して仕事ができる環境を整えることができます。
信頼できる登録支援機関の選び方
特定技能1号の外国人を雇用する際には、企業が自社で支援する場合を除き、生活支援や行政手続きの補助などを担う「登録支援機関」の活用が義務づけられています。
この登録支援機関は全国に多数存在しますが、サービスの質や支援内容にはバラつきがあるのが現状です。
したがって、支援機関を選ぶ際は以下の点を確認しましょう。
- 実績があるか(特定技能支援の経験年数や業種実績)
- 外国人とのコミュニケーション能力(多言語対応など)
- 定期的なフォロー体制の有無
- 急なトラブル対応のスピード感
信頼できる支援機関をパートナーとすることで、企業の負担を軽減し、外国人材も安心して働くことができます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
受け入れ体制の整備と社内教育の重要性
現場での混乱を避けるためには、受け入れ前に社内体制を整備しておくことが不可欠です。たとえば、以下のような準備が求められます。
- 外国人材の業務内容を明確にしたマニュアル作成(業務指導に活用)
- わかりやすい日本語や視覚的資料の活用
- 受け入れ部署への事前説明会や、社員向けの異文化理解セミナーを実施すること
また、言語や文化の違いから生じる誤解や摩擦を未然に防ぐには、「日本人側の教育」も同じくらい重要です。双方向の理解があってこそ、職場内の信頼関係は築かれます。
継続的なコミュニケーションとフォローアップ
外国人材が安心して長く働き続けるには、受け入れ後の継続的なフォロー体制が必要です。入社初期のオリエンテーションだけでなく、以下のような取り組みが効果的です。
- 定期的な1on1ミーティングやヒアリング
- 日本語学習支援(eラーニングや語学教室の紹介)
- プライベートの悩みも相談できる体制(信頼できる担当者の配置)
特に「困っていても自分から言い出せない」ケースも多いため、企業側から積極的に声をかける姿勢が定着率を大きく左右します。
成功事例に学ぶ
既に多くの企業が特定技能人材の受け入れを成功させています。そうした企業が行っている工夫を学ぶことも非常に有効です。
成功している企業は、マニュアルの多言語化や、日本人社員との交流会を定期的に行うなど、独自の工夫を凝らしています。自社で応用できる点はないか、積極的に情報を集め、参考にしましょう。
まとめ|特定技能制度は人材確保の有効な選択肢

本記事では、特定技能制度の概要から、技能実習との違い、導入のメリット・デメリット、そして受け入れ成功のための実践的なポイントまでを解説してきました。
深刻な人手不足に直面する中、特定技能制度は企業にとって即戦力となる人材を確保し、持続的な経営を支える有力な手段です。ただし、メリットだけに目を向けず、言語や文化の違い、制度上のリスクについても把握し、適切な体制整備と支援が必要不可欠です。
今後、日本の労働市場において外国人材の存在はますます重要になると予想されます。早期に制度を理解し、実践に移すことで、他社に先んじて多様で安定した人材基盤を築くことを提案します。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。