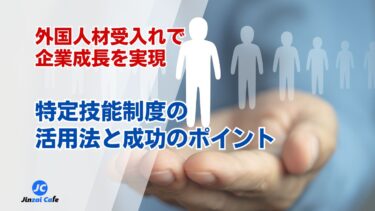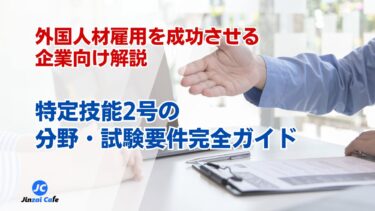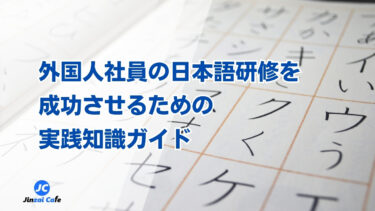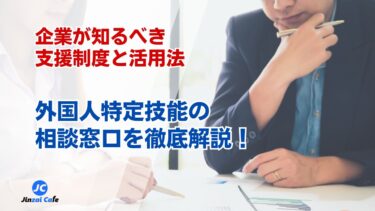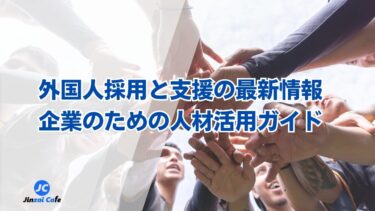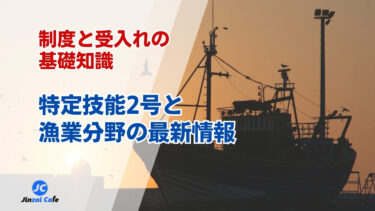農業の現場は、繁忙期に人手が「ぐっと」足りなくなる——そんな声を全国で耳にします。地域の農業を支える立場にある方々にとって、法制度の更新、受入れの手続き、現場の安全管理まで、同時並行で判断が求められる場面が少なくありません。正直、「どこから手を付けるべきか」と感じていませんか。
このような課題への有効な一手として注目されているのが、特定技能(1号・2号)制度です。これは人材確保の実効性ある選択肢であり、たとえば特定技能2号は、熟練者を長期に雇用できる可能性があり、経営の中核に据える設計も視野に入ります。
一方で、試験や在留資格の要件、日本語・技能の確認、書類の流れ等、押さえるべき点は少なくありません。「制度の全般像→試験の詳細→実務→支援→展望」の順に整理して理解することが近道です。
本記事では、農業分野における特定技能の基本から試験の実務、耕種・畜産の活用例、成功事例、2号取得に向けた支援と課題までを一気通貫で解説します。実のところ、要点を順番に並べていけば難しくありません。次の章から“使える”知識へ踏み込みます。
農業と特定技能制度の概要

人手不足に悩む農業という産業で、特定技能制度は実務的な解決策の一つとなっています。制度は2019年に創設され、外国人材が一定の技能水準を証明すれば、就労しやすくなる仕組みです。
その中でも「農業」は対象分野のひとつに位置付けられ、作物の栽培から畜産に至るまで幅広くカバーされています。実のところ、制度の基本を理解しておくことが、後の試験や雇用管理をスムーズに進めるための第一歩です。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度 農業分野
農林水産省 在留資格「特定技能」について (農業分野)
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれ要件が異なります。1号は技能水準が基本的で、在留期間は最長5年であり家族帯同は認められていません。一方、2号は熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新制限がなく、家族の帯同も可能です。つまり、長期的に安定した人材確保をめざすなら、2号の活用が鍵となります。
農業分野における特定技能2号は、2023年6月から本格的に運用が開始されており、2025年時点で多くの試験合格者が誕生し、現場で即戦力として活躍しています。特に熟練技術者としてリーダーシップを発揮する外国人材も増えており、制度は段階的な整備を経て着実に実務に根付いています。
今後も対象業務の拡大や受け入れ環境の充実が期待されており、農業現場の持続可能な発展に寄与することが見込まれています。
農業分野が対象となった背景
農業分野が特定技能制度の対象に加わった背景には、慢性的な労働力不足があります。特に高齢化と後継者不足が進む中、耕種や畜産の現場では繁忙期に人手が不足することが課題となっていました。外国人材を制度的に受け入れることで、一定の技能を持つ労働者を安定的に確保する狙いがあります。
たとえば、定植や収穫といった短期集中作業、家畜の飼養管理などは外国人材が力を発揮しやすい領域です。こうした背景を理解すると、制度の必要性がより鮮明になります。
農林水産省の方針と制度の流れ
農林水産省は、農業分野の外国人雇用を円滑に進めるため、特定技能制度の運用方針を定めると共に、その実施要領も示しています。具体的には、技能測定試験や日本語能力試験の実施、登録支援機関による生活支援などが制度の規定の一部として整備されています。
申請から受入れまでの流れは、大まかに以下のステップで進みます。「試験合格 → 在留資格申請 → 登録支援 → 就労開始」というステップです。制度の全体像を理解しておくことで、実際に人材を受け入れる際に混乱を避けられるでしょう。
参考:法務省・農林水産省 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
試験と必要条件の詳細
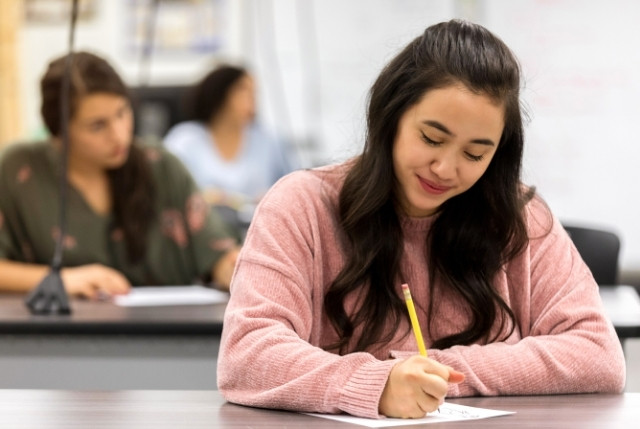
特定技能2号を取得するためには、一定の試験や条件をクリアする必要があります。農業分野では「技能測定試験」と「日本語能力試験」の2つが大きな柱です。これらに合格した後、在留資格の申請や書類確認といった手続きが進みます。
特に試験の内容や受験の流れを正しく理解しておくことは、受け入れ準備をスムーズに進めるための重要な要素です。
技能測定試験の内容と範囲
技能測定試験は、農業業務全般で実際に必要とされる作業能力を確認するために実施されます。耕種農業では、播種、定植、収穫、出荷等の作業手順が対象となり、畜産分野では、給餌、搾乳、飼養管理などが範囲に含まれます。
単なる知識問題ではなく、実務で活かせるかどうかが評価される点が特徴です。そのため、現場経験を持つ外国人材にとっては、自分の強みを直接示す機会とも言えるでしょう。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
日本語能力と書類要件
特定技能2号を目指すには、日本語能力の証明も不可欠です。試験では「日常会話が可能で、業務上の指示を理解できる水準」が求められ、一般的には日本語能力試験(JLPT)N4程度以上が目安とされています。
また、資格取得には在留資格変更に係る書類提出も必要で、雇用契約書、労働条件通知書、支援計画書などが代表例です。提出すべき書類の一覧は公式サイトで確認でき、これらの要件を満たしていないと、試験合格後でも在留資格が認められない可能性があります。
参考:日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
グローバル化が進む中、多くの日本企業が外国人社員を採用するようになっています。しかし、採用後に直面する大きな課題のひとつが「日本語でのコミュニケーション」です。業務の指示が伝わらない、会議で発言が難しい、日常会話に壁を感じるといった問題は、[…]
受験手続きと登録機関の役割
受験手続きの方法として、受付は、農林水産省が委託する登録試験機関の公式サイト等を通じて行われます。受験者はインターネット上で申し込みを行い、必要に応じて証明書類を提出します。試験実施後は、合格証明書が発行され、それをもとに在留資格の申請を行う流れです。
また、登録支援機関は、合格者が日本国内で生活・就労できるようサポートする役割を担います。生活ガイダンスや相談窓口の設置などが含まれ、受験から受入れ後まで一貫して関与する点も見逃せません。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
農業分野での実務と活用例

特定技能の外国人材が農業現場で担う役割は幅広く、単なる労働力補填にとどまりません。耕種や畜産の基本作業から、衛生・安全管理、さらに地域団体と連携した販売支援まで多岐にわたります。制度を理解したうえで利用すれば、農業経営の持続性を高める有力な手段となるでしょう。
耕種農業と畜産の業務例
耕種農業では、播種・定植・収穫・選果・出荷といった一連の作業を支援できます。繁忙期に集中するこれらの業務を担ってもらうことで、収穫ロスを防ぎ、生産性を維持することが可能です。
畜産分野では、給餌や搾乳、飼養管理が中心です。家畜の健康管理や衛生面の徹底も含まれるため、一定の技能と責任感が必要とされます。こうした作業を外国人材が分担することで、経営者や従業員の負担軽減につながるのです。
衛生・安全管理のポイント
農業分野における衛生・安全管理は、単なるルール遵守ではなく「品質保証」の観点からも欠かせません。作業着の着用、手洗いの徹底、農業用器具の消毒、農薬の適切な取り扱いなど、細かな指導が必要です。
特定技能人材には、日本語でのマニュアルやピクトグラムを用いた教育が効果的です。安全に従事できる環境を整えることが、長期的な雇用定着の前提条件となるでしょう。
全国農業会議所や団体の支援事例
全国農業会議所や地域の農業団体は、特定技能制度の普及や受入れ支援を積極的に行っています。たとえば、試験対策講座や生活支援の相談窓口設置など、受入れ側の不安を軽減する仕組みを整えています。
制度の情報をタイムリーに得るためにも、これら団体との連携は不可欠です。制度利用に不慣れな農業事業者にとって、信頼できる相談先があることは大きな安心材料となります。
生活支援と制度活用がもたらす成功例
特定技能制度の導入から5年が経ち、株式会社八街産直会では特定技能1号として働いてきたベトナム人4名が特定技能2号試験に合格しました。耕作面積23ヘクタールの農場では多品目の野菜を栽培しており、外国人39名と日本人16名が協力して業務にあたっています。そのうち27名は技能実習から継続して雇用されており、長期的な人材確保に結びついています。
2号の在留資格は規定上、更新制限がなく、家族帯同も可能なため、働く意欲が一層高まっています。職場では6組の外国人カップルが誕生し、互いに支え合う雰囲気が広がりました。住居は男女別に一軒家を借り上げ、一人一部屋を確保するなど生活支援も充実しています。制度と環境の整備により、所属する企業と外国人材が共に発展する好事例となっています。
参考:一般社団法人全国農業会議所 農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集【令和6年度版】事例4
2号取得に向けた支援と課題

特定技能2号は長期的な就労を可能にする一方で、制度の運用や現場での受入れには課題もあります。試験に合格しても、その後の在留資格申請や生活支援が十分でなければ、外国人材の定着は難しくなります。
受け入れる側の事業者が法的条件を理解し、経営や労務管理に反映させることが成功のカギです。ここでは、支援と課題を整理し、担当者が押さえておくべきポイントを示します。
試験合格後の在留資格更新
特定技能2号に合格しても、在留資格の更新申請を適切に行うことでなければ継続就労はできません。更新制限がないとはいえ、定められた書類提出や審査は毎回必要です。
農業分野では雇用契約書や支援計画書等の作成が欠かせず、経営者側の準備不足が遅延につながることもあります。行政書士や支援機関と連携し、更新のスケジュール管理を徹底することが安定的な受入れに直結します。
雇用管理と経営上の留意点
外国人材を長期的に雇用する場合、労働条件や処遇を日本人従業員と同等に整えることが前提です。賃金、労働時間、安全管理などの点で不公平が生じると、職場全体の士気に影響します。
また、言語や文化の違いから誤解が生じやすいため、マニュアル整備や定期的な面談が有効です。経営面では、2号人材を単なる労働力ではなく「熟練者」と位置付け、教育や責任ある業務を任せる視点が求められるでしょう。
情報提供と制度利用の工夫
制度を正しく使いこなすには、最新の関連情報を常に把握することが欠かせません。農林水産省や全国農業会議所の公式サイト、登録支援機関のセミナー等を利用し、詳細を確認することで、誤った運用を防ぐことができます。
さらに、外国人材にも制度や在留資格のルールを理解してもらうことが大切です。母国語でのガイドや説明会を用意すれば、安心して働き続けられる環境が整います。こうした情報共有の工夫が、制度の定着と農業経営の安定に結びつきます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は重要な選択肢の一つです。しかし、複雑な制度内容や手続きに関して「どこに相談すればよいのか分からない」「適切な支援を受けられるのか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も多いの[…]
農業人材の今後と展望

特定技能制度の運用が進む中で、農業人材の役割は今後さらに広がっていくと考えられます。制度改善や現場の工夫によって、外国人と日本人が共に働きやすい環境を作り出せるかどうかが重要です。
こうした動きは数多く見られます。ここでは、国内人材との関係、持続可能な仕組みづくり、そして将来の制度改正の方向性について整理します。
国内人材との役割分担
外国人材の受入れは、日本人従業員の雇用を奪うものではなく、むしろ役割分担を通じて効率化を実現します。たとえば、外国人材が収穫や管理など労働集約的な作業を担い、日本人は販売戦略や経営企画に集中する、といった形です。
これらは前から議論されてきた役割分担の一つの方法です。両者の強みを組み合わせることで、生産から販売までの一体的な体制を築くことが可能になります。こうした補完関係は、農業経営の安定と地域の活性化につながるでしょう。
外国人雇用の持続的な仕組み
持続的に外国人材を利用するには、働きやすい職場環境を整えることが不可欠です。賃金や労働時間といった基本条件だけでなく、生活支援や地域社会への参加機会を提供することも効果的です。
たとえば、地域イベントへの参加や語学学習のサポートは、帰属意識を高めます。また、長期雇用を見据えてキャリアパスを提示することも重要です。働き手が将来を描ける環境こそが、持続可能な農業経営の基盤になります。
制度改善と新しい動き
特定技能制度は始まってまだ数年ですが、改正や改善の議論は常に行われています。農林水産省も現場の声を踏まえて試験内容や受入れ条件を調整しており、将来的には対象分野の拡大など、さらなる柔軟化が期待されます。
加えて、デジタル技術やスマート農業との連携により、外国人材が担う業務の幅も変化していくでしょう。こうした新しい動きを把握しておくことで、先を見据えた経営判断が可能になります。
近年、日本では人手不足が深刻化し、多くの企業が外国人材の採用を検討するようになっています。特に中小企業では、国内での人材確保が難しいため、外国人労働者の活用が避けられない状況になりつつあります。とはいえ、採用や雇用管理に関する制度は複雑で、[…]
まとめ|農業の特定技能2号を正しく理解する

農業分野の特定技能2号は、人手不足の解消だけでなく、熟練人材を中核に据えた経営の安定化にもつながります。本記事では、制度の概要、試験内容、実務での活用例、生活支援を伴う成功事例、そして今後の展望までを整理しました。重要なのは、制度を単に「人材確保の仕組み」として捉えるのではなく、外国人材と共に地域農業を発展させるための基盤と考えることです。
とはいえ、試験合格後の在留資格更新や生活環境の整備など、受入れ側の責任は決して軽くありません。ですが、正しい知識と支援体制を整えれば、外国人材は長期的に農業経営を支える大きな存在になります。次に行動に移すときは、制度の全般を理解したうえで、信頼できる支援機関や団体と連携して進めることが成功の近道となるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。