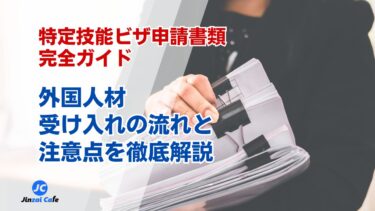自動車整備業界は慢性的な人手不足に直面しており、特に若年層の担い手不足が課題となっています。この状況を背景に、日本では外国人材の活用を目的とした「特定技能制度」が導入されました。中でも特定技能2号は、2023年に対象分野が拡大されて以降、長期的に就労できる資格として注目を集めています。本記事では、自動車整備分野における特定技能2号の概要や試験制度、受入れ条件を解説し、経営者が実務に役立てられる知識を整理していきます。
特定技能制度の概要と自動車整備分野

特定技能制度は、2019年に開始された在留資格で、日本国内の人手不足分野に限定して外国人の就労を認める仕組みです。自動車整備業界もその対象に含まれており、国土交通省が制度設計を担っています。
業務に必要な技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れることで、事業場の人材不足を補える可能性があります。制度の全体図を理解することが、経営戦略に直結する第一歩といえるでしょう。
参考:
出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
出入国在留管理庁 自動車整備分野
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、一定の知識と実務能力を持つ外国人が対象で、在留期間は通算5年に制限されています。これに対して特定技能2号は、日本の自動車整備士級でいえば2級相当、あるいはそれ以上の高度な技能を有する人材に付与され、在留資格の更新や家族帯同が可能です。
自動車整備分野では、まず1号で経験を積んだ後、試験や評価を経て2号へ移行する流れが一般的です。両者の違いを正しく理解することで、将来的な、そしてより長期的な雇用計画を立てやすくなります。
自動車整備分野が制度対象となった経緯
自動車整備業界は、少子高齢化に伴う人材不足や、電動化・電子制御といった新技術への対応が急務となっています。こうした背景から、国土交通省は整備分野を特定技能の対象に位置付け、自動車整備業全体の活性化を図ってきました。
特に点検や修理といった基礎業務を担う人材が不足しており、外国人が活躍できる環境が整いつつあります。経緯を知ることで、制度がなぜ必要とされたのかが理解できるはずです。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
国土交通省が定める受入れ方針
国土交通省は、外国人自動車整備士の受入れに関する指針を定めています。具体的には、技能検定や実技試験の合格者を対象とし、地方運輸局や関連協議会が監督を行います。また、受入れ企業には労働環境の整備や支援体制の構築が求められ、登録支援機関との連携も重要です。これらを遵守しなければ受入れは認められないため、事前の準備が欠かせません。
参考:国土交通省 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ
自動車整備業界は今、深刻な人手不足に直面しています。ベテラン整備士の高齢化が進む一方で、若手の担い手はなかなか増えません。実際、国土交通省のデータでも有効求人倍率は4倍を超えており、多くの事業所様が「必要な人材が集まらない」という悩みを抱え[…]
自動車整備分野における試験制度

特定技能として自動車整備分野で就労するには、所定の試験に合格する必要があります。試験は学科と実技に分かれており、整備に必要な知識と技能の両方を評価する仕組みです。このテストに合格することで、日本で働く道が開かれます。
さらに、日本語能力の確認も行われ、業務上の安全性を確保する狙いがあります。試験の詳細は認定機関によって定期的に実施されており、一部ではCBT(Computer Based Testing)方式も採用されています。受験者は事前に概要や実施要項を確認することが重要です。
参考:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 特定技能評価試験
学科試験と実技試験の概要
学科試験では、道路運送車両法第48条に基づく基礎知識や、自動車整備に必要な点検・修理に関する内容が問われます。一方の実技試験では、実際の作業を通じて技能レベルが確認され、具体的な整備手順や問題解決能力が評価されるでしょう。
学科と実技の両方に合格することが条件です。いずれか一方では在留資格の取得はできません。こうした試験内容は国土交通省が公表しているため、事前学習が不可欠です。
試験実施機関と受験資格
試験は国土交通省が認定した機関によって実施され、地方運輸局や一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)等の関連団体が運営に関わります。これらの機関は厳格な基準に基づいて認証されているのです。
受験資格としては、技能実習修了者や一定の経験を持つ外国人が対象であり、所属機関や国によって申請方法が異なる場合があります。その他、日本語試験の合格証明を併せて提示する必要があるケースもあります。これらの条件を満たしていなければ受験できないため、事前の確認が不可欠です。
合格基準と評価方法
合格基準は、学科と実技それぞれで定められています。学科では基礎知識を一定以上理解しているかどうか、実技では点検や修理作業を適切に行えるかが評価の中心です。評価は点数制で行われ、得点が基準以下の場合は不合格と判断されますが、再受験も可能です。
合格者は特定技能として登録され、受入れ企業での就労資格を得られます。評価基準を把握することは、企業にとっても人材選考の参考になります。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
特定技能2号への移行と要件

特定技能1号から2号へ移行するには、一定の実務経験や技能水準を満たす必要があります。自動車整備分野では、実際の業務を通じて能力を証明する仕組みが整備されており、在留資格の更新や長期就労を可能にする点が特徴です。2号を取得することで、より安定した雇用や家族帯同が認められるため、企業にとっても人材定着の大きな利点となります。
参考:国土交通省 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ
移行に必要な実務経験と証明
特定技能2号へ移行するには、原則として3年以上の実務経験が求められます。具体的には、自動車整備士として点検や修理などの作業を行い、その能力が評価機関により確認されなければなりません。
実務証明には、所属工場や事業場からの証明書等の書類提出が必要となり、国土交通省が定めた様式に基づいて提出されます。経験を適切に記録し、証明できる体制を整えることが企業側の責任といえるでしょう。
在留資格2号取得の手続き
在留資格2号を取得するためには、地方運輸局や入管への申請が必要です。申請書には、必要事項を記載した上で、試験合格証明や実務経験を裏付ける資料が添付され、外国人本人と受入れ企業の双方で手続きを行います。
近年では電子申請も可能になりつつあります。また、更新時には定期的な確認が行われ、制度に基づく適正な受入れが審査されるのです。こうした申請プロセスを理解し、書類不備を防ぐことが、スムーズな移行の鍵となります。
企業が確認すべきポイント
企業は、2号人材を受け入れる際に下記の一覧のようなポイントを確認する必要があります。
- 実務経験や技能評価の証明が適切に揃っているか
- 在留資格の更新条件を満たしているか
- 支援体制や労働環境が法律に基づいて整備されているか
これらを怠ると受入れが認められない場合があるため、企業自身がチェックリストを作成して管理することが推奨されます。適切な確認を行うことで、安定した人材活用が実現できるでしょう。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
自動車整備人材の受入れと支援体制

特定技能制度の下で外国人を受け入れる場合、企業には単なる雇用契約以上の責任が求められます。国土交通省の方針に基づき、労働条件や生活支援の整備が不可欠です。
特に自動車整備分野では、技能実習から移行してくる人材が多いため、受入れ環境の整備が人材定着の成否を左右します。企業は法令遵守だけでなく、実務に即した支援体制を整えることが重要でしょう。
受入れ事業場の体制整備
外国人を受け入れる事業場は、労働基準法や道路運送車両法に準拠した環境を整備する必要があります。例えば、定期点検の業務を適切に割り当て、必要な教育やOJTを行う体制を作らなければなりません。
また、外国人整備士が安全に作業できるよう、マニュアルや多言語対応の資料を準備することも求められます。こうした整備が行き届くことで、業務効率と人材定着率の両立が可能となるでしょう。
登録支援機関によるサポート
登録支援機関は、受入れ企業の相談先として補助する役割を担います。たとえば、在留資格申請の手続き支援、日本語学習のサポート、生活上の相談対応などが挙げられます。
特に自動車整備分野では、専門的な用語や作業工程が多いため、機関による学習支援が有効です。企業単独では難しい部分を補うことで、外国人整備士が安定して働ける環境を実現できるのです。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
労働環境・定着支援の具体例
労働環境の改善と定着支援は、長期雇用を目指す上で不可欠です。例えば、勤務時間や休日制度の適正化、社会保険の完備はもちろんのこと、文化的な違いを考慮した交流イベントの開催も有効です。
さらに、定期的な評価やフィードバックを行うことで、外国人整備士のモチベーションを高められます。これらの取り組みが組み合わさることで、人材の流出を防ぎ、企業の成長に直結していくでしょう。
活用事例と今後の展望

特定技能2号を活用した自動車整備人材の受入れは、すでに全国の整備工場で進みつつあります。制度を導入した企業は、人材不足の解消だけでなく、現場の効率向上や新しい技術への対応にも成果を挙げています。
一方で、言語や文化の壁といった課題も残されています。こうした現状を踏まえ、事例の共有と改善策の検討が今後の業界発展に欠かせない要素になるでしょう。
実際の受入れ事例と成果
山形県内の自動車整備工場で働くベトナム出身の男性2人が、「自動車整備分野特定技能2号」の試験に合格しました。合格率は約30%という難関で、2人とも5年前に技能実習生として来日し、日々の整備業務に励んできたことが、今回の成果につながったとのことです。特定技能2号を取得したことで、在留期間の制限が撤廃され、家族帯同も可能となりました。
県内ではこの2名が初の取得者であり、全国でもこの資格保有者は2024年末時点でわずか3人という非常に限られた存在です。職場では「店を支える中心的存在」として評価され、地域社会からも働き手不足解消への期待が寄せられています。彼らは「長く暮らしたい」「家族のため努力し続けたい」と語っています。
制度活用における課題と解決策
一方で、制度活用には課題も存在します。特に、日本語の壁や専門用語の理解不足が原因で業務に支障をきたすケースがあります。また、労働条件や待遇に対する不満が定着率を下げる要因になることも少なくありません。
解決策としては、OJTと並行した語学教育や労働環境の改善が挙げられます。例を挙げると、定期的な面談による問題把握が有効です。こうした取り組みを積極的に導入することで、制度の真価が発揮されるのです。
業界全体への影響と将来像
特定技能2号制度は、自動車整備業界の労働力不足に対する即効性のある対策となり得ます。外国人材の数が増加することにより、整備現場は多様化が進み、グローバルな視点を取り入れた技術力の向上が期待されます。
今後は、電動車や自動運転技術に対応できる人材育成も課題となるでしょう。制度を活用する企業が増えるほど、業界全体が変革期を迎え、持続可能な成長へつながると考えられます。
日本の多くの会社が直面している最大の課題のひとつは、人手不足です。特に介護や製造、建設などの特定技能分野では、外国人労働者の採用が急速に拡大しており、その事業規模も大きくなっています。しかし、その一方で職場における日本語でのコミュニケーショ[…]
まとめ|自動車整備業界の未来に向けて

本記事では、自動車整備分野における特定技能2号制度の概要、試験制度、移行要件、受入れ体制、さらに活用事例と今後の展望を解説しました。制度を正しく理解し、企業として適切な準備を進めることが、人材不足の解消につながります。
また、外国人材の安定的な定着は、整備業務の効率化や顧客満足度の向上にも寄与します。今後は、国土交通省の発表や地方運輸局の最新情報を確認しつつ、自社に最適な活用方法を検討することが重要です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。