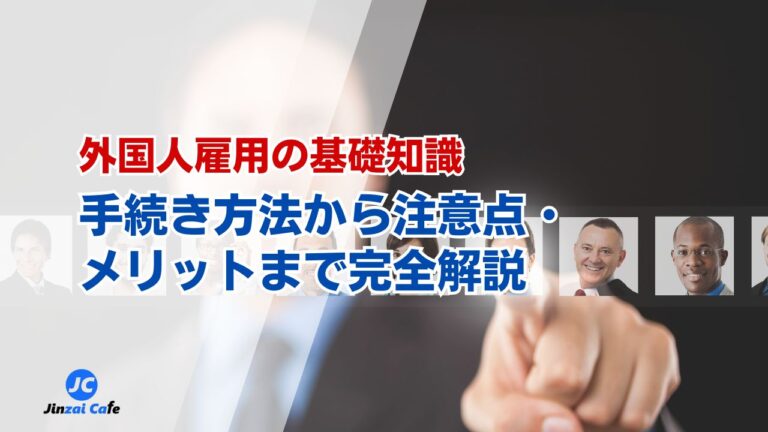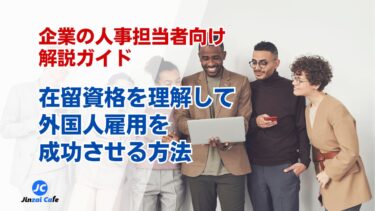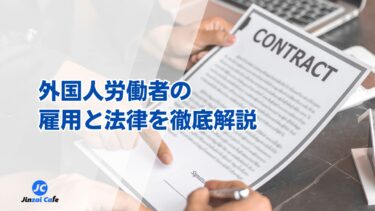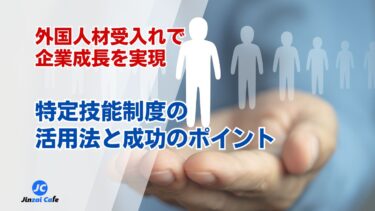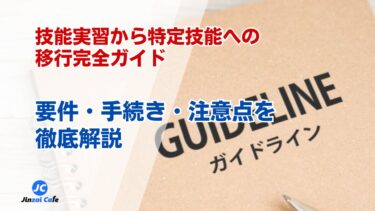人手不足が深刻化する現在の日本企業において、外国人材の活用は避けて通れない課題となっています。厚生労働省が掲載する資料によると、外国人労働者数は年々増加傾向にあり、多くの企業が新たな労働力として注目しているのが現状です。
しかし、外国人雇用には在留資格の確認から労働条件の整備まで、日本人採用とは異なる複雑な手続きが必要になります。適切な知識なしに進めてしまうと、不法就労助長罪に問われた事例もあり、法的リスクを招く可能性もあるでしょう。
今回、本記事では、外国人雇用を検討している人事担当者の方に向けて、基礎知識から実際の手続き方法、注意すべきポイントまでを詳しく解説いたします。正しい理解のもとで外国人材を受け入れることで、企業の成長と競争力向上につなげていきましょう。
外国人雇用の基礎知識と現状

日本の外国人雇用市場は急速な変化を遂げており、企業にとって重要な人材確保の手段となっています。まずは現在の状況と基本的な仕組みを理解することから始めましょう。次に外国人労働者の動向や雇用が注目される背景、そして実際に採用可能な外国人の種類について詳しく見ていきます。
外国人労働者の現状と動向
厚生労働省の発表によると、日本で働く外国人労働者数は年々増加を続け、2024年10月時点ではついに230万人を超える規模まで拡大しました。これは、多くの企業が外国人材の採用を積極的に行っている証拠といえるでしょう。
特に製造業、建設業、介護や医療分野での需要が高く、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ高度人材も増加しています。留学生のアルバイトから始まり、卒業後に正社員として就職するケースも多く見られます。
国籍別では中国、ベトナム、フィリピン出身者が多数を占めており、その他にも多様な国籍の人材が活躍しています。それぞれ異なる文化的背景や言語能力を持っているのが特徴です。企業側は多様性を活かした組織作りが求められる時代となっています。
参考:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)
外国人雇用が注目される理由
日本の労働人口減少は避けられない現実であり、外国人材への期待は年々高まっています。特に地方企業では深刻な人手不足が続いており、外国人雇用が事業継続の鍵を握るケースも珍しくありません。会社の存続のために、新たな労働力確保は急務です。
外国人労働者は単なる労働力補完以上の価値をもたらします。多言語対応能力、海外市場への理解、そして異なる視点からの業務改善提案など、グローバル化を目指す企業にとって貴重な戦力となるでしょう。加えて、特定の要件を満たせば、雇用関係の助成金が活用できる場合もあります。
また、若い世代の外国人材が多いことも魅力の一つです。日本人の新卒採用が困難な企業でも、意欲的な外国人留学生を採用することで組織の活性化を図れます。長期的な視点で見れば、企業の国際競争力向上にも大きく貢献するはずです。
雇用可能な外国人の種類
外国人雇用を検討する際は、在留資格によって就労できる範囲が大きく異なることを理解しておく必要があります。
技術・人文知識・国際業務の資格を持つ人材は、専門性を活かした幅広い業務に従事可能です。在留資格の一覧や概要は、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
特定技能の在留資格者は、16の特定分野で即戦力として活躍できます。介護、建設、製造業などの現場で、一定の技能と日本語能力を持った人材を採用できるのが大きなメリットでしょう。
永住者や定住者、日本人の配偶者等の資格を持つ外国人は、就労に制限がないため日本人と同じように雇用できます。外交ビザなど一部の特殊な資格以外は、一般的に就労が認められていない在留資格でも、資格外活動許可を得ればアルバイトが可能です。
ただし単純労働目的の入国は原則認められていません。留学生や家族滞在の資格者をアルバイトで雇う場合は、資格外活動許可の確認が必須となります。技能実習生については、受け入れ機関を通じた特別な制度のもとでの雇用となるため、別途詳細な検討が必要です。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
外国人雇用に必要な手続きと流れ

外国人を雇用する際は、日本人採用とは異なる特別な手続きが求められます。在留資格の確認から雇用契約の締結、各種届出まで、段階的に進める必要があるでしょう。手続きを怠ると法的な問題に発展する可能性もあるため、事前の準備と正確な対応が重要になります。
雇用前の確認事項と準備
外国人採用を検討する際は、まず社内体制の整備から始めましょう。人事担当者が入管法や労働基準法の基礎知識を身につけることが最優先です。厚生労働省や出入国在留管理庁の最新情報を各種メディアで定期的に確認する体制も必要になります。公式サイトからダウンロードできる資料も役立つでしょう。
募集段階では、外国人が応募可能な職種かどうかを慎重に判断してください。在留資格によって従事できる業務内容が制限されているため、事前の確認が欠かせません。また、多言語での求人情報作成や、文化的背景を考慮した面接方法の準備も重要なポイントです。
社内では受け入れ環境の整備も進めておきましょう。多言語対応マニュアルの作成、既存従業員への説明、そして外国人材をサポートする担当者の選定などが必要になります。これらの準備を怠ると、入社後のトラブルの原因となりかねません。
参考:
厚生労働省 外国人の雇用
出入国在留管理庁 特定技能制度
在留資格と就労可能範囲の確認方法
外国人を雇用する前に、必ず在留カードを使用して本人確認と在留資格の確認を行ってください。在留カードの表面には在留資格の種類と在留期間が記載されており、裏面では就労制限の有無を確認できます。偽造防止のため、ICチップの読み取りも実施しましょう。許可されていない業務への従事は不可です。
就労制限がある場合は、資格外活動許可の有無も確認が必要です。留学生や家族滞在の資格者がアルバイトをする際は、この許可なしには働くことができません。許可証が交付された内容を詳細にチェックし、時間制限や業務内容の制約がないかを確認してください。
不明な点がある場合は、出入国在留管理庁への相談をおすすめします。電話相談や窓口での確認により、適切な雇用が可能かどうかを事前に判断できるでしょう。間違った解釈による不法就労助長を防ぐためにも、疑問があれば専門機関に相談することが大切です。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
雇用契約から入社までの手続き
雇用契約書の作成では、労働条件を明確に記載することが重要です。給与、勤務時間、休日、仕事の内容などを具体的に定め、可能であれば母国語での説明も併用しましょう。文化的な違いから生じる誤解を防ぐため、詳細な説明を心がけてください。
必要書類の準備では、雇用契約書のほかに履歴書、在留カードのコピー、資格外活動許可証(該当者のみ)などを収集します。また、雇用保険や社会保険への加入手続きも日本人と同様に行う必要があります。
入社時には、業務内容の詳細説明とともに、日本の労働慣行や社内ルールについても丁寧に説明しましょう。言語の壁がある場合は、通訳の手配や多言語マニュアルの活用も検討してください。スムーズな職場適応を支援することで、長期雇用につながる基盤を作れます。
ハローワークへの届出義務
外国人を雇用した企業は、ハローワークに対する届出が法律で義務付けられています。雇用開始時と離職時の両方で手続きが必要となるため、忘れずに対応しましょう。この届出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出書類には、外国人の氏名、在留資格、在留期間、国籍などの基本情報を記載します。雇用保険の被保険者に該当する場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出に加え、外国人雇用状況の通知も併せて届け出ることが可能です。
オンラインでの届出も利用できるため、効率的な手続きを心がけてください。定期的な労働施策の参考とするための重要なデータとなりますので、正確な情報の提供が求められます。届出期限は雇用開始の翌月末日となっているため、計画的な対応が必要です。
近年、日本では少子高齢化と人口減少が進行し、多くの業種で深刻な人手不足が続いています。とりわけ、製造業、建設業、介護、宿泊、外食等の分野では、日本人労働力のみでの人材確保が困難な状況です。こうした背景から、外国人材の活用が急速に進展していま[…]
外国人雇用のメリットと企業への影響

外国人材の採用は、単純な労働力不足の解決以上の価値をもたらします。多様な背景を持つ人材の加入により、企業文化の活性化から海外展開への足がかりまで、幅広いメリットが期待できるでしょう。これらの利点を最大限に活用することで、企業の持続的成長と競争力向上を実現できます。
人手不足解消と労働力確保
深刻な人手不足に悩む企業にとって、外国人材は即効性のある解決策となります。特に製造業や建設業、介護分野では、技能を持った外国人労働者の採用により生産性の向上を図れるでしょう。日本人の応募が少ない職種でも、意欲的な外国人材を確保できる可能性があります。
若い世代の外国人材が多いことも大きな魅力です。高齢化が進む日本の労働現場において、体力と意欲を兼ね備えた人材の確保は企業の将来性を左右します。長期的な視点で育成すれば、将来の幹部候補としても期待できるはずです。
また、外国人材は比較的長時間労働にも対応可能な場合が多く、シフト制の職場や残業の多い部署での活用も検討できます。ただし、労働基準法の遵守は必須であり、適切な労働環境の提供が前提となることは言うまでもありません。
多様性がもたらす組織力向上
異なる文化的背景を持つ外国人材の加入は、組織に新たな視点を与えます。これまでの日本的な発想だけでは解決できなかった課題に対し、斬新なアプローチを提案してくれる可能性が高いでしょう。イノベーションの創出にも大きく貢献するはずです。
多言語対応能力は、グローバル化を目指す企業にとって貴重な資産となります。海外顧客との商談や現地法人との連絡において、母国語での対応ができる人材は重宝されるでしょう。よい人材は翻訳や通訳のコストを削減できる効果も期待できます。
職場の国際化により、日本人社員の意識変化も期待できます。異文化理解の向上やコミュニケーション能力の発達など、組織全体のスキルアップにつながる副次的効果も見逃せません。多様性を受け入れる企業文化の醸成は、優秀な人材の採用にも有利に働くでしょう。
海外展開への足がかり効果
外国人材の採用は、将来的な海外進出の準備としても機能します。現地の商習慣や法規制に詳しい人材を社内に確保できれば、市場調査や現地法人設立の際に大きな助けとなるでしょう。リスクを抑えた段階的な国際化が可能になります。
海外サプライヤーとの取引においても、外国人材の存在は心強い支援となります。言語の壁を越えたスムーズな商談により、より有利な条件での調達や販売が実現できる可能性があります。国際的なネットワークの構築や、新たなサービス展開にも貢献してくれるはずです。
また、外国人材の母国における人脈活用も検討できます。現地での販売代理店探しや技術提携先の発掘など、通常のビジネス手法では困難な案件でも、人的なつながりを通じて成功に導ける場合があります。長期的な企業戦略の一環として外国人雇用を捉えることで、より大きなメリットを享受できるでしょう。
いま、多くの企業がグローバルビジネスの展開を模索しています。人口減少や国内市場の縮小に直面する中で、海外進出は日本企業にとって避けて通れない課題となっています。しかし、国際的な市場で競争力を維持するためには、多様な人材の力が必要です。[…]
外国人雇用の注意点とデメリット

外国人材の採用には多くのメリットがある一方で、特有の課題やリスクも存在します。言語の壁や文化的な違いから生じる問題、そして法的コンプライアンスの複雑さなど、事前の対策が重要になるでしょう。これらの注意点を十分に理解し、適切な対応策を講じることが成功の鍵となります。
参考:出入国在留管理庁 外国人生活支援ポータルサイト「雇用・労働」
言語とコミュニケーションの課題
日本語能力の個人差は、外国人雇用における最も大きな課題の一つです。業務指示の理解不足や報告内容の曖昧さから、作業ミスや安全事故につながる可能性があります。特に製造現場や建設業では、正確な意思疎通が生命に関わる場合もあります。
文書による連絡事項を理解しやすくするための工夫も問題となりがちです。社内メールや業務マニュアルの内容を正しく把握できない場合、重要な情報の見落としや誤解が発生します。多言語対応や図解を活用した説明資料の準備が必要になるでしょう。
コミュニケーションスタイルの違いも注意が必要です。直接的な表現を好む文化圏出身者と、間接的な日本式コミュニケーションの間には大きなギャップがあります。お互いの文化的背景を理解し、適切な伝達方法を模索することが求められます。定期的な面談を通じて、理解度を確認する取り組みも効果的です。
文化的背景の違いへの対応
宗教的な配慮は、外国人雇用において重要な要素となります。イスラム教徒の場合は礼拝時間の確保やハラール食品への対応、ヒンドゥー教徒の場合は牛肉を使用しない食事の提供など、個別の対応が必要になる場合があります。
労働観や時間感覚の違いも調整が必要な点です。残業や休日出勤に対する考え方、有給休暇の取得パターンなど、日本の労働慣行とは異なる価値観を持つ外国人材も少なくありません。柔軟な働き方の導入や相互理解の促進が求められるでしょう。
家族との時間を重視する文化圏出身者の場合、長時間労働や頻繁な出張に抵抗を示すケースもあります。ワークライフバランスの確保や、家族帯同での来日に対する支援なども検討する必要があるかもしれません。事前の説明と合意形成により、トラブルの回避を図りましょう。
法的リスクと不法就労の防止
在留資格の確認不備は、企業にとって深刻な法的リスクをもたらします。不法就労助長罪に問われる可能性があり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。人事担当者本人の責任問題にも発展しかねません。
在留期間の更新手続きも法律上、注意が必要です。更新申請中であっても在留期間を超えて就労させると不法就労となるため、適切な雇用管理が求められます。この類のトラブルを避けるためにも、定期的な在留カードの確認と、更新手続きのサポート体制を整備しておきましょう。
資格外活動の範囲を超えた業務に従事させることも違法行為となります。特に留学生のアルバイトでは、週28時間以内の労働時間制限や風俗営業への従事禁止など、厳格なルールが設けられています。労働時間の適切な管理と、業務内容の事前確認を徹底してください。社内教育を通じて、全ての管理者が法的要件を理解することも重要です。
労働条件と待遇面での配慮
外国人労働者に対する差別的な待遇は、労働基準法違反となる可能性があります。同一労働同一賃金の原則に基づき、日本人と同じ条件での雇用が求めらます。国籍を理由とした不当な扱いは厳に慎まなければなりません。
社会保険への加入も日本人と同様に義務付けられています。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への適切な加入手続きを行い、保険料の事業主負担分も適正に処理してください。手続きの複雑さを理由に加入を怠ると、法的な問題に発展します。
住環境のサポートも重要な課題です。日本での住居確保が困難な外国人材に対し、社宅の提供や賃貸契約の保証など、何らかの支援が必要になる場合があります。生活基盤の安定は、職場でのパフォーマンス向上にも直結するため、長期的な視点での投資と考えるべきでしょう。
関連法律と制度の理解
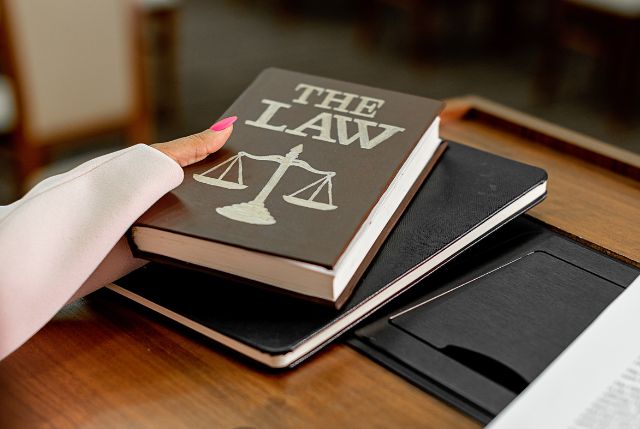
外国人雇用を適切に行うためには、関連する法律や制度の正確な理解が欠かせません。入管法から労働基準法まで、複数の法令が関わる複雑な分野だけに、最新の情報を把握し続ける必要があります。特に近年導入された特定技能制度や、従来からの技能実習制度との違いを明確にしておくことが重要です。
入管法と労働基準法の要点
出入国管理及び難民認定法(入管法)は、外国人の入国から在留資格と就労範囲を定める基本的な法律です。在留資格は29種類に分かれており、それぞれ異なる活動内容と在留期間が設定されています。企業は雇用前に必ず在留資格の種類と就労制限の有無を確認しなければなりません。こうした基本的な概要の理解が不十分なまま手続きが行われると、後に大きな問題となる可能性があります。
労働基準法では、外国人労働者も日本人と同様の保護を受けることが明記されています。最低賃金、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇など、全ての規定が平等に適用されるため、国籍による差別的扱いは一切認められません。
在留資格の変更や更新手続きについても理解が必要です。就労内容が変わる場合や、より長期の雇用を予定する場合は、適切な在留資格への変更申請が求められます。企業としても手続きをサポートし、合法的な就労の継続を支援する体制を整えておくべきでしょう。違反行為は企業の社会的信用を大きく損なう結果につながります。
近年、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中で、グローバル人材、特に外国人労働者の活用が多くの日本企業にとって喫緊の課題となっています。多様な知識や文化を持つ外国人材を受け入れることは、企業の競争力向上やイノベーション創出につながる一方で[…]
特定技能制度の活用方法
2019年に開始された特定技能制度は、人手不足が深刻な16分野で外国人材の受け入れを可能にする制度です。対象となるのは介護、建設、製造業、農業など、幅広い分野で、これらの活用が期待されています。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を、最大5年間雇用できるのが特徴です。
特定技能1号の取得には、技能試験と日本語試験の合格が必要となります。ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されるため、技能実習生からの移行も可能です。企業は受け入れ機関として、支援計画の作成と実施が義務付けられています。
支援内容には、事前ガイダンスの実施、住居確保の支援、生活オリエンテーションの提供、日本語学習の支援など、包括的な項目が含まれます。自社で対応が困難な場合は、登録支援機関に委託することも可能です。制度を活用する企業は、これらの要件を十分に理解し、適切な受け入れ体制を構築する必要があるでしょう。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
技能実習制度との違い
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした国際協力の一環として位置づけられています。最大5年間の実習期間中は、原則として転職や職種変更が認められていません。日本の企業で技能を学び、帰国後に母国での就職に活かすことが期待されています。企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れる仕組みとなっています。
特定技能制度との最大の違いは、転職の可否です。特定技能外国人は同一分野内での転職が可能であり、より柔軟な労働移動が認められています。また、技能実習では禁止されている家族の帯同も、特定技能2号では可能となっています。
制度の目的も異なります。技能実習は、主として開発途上国への技能移転を目的とする一方、特定技能は人手不足の解消を明確に目的としています。そのため、特定技能の方がより実務的な労働力確保の手段として活用しやすいでしょう。企業は自社のニーズに応じて、どちらの制度を活用するかを慎重に検討する必要があります。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
外国人雇用を成功させるポイント

外国人材の採用を成功に導くためには、戦略的なアプローチが不可欠です。採用活動の段階から受け入れ体制の整備、そして長期雇用に向けた支援まで、一貫した取り組みが求められるでしょう。これらのポイントを押さえることで、外国人材の能力を最大限に引き出し、企業の成長につなげることができます。
採用活動と面接のコツ
外国人材の採用では、従来の日本人向け手法とは異なるアプローチが必要です。求人情報は可能な限り多言語化し、海外の求職者にも理解しやすい内容にしましょう。SNSや国際的な求人サイトの活用により、より幅広い候補者にリーチできるはずです。
面接では、言語能力だけでなく、日本での就労に対する意欲や適応力を重視しましょう。求人票の記載通りに、具体的な業務内容や労働条件を詳しく説明し、候補者の理解度を確認することが重要です。文化的な違いによる誤解を防ぐため、十分な時間を確保した丁寧な説明を心がけてください。
実技試験や職場見学の機会を設けることも効果的です。実際の作業環境を見せることで、入社後のミスマッチを防げるでしょう。また、既に勤務している外国人社員との面談機会を提供すれば、候補者の不安解消にもつながります。相互理解を深める採用プロセスを構築することが、長期雇用の基盤となるのです。
外国人材の雇用を検討されている企業の経営者様にとって、特定技能外国人の採用は重要な経営判断の一つです。しかし、「どのような質問をすれば良い人材を見極められるのか」「面接でどうすれば適切な評価ができるのか」「なぜ採用後にミスマッチが起きてしま[…]
受け入れ体制の整備方法
外国人材の受け入れ前に、社内体制の整備を進めておくことが重要です。多言語対応マニュアルの作成、業務手順書の図解化、そして緊急時の連絡体制の構築など、言語の壁を越えた情報共有の仕組みを用意しましょう。
メンター制度の導入も効果的な手法です。経験豊富な日本人社員や、先輩の外国人社員をメンターとして配置し、業務指導だけでなく生活面のフォローも行える体制を構築してください。定期的な面談を通じて、困りごとや要望を早期に把握することが大切です。
職場環境の国際化も進めておきましょう。宗教的な配慮が可能な休憩室の設置、多様な食事メニューの提供、そして異文化理解研修の実施など、外国人材が働きやすい環境を整備してください。日本人社員の意識改革も同時に進めることで、真の多文化共生職場を実現できるでしょう。
長期雇用に向けた支援策
外国人材の定着率向上には、継続的な支援が欠かせません。日本語研修の提供、資格取得の支援、そしてキャリア開発の機会創出など、長期的な成長を支援する制度を整備しましょう。こうした支援にはコストもかかりますが、投資に見合うリターンを得るためには、人材育成への積極的な取り組みが役立ちます。
生活面での支援も重要な要素となります。住居の確保、銀行口座開設の手続き、家族の呼び寄せサポートなど、日本での生活基盤を安定させる支援を提供してください。生活の不安が解消されれば、業務への集中度も向上するはずです。様々な対策を講じるのにどれくらい時間がかかるか、事前に計画を立てましょう。
在留資格の更新手続きや、より安定した資格への変更申請についても、企業としてサポートする体制を整えておきましょう。行政書士などの専門家との連携により、スムーズな手続きを支援できます。外国人材が安心して長期間働ける環境を提供することで、企業への帰属意識も高まり、優秀な人材の流出防止にもつながるでしょう。
森町とフィリピン・アクラン州の外国人雇用連携事例
北海道茅部郡森町は、人口減少と労働者不足を背景に、フィリピンのアクラン州と協力しながら外国人材の雇用促進に取り組んでいます。地域の持続的な発展を目指し、地元企業と連携して人材確保を推進しています。
連携の背景と目的
森町では少子高齢化や都市部への人口流出が進み、地元企業の人手不足が深刻化しています。一方でアクラン州は若年層の失業率が高く、海外での就労を希望する声が多いため、双方の課題解決を目指して今回の連携が実現しました。地域の課題に対しお互いの強みを活かした共生の道を探っています。
調印式と具体的な取り組み内容
2025年2月に森町の岡嶋町長とアクラン州のメラフロレス知事が調印式を行い、外国人材の就労支援に合意しました。現地の大学では日本語教育を支援し、説明会や企業面談も活発に行っています。E-MAN社のオンライン日本語学習ツールも活用し、現地の学生の日本での永住も視野に入れた育成をしています。
外国人材受け入れのメリットと今後の展望
外国人労働者の受け入れは、森町の労働力不足の改善だけでなく、地域活性化にも大きく貢献します。E-MAN会長の三木雅史氏は、地元愛や会社愛を持つ外国人材の育成と長期的な定住支援を今後の重要な課題とし、地域に調和した共存を目指す考えです。
まとめ|外国人雇用で企業成長を実現

外国人雇用は、人手不足の解消だけでなく、企業の国際競争力向上と持続的成長を実現する重要な戦略です。適切な知識と準備のもとで実行すれば、多様性に富んだ強い組織を構築できるでしょう。一般的な採用とは異なる点が多いですが、臆する必要はありません。
成功の鍵は、法的要件の遵守と受け入れ体制の整備にあります。在留資格の確認から労働条件の設定、ハローワークへの届出まで、一つひとつの手続きを確実に実行することが不法就労などのリスクを回避する基本となります。
また、言語や文化の違いを理解し、それらを組織の強みに変える取り組みが重要です。多言語対応の業務マニュアル整備、メンター制度の導入、そして継続的な日本語教育の提供など、外国人材が能力を最大限発揮できる環境作りに投資しましょう。
長期的な視点での人材育成と支援により、外国人材は企業にとって貴重な戦力となります。海外展開の足がかりとしての活用や、多様性がもたらすイノベーションの創出など、単なる労働力以上の価値を期待できるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。