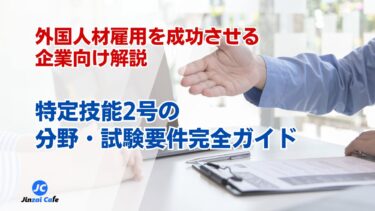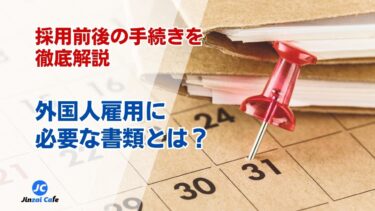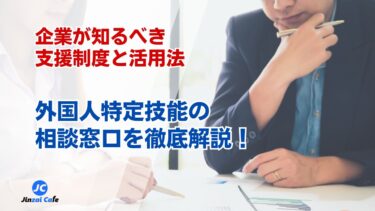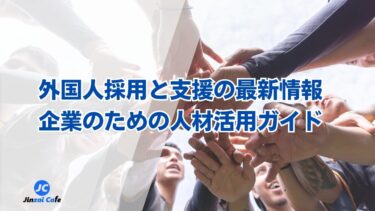建設業界では深刻な人手不足が続き、多くの会社が現場の安定稼働に不安を抱えています。その解決策のひとつが「特定技能制度」であり、即戦力となる人の確保が急務です。とくに特定技能2号は、長期的な雇用や家族帯同が可能となり、企業にとって安定した人材確保の手段となります。この記事では、建設分野における2号の仕組みや取得要件、活用のポイントをわかりやすく解説していきます。
特定技能制度の概要と建設分野

特定技能制度は、深刻な人手不足を補うために2019年4月に創設されました。本制度は現在16分野を対象としており、その中には建設分野も含まれています。建設業では現場作業から管理まで幅広い役割を担える人材を確保することを目的としており、制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分されます。
2022年11月からは建設分野において2号の運用も開始され、長期在留や家族帯同が認められることで、企業にとって安定した人材確保の手段となっています。
特定技能制度の背景と目的
現在、日本の建設業界は、高齢化や若手人材の不足により深刻な人手不足に直面しています。国はその解決策として、外国人材が即戦力として働ける「特定技能制度」を創設しました。この制度は、育成を主目的とする技能実習制度とは異なり、即戦力としての活躍を期待するものです。
その目的は、単に労働力を補充するだけでなく、一定の技能水準を持つ人材を受入れ、現場の安全性や品質を維持することにあります。特に建設分野では、技能検定や評価基準を通じて能力を確認し、安定した人材確保を目指しています。
建設分野が対象となった理由
建設業が特定技能制度の対象に選ばれたのは、人手不足が最も顕著で社会基盤に直結する産業だからです。道路や橋梁、建築物、ライフライン工事等、社会生活を支える業務には、とび作業やコンクリート圧送といった専門業務が不可欠であり、これらが停滞すれば経済活動全体に影響が及びます。
そのため、国土交通省は制度設計において建設業を重要分野に位置づけました。企業にとっては、必要な技能を持つ外国人材を確保することで、事業の継続性や品質の安定が期待できるのです。
参考:一般社団法人日本建設業連合会 建設業デジタルハンドブック
近年、建設業界では深刻な人手不足が課題となっています。少子高齢化の影響もあり、若手人材の確保は年々難しくなっており、「このままでは事業の継続が危うい…」と頭を抱える経営者の方も少なくないのではないでしょうか。特に、現場の技能者の高齢化は顕著[…]
特定技能2号の取得要件と条件
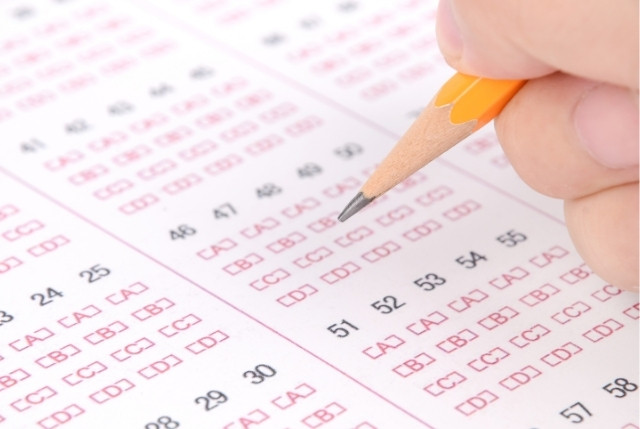
特定技能2号は、1号からのステップアップとして高度な技能と経験を求められる在留資格です。取得を希望する者は、試験合格や一定の国内での就労年数など、厳格な条件をクリアする必要があります。さらに、家族帯同や在留資格の更新が可能であり、長期的な就労を前提とした制度設計が特徴です。人材確保を目指す企業は、この制度の活用を検討する価値が十分にあるでしょう。
2号取得に必要な試験・技能レベル
特定技能2号を取得するためには、建設分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する必要があります。求められる技能レベルは技能検定1級に相当し、非常に高度なものです。試験内容は専門的な作業知識に加え、安全管理や工程管理など現場全体を把握する力も求められます。
ただし、実践的な指導能力については試験科目には明記されておらず、指導的役割を担う能力は、試験合格に加えて現場での班長や職長としての実務経験を通じて評価されます。実技試験では高い水準の技能が求められ、単なる補助作業者ではなく指導的役割を果たせるかが重視されます。これらの要件を満たすことが、特定技能1号から2号への移行を可能にする条件です。
参考:国土交通省 「建設分野特定技能2号評価試験」試験実施要領
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
就労年数や実務経験の確認方法
2号の取得には、1号での就業経験や実務の積み重ねが不可欠です。一般的には、一定日数以上の継続就労や技能検定の合格によって能力を証明します。企業は、対象者が所属する現場での勤務実績を通じて、要件を満たしているかを確認する必要があります。
加えて、登録支援機関や関係機関と連携しながら、書類の正確性を担保することも重要です。適切な確認手続きによって、移行申請が円滑に進められるでしょう。
家族帯同や更新制度の特徴
特定技能2号は、長期的な在留を前提にしているため、家族の帯同を受け入れることが認められている点が大きな特徴です。これにより外国人材が安心して日本で生活を築き、職場への定着率も高まります。
また、在留資格の更新に制限がなく、長期的なキャリア形成が可能となります。企業側にとっても、経験豊富な人材を継続的に確保できるメリットがあり、結果として現場の安定と生産性向上につながるのです。
建設業における対象職種と業務内容

特定技能2号の対象となる建設分野は、多様な現場で必要とされる技能を網羅しています。土木や建築に加え、ライフラインや設備に関連する業務まで幅広くカバーしており、それぞれに専門性の高い作業が含まれます。企業は対象区分や評価基準を正しく理解することで、適切な人材配置やキャリア形成の支援が可能になるでしょう。
建設3区分の特徴と対象業務
建設分野は大きく「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つに分類されます。土木区分では道路や橋梁などのインフラ施設の工事、建築区分では住宅やビルの施工が中心です。
一方、ライフライン・設備区分は電気通信や上下水道といった生活基盤の維持に直結します。これらはいずれも国土交通省が定めた基準に基づき、技能検定や実務経験を通じて適性が評価されます。企業は必要な区分を見極めて採用を進めることが重要です。
技能検定・評価基準の位置づけ
対象業務に従事するには、技能検定や評価試験で一定の水準を満たす必要があります。これにより、現場で必要な知識や作業能力を客観的に確認できます。評価基準には、施工の精度や安全意識の高さが含まれており、外国人材が単なる作業員ではなく、現場の一員として責任を担えるかどうかが重視されます。
企業にとっても、技能検定の結果は、採用後の育成計画や配置判断の参考として活用できる指標となるでしょう。
施工管理や班長などキャリアアップ例
特定技能2号を取得した人材は、単に作業を行うだけでなく、班長や職長といった指導的役割を担うことが期待されています。現場での施工管理や後輩への技能指導など、責任ある業務に関与するケースも増えています。
こうしたキャリアアップは、本人にとってモチベーション向上につながり、企業にとっては中核人材の育成につながるでしょう。長期的な雇用を前提とする2号だからこそ、キャリア形成の可能性が広がるのです。
参考:国土交通省 建設分野の2号特定技能外国人に求める実務経験等について
申請から受入れまでの流れ

特定技能2号の人材を採用するには、企業が制度に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。登録支援機関の活用や雇用契約の整備、必要書類の提出など、複数の段階を経て受入れが完了します。各ステップを理解しておくことで、申請時の不備や時間的なロスを防ぎ、スムーズな受入れが可能となるでしょう。
登録支援機関の役割と利用方法
外国人材の受入れにあたり、企業がすべての手続きを単独で行うのは負担が大きいです。そこで重要となるのが登録支援機関の存在であり、これは民間団体や法人が担っています。例えば一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のような機関も情報提供を行っています。
支援機関は、制度に関する詳細な説明や、生活支援、日本語教育のサポート、行政への手続き代行などを担います。企業は適切な支援機関を選定し、役割分担を明確にすることで、受入れ体制を強化できます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
雇用契約・申請手続きの流れ
受入れの第一歩は、外国人材との雇用契約を締結することです。契約内容には労働条件や業務内容を明記し、法令で定められたとおりの形式で行われる必要があります。その後、入管庁への在留資格申請を実施し、審査を経て許可が下ります。
申請には雇用契約書や受入計画の書類が必要であり、正確かつ詳細な記載が求められます。企業が準備を怠ると審査に時間がかかるため、事前確認を行ったうえで進めることが不可欠です。
参考:国土交通省 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】
必要書類・確認事項のまとめ
申請時には、多くの書類が必要となります。以下に挙げる雇用契約書、在留資格変更許可申請書、受入れ計画書、登録支援機関との契約書等が主なものです。提出書類はpdf形式での提出が求められる場合もあります。
さらに、従事予定業務に係る資料や技能検定の合格証明も確認対象となります。書類は一部でも不備があれば受理されない可能性があるため、作成と確認を慎重に進める必要があります。社内チェックに加えて、専門機関の助言を受けることも有効でしょう。
グローバル化が進む現在、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。しかし、多くの人事担当者が「外国人を採用したいけれど、どんな書類が必要なのかわからない」「手続きでトラブルを起こしたくない」といった不安を抱えているのではないでしょ[…]
企業が直面する課題と支援体制
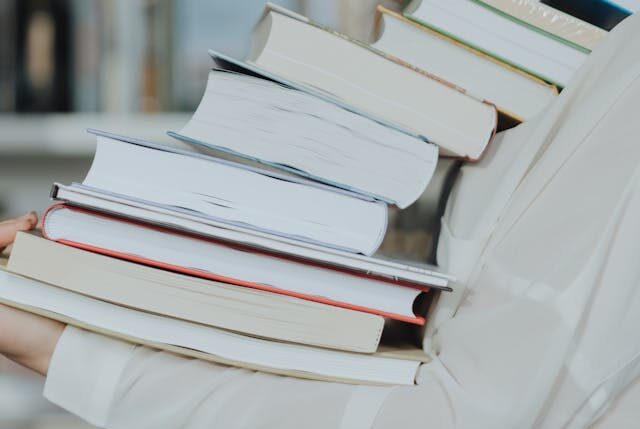
外国人材を受入れる際、企業は言語や文化の違い、安全管理など多くの課題に直面します。とくに建設分野では現場の危険性が高く、十分な指導体制が欠かせません。こうした課題を解決するために、国や登録支援機関による多様なサポート制度が用意されています。企業は制度を効果的に活用することで、受入れのリスク軽減が可能となります。
日本語教育と安全指導のポイント
現場でのコミュニケーション不足は、緊急時に大きなリスク要因となります。日本語教育を計画的に実施することで、作業指示の理解度や安全意識が向上します。
また、危険を伴う作業が多い建設現場では、事故防止のための安全指導が不可欠です。具体的には、マニュアルの多言語化や映像教材の活用が有効でしょう。企業が積極的に教育体制を整えることで、外国人材が安心して働ける環境が整います。
日本の多くの会社が直面している最大の課題のひとつは、人手不足です。特に介護や製造、建設などの特定技能分野では、外国人労働者の採用が急速に拡大しており、その事業規模も大きくなっています。しかし、その一方で職場における日本語でのコミュニケーショ[…]
生活支援・家族帯同への対応策
特定技能2号では家族帯同が認められており、生活支援の充実が定着率に直結します。住居の確保や地域との交流機会の提供は、安心して生活を送るうえで重要です。
さらに、医療や教育面での情報提供を行うことも必要です。企業が主体的に生活支援を行うことで、外国人材とその家族が地域社会に溶け込みやすくなり、長期的な雇用継続にもつながります。
国土交通省や機構による支援制度
建設分野における特定技能の運用は、国土交通省や出入国在留管理庁の監督のもとで進められています。これらの機関は国の方針に基づきガイドラインを示し、登録支援機関を通じて企業や外国人材をサポートします。
さらに、研修プログラムや相談窓口も整備されており、制度の適正な運用を後押ししています。企業はこうした制度を把握し、必要に応じて活用することで、受入れの負担を大きく軽減できるでしょう。
参考:出入国在留管理庁 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は重要な選択肢の一つです。しかし、複雑な制度内容や手続きに関して「どこに相談すればよいのか分からない」「適切な支援を受けられるのか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も多いの[…]
【活用事例】人材定着とリーダー育成を実現した企業の取り組み
株式会社nonakaは、2008年から特定技能2号を含む外国人材の受入れを進めている建設分野の成功事例です。同社にはすでに特定技能2号取得者が在籍しており、彼らは班長やリーダーとして現場を牽引しています。労働環境の改善や安全教育の徹底により、日本人社員の不安を払拭しながら外国人労働者を育成しています。
特に、特定技能2号を目指すベトナム人スタッフがキャリアアップを目指して日々努力しており、企業の持続的な成長と安定した人材確保につながっています。
参考:JAC特定技能導入事例集 ヴィジョニスタ 外国人材受入れの成功事例【株式会社nonaka】
近年、日本では人手不足が深刻化し、多くの企業が外国人材の採用を検討するようになっています。特に中小企業では、国内での人材確保が難しいため、外国人労働者の活用が避けられない状況になりつつあります。とはいえ、採用や雇用管理に関する制度は複雑で、[…]
まとめ|建設分野における特定技能2号の活用

特定技能2号は、建設業における深刻な人手不足を補い、長期的に安定した人材確保を可能にする制度です。必要な研修を修了し、取得要件や申請の流れ、支援体制を正しく理解すれば、外国人材の受入れは企業の成長戦略に直結します。今後はキャリア形成や定着支援を重視し、制度を積極的に活用していくことが求められるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ホームページをご覧の上、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。問合せフォームからご連絡いただければ、企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介いたします。