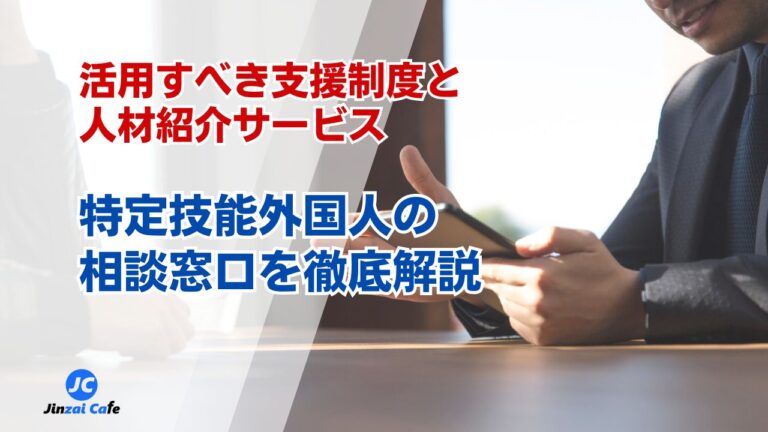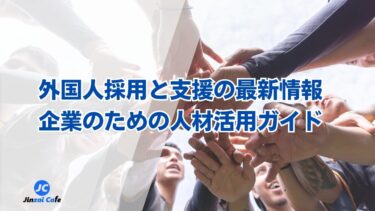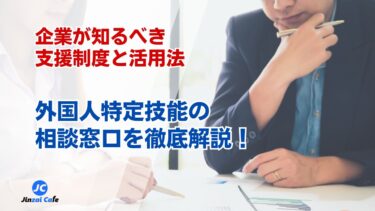深刻化する人材不足に直面している企業にとって、特定技能外国人の受入れは有力な解決策となっています。しかし、制度の複雑さや手続きの煩雑さから、どこに相談すればよいのか分からず、一歩を踏み出せない経営者の方も多いのではないでしょうか。特定技能外国人の受入れには、在留資格の取得から雇用管理、生活支援まで幅広い知識が求められます。
本記事では、公的機関から民間サービスまで、特定技能外国人に関する相談窓口を網羅的に解説し、経営者の皆様が適切な支援を受けられるよう、実践的な情報を提供していきます。
特定技能制度と相談窓口の全体像

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、人材不足が深刻な16分野において外国人材の受入れを可能にする制度です。製造業や建設業、介護分野など、色々な業種で活用が進んでいます。
この制度を活用するには、在留資格の申請手続き、雇用契約の締結、支援計画の作成など、多岐にわたる業務への対応が必要となります。そのため、制度の理解から実際の受入れまで、適切な相談窓口を活用することが成功の鍵となるでしょう。
特定技能制度の基本と受入れ要件
特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ受入れ可能な分野や在留期間が異なります。特定技能1号は、特定の産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が対象で、在留期間は通算5年までとなっています。
受入れ企業には、適切な報酬の支払い、日本人と同等以上の待遇、支援体制の整備などが義務付けられており、これらの要件を満たさなければなりません。また、外国人材には技能試験と日本語試験の合格が求められるため、採用前の段階から計画的な準備が重要です。
相談窓口の種類と役割分担
特定技能外国人に関する相談窓口は、大きく分けて公的機関、業界団体、民間サービスの3つに分類されます。それぞれの特徴と役割を以下の表で整理しました。
| 窓口の種類 | 主な機関 | 相談内容 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 公的機関 | 出入国在留管理庁、外国人技能実習機構(OTIT)、自治体窓口 | 制度の基本情報、在留資格申請、法的手続き | 無料 | 正確な制度情報、公正な立場からの助言 |
| 業界団体・協同組合 | 業界別協同組合、登録支援機関 | 業界特有の課題、実務的アドバイス、支援業務 | 一部有料 | 業界の実績とノウハウ、同業他社の事例 |
| 民間サービス | 人材紹介会社、総合サポート企業 | 人材募集、マッチング、包括的サポート | 有料 | スピード感、個別ニーズへの柔軟な対応 |
※横スクロールできます→
それぞれの窓口には特徴があるため、相談内容や企業の状況に応じて使い分けることが効果的でしょう。初期段階では公的機関で基礎知識を習得し、具体的な受入れ段階では業界団体や民間サービスを活用するという流れが一般的です。
参考:
特定技能総合支援サイト
出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等
相談窓口を活用すべきタイミング
相談窓口の活用は、特定技能外国人の受入れを検討し始めた初期段階から重要となります。制度の概要を理解する段階では、公的機関の相談窓口で基礎知識を得ることから始めるとよいでしょう。具体的な受入れ計画を立てる段階では、業界団体や登録支援機関に相談し、自社の業種に適した受入れ方法を確認することが求められます。
また、実際に外国人材の採用活動を開始する際には、民間の人材紹介会社の活用も検討すべきです。受入れ後も、在留資格の更新時や労務管理上の疑問が生じた際には、適切な相談窓口に問い合わせることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
近年、日本では人手不足が深刻化し、多くの企業が外国人材の採用を検討するようになっています。特に中小企業では、国内での人材確保が難しいため、外国人労働者の活用が避けられない状況になりつつあります。とはいえ、採用や雇用管理に関する制度は複雑で、[…]
公的機関と業界団体の相談窓口

公的機関や業界団体が提供する相談窓口は、特定技能外国人の受入れにおいて最も基本的な情報源となります。これらの窓口では、制度の正確な情報や法令に基づいた手続きの案内を無料で受けることができるため、初めて外国人材の受入れを検討する企業にとって心強い存在です。
国の機関から地方自治体、業界特有の支援を行う団体まで、目的に応じて適切な窓口を選択することで、効率的に必要な情報を得ることができるでしょう。
国・自治体の相談窓口一覧
出入国在留管理庁では、特定技能制度に関する総合的な相談窓口を設置しており、在留資格の申請手続きや制度の概要について、電話やメールで問い合わせることができます。
外国人技能実習機構(OTIT)は、技能実習から特定技能への移行に関する相談や、外国人材の労働条件に関する相談を受け付けている機関です。また、東京都新宿区には外国人在留支援センター(FRESC)が設置されており、出入国在留管理庁をはじめ、法テラス、ハローワーク等の関係機関がワンストップで相談に対応しています。
各都道府県や市区町村でも外国人相談窓口が設置され、多言語での対応や生活支援に関する情報提供を行っているケースが多いです。以下の表に主要な公的相談窓口をまとめました。
| 機関名 | 相談内容 | 対応言語 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 出入国在留管理庁相談窓口 | 在留資格、制度概要、申請手続き | 日本語、英語等 | 平日9:00-17:00 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 技能実習、特定技能への移行、労働条件 | 日本語、多言語対応 | 平日9:00-17:00(祝日除く) |
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 在留手続き、雇用、医療、福祉、出産・育児等の総合相談 | 14言語対応 | 平日9:00-17:00 |
| 外国人在留総合インフォメーションセンター | 在留手続き全般、生活情報 | 14言語対応 | 平日8:30-17:15 |
| 各自治体の外国人相談窓口 | 生活支援、行政手続き、日常生活相談 | 自治体により異なる | 自治体により異なる |
※横スクロールできます→
各機関の詳細な電話番号や相談内容については、それぞれの公式ウェブサイトの相談窓口案内ページで確認できます。初めて相談する際には、事前に各機関のページを確認し、相談内容に応じた適切な窓口を選択することをお勧めします。
FRESCは特に、複数の支援機関が一箇所に集まっているため、様々な相談を効率的に行いたい企業にとって便利な窓口となるでしょう。
参考:
外国人技能実習機構 技能実習生の皆様へ
出入国在留管理庁 外国人在留支援センター(FRESC)
出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等
業界団体と登録支援機関
業界団体や協同組合は、各分野に特化した実践的な相談対応を行っています。製造業であれば製造業に特化した協同組合、建設業であれば建設業の業界団体が、それぞれの業界特有の課題や受入れノウハウを提供しているのです。
登録支援機関は、特定技能外国人の支援計画の作成や実施を委託できる機関として、出入国在留管理庁に登録されています。自社で支援体制を整備することが難しい企業は、登録支援機関に委託することで、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を適切に実施できるでしょう。
登録支援機関を選ぶ際には、対応可能な分野、実績、サポート内容、費用などを比較検討することが大切です。
各窓口の特徴と使い分け
公的機関の相談窓口は、制度の基本情報や法的な手続きに関する正確な情報を得たい場合に最適です。費用がかからず、公正な立場からのアドバイスを受けられる点が大きなメリットとなります。業界団体や協同組合は、同業他社の受入れ事例や業界特有の課題への対処法など、より実務的な相談に適しているでしょう。
登録支援機関は、実際の支援業務を委託したい企業や、自社での支援体制構築に不安がある企業に向いています。初期段階では公的機関で基礎知識を習得し、具体的な受入れ計画の段階では業界団体や登録支援機関に相談するという流れが効率的です。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
民間人材紹介サービスの活用法

民間の人材紹介会社は、特定技能外国人の募集から採用、受入れ後のフォローまで、一貫したサポートを提供しています。公的機関が制度の説明や手続きの案内を中心とするのに対し、民間サービスは実際の人材マッチングや企業の個別ニーズに応じた柔軟な対応が特徴です。
スピード感を持って外国人材を確保したい企業や、受入れ経験が少なく包括的なサポートを求める企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。
民間サービスの種類と特徴
民間の人材紹介サービスは、提供する内容や料金体系によって複数のタイプに分類されます。以下の表で各サービスの特徴を比較してみましょう。
| サービス種類 | 主な内容 | 料金体系 | 適している企業 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介型 | 企業ニーズに合った外国人材を紹介し、マッチング支援を実施 | 成功報酬型(年収の20〜30%) | 直接雇用を希望する企業、採用後は自社で管理できる企業 |
| 人材派遣型 | 外国人材を派遣社員として提供、一定期間後の直接雇用も可能 | 月額料金制 | まず試用期間を設けたい企業、派遣から始めたい企業 |
| 登録支援機関型 | 支援計画の作成・実施を代行、生活支援や相談対応を提供 | 月額固定費(2〜3万円/人) | 自社で支援体制を構築できない企業、初めて受入れる企業 |
| 総合サポート型 | 採用から受入れ、支援まで全てを一括で提供 | 初期費用+月額費用 | 包括的なサポートを求める企業、人事リソースが限られる企業 |
※横スクロールできます→
これらのサービスは、それぞれ異なる強みを持っています。海外に拠点を持ち現地での採用活動をサポートする会社や、特定の国や地域に特化した会社など、専門性も様々です。自社の状況やニーズに合わせて最適なサービスを選択することが、成功への第一歩となるでしょう。
人材紹介会社の選定基準
人材紹介会社を選定する際には、以下のポイントを重点的にチェックする必要があります。
- 実績と信頼性
- 対応可能な国籍と言語
- 受入れ後のサポート体制
- 料金体系の明確性
- 担当者の専門知識
これらの基準を満たす会社を選ぶことで、ミスマッチを防ぎ、長期的な雇用の安定につながります。実績と信頼性では、特定技能外国人の紹介実績が豊富で、自社の業種や職種での受入れ経験があるかを確認しましょう。
対応可能な国籍と言語については、希望する国籍の人材を確保でき、必要な言語でのコミュニケーションが可能かが重要です。受入れ後のサポート体制では、在留資格の更新、日本語教育、生活面のトラブル対応など継続的なフォローがあるかをチェックする必要があります。
料金体系の明確性は、初期費用、月額費用、追加費用の条件が事前に明示されているかを確認すべきポイントです。担当者の専門知識については、特定技能制度や入管法に精通し、適切なアドバイスができるかを見極めることが大切でしょう。
会話トレーニングコースではN5〜N3の日本語レベルに応じて、会話に必要な日本語の使い方を学ぶことで、日常的な会話を理解し…
費用対効果と活用戦略
民間サービスの利用には費用が発生しますが、その費用対効果を適切に評価することが大切です。
人材紹介の場合、一般的に年収の20〜30%程度が紹介手数料の相場となっており、登録支援機関への委託費用は月額2〜3万円程度が目安となります。これらの費用は一見高く感じられるかもしれませんが、自社で採用活動や支援体制を構築するコストと比較して判断する必要があるでしょう。
また、民間サービスと公的機関を組み合わせて活用する戦略も効果的です。制度の基本情報は公的機関で収集し、実際の人材確保は民間サービスを利用するという使い分けにより、コストを抑えながら効率的な受入れを実現できます。初めての受入れでは民間サービスを活用してノウハウを蓄積し、2人目以降は自社で対応するという段階的なアプローチも検討に値するでしょう。
日本企業を取り巻く人材不足の深刻化により、多くの企業経営者が自社に合う人材を探し、新たな解決策を模索しています。特に製造業、介護業界、建設業界では、労働力確保が喫緊の課題となっており、従来の採用方法だけでは必要な人材を確保することが困難な状[…]
人材紹介サービスを利用する際、「違約金」という言葉を契約書で目にして不安を感じたことはありませんか。特に外国人材の採用を検討している企業では、採用後の定着率や契約内容について慎重になる必要があります。違約金は、契約違反があった場合などに、職[…]
相談窓口の効果的な活用実践ガイド

相談窓口を最大限に活用するためには、事前の準備と戦略的なアプローチが欠かせません。適切な情報を整理し、明確な質問を用意することで、相談時間を有効に使い、必要な回答を得ることができます。
また、複数の相談窓口を目的に応じて使い分けることで、より包括的な支援を受けられるでしょう。ここでは、実際に相談窓口を利用する際の具体的な手順とノウハウを解説していきます。
相談前の準備と必要書類
相談窓口を訪れる前に、自社の状況を整理し、必要な情報や書類を準備しておくことが重要です。
- 自社の事業内容と受入れ予定の職種
- 希望する外国人材の人数と国籍
- 受入れ時期と雇用条件の概要
- 現在の支援体制の有無
- 予算と費用負担の範囲
これらの項目を事前に明確にしておくことで、相談担当者は適切なアドバイスを提供しやすくなります。特に初回相談では、会社案内や事業概要が分かる資料を持参すると、より具体的な提案を受けられるでしょう。
また、過去に外国人材を雇用した経験がある場合は、その際の課題や成功事例もまとめておくと有益です。登録支援機関や民間サービスに相談する際には、見積もり比較のために複数社に同じ条件を提示できるよう、情報を統一しておくことをお勧めします。
効果的な相談の進め方
相談を効果的に進めるためには、質問を具体的にし、優先順位をつけることが大切です。
- 制度理解に関する基本的な質問
- 自社の状況に応じた具体的な手続き
- 費用や期間の見積もり
- トラブル事例と対処法
- 次のステップと必要な行動
限られた相談時間を有効活用するため、最も知りたい内容から順番に質問していきましょう。相談中はメモを取り、担当者の名前や連絡先も記録しておくと、後日の追加質問がスムーズになります。
また、口頭での説明だけでなく、可能であれば資料やパンフレットをもらっておくと、社内での情報共有に役立つでしょう。相談後は、得られた情報を整理し、不明点があれば早めに再度問い合わせることで、理解を深めることができます。
複数窓口の併用とトラブル対処
複数の相談窓口を戦略的に併用することで、より充実した情報とサポートを得ることができます。
- 公的機関で制度の基礎知識を習得
- 業界団体で実務的なノウハウを収集
- 民間サービスで人材確保を実施
- 定期的な相談で継続的な支援を受ける
- トラブル発生時の迅速な相談先確保
それぞれの窓口には得意分野があるため、目的に応じて使い分けることが効率的です。
例えば、制度の法的解釈については公的機関が最も信頼できる情報源となり、実際の運用面では業界団体の経験値が参考になるでしょう。相談内容や進捗状況を記録しておくことで、どの窓口でどのような回答を得たかが明確になり、情報の整理がしやすくなります。
また、緊急時の連絡先リストを作成し、労働問題、在留資格問題、生活トラブルなど、問題の種類ごとに適切な相談先を把握しておくことで、迅速な対応が可能となるでしょう。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は重要な選択肢の一つです。しかし、複雑な制度内容や手続きに関して「どこに相談すればよいのか分からない」「適切な支援を受けられるのか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も多いの[…]
まとめ|特定技能外国人の相談窓口を戦略的に活用しよう

特定技能外国人の受入れを成功させるためには、適切な相談窓口の活用が不可欠です。本記事では、公的機関、業界団体、民間サービスという3つのカテゴリーの相談窓口について、それぞれの特徴と活用方法を解説してきました。
出入国在留管理庁や外国人技能実習機構などの公的機関は、制度の正確な情報と法的な手続きに関する相談に適しており、無料で利用できる点が大きなメリットです。業界団体や協同組合は、各業界特有の実務的なノウハウを提供し、登録支援機関としての役割も担っています。
民間の人材紹介サービスは、人材確保から受入れ後のサポートまで包括的な支援を提供し、スピード感のある対応が特徴となっているでしょう。これらの相談窓口を目的に応じて戦略的に使い分けることで、効率的な外国人材の受入れが実現できます。人材不足という経営課題の解決に向けて、まずは公的機関への相談から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。