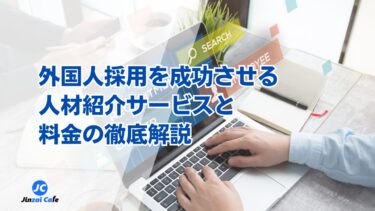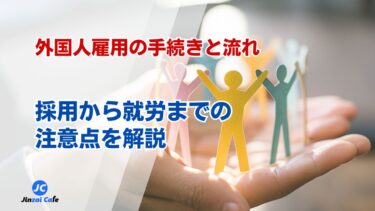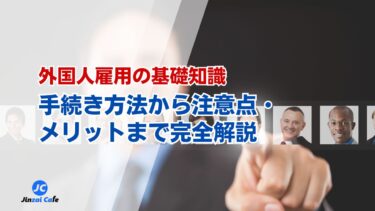人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討する企業が急増しています。しかし、「実際にどれくらいの費用がかかってくるのか」「予想以上にコストが膨らんでしまうのでは」といった不安を抱く経営者の方も多いのではないでしょうか。外国人採用は確かに日本人採用とは異なる費用構造があり、事前の理解なしに進めると想定外の出費に直面するケースも少なくありません。
本記事では、外国人材の採用から雇用定着まで、企業が負担する費用の全体像を詳しく解説します。人材紹介会社の手数料から在留資格手続き、受け入れ環境整備まで、具体的な相場とともに紹介していきます。さらに、助成金の活用や効率的な支援体制構築など、コストを抑える実践的な方法もお伝えします。この記事を読むことで、外国人採用の費用計画を立てる際に知っておくべきポイントがわかるはずです。ぜひ、貴社の採用戦略のお役立ち情報としてご活用ください。
外国人採用でかかる費用の全体像

外国人材を雇用する際の費用は、採用活動から実際の業務開始、そしてその後の継続的な支援まで多岐にわたります。この記事の目次でも示しているように、本章ではまず費用の全体像を解説し、その後で採用方法や手続き別の詳細なコストについて触れていきます。
多くの企業が見落としがちなのは、採用時の一時的な費用だけでなく、長期的に発生する継続費用も含めた全体的なコスト設計です。特に初めて外国人採用を行う企業では、社内体制の整備や各種手続きの学習コストも発生するため、想定より高額になる傾向があります。この学習コストが、主な想定外費用の原因となることも少なくありません。
初期費用と継続費用の違い
外国人採用では、雇用開始までにかかる「初期費用」と、雇用後に毎月発生する「継続費用」の2種類のコストが存在します。初期費用は採用決定から着任までの諸費用、継続費用は支援や管理など長期的に必要となるものです。下記に主な費用項目と目安をまとめます。
| 費用区分 | 主な項目 | 具体例・金額相場 | 発生タイミング | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 人材紹介会社手数料 | 20万~50万円/1人、年収の30%~50% | 採用決定時 | 年収300万円の場合、90万~150万円も |
| 登録支援機関への初期委託費 | 10万~20万円/1人 | 雇用開始前 | 支援計画、生活オリエン等含む | |
| 在留資格申請・行政書士報酬 | 10万~20万円/件 | 採用~雇用開始前 | 申請手続きの外部委託に必要 | |
| 住居確保(敷金・礼金・仲介手数料等) | 20万~30万円/1人 | 雇用開始前 | 家賃補助や社宅の場合は一部企業負担 | |
| 家具・家電準備費用 | 10万~15万円/1人 | 雇用開始前 | 基本生活品一式の目安 | |
| 書類翻訳費用 | 数千円~数万円 | 随時 | 学歴証明等に必要 | |
| 入国時オリエンテーション費 | 2万~4万円/1人 | 雇用開始時 | 通訳追加時は+1万~2万円 | |
| 健康診断 | 5,000円~1万円/1人 | 雇用開始前 | 業種で金額変動 | |
| 生活手続きサポート(口座・携帯等) | 1万~2万円/1人 | 雇用開始時 | ||
| 初期費用合計目安 | 30万~100万円/1人 | 採用~雇用開始まで | ||
※横スクロールできます→
| 費用区分 | 主な項目 | 具体例・金額相場 | 発生タイミング | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 継続費用 | 登録支援機関への月額委託料 | 2万~4万円/月/1人 | 雇用期間中毎月 | 定期面談・届出代行等 |
| 定期的な面談・相談対応費 | 1万~2万円/月/1人 | 雇用期間中必要に応じて | 外部委託・通訳利用時 | |
| 在留資格更新・変更手続き費(行政書士報酬) | 5万~10万円/件 | 更新・変更時 | 定期発生(1年ごと等) | |
| 在留資格更新・変更の法定手数料 | 5,500円~6,000円/件 | 更新・変更時 | 2025年以降料金 | |
| 継続費用合計目安 | 月額3万~5万円/1人 | 雇用中毎月 | 支援委託料+サポート費 | |
※横スクロールできます→
※金額や項目は条件により変動します
費用が発生するタイミング
外国人採用の費用発生の流れを理解しておくことは、キャッシュフローの管理において非常に重要です。まず採用決定と同時に発生するのが、人材紹介会社への成功報酬や在留資格申請費用です。これらは通常、雇用開始の1か月から2か月前後に支払う必要があります。住居の確保についても、外国人材の来日前に契約を完了させる必要があるため、敷金礼金や初月家賃の支払いが先行します。
雇用開始後には、毎月の給与に加えて登録支援機関への委託料、定期的な研修費用などが継続的に発生します。さらに在留資格の更新時期には、再び申請手数料や行政書士への報酬が必要になります。このように、外国人採用では日本人採用と比べて費用の発生タイミングが複雑で、事前の資金計画が欠かせません。適切な予算管理のためには、最低でも雇用開始から1年以上の期間を見据えた費用スケジュールを作成しておくことをおすすめします。
企業規模による費用の変動
企業規模によって外国人採用にかかる費用構造は大きく異なります。大企業、例えば従業員数が1000名を超えるような株式会社の場合、採用人数が多いため、複数名の同時採用により人材紹介会社との交渉で手数料率を下げることが可能で、1名あたりのコストを抑えられる傾向があります。また、社内に人事部門や法務部門が充実している場合、外部への委託費用を削減できる部分も多くあります。一方で、受け入れ環境の整備には相応の投資が必要で、外国人専用の研修プログラムや多言語対応システムの導入に数百万円を要することも珍しくありません。
中小企業では1名あたりの採用コストは高くなりがちですが、コスト管理と手厚いサポートの両立を目指し、小回りの利く柔軟な対応が可能です。例えば、経営層との距離が近く、外国人材が抱える問題や要望に対して迅速な意思決定ができる点は大きな強みです。このような細やかな対応が信頼関係を築き、早期離職を防ぐことで、結果的に再採用にかかるコストを抑制することに繋がります。ただし、専門知識を持つ人材が不足しているため、行政書士や登録支援機関への依存度が高く、外部委託費用がかさむ傾向にあります。企業規模に応じて最適なコスト配分を検討することが、効率的な外国人採用実現の鍵となるでしょう。
採用方法別の費用相場を比較

外国人材の募集方法は大きく分けて人材紹介会社の利用、企業による直接採用、登録支援機関を通じた採用の3つがあります。今回は、それぞれの採用方法別に費用相場を比較してみましょう。特定の業種によって採用の特徴も大きく異なるため、新卒採用か中途採用かによっても、最適なプランは異なります。それぞれ費用構造や期待できる効果が異なるため、自社の状況に最適な方法を選択することが重要です。
人材紹介会社利用時の費用
では、成功報酬として想定年収の25%から35%程度の手数料が発生します。例えば年収300万円の人材を採用する場合、75万円から105万円の費用が必要になる計算です。この手数料には、人材のスクリーニングや面接調整、基本的な在留資格確認などのサービスが含まれています。ただし、在留資格の申請代行や来日後の生活支援については別途費用が発生するケースが多く、追加で20万円から50万円程度を見込んでおく必要があります。
各種メディアが発表する人材紹介会社のランキングで常にtopクラスに位置するような大手では、豊富な候補者データベースと専門的なマッチング機能により、企業の求める経験やスキルといった条件に合った人材を効率的に紹介してもらえます。しかし、その分手数料も高く設定されており、中小規模の紹介会社と比べて10%から15%程度高額になることも珍しくありません。一方、特定の業界や職種に特化した紹介会社を利用することで、より適切な人材を紹介してもらいながら費用を抑制できる可能性もあります。
人手不足が続くなか、今や外国人の採用・雇用を本格的に検討する企業が増えています。とはいえ、関連情報の収集から、在留資格の確認や手続き、言語・文化の違いへの対応、入社後のフォローまでを自社だけで完結させるのは負担が大きいのも事実でしょう。採用[…]
直接採用における費用
企業が独自に外国人材を直接採用する場合、人材紹介会社への手数料は不要ですが、その分社内でのリソース投入が必要になります。自社のウェブサイトやSNSを活用し、企業の魅力を伝える求人広告の多言語対応費用として月額10万円から30万円程度、外国人向け求人サイトへの掲載料として1案件あたり5万円から15万円程度が相場です。また、採用イベントへの出展費用も考慮に入れる必要があります。これにより、多くの外国人求職者からの応募が期待できます。また、オンラインでのインタビュー(面接)時の通訳手配や書類翻訳などの費用も、1名の採用につき5万円から10万円程度は必要でしょう。
直接採用の最大のメリットは、中長期的に見た場合のコスト削減効果です。そのため、初回採用時に構築したノウハウや人脈を活用することで、2回目以降の採用コストを大幅に削減できます。ただし、在留資格手続きや法的要件の確認等、専門知識が必要な領域については行政書士などの専門家への依頼が不可欠です。これらの費用を含めると、初回採用では人材紹介会社利用時と大差ない費用がかかることも多く、長期的な視点での判断が重要になります。
登録支援機関委託の費用
特定技能という在留資格制度を利用して外国人を雇用する場合、登録支援機関という専門団体への委託が現実的な選択肢となります。特に人手不足が深刻な介護業界などでは、この方法が主流です。委託費用は月額2万円から4万円程度が相場で、この中には生活オリエンテーション、定期面談、各種手続きサポートなどの法定支援業務が含まれています。年間で考えると1名につき24万円から48万円程度の継続費用が発生することになりますが、企業側の負担軽減効果は非常に大きいといえます。
登録支援機関のサービス内容は機関によって大きく異なります。基本的な法定支援のみか、充実したサポートまで含むか、どちらのプランを選ぶか、自社の支援体制と必要なサポートレベルを十分に考えることが重要です。もし手厚いサポートを望むなら、サービス内容が充実している機関を選ぶのがおすすめです。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
在留資格・ビザ手続きにかかるコスト

外国人材を雇用する際に避けて通れないのが、在留資格やビザに関する各種手続きです。これらの手続きは法的要件が厳格で、国内在住者でも手続きが難しいと感じるかもしれません。あっ、ここにも重要な注意点があります。手続きの不備は、後々大きな問題に発展しかねません。ここでは、そのコストについて徹底解説します。
申請手数料と書類作成費
在留資格に関わる申請手数料は、法務省の公式サイトで申請資料をダウンロードすれば確認でき、比較的明確に定められています。例えば、海外からの渡航を伴う在留資格認定証明書交付申請は手数料無料です。一方、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、2025年4月1日の改定により窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円の手数料がかかります。
しかし、実際の申請手続きでは、これらの手数料以外にもさまざまな費用が発生します。申請に必要な証明書の数はケースバイケースで、取得費用として1万円から3万円程度、書類の翻訳費用として1万円から5万円程度が必要になることが一般的です。
特に海外から外国人を招聘する場合は、現地での書類取得費用が追加で発生することがあり、国によっては行政機関や教育機関への手数料として1万円から3万円ほどかかるケースもあります。さらに、それらの書類を日本の公的機関で認証してもらう際にも別途費用が必要です。これらの対応をすべて自社で行った場合でも、最低でも10万円から20万円程度の費用がかかると見込んでおくことが望ましいです。
行政書士依頼時の報酬相場
在留資格手続きを行政書士に依頼する場合、報酬相場は申請の種類や難易度によって大きく異なります。在留資格認定証明書交付申請の場合、15万円から25万円程度が一般的な相場となっています。在留資格変更許可申請は10万円から20万円程度、在留期間更新許可申請は5万円から15万円程度が目安です。ただし、申請内容が複雑な場合や緊急対応が必要な場合は、追加費用が発生することも少なくありません。
行政書士への依頼メリットは、確実性の高さと時間的コストの削減にあります。専門知識を持つ行政書士が申請書類を作成することで、不許可となるリスクを大幅に軽減できます。報酬が安いという理由だけで選ばず、外国人在留資格に特化した実績豊富な事務所を選ぶことが重要です。
在留資格変更・更新費用
日本にすでに在住している外国人を雇用する場合、在留資格の変更手続きが必要になることがあります。たとえば、留学生を新卒採用する際に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更や、技能実習からの資格変更、さらには雇用形態が変わった場合も該当します。アルバイトとしての雇用でも手続きが必要となるケースがあります。申請が許可されるまでには時間がかかるため、余裕をもって準備することが重要です。
在留資格変更や在留期間更新の申請手数料は、2025年4月1日の法改正により、窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円に引き上げられています(在留資格認定証明書交付申請は引き続き無料です)。ただし、申請書類の準備や行政書士への依頼を含めると、トータルで10万円から20万円程度の費用がかかることが一般的です。
在留期間の更新は、外国人が継続して就労する限り定期的に必要で、更新サイクルは在留資格の種類によって1年から5年の間で設定されています。これらの費用は予測可能なため、雇用計画に含めて予算化することが大切です。長期的な雇用を前提に、更新費用も含めた総コストで採用効果を評価しましょう。
外国人材の雇用に興味はあるものの、「どんな手続きが必要なのか分からない」「法令違反が怖い」と感じている企業担当者は少なくありません。特に、これまで外国人を雇った経験がない企業にとっては、在留資格の種類や手続きの流れ、管理体制など、知らなけれ[…]
外国人材の受け入れ環境整備費用

外国人材を雇用する際、単に採用するだけでなく、日本で安心して働ける良い環境を整備することが不可欠です。この受け入れ環境整備は、外国人材が安心して働くための土台となり、定着率に直結する大切な投資です。彼らが日本での就職を選んでくれた希望に応えるためにも、ここは手を抜けません。多くの企業が見落としがちなのは、住居確保から日本語教育、生活サポートまで含めた包括的な支援体制の構築です。
住居確保とサポート費用
外国人材の住居を探すことは、多くの企業が直面する最初の課題です。日本の賃貸住宅市場では外国人への貸し渋りが依然として存在するため、企業が保証人になったり、外国人専門の不動産会社を利用したりする必要があります。一般的な住居確保費用として、敷金礼金で家賃の4か月から6か月分、仲介手数料で家賃の1か月分程度が必要になります。家賃5万円の物件であれば、初期費用だけで25万円から35万円程度の支出となります。一例として、ペット、例えば犬と一緒に暮らしたいという希望がある場合、物件探しはさらに困難になり、追加費用がかかることもあります。
社宅や寮を提供する場合は、さらに設備投資が必要です。外国人材が快適に生活できるよう、多言語対応の生活マニュアル作成、インターネット環境の整備、基本的な生活用品の準備などが求められます。これらの費用は1名あたり10万円から20万円程度が相場です。また、住居に関するトラブル対応や契約更新手続きなど、継続的なサポート体制の構築も重要で、年間で5万円から10万円程度の管理費用を見込んでおく必要があります。
日本語研修・教育費用
外国人材の日本語能力向上は、業務効率化と職場コミュニケーション円滑化のために極めて重要です。企業内研修を実施する場合、専門講師への謝礼として1時間あたり5,000円から1万円程度、教材費として1名あたり2万円から5万円程度が必要になります。週2回、3か月間の集中研修を行う場合、1名あたり15万円から30万円程度の費用を見込む必要があります。
外部の日本語学校や研修機関を利用する場合は、より体系的な教育が期待できる一方、費用も高額になります。ビジネス日本語コースの受講料は3か月で20万円から40万円程度が相場となっています。ただし、これらの教育投資は外国人材の業務習得速度向上や職場定着率向上に直結するため、中長期的にはコスト削減効果が期待できます。研修内容も、日本語能力試験の基準に合わせた一般的な学習だけでなく、業界特有の専門用語や職場でのコミュニケーションマナーなど、より理解しやすく実践的な内容を含むeラーニングプログラムを選択することが重要です。
生活支援にかかる費用
外国人材の日本生活における様々な支援も、企業が負担を検討すべき重要な費用項目です。携帯電話契約、銀行口座開設、各種保険手続き等、来日直後に必要となる手続きのサポート費用として、1名あたり5万円から10万円程度が発生します。これらの手続きには通訳が必要な場合も多く、通訳費用として1日あたり2万円から3万円程度の支出も見込まれます。
継続的な生活支援としては、医療機関受診時の同行サポート、各種行政手続きの代行、緊急時対応などがあります。これらのサービスを外部機関に委託する場合、月額1万円から3万円程度の費用が発生します。自社で対応する場合でも、担当者の時間コストを考慮すると相応の負担となります。企業によっては、住宅手当と同様に、生活支援のための特別な手当を設けるケースもあります。また、文化的な違いから生じるトラブル対応や、メンタルヘルスケアなど、予期しない支援が必要になる場合もあります。これらの費用を含めて、年間で1名あたり20万円から40万円程度の生活支援費用を予算に組み込んでおくことをおすすめします。
外国人採用の費用を抑える方法

外国人採用にかかる費用を適切に管理し抑えることは、持続可能な雇用戦略において極めて重要です。ここでは、コストを抑えるための具体的な方法を、実際の事例も参考に解説します。人手不足という課題を解決するためにも、費用対効果の高い方法を検討しましょう。ただし、単純にコストカットを優先するデメリットとして、必要な支援を怠ると外国人材の定着率低下や生産性悪化を招く恐れがあります。
助成金・補助金の活用
外国人材雇用に関連する助成金や補助金を積極的に活用することで、実質的なコスト負担を大幅に軽減できます。厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では、外国人労働者の就労環境整備に要した費用の2分の1が支給され、1制度あたり20万円、最大で4制度合計80万円まで助成されます。具体的には、通訳費用、翻訳機器導入費、労務管理システム導入費、外国人労働者向け研修費などが対象となります。申請手続きは複雑ですが、適切に活用すれば初期投資の大部分を回収できる可能性があります。
また、地方自治体ごとに独自の補助金制度も実施されており、外国人材の住居確保支援として家賃補助や保証料補助を行う自治体もあります。さらに地域の人材不足解消を目的とした外国人採用支援事業として、人材紹介手数料の一部補助や研修費用の助成を行う例もあります。これらの制度は自治体によって内容や支給条件が大きく異なるため、所在地の自治体に直接問い合わせて詳細を確認することが重要です。
参考:厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
現在、多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。特に建設業、介護分野、製造業などでは、日本人労働者の確保が困難な状況が続いており、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。2024年から2025年にかけて、特定技能制度の対象[…]
自社での直接採用体制構築
人材紹介会社への依存度を下げ、自社での直接採用体制を構築することは、中長期的な費用削減の有効な手段です。初回投資として、外国人向け求人サイトへの掲載や多言語対応の採用ページ作成に50万円から100万円程度の費用が必要になりますが、継続的な利用により1名あたりの採用コストを大幅に削減できます。また、過去に採用した外国人材からの紹介による採用も効果的で、紹介謝礼として10万円程度を支払っても人材紹介会社の手数料と比較すれば格段に安価です。
直接採用体制の構築では、社内の専門知識向上も重要な要素となります。日本人社員の採用と同様に、人事担当者が外国人採用に関する法的要件や手続きを習得することで、外部への委託費用を削減できます。行政書士主催の研修会参加費用は1回あたり1万円から3万円程度と比較的安価で、得られる知識は継続的に活用できます。ただし、複雑な案件については専門家への相談が必要な場合もあるため、顧問契約を結ぶなど柔軟な体制を整えることが重要です。
効率的な支援体制の作り方
外国人材への継続的な支援において、効率性とコストバランスを両立させる体制作りが重要です。まず検討すべきは、複数の外国人材を同時に雇用することによる規模の経済効果の活用です。また、先輩外国人材によるメンター制度を導入すれば、新規採用者がいつでも相談できる環境が整い、孤独を感じさせずに早期定着を図りながら通訳や生活支援にかかる費用を抑制できます。
以下のデジタルツール活用もコストを抑える上で有効です。翻訳アプリや多言語対応のコミュニケーションツール導入により、日常的な通訳費用を大幅に削減できます。また、外国人材向けの生活情報や業務マニュアルを動画コンテンツとして作成し、オンラインで提供することで、個別対応の必要性を減らすことも可能です。これらのデジタル投資は初期費用として20万円から50万円程度が必要ですが、長期的には大幅なコスト削減効果が期待できます。重要なのは、技術と人的サポートのバランスを適切に保ち、外国人材が孤立感を感じないような配慮です。
まとめ|外国人採用費用の重要ポイント

本記事で解説してきた通り、外国人材の採用には日本人採用とは異なる多様な費用が発生することをご理解いただけたでしょうか。自社の状況に合わせて適切な計画を立てることが大切です。人材紹介会社の手数料から在留資格手続き、受け入れ環境整備まで含めると、1名あたり100万円から200万円程度の初期費用が必要になるケースが一般的です。しかし、これらの費用は単なる支出ではなく、優秀な外国人材を獲得し、長期的に戦力として活用するための重要な投資です。
特に重要なのは、助成金の活用や効率的な支援体制の構築により、費用を適切にコントロールしながら外国人材の定着率を高めることです。初回採用では外部専門家への依存度が高くなりがちですが、社内ノウハウの蓄積により継続的なコスト削減が可能になります。外国人材の雇用は一時的な人手不足解消策ではなく、企業の成長戦略の一環として捉え、中長期的な視点での投資判断が求められるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。