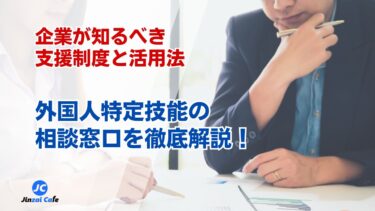特定技能外国人の受け入れを検討する際、多くの企業が最初に直面するのが「実際にどれくらいの費用がかかるのか」という疑問です。人材紹介会社への手数料、登録支援機関への委託費用など、さまざまな費用項目が存在し、その全体像を把握することは難しいものです。特に建設業や製造業など人手不足が深刻な分野では、外国人労働者の受け入れが重要な経営課題となっています。
本記事では、特定技能1号・2号の受け入れにかかる費用を採用前から受け入れ後まで時系列で整理し、具体的な相場とともに解説していきます。さらに、費用を抑えるための実践的なポイントや、企業側と外国人本人の費用負担の考え方についても詳しく説明しますので、予算計画の立案にお役立てください。ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなど国籍別の違いについても参考情報として触れていきます。
特定技能外国人の受け入れにかかる費用の全体像

特定技能外国人の受け入れ費用は、採用前の準備段階から受け入れ後の継続的な支援まで、複数の段階にわたって発生します。ここでは、まず費用の全体像とその概要を見ていきましょう。これらの費用を時系列で整理すると、初期費用、採用時費用、継続費用の3つに大きく分類できます。
初期費用には求人広告費や書類作成費が含まれ、採用時には人材紹介会社への紹介料や在留資格(ビザ)申請費用が必要です。受け入れ後は登録支援機関への委託費や住居費、社会保険料などが毎月継続的な負担となります。全体の費用規模を把握することで、適切な予算計画を立てることが可能になります
特定技能1号の場合、在留期間は通算5年が上限となっており、更新手続きも定期的に必要です。一方、特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められていますが、2025年9月時点では対象分野が限定されています。
採用前にかかる初期費用の内訳
特定技能外国人の採用を開始する前段階では、主に求人活動と準備に関する費用が発生します。求人広告を掲載する場合は媒体によって異なりますが、月額5万円から20万円程度が目安です。
海外在住の外国人を対象とする場合は、国外の送り出し機関との契約に伴う費用も考慮する必要があります。技能実習から特定技能への移行を検討している場合は、すでに国内に居住している技能実習生を採用することで、渡航費用や海外での手続き費用を削減できるメリットがあります。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 求人広告掲載費 | 月額5万円〜20万円 | 媒体により変動 |
| 送り出し機関契約費用 | 5万円〜15万円 | 海外在住者採用時 |
| 行政書士への書類作成依頼 | 10万円〜15万円 | 1件あたり、1名分 |
| 求人サイト掲載費 | 月額3万円〜10万円 | 自社採用の場合 |
| オンライン面接環境整備 | 5万円〜10万円 | 初期投資 |
| 合計 | 10万円〜35万円 | 採用前段階 |
この段階では、外部の専門家に依頼するか自社で対応するかによって費用が大きく異なります。知識やノウハウが社内にない場合は、一般社団法人や行政書士などの専門機関を通した方が、結果的に時間とコストの面で得策と言えるケースも多いです。
採用時に発生する費用項目
外国人材の採用が決定した段階では、人材紹介会社を利用している場合に紹介手数料(仲介手数料)が発生します。この手数料の支払いは想定年収の20%から35%が相場で、年収300万円の場合は60万円から105万円程度になります。在留資格の取得には法令で定められた書類の提出が必須となり、専門的な知識が求められます。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 60万円〜105万円 | 年収300万円の場合 |
| 在留資格申請(行政書士依頼) | 8万円〜15万円 | 専門家に依頼する場合 |
| 在留資格申請(自社対応) | 2万円程度 | 収入印紙代等 |
| 渡航費用 | 5万円〜10万円 | 東南アジアから |
| 来日前健康診断費用 | 1万円〜2万円 | 企業負担の場合 |
| 入国後オリエンテーション | 3万円〜5万円 | 通訳・資料作成含む |
| 合計 | 80万円〜130万円 | 採用決定時 |
ベトナムやフィリピンなど国籍によって、送り出し機関の料金体系や必要な手続きが異なる点に注意が必要です。特に海外から直接採用する場合は、各国の制度や法令を理解しておくことが重要です。
受け入れ後の継続的な費用
特定技能外国人を受け入れた後は、法令で定められた義務的支援の実施に関する費用が継続的に発生します。登録支援機関に支援業務を委託する場合、月額2万円から4万円が一般的な料金です。1年間(12か月)で計算すると24万円から48万円の負担となります。
| 費用項目 | 月額 | 年額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録支援機関委託費 | 2万円〜4万円 | 24万円〜48万円 | 義務的支援の実施 |
| 住居費補助 | 3万円〜6万円 | 36万円〜72万円 | 家賃補助として |
| 社会保険料(企業負担分) | 3万円〜5万円 | 36万円〜60万円 | 給与額により変動 |
| 通勤手当 | 5,000円〜1万円 | 6万円〜12万円 | 実費支給 |
| 健康診断費用 | – | 1万円 | 毎年1回実施 |
| 合計 | 8万円〜16万円 | 100万円〜150万円 | 年間継続費用 |
在留資格の更新手続きは、特定技能1号の場合は通常1年ごとまたは6か月ごとに必要となり、その都度、更新申請費用として数万円程度が発生します。更新時には、雇用契約の継続や支援計画の実施状況などが審査されるため、制度の変更にも注意しながら、日頃から適切な記録管理が求められます。
人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の採用を具体的に検討される企業が増えています。しかし、実際に外国人材の受け入れを進めようとすると「あっ、一体どのくらいの費用がかかるのだろうか」という疑問が必ず浮かんでくるでしょう。採用にかかる[…]
特定技能外国人の採用費用の相場と詳細

特定技能外国人の採用ルートは大きく分けて、人材紹介会社の利用、登録支援機関への委託、自社での直接採用の3つです。それぞれの方法によって費用構造が大きく異なるため、自社の体制や予算に応じた選択が求められます。人材紹介会社を利用する場合は初期費用が高額になる傾向がありますが、採用の確実性が高まるメリットがあります。
登録支援機関に委託する場合は、採用から支援まで一貫してサポートを受けられる点が特徴です。自社採用は費用を抑えられる反面、特定技能制度に関する専門知識を有する担当者が必要になります。建設分野や産業機械製造業など、特定の分野では業界団体や国際交流機構(例:通称JAC)などを通じた採用ルートも存在します。
人材紹介会社を利用する場合の費用
人材紹介会社を通じて特定技能外国人を採用する場合、紹介料(紹介手数料)が最も大きな費用項目となります。手数料の算定方法は想定年収に対する料率制が一般的で、20%から35%の範囲で設定されているケースが多く見られます。この料金体系は、日本人の採用と同様の仕組みです。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 紹介手数料(年収300万円の場合) | 60万円〜105万円 | 年収の20-35% |
| 月額固定費用制の場合 | 月額10万円〜15万円 | 複数名紹介可能 |
| 在留資格申請サポート | 込み〜10万円 | 会社により異なる |
| 来日後初期対応サポート | 込み〜5万円 | 会社により異なる |
| 初年度総額(1名) | 60万円〜120万円 | 紹介手数料+サポート費 |
人材紹介会社を選ぶ際の目安として、過去の実績や対応可能な国籍、アフターサポートの内容などを一覧で比較することをおすすめします。特にベトナム人やフィリピン人など、特定の国籍に強い紹介会社もあるため、採用したい人材の背景に応じて選択することが重要です。
登録支援機関に委託する場合の費用
登録支援機関に採用から支援まで一括して委託する場合、初期費用と継続費用の両方が発生する料金体系が一般的です。初期費用としては、求人活動から採用決定までのサポート費用として30万円から50万円程度が相場となっています。登録支援機関を通さずに自社で対応する場合と比較すると、専門的なノウハウを活用できる点がメリットです。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期費用(採用サポート) | 30万円〜50万円 | 求人〜採用決定まで |
| 月額委託費用 | 2万円〜4万円 | 義務的支援の実施 |
| 年間委託費用 | 24万円〜48万円 | 月額×12か月 |
| 年間契約割引 | -10%〜-15% | 適用される場合 |
| 複数名割引(5名以上) | -20%〜-30% | 1名あたり |
| 初年度総額(1名) | 54万円〜98万円 | 初期費用+年間委託費 |
登録支援機関によっては、特定技能2号への移行支援や、在留資格更新時のサポートなども別途提供しているケースがあります。長期的な視点で外国人材の定着を図る場合は、こうした追加サービスの有無も確認しておくと良いでしょう。
自社で直接採用する場合の費用
自社で特定技能外国人を直接採用する場合、人材紹介手数料や支援委託費を削減できるため、全体的な費用を大幅に抑えることが可能です。主な費用項目としては、求人広告の掲載費用と在留資格申請関連の費用が中心となります。ただし、自社で対応するには特定技能制度に関する専門知識が必須となり、担当者の教育や体制整備に時間がかかる点に注意が必要です。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 求人広告掲載費 | 月額5万円〜10万円 | 3か月程度必要 |
| 在留資格申請(行政書士依頼) | 8万円〜15万円 | 専門家に依頼 |
| 在留資格申請(自社対応) | 2万円程度 | 収入印紙代等 |
| 送り出し機関との直接契約 | 10万円〜20万円 | 海外在住者の場合 |
| 現地面接費用 | 10万円〜20万円 | 渡航費・宿泊費 |
| 担当者研修費用 | 5万円〜10万円 | 制度理解のため |
| 初年度総額(1名) | 15万円〜75万円 | 採用ルートにより変動 |
自社採用を成功させるには、海外の送り出し機関や国内の技能実習生受け入れ団体などとのネットワーク構築が重要です。特に建設業界では、業界団体を通じた情報共有や共同での採用活動を行っているケースもあり、こうした仕組みを活用することで効率的な採用が可能になります。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討する企業が急増しています。しかし、「実際にどれくらいの費用がかかってくるのか」「予想以上にコストが膨らんでしまうのでは」といった不安を抱く経営者の方も多いのではないでしょうか。外国人採用は確かに日[…]
受け入れ後に企業が負担する費用項目

特定技能外国人を受け入れた後は、法令で定められた義務的支援の実施に関する費用が継続的に発生します。これらの費用は外国人材が安定して就労できる環境を整えるために必要不可欠なものです。主な費用項目としては、登録支援機関への委託費用、住居の確保と生活支援に関する費用、社会保険料や福利厚生費などがあります。
受け入れ人数が増えるほど総額は大きくなりますが、スケールメリットを活かして1名あたりの単価を下げることも可能です。年間の継続費用を正確に把握し、予算に組み込んでおくことが安定的な受け入れ体制の構築につながります。企業側としては、これらの費用を給与とは別途の負担金として管理することが重要です。
義務的支援にかかる費用
特定技能制度では、受け入れ企業に対して10項目の義務的支援の実施が法令で定められています。この支援業務を登録支援機関に委託する場合、月額2万円から4万円が一般的な料金です。
自社で支援体制を構築する場合、外部への委託料金は発生しませんが、担当者の人件費や通訳費用などの実質的なコストが必要になります。具体的な支援項目と費用感について、以下の表をご覧ください。
| 支援項目 | 内容 | 自社対応時の費用 |
|---|---|---|
| 1.事前ガイダンス | 雇用契約締結後の説明 | 通訳費1万円程度 |
| 2.出入国時の送迎 | 空港等への送迎、帰国時対応 | 交通費5,000円程度 |
| 3.住居確保・生活契約支援 | 銀行口座・携帯電話契約等 | 通訳費1万円程度 |
| 4.生活オリエンテーション | 生活ルール等の説明 | 資料作成費2万円程度 |
| 5.公的手続きへの同行 | 市区町村役場での手続き | 通訳費5,000円程度 |
| 6.日本語学習機会の提供 | 教材提供・教室情報 | 教材費月額5,000円 |
| 7.相談・苦情対応 | 母国語での相談体制 | 通訳費月額2万円 |
| 8.日本人との交流促進 | 交流イベント参加支援 | イベント費年1万円 |
| 9.転職支援 | 受入れ困難時のサポート | 必要時のみ発生 |
| 10.定期面談 | 3か月に1回以上の実施 | 通訳費年4万円 |
| 月額委託費 | 2万円〜4万円 | 実質月額3万円〜5万円 |
| 年間費用 | 24万円〜48万円 | 36万円〜60万円 |
支援の質を高く保つことは、外国人材の定着率向上につながり、長期的には採用コストの削減にもつながります。そのため、単に費用を抑えることだけを目的とするのではなく、適切な支援体制の構築が重要です。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
特定技能外国人労働者を採用する際、多くの企業が「生活オリエンテーション」という言葉を耳にするでしょう。しかし、具体的に何を伝えればいいのか、どのように実施すればよいのか、悩まれる人事担当者の方は少なくありません。生活オリエンテーショ[…]
特定技能外国人を受け入れる際、企業には様々な支援義務が課せられています。その中でも最初に実施すべきなのが「事前ガイダンス」です。採用活動を経て、入国前に労働条件や生活情報を十分に説明することで、外国人材の不安や悩みを解消し、スムーズな受入れ[…]
住居確保と生活支援の費用
特定技能外国人の住居については、企業が借り上げて提供するか、外国人本人が契約する際の連帯保証人になることが一般的です。企業が借り上げる場合、家賃の全額または一部を補助するケースが多く、地域によって相場は異なりますが月額3万円から6万円程度の負担が発生します。物件の選定にあたっては、職場への通勤の便や生活環境を考慮することが必要です。
| 費用項目 | 金額相場 | 発生タイミング | 備考 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃の1〜2か月分 | 契約時 | 3万円〜12万円 |
| 礼金 | 家賃の1〜2か月分 | 契約時 | 3万円〜12万円 |
| 仲介手数料 | 家賃の1か月分以内 | 契約時 | 3万円〜6万円 |
| 家具・家電購入費 | 10万円〜15万円 | 入居時 | 冷蔵庫・洗濯機等 |
| 月額家賃補助 | 3万円〜6万円 | 毎月 | 全額または一部 |
| 生活必需品 | 3万円〜5万円 | 入居時 | 寝具・調理器具等 |
| 自転車購入費 | 1万円〜3万円 | 入居時 | 通勤用 |
| 携帯電話初期費用 | 3,000円〜5,000円 | 契約時 | 契約手数料 |
| 初期費用合計 | 25万円〜50万円 | 入居時 | 地域により変動 |
| 月額継続費用 | 3万円〜6万円 | 毎月 | 年間36万円〜72万円 |
住居の居住環境は、外国人材の生活満足度に直結します。単に安い物件を選ぶのではなく、適切な環境を用意することが重要な理由はここにあります。特に複数名を受け入れる場合は、シェアハウス形式の物件を活用することで、1名あたりの費用を抑えることも可能です。
社会保険料と福利厚生費
特定技能外国人も日本人従業員と同様に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用対象となります。企業が負担する社会保険料は給与額によって異なりますが、月額給与20万円の場合で月額約3万円から4万円程度です。これは日本人と同等の扱いとなり、国籍による違いはありません。
| 費用項目 | 月額(給与20万円) | 年額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料(企業負担分) | 約1万円 | 約12万円 | 給与の約5% |
| 厚生年金保険料(企業負担分) | 約1.8万円 | 約21.6万円 | 給与の約9.15% |
| 雇用保険料(企業負担分) | 約1,200円 | 約1.4万円 | 給与の約0.6% |
| 労災保険料 | 約400円 | 約5,000円 | 業種により変動 |
| 社会保険料合計 | 約3.2万円 | 約38.4万円 | 給与20万円の場合 |
| 通勤手当 | 5,000円〜1万円 | 6万円〜12万円 | 実費支給 |
| 健康診断費用 | – | 1万円 | 毎年1回実施 |
| 制服・作業着代 | – | 2万円〜3万円 | 初年度のみ |
| 一時帰国費用補助 | – | 10万円〜15万円 | 実施する場合 |
| 福利厚生費合計 | 約1万円 | 19万円〜31万円 | 企業により異なる |
| 総合計 | 約4.2万円 | 57万円〜69万円 | 1名あたり年間 |
福利厚生の充実は、外国人材の定着率を高める上で重要な要素です。特に母国への一時帰国支援は、外国人材のモチベーション維持に大きく寄与するため、可能性がある場合は検討する価値があります。
特定技能外国人本人が負担する費用

特定技能外国人の受け入れにあたっては、企業側だけでなく外国人本人にも一定の費用負担が発生します。来日前の準備段階から来日後の生活立ち上げまで、本人が支払うべき費用項目を正確に理解しておくことは、トラブル防止の観点から非常に重要です。
企業によっては本人負担分の一部または全額を支援するケースもあり、採用競争力を高める手段として活用されています。ただし、法令で禁止されている費用徴収もあるため、適切な費用分担のルールを把握しておく必要があります。本人負担の範囲を明確にすることで、採用後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
特に保証金や違約金の徴収は法令で厳しく禁止されており、これに違反すると受け入れ企業としての認定が取り消される問題にもつながります。
来日前に本人が負担する費用
海外在住の特定技能外国人が来日する際には、いくつかの費用を本人が負担するのが一般的です。以下の表は、来日前に発生する主な費用項目と相場をまとめた一覧です。
国籍によって費用が異なる点にも注意が必要で、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなど、それぞれの国で制度や相場が異なります。
| 費用項目 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康診断費用 | 1万円〜2万円 | 母国での受診が必須 |
| 在留資格関連手続き費用 | 5,000円〜1万円 | 国によって異なる |
| パスポート取得・更新費用 | 1万円〜2万円 | 国籍により変動 |
| 渡航費用(航空券) | 5万円〜10万円 | 企業負担のケースも多い |
| 日本語教育・職業訓練費用 | 10万円〜30万円 | 送り出し機関利用時、特定技能評価試験の対策費を含む |
| 各種証明書取得費用 | 5,000円〜1万円 | 卒業証明書等 |
ただし、法令では保証金や違約金の徴収は厳しく禁止されているため、これらの名目で費用を請求することは認められていません。送り出し機関を利用する場合でも、適正な費用であることを確認する必要があります。特にベトナムでは、送り出し機関による過剰な費用徴収が問題となっているケースもあるため、企業側も注意深く確認することが求められます。
MWO申請に必要な費用一覧や手続きの流れを分かりやすく解説。フィリピン人材の雇用を検討中の企業担当者様向けに、特定技能ビ…
来日後に本人が負担する費用
来日後の生活立ち上げ段階では、外国人本人が負担する費用がいくつか発生します。以下の表は、来日後に発生する主な費用項目を継続費用と初期費用に分けて整理した詳細一覧です。
| 費用区分 | 費用項目 | 金額相場 |
|---|---|---|
| 継続費用(毎月) | 住居費(家賃) | 3万円〜5万円 |
| 継続費用(毎月) | 食費・光熱費・通信費 | 5万円〜8万円 |
| 継続費用(毎月) | 国民健康保険料 | 数千円〜1万円 |
| 継続費用(毎月) | 日本語学習費用 | 5,000円〜2万円 |
| 初期費用 | 生活必需品の購入 | 5万円〜10万円 |
| 初期費用 | 行政手続き関連 | 数百円程度 |
| 初期費用 | 通勤用品の購入 | 1万円〜3万円 |
住居費の負担割合は企業によって異なり、全額企業負担、一部補助、全額本人負担など様々です。企業の支援体制によって本人の実質的な負担額は大きく変わります。特に建設業など現場作業が中心の業種では、企業が住居を用意して家賃の大部分を負担するケースが多く見られます。
企業が代わりに負担するケースと注意点
特定技能外国人の採用競争が激化する中、企業が本人負担分の一部または全額を支援するケースが増えています。以下の表は、企業が負担することの多い費用項目をまとめた一覧です。
| 負担項目 | 企業負担の傾向 | 効果 |
|---|---|---|
| 渡航費用(航空券代) | 全額負担が増加 | 採用決定率の向上 |
| 住居の初期費用 | 敷金・礼金を企業負担 | 採用競争力の強化 |
| 家具・家電費用 | 提供または購入費補助 | 生活立ち上げの円滑化 |
| 来日前健康診断費用 | 企業負担のケースあり | 採用プロセスの促進 |
企業が費用を負担する際の重要な注意点は以下の通りです。これらは法令で定められた義務であり、遵守しないと受け入れ企業としての認定に問題が生じる可能性があります。
- 雇用契約書や支援計画書への明記が必須
- 保証金や違約金の徴収は法令で厳しく禁止
- 立て替え費用の回収は本人から同意をもらうことが前提
- 給与からの控除額は生活を圧迫しない範囲に設定(1年以内の返済が目安)
- 返済計画は期間と月額を明確に文書化
当然ながら、本人の生活が困窮するような高額な返済を無理に支払わせることは認められません。費用負担の範囲と方法を事前に明確化し、双方が納得できる形で契約を結ぶことが、採用後のトラブルを防ぐ最も効果的な方法です。
特定技能外国人の受け入れ費用を抑えるポイント

特定技能外国人の受け入れには相応の費用が必要ですが、適切な戦略を立てることでコストを削減することが可能です。費用を抑えるためには、登録支援機関の選定方法、自社支援体制の構築、助成金・補助金の活用という3つの主要なアプローチが効果的です。
ただし、費用削減を優先するあまり支援の質が低下すると、外国人材の定着率が下がり、結果的に採用コストが増大するリスクもあります。適切なバランスを保ちながら、長期的な視点でコスト最適化を図ることが重要です。
本セクションでは、実践的なコスト削減方法を具体的に解説していきます。特に建設業や製造業など、複数名の外国人材を受け入れる分野では、スケールメリットを活かした運用が可能です。
登録支援機関の選び方と比較ポイント
登録支援機関への委託料金は月額2万円から4万円と幅があり、年間では24万円から48万円の差が生まれます。複数の登録支援機関を比較検討する際の重要なポイントを以下にまとめました。選定の目安として、料金だけでなくサービスの質や実績も重視することが重要です。
| 比較項目 | 確認ポイント | コスト削減への影響 |
|---|---|---|
| 月額委託料金 | 基本料金と追加費用の内訳 | 年間24万円の差が発生する可能性 |
| 対応言語 | 外国人の母国語対応の有無 | 通訳費用の削減につながる |
| サービス範囲 | 基本サービスに含まれる支援内容 | 追加費用の発生を防ぐ |
| 複数名割引 | 受け入れ人数に応じた料金体系 | 5名以上で1名あたり20-30%削減 |
| 契約期間 | 年間契約での割引制度 | 月額契約より10-15%安くなる |
| 実績と評判 | 同業種での支援実績 | トラブル対応コストの削減 |
登録支援機関を選ぶ際は、単純な料金比較だけでなく、提供されるサービスの質と範囲を総合的に評価することが重要です。特に以下の点に注意して選定を進めましょう。詳細な比較表やページを用意して、複数の機関を検討することをおすすめします。
- 初期費用の有無と金額
- 定期面談の頻度と実施方法
- 緊急時の対応体制(24時間対応の有無)
- 行政機関への届出代行の有無
- 日本語学習支援の内容と追加料金
- 更新手続きのサポート範囲
- 特定技能2号への移行支援の有無
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
自社支援体制の構築による削減方法
登録支援機関への委託料金を削減する最も効果的な方法は、自社で義務的支援を実施できる体制を構築することです。自社支援に切り替えることで、年間24万円から48万円の委託料金を削減できます。
ただし、自社支援を行うためには一定の要件を満たす必要があり、初期投資と継続的な運用コストも考慮する必要があります。複雑な制度理解が求められるため、専門知識を持った担当者の配置が必須です。
自社支援体制を構築する際に必要な準備と費用は以下の通りです。
| 準備項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 支援責任者の配置と研修実施 | 10万円程度 | 外部研修費用 |
| 外国人との面談記録システム整備 | 20万円程度 | システム導入費 |
| 多言語対応マニュアル作成 | 1言語あたり10万円程度 | 翻訳費用 |
| 通訳者確保または通訳システム導入 | 月額3万円〜5万円 | 継続費用 |
| 行政機関への届出業務習得 | 5万円程度 | 研修費用 |
| 出入国在留管理庁への各種届出の代行体制構築 | 初期10万円程度 | 体制整備費用 |
自社支援を実施する場合の実質的なコストは、担当者の人件費が主要な負担となります。専任担当者を1名配置する場合、年間300万円から400万円程度の人件費が発生しますが、10名以上の外国人材を受け入れる場合は、登録支援機関への委託(10名で年間240万円から480万円)よりも自社対応の方がコスト効率が良くなる計算です。
また、部分的な自社対応も可能で、定期面談や日常的な相談対応は自社で行い、専門的な手続きのみを外部に委託するハイブリッド方式を採用する企業も増えています。この方式なら、外部委託料金を月額1万円〜2万円程度に抑えることも可能です。
助成金・補助金の活用術
あっ、こんな制度があったのか!と後で気づいても申請期限を過ぎているケースは少なくありません。特定技能外国人の受け入れに関連する助成金や補助金を活用することで、実質的な負担を軽減することができます。
国や自治体が提供する主要な支援制度を以下の表にまとめました。これらの制度を知っているかどうかで、年間数十万円の差が生まれる可能性があります。
| 制度名 | 支援内容 | 金額規模 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) | 就労環境整備費用の助成 | 上限72万円 | 都道府県労働局 |
| 地域雇用開発助成金 | 雇用創出に対する助成 | 1名あたり最大60万円 | 都道府県労働局 |
| 自治体独自の補助金 | 受け入れ企業への補助 | 自治体により異なる | 各自治体の窓口 |
| キャリアアップ助成金 | 正社員化への助成 | 1名あたり57万円 | 都道府県労働局 |
| 建設業特有の助成金 | 建設分野での受入支援 | 分野ごとに異なる | 建設業協会等 |
助成金・補助金を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。
- 申請要件の詳細確認
- 申請期限の事前把握
- 必要書類の早期準備
- 社会保険労務士への相談
- 複数制度の組み合わせ活用
- 自治体の無料相談窓口の活用
特に人材確保等支援助成金は、通訳費用、翻訳機器の導入費用、社内マニュアルの多言語化費用などが対象となるため、受け入れ環境の整備と同時に助成金を受けられる可能性があります。
ただし、助成金の申請には事前計画の提出や一定期間(通常は1年以上)の雇用継続などの条件があるため、受け入れ計画の段階から助成金の活用を視野に入れておくことが重要です。申請のタイミングや流れについても、事前に確認しておくことをおすすめします。
参考:
厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック
厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)
現在、多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。特に建設業、介護分野、製造業などでは、日本人労働者の確保が困難な状況が続いており、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。2024年から2025年にかけて、特定技能制度の対象[…]
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は重要な選択肢の一つです。しかし、複雑な制度内容や手続きに関して「どこに相談すればよいのか分からない」「適切な支援を受けられるのか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も多いの[…]
まとめ|特定技能外国人の費用を正しく理解して受け入れを成功させる

特定技能外国人の受け入れには、採用前の初期費用から受け入れ後の継続費用まで、様々な段階で費用が発生します。人材紹介会社を利用する場合は初期費用として60万円から130万円程度、登録支援機関への委託や住居費補助などの継続費用として年間100万円から150万円程度が必要です。ただし、自社支援体制の構築や助成金の活用によって、これらの費用を大幅に削減することも可能となっています。
重要なのは、単に費用を抑えることだけを目的とするのではなく、外国人材が安定して働ける環境を整備し、長期的な定着を実現することです。特定技能1号から特定技能2号への移行を見据えた長期的な視点も重要となります。費用の全体像を正確に理解し、自社の体制や予算に応じた最適な受け入れ方法を選択することが、特定技能外国人の受け入れ成功への第一歩となります。
建設業、製造業、介護分野など、それぞれの産業分野によって求められる支援内容や費用構造も異なるため、同業他社の事例を参考にしながら、自社に最適な受け入れ方法を検討することをおすすめします。また、在留資格の更新や特定技能2号への移行など、長期的な視点での費用計画も重要です。デメリットやリスクも含めて総合的に判断し、外国人材との良好な関係を構築することが、企業の持続的な成長につながります。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。