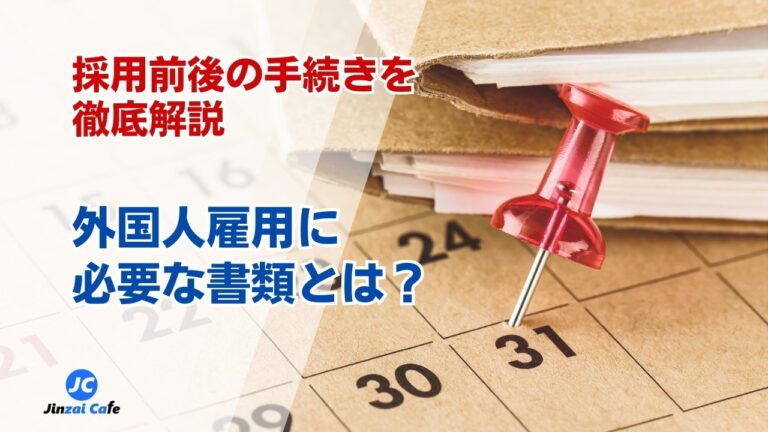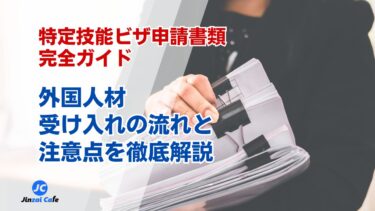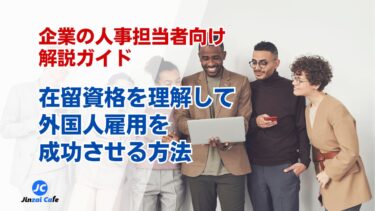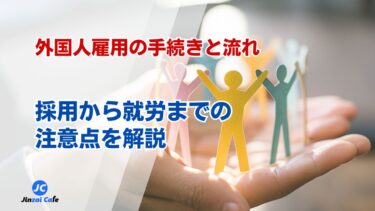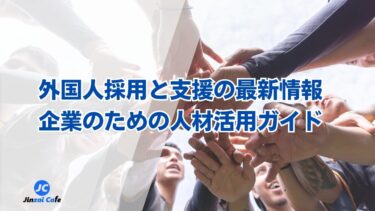グローバル化が進む現在、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。しかし、多くの人事担当者が「外国人を採用したいけれど、どんな書類が必要なのかわからない」「手続きでトラブルを起こしたくない」といった不安を抱えているのではないでしょうか。この記事は、初めて外国人雇用に携わる方にも分かりやすく、実践的なガイドとなることを目指しています。
実のところ、外国人雇用には日本人の採用とは異なり、数多くの書類が必要です。あれもこれもと準備すべきものがあり、在留資格の確認から雇用保険の届出まで、一つひとつの手続きには法律上の意味があり、企業側の義務として定められています。これらの知識がないまま進めてしまうと、不法就労助長罪に問われる可能性もあり、会社にとって大きなリスクとなりかねません。
この記事では、外国人材の雇用で必要となる書類を時系列に沿って詳しく解説します。採用前の確認事項から入社後の各種届出まで、実際の現場で役立ちそうな実践的な情報をお届けします。記事の概要を掴んで読み終える頃には、外国人雇用の手続きに対する不安が解消され、自信を持って採用活動を進められるはずです。
外国人雇用前に確認すべき必要書類

外国人を採用する前段階では、その人が日本で合法的に働くことができるかを確認することが最も重要です。この確認を怠ると、知らず知らずのうちに不法就労を助長してしまう恐れがあります。企業側には雇用前の十分な書類確認が義務付けられており、以下の各書類を必ず確認しましょう。
- 在留カード(原本の提示必須)
- パスポート(有効期限要確認)
- 資格外活動許可証(該当者のみ)
在留カードと在留資格の確認方法
在留カードは、外国人が日本に適法に滞在していることを証明する最も重要な書類です。一般的にビザや就労ビザとも呼ばれますが、法律上の正式名称は在留資格です。採用面接の時には必ず原本の提示を求め、偽造でないかを慎重に確認する必要があります。
- 表面:氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間
- 裏面:資格外活動許可の有無
- ICチップの有無と偽造防止機能
- 写真と本人の照合
確認のポイントとして、いくつか重要な点があります。まず在留資格欄をチェックしましょう。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」など、就労可能な在留資格かどうかを見極めます。一方で「留学」や「家族滞在」の場合は、原則として就労が制限されているため、裏面の資格外活動許可の記載を確認することが不可欠です。
また、在留期間の満了日も重要な確認事項です。採用予定日から満了日まで十分な期間があるか、更新手続きのタイミングはいつかを把握しておきましょう。
パスポートと入国記録の見方
パスポートは本人確認の基本書類であり、在留カードと併せて確認することで、その外国人の滞在状況をより詳細に把握できます。パスポートに押印されている入国スタンプや在留資格認定証明書の写しから、入国の経緯や滞在の合法性を確認できます。
特に注目すべきは、最新の入国記録です。短期滞在から他の在留資格への変更があった場合、その手続きが適切に行われているかを確認する必要があります。また、パスポートの有効期限も重要な確認事項です。在留期間内であってもパスポートが失効していると、各種手続きに支障をきたす可能性があります。
さらに、過去の出入国記録から、その人の滞在パターンや他国での就労経験なども読み取ることができ、採用判断の参考情報として活用できます。
資格外活動許可証の重要性
留学生や家族滞在の在留資格を持った外国人を雇用する場合、資格外活動許可が必須となります。この許可なしに就労させると、企業側も不法就労助長罪に問われる危険性があります。資格外活動許可証は独立した書類として発行される場合もあれば、在留カードの裏面に記載される場合もあります。
留学生の場合、「包括的許可」として週28時間以内の就労が認められているケースが一般的です。しかし、風俗関連業務は明確に禁止されており、該当する職種での雇用はできません。一方、「個別許可」の場合は、特定の雇用主での特定業務に限定されているため、業務内容や勤務時間を詳細に確認する必要があります。
また、技能実習生の場合は原則として資格外活動は認められていないため、実習計画に基づく業務以外への従事は避けなければなりません。
雇用契約時に必要となる書類一覧
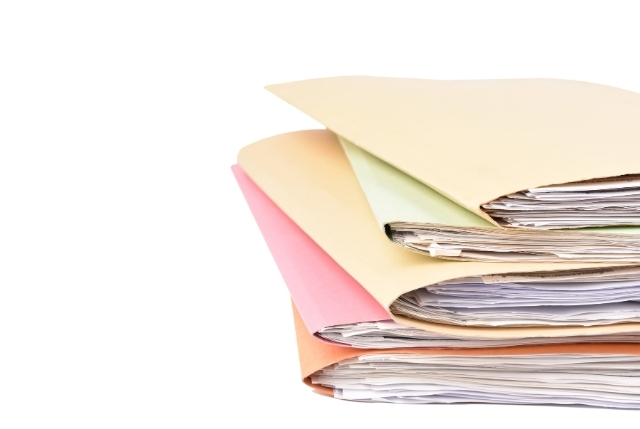
内定を出し採用が決定し、希望する労働条件について候補者と企業との間で合意を行い、雇用契約を締結する段階では、労働関連法令に基づいた適切な書類の準備が求められます。外国人雇用においても日本人と同様の労働条件を適用する必要がありますが、言語の壁や文化の違いを考慮した丁寧な説明と書面による明示が特に重要となります。
- 雇用契約書(日本語版・母国語版)
- 労働条件通知書
- 身元保証書
- 緊急連絡先届
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 雇用保険・社会保険関連書類
雇用契約書の作成ポイント
雇用契約書は労働条件を明確に定める重要な書類であり、外国人雇用においては日本語版に加えて母国語版も用意することをおすすめします。
- 賃金(基本給・諸手当・計算方法・支払日)
- 労働時間・休憩時間・休日
- 業務内容(在留資格の範囲内であることを明記)
- 契約期間・更新の有無
- 就業場所
- 退職に関する事項
外国人特有の注意点として、在留資格に定められた活動範囲内での業務であることを明記しましょう。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者に対して、単純労働を主とする業務を契約に盛り込むことはできません。
また、在留期間の満了に伴う契約終了の可能性についても明示することが望ましいでしょう。給与の支払い方法や各種手当についても、海外送金の可能性を考慮して詳細に定めておく必要があります。
労働条件通知書の記載事項
労働基準法第15条に基づき、雇用主は労働者に対して労働条件を書面で明示する義務があります。外国人労働者に対しても同様の義務が適用されるため、労働条件通知書の適切な作成と交付が必要です。
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、交替勤務
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期
- 退職に関する事項(解雇事由含む)
- 昇給に関する事項
- 退職手当に関する事項
- 賞与等に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
言語の問題を考慮し、必要に応じて母国語での説明資料を併用することで、労働者の理解を深めることができるでしょう。
身元保証書と緊急連絡先
外国人労働者の雇用において、身元保証書の提出を求めるケースが多くあります。これは万が一のトラブルや緊急事態に備えた重要な書類です。身元保証人は日本国内在住者である必要があり、本人との関係や連絡先を詳細に記載してもらう必要があります。
緊急連絡先については、本人の家族や友人の連絡先に加えて、母国の家族の連絡先も確保しておくことが望ましいでしょう。海外在住の家族については、時差を考慮した連絡可能時間も併せて記録しておきます。
また、本人が日本語での意思疎通に不安がある場合は、通訳付きでの面談を検討するなど、緊急時の対応がスムーズに行えるよう配慮することが重要です。これらの情報は個人情報として厳重に管理し、必要最小限の関係者のみが閲覧できるよう配慮することが重要です。
入社後の手続きで提出する書類

外国人労働者が実際に勤務を開始した後は、各種行政機関への届出や保険加入などの手続きが必要となります。これらの手続きには法定期限が設けられているものが多く、期限内の適切な対応が求められます。
| 【入社後に提出が必要な書類と期限】 | |
|---|---|
| 外国人雇用状況届出書 | 雇用開始から14日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用開始日の翌月10日まで |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 雇用開始から5日以内 |
| 給与所得者の扶養控除等申告書 | 給与支払開始前まで |
| 住民税関連書類 | 該当者のみ |
外国人雇用状況届出書の作成
外国人雇用状況届出書は、外国人を雇用または離職させた際にハローワークに提出が義務付けられている重要な書類です。ハローワークの窓口への持参のほか、様式を公式サイトからダウンロードして郵送や電子申請を行い、提出することもできます。
| 【届出のタイミング】 | |
|---|---|
| 雇用保険被保険者 | 雇用保険被保険者資格取得届と同時 |
| 雇用保険非被保険者 | 雇用開始から14日以内 |
- 外国人労働者の基本情報(氏名・生年月日、国籍)
- 在留資格・在留期間
- 従事する業務内容
- 事業所情報(所在地・名称・産業分類)
届出書には、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍、生年月日などの基本情報に加え、従事する業務内容を詳細に記載します。在留資格と実際の業務内容に齟齬がないよう、慎重に確認しながら作成しましょう。
この届出により、国は外国人労働者の就労状況を把握し、適切な雇用管理の指導や支援を行っています。届出を怠った場合は30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、必ず期限内に提出するよう注意が必要です。
近年、日本では少子高齢化と人口減少が進行し、多くの業種で深刻な人手不足が続いています。とりわけ、製造業、建設業、介護、宿泊、外食等の分野では、日本人労働力のみでの人材確保が困難な状況です。こうした背景から、外国人材の活用が急速に進展していま[…]
雇用保険と社会保険の手続き
外国人労働者も日本人と同様に、一定の条件を満たせば雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上の雇用見込み
- 雇用保険被保険者資格取得届の作成
- 雇用開始日の翌月10日までにハローワークに提出
- アルファベット表記の氏名も併記
- 国籍欄の記入も必須
- 対象:常時雇用される労働者
- 提出先:日本年金機構
- 期限:雇用開始から5日以内
外国人特有の注意点として、短期在留者の場合は脱退一時金の受給資格があることを説明し、必要な手続きについて案内することが重要です。なお、条件によっては一部保険への加入が不要となるケースもあります。これらの手続きを忘れずに行いましょう。
税務関連書類の準備
外国人労働者の給与からも所得税の源泉徴収が必要となるため、税務関連の手続きも欠かせません。まず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける必要があります。外国人の場合、扶養親族が海外在住のケースも多いため、適用要件を慎重に確認しましょう。
住民税については、前年の所得に基づいて課税されるため、日本での勤務が初年度の外国人には課税されません。しかし、2年目以降は住民税の特別徴収を行う必要があります。また、居住者・非居住者の判定により税額計算が異なるため、在留期間や滞在予定期間を考慮した適切な処理が求められます。
年末調整においては、海外の親族に対する扶養控除の適用可否や、母国での所得との重複課税の回避など、複雑な論点があるため、税務専門家への相談も検討すべきでしょう。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
在留資格別の注意点と追加書類

外国人労働者の在留資格は多岐にわたり、それぞれに異なる就労制限や必要書類があります。また国により独自の書類が必要になることがあります。フィリピン人を雇用するためには、MWO申請が必要です。
企業側は雇用する外国人が所属する予定の部署や業務内容を明確にし、その資格に応じた適切な雇用管理を行う責任があります。不適切な業務への従事や必要書類の不備は、在留資格の取消しや更新不許可につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務の場合
「技術・人文知識・国際業務」は最も一般的な就労系在留資格の一つであり、IT関連業務、通訳・翻訳、現地法人との折衝といった海外業務などに従事する外国人が該当します。この在留資格では、大学での専攻分野や実務経験と関連性のある業務に従事する必要があり、学歴や職歴が重要な要件となります。単純労働は原則として認められていません。
雇用時に追加で確認すべき書類として、大学の卒業証明書や成績証明書、その他技能を証明する資格証明書などがあります。これらの書類により、本人の学歴や経験が従事予定の業務内容と適合しているかを確認できます。また、在留資格の更新時には、実際の業務内容が在留資格の趣旨に合致していることを証明する必要があるため、業務日報や プロジェクト資料なども適切に保管しておくことが重要です。
転職の場合は、前職での業務内容や在留資格との整合性についても確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を検討する必要があります。
特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は、どちらも外国人材の受け入れ制度ですが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。特定技能は即戦力として働くことを目的とした制度であり、介護分野をはじめとした特定産業分野で、一定の技能水準と日本語能力が要求されます。一方、技能実習は技能の取得を目的とした制度であり、段階的な技能向上が前提となっています。
特定技能外国人を雇用する場合、1号特定技能外国人支援計画の作成と実施が義務付けられています。この支援計画には、生活オリエンテーションの実施、住居確保の支援、日本語学習の機会提供など、詳細な支援内容を記載する必要があります。また、登録支援機関への委託も可能ですが、その場合は委託契約書の締結が必要です。
技能実習の場合は、国から認定を受けた技能実習計画に基づいた指導が必要であり、定期的な技能検定の受検や実習記録の作成なども求められます。どちらの制度も、出入国在留管理庁(旧:入国管理局)への定期的な報告義務があるため、適切な記録管理が不可欠です。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度
出入国在留管理庁 外国人技能実習制度について
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
留学生アルバイトの特別対応
留学生をアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可の範囲内での就労に限定されるため、特別な配慮が必要です。包括的許可の場合、週28時間以内という時間制限があり、この時間数を超過すると不法就労となってしまいます。
時間管理においては、他のアルバイト先での勤務時間も含めて週28時間以内に収める必要があるため、本人からの申告を適切に管理することが重要です。また、留学生の本来の目的は学業であるため、学業に支障をきたさないよう勤務シフトを調整する配慮も必要でしょう。
長期休暇中(夏休み、春休みなど)は1日8時間以内であれば週28時間の制限を超えて働くことができますが、この場合も事前に資格外活動許可の変更申請が必要な場合があります。さらに、卒業後の就職を見据えて、在留資格変更のタイミングや必要な手続きについても早めに相談に乗ることで、優秀な人材の確保につなげることができます。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
手続きでよくあるトラブルと対処法

外国人雇用の手続きは複雑であり、企業側の準備不足や理解不足によりトラブルが発生するケースが少なくありません。あっ、しまった!とならないためにも、事前の対策と適切な対処法を理解しておくことが重要です。実際の現場でよく発生するトラブル事例を参考に、予防策を講じましょう。
書類不備による遅延の防止策
外国人雇用の手続きで最も多いトラブルが書類の不備による手続き遅延です。特に、在留カードのコピーの不鮮明さや、証明書類の有効期限切れなどが頻繁に発生します。その理由は、単純な確認漏れであることが大半です。
- チェックリストの作成と活用
- 各書類の確認項目を詳細化し、確認しやすくする。
- 複数人での確認体制
- 書類受け取り時の原本照合やコピーの鮮明さチェックを徹底する。
- 外国人本人へのサポート
- 必要書類の一覧を母国語で提供し、取得にかかる時間や費用について事前に説明する。
- 不備発見時の迅速な対応フロー整備
- 問題発生時の対応を事前に決めておく。
これらの対策により、書類の受け取り時に必ず原本と照合し、コピーの鮮明さを確認することが重要です。また、書類の不備を防ぐため、事前にフローを定めておくことで、迅速な修正対応が可能になります。
在留期間更新のタイミング
在留期間の更新手続きは、外国人労働者の継続雇用にとって極めて重要な手続きです。しかし、あっという間に期限が来てしまうことも多く、更新時期の把握不足により、在留期間が満了してしまうトラブルが発生することがあります。
- 更新申請可能期間:満了日の約3ヶ月前から
- 推奨申請時期:満了日の1ヶ月前まで
- 企業側の準備期間:申請の2週間前から書類準備開始
- 在職証明書
- 給与証明書(源泉徴収票等)
- 雇用契約書の写し
- 業務内容を証明する資料
- 雇用開始時に在留期間満了日を自社システムに登録し、リマインダーを設定しておく。
- 必要書類の発行体制を整備しておく。
- 万が一不許可となった場合の対応策も事前に検討する。
在留期間満了後の就労は不法就労となるため、企業側も重大な責任を問われる可能性があります。手続きに時間がかかり、複雑な場合は専門家への依頼も有効です。依頼には別途費用がかかりますが、計画的な更新手続きの管理が不可欠です。
転職時の手続きミス回避
外国人労働者が転職する場合、新しい雇用主での届出手続きが必要となります。この際、前職での離職届出と新職での雇用届出の両方が適切に行われない場合、外国人の就労状況が正確に把握できなくなってしまいます。
転職時の手続きミスを防ぐためには、まず前職の企業から適切な離職証明書や退職証明書を取得することが重要です。また、在留資格に変更がある場合は、在留資格変更許可申請も必要となるため、転職前に十分な検討と準備期間を設けることが必要でしょう。
新しい雇用主としては、外国人の前職での業務内容や在留資格との整合性を確認し、必要に応じて専門家への相談を検討することをおすすめします。さらに、転職に伴う社会保険の手続きや税務上の手続きも忘れずに行い、労働者に不利益が生じないよう配慮することが重要です。
外国人材の雇用に興味はあるものの、「どんな手続きが必要なのか分からない」「法令違反が怖い」と感じている企業担当者は少なくありません。特に、これまで外国人を雇った経験がない企業にとっては、在留資格の種類や手続きの流れ、管理体制など、知らなけれ[…]
まとめ|外国人雇用書類の準備で成功するポイント

以上、外国人雇用に必要な書類と手続きについて詳しく解説してきましたが、成功の鍵は事前の準備と継続的な管理にあります。まず重要なのは、採用前段階での在留資格と就労可能性の確認です。在留カードの真偽確認から始まり、在留資格の種類と業務内容の適合性を慎重に検討することで、後々のトラブルを大幅に減らせるでしょう。
雇用契約締結時には、日本人労働者と同じ労働条件を確保しつつ、外国人特有の配慮(母国語での説明、文化的違いの考慮など)を行うことが重要です。入社後の各種届出についても、法定期限を遵守し、必要書類を漏れなく提出することで、企業としての信頼性を保つことができます。
とはいえ、在留資格ごとの細かな要件や頻繁に変更される制度への対応は、専門知識なしには困難な面もあります。そのため、必要に応じて行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することも、リスク管理の観点から有効な選択肢といえるでしょう。適切な専門家のサポートを得ることで、より安心して外国人材の雇用を進めることが可能になります。この記事が専門家の監修のもと、皆様のお役に立てれば幸いです。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。当社のサービスには多くのメリットがあり、企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。