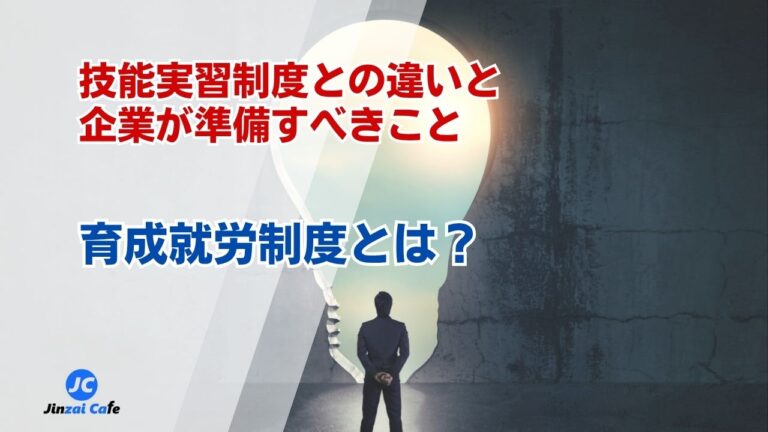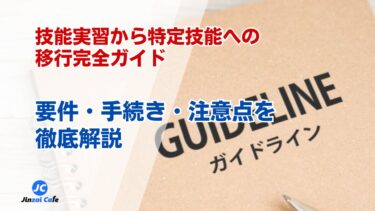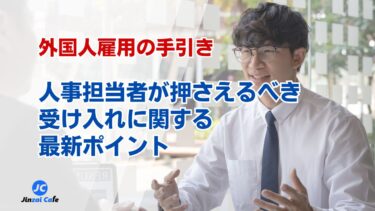外国人材の受入れを検討する企業にとって、2027年に施行予定の育成就労制度は見逃せない制度改正です。長年指摘されてきた技能実習制度の課題を解消し、人材育成と人手不足対応を両立させる新たな枠組みとして注目されています。
本記事では、育成就労制度の全体像から技能実習制度との違い、転籍要件、企業が満たすべき受入れ条件まで、人事担当者が押さえるべき情報を網羅的に解説します。制度施行までに準備すべきことも具体的にお伝えしますので、外国人雇用を成功させるための指針としてお役立てください。
育成就労制度の概要と創設背景

技能実習制度に代わる新しい仕組みとして、政府は育成就労制度の創設を決定しました。この制度は人材確保と人材育成を明確な目的とし、外国人労働者の権利保護を強化する内容となっています。2023年には有識者会議の報告書がまとめられ、2024年に関連法が国会で可決・成立しました。現在は2027年の施行に向けて、省令や具体的な運用方針の検討が進められています。
産業界からは人手不足解消への期待が寄せられる一方、一部からは懸念も示されており、適正な労働環境の整備が重要な課題として挙げられています。
育成就労制度とは何か
育成就労制度とは、特定の産業分野において外国人材を受け入れ、日本の技能や技術を段階的に習得してもらう在留資格です。従来の技能実習制度が「国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労では「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げています。
対象となる分野は人手不足が深刻な業種を中心に設定され、農業や製造業、建設、漁業、林業といった幅広い職種が含まれる予定です。在留期間は最長3年間で、一定の要件を満たせば特定技能1号への移行が許可される仕組みとなっています。
この制度により、外国人材が日本でキャリアアップしながら長期的に働ける道筋が整備されるのです。企業にとっては、育成した人材を継続的に雇用できるメリットがあります。
技能実習制度が抱えていた課題
技能実習制度は、国際貢献を目的として1993年に創設されました。しかし実態としては人手不足対応の側面が強く、制度の建前と実際の運用に乖離があると長年指摘されてきました。とりわけ深刻だったのが、転籍の制限による人権侵害の問題です。
実習生は原則として受入れ企業を変更できず、劣悪な労働環境や低賃金でも転職が困難でした。このため一部の悪質な企業では、賃金未払いやハラスメントといった問題が発生していたのです。また、一部の送出機構やブローカーが関与する高額な手数料の徴収も、実習生の経済的負担となっていました。
有識者会議ではこれらの実態が詳しく検討され、制度の在り方そのものを見直す必要性、すなわち外国人材の権利を守りながら適正に受け入れる新制度の必要性が強調されました。制度改正は、こうした課題への対応として位置づけられています。
参考:公益財団法人 国際人材協力機構 外国人技能実習制度とは
制度改正のポイントと施行時期
今回の改正では、制度目的の明確化と転籍ルールの柔軟化が大きな柱となっています。育成就労制度では、一定の条件下で本人の意向による転籍を認めることで、外国人材の権利保護を強化しました。また受入れ企業には、育成就労計画の作成と認定取得が義務づけられます。
監理団体は許可性の監理支援機関へと改組され、外部監査人の設置義務化などにより独立性・中立性が強化されます。また、継続的な学習による段階的な日本語能力向上や、育成期間中および特定技能1号移行時における技能評価(試験)の義務付けなど、育成・評価の仕組みも見直されました。
改正法は2024年6月21日に公布されましたが、施行日は公布日から起算して3年以内の政令で定める日であり現時点では未定です。施行までに基本方針や主務省令、分野別運用方針が決定される見込みです。
現在技能実習生を受け入れている企業は、新制度への円滑な移行のため、移行期間を十分に確保した上で、計画的な準備を進めることが求められています。政府は、人権侵害行為への迅速な対処 とともに、丁寧な事前広報を通じて、円滑な移行を支援する方針です。
技能実習制度との主な違い

育成就労制度は技能実習制度を大きく見直した内容となっており、制度目的から運用ルールまで幅広い変更が加えられています。最も注目すべきは、人材育成と人手不足対応を正式な目的として位置づけた点でしょう。これにより制度の透明性が高まり、企業も外国人材も明確な目標を持って取り組めるようになりました。
また転籍の柔軟化や特定技能制度への移行しやすさなど、外国人材のキャリア形成を支援する仕組みが強化されています。企業にとっては受入れ要件が厳しくなる面もありますが、この点は注意が必要であり、適正な運用により長期的な人材確保が可能になるのです。
制度目的の明確化と人材育成の位置づけ
技能実習制度では「国際貢献」が建前の目的とされ、人材確保は表向きの目的ではありませんでした。しかし実態としては人手不足対応として機能しており、この矛盾が様々な問題を生んでいたのです。育成就労制度では、こうした建前を廃止し、人材育成と人材確保を正式な目的として明記しました。
これにより企業は、外国人材を育成しながら戦力として活用することが制度上も認められます。同時に外国人材にとっても、技能向上とキャリア形成が明確な目標となるでしょう。
受入れ機関には育成就労計画の作成が求められ、具体的な育成内容や到達目標を設定する必要があります。提出された計画は外国人育成就労機構による認定を受けなければならず、適正な育成体制の構築が義務づけられました。目的の明確化は、制度全体の透明性を高める重要な変更点といえます。
受入れ分野と対象職種の変更
育成就労制度の対象分野は、人手不足が深刻で外国人材の受入れが必要と認められる産業に限定されます。具体的な分野は今後の省令で定められますが、特定技能制度の分野との整合性が図られる方針です。農業、製造業、建設、漁業、介護といった分野が中心になると見込まれており、これら以外の分野についても今後の検討課題とされています。
技能実習制度では対象職種が細かく区分されていましたが、育成就労では分野別の運用となり、より柔軟な業務配分が可能になる見通しです。ただし対象外の分野では育成就労制度を利用できないため、企業は自社の業種が該当するか確認する必要があります。
また分野ごとに受入れ人数の上限や、必要な育成内容の基準が設定される予定です。対象職種の一覧は施行前に公表されるため、最新情報を随時チェックしておきましょう。制度設計の段階から、業界団体との協議も進められています。地方の経済団体とも協力し、地域の実情を踏まえた設計が進められており、対象分野の拡大も将来的に検討されています。
在留期間と特定技能制度への移行
育成就労制度の在留期間は最長3年間とされており、技能実習制度の基本的な枠組みを踏襲しています。しかし大きく異なるのが、特定技能1号への移行がスムーズになった点です。育成就労で3年間の経験を積み、技能試験と日本語能力試験に合格すれば、特定技能1号へ移行できます。
特定技能1号の在留期間は最長5年間ですから、合計で最長8年間の就労が可能になるのです。さらに特定技能2号の対象分野であれば、在留資格の更新は必要ですが、在留期間の上限なく日本で働き続けられます。この仕組みにより、外国人材は段階的にキャリアアップしながら長期的に日本で活躍できるでしょう。
これは技能実習制度の課題であった、3年や5年での帰国を前提とした仕組みからの大きな転換です。企業にとっては、育成した人材を継続雇用できるメリットが大きくなります。ただし移行には試験合格が必須のため、企業は外国人材の学習支援体制を整える必要があります。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
転籍要件と外国人材の権利保護

育成就労制度で最も注目される変更点が、転籍ルールの柔軟化です。技能実習制度では原則として転籍が認められず、これが人権侵害の温床となっていました。新制度ではやむを得ない事情がある場合に加え、一定期間経過後は本人の意向による転籍も可能になります。この変更により外国人材の選択肢が広がり、劣悪な労働環境から逃れる手段が確保されるのです。
企業側は適正な労働条件と育成環境を提供することで、人材の定着を図る必要があります。転籍を防ぐのではなく、企業間の人材獲得競争を意識した上で、選ばれる職場づくりが求められる時代になったといえるでしょう。人材の定着は、企業の持続的な発展にも不可欠です。
やむを得ない事情による転籍の条件
現行制度と同様に、育成就労制度では、受入れ機関の倒産や事業縮小など、やむを得ない事情がある場合には就労開始直後でも転籍が認められます。これは技能実習制度でも一部認められていましたが、新制度ではその範囲が明確化され、手続きも簡素化される見込みです。
やむを得ない事情には以下のようなケースが含まれます。
- 受入れ企業の倒産や事業廃止
- 自然災害による事業継続の困難
- 受入れ機関の不正行為による認定取消
- ハラスメントや労働条件の重大な違反等
こうした状況では、外国人材が速やかに新しい受入れ機関へ移れる仕組みが整備されます。監理支援機関は、転籍先の紹介や手続きのサポートを行う責任を負います。企業としては、万が一の事態に備えて関係機関と連携体制を構築しておくことが重要です。
本人意向による転籍の要件
育成就労制度の大きな特徴が、本人の意向による転籍を一定条件下で認めた点です。具体的には就労開始から原則として1年が経過し、かつ一定の技術水準と日本語能力に到達した後に、同一分野内での転籍が可能になります。原則、1年以内の転籍は認められません。この仕組みにより、外国人材はより良い労働条件や成長機会を求めて転職できるのです。
転籍を希望する場合、外国人材は監理支援機関を通じて手続きを進めます。転籍先の受入れ機関は、育成就労計画の認定を受けている必要があります。また転籍回数には制限が設けられ、頻繁な転籍は認められない見通しです。
企業にとっては、育成した人材が他社へ移る可能性があるため、魅力的な職場環境の整備が不可欠となります。適正な賃金水準の設定、日本語教育の充実、キャリアパスの明示などにより、外国人材に選ばれる企業を目指しましょう。
外国人材の権利保護と適正な労働環境
育成就労制度では、外国人材の権利保護が大幅に強化されています。受入れ機関には日本人と同じ、もしくはそれ以上の報酬を支払うことが義務づけられ、最低賃金の遵守はもちろん、地域や職種の相場に応じた適切な水準が求められます。また労働時間や休日についても、労働基準法を厳格に適用する方針です。
相談体制の整備も重要なポイントです。外国人材が困ったときに気軽に相談できる窓口を設置し、母国語でのサポートを提供する必要があります。監理支援機関には定期的な訪問指導が義務づけられ、労働環境や生活状況を確認します。さらに悪質な受入れ機関に対しては、認定の取消や受入れ停止といった厳しい措置が科されるでしょう。
企業は法令遵守を徹底し、外国人材が安心して働ける環境を整えることで、制度の適正な運用に貢献できます。権利保護は企業の社会的責任であると同時に、人材定着の基盤にもなるのです。
人材不足が深刻化する現代の日本社会において、外国人材の活用は企業の持続的成長に欠かせない重要な戦略となっています。共生社会の実現に向けた具体的な取り組みを解説します。外国人材との共生を推進し、多様性を活かした組織づくりを行うことで、[…]
企業の受入れ要件と支援体制

今回導入される育成就労制度を利用して外国人材を受け入れるには、企業が一定の要件を満たし認定を受ける必要があります。技能実習制度と比べて基準が厳格化され、適正な育成体制と労働環境の整備が求められるのです。具体的には育成就労計画の作成と認定取得が必須となり、計画には育成内容や到達目標、支援体制などを詳細に記載しなければなりません。
また監理支援機関との連携も重要な要素です。認定要件を満たすことは、外国人材を適切に受け入れるための最低限の条件であり、企業の信頼性を示す証でもあります。
参考:
厚生労働省 育成就労制度の概要
厚生労働省 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
出入国在留管理庁 育成就労制度・特定技能制度Q&A
受入れ企業が満たすべき要件
育成就労制度で外国人材を受け入れる企業には、以下のような要件が設定されています。
- 労働関係法令の遵守実績
- 安定した経営基盤と事業継続性
- 適正な賃金水準の確保
- 社会保険への適切な加入のほか、納税義務の履行
- 育成支援体制の適正化
- 育成計画に基づく指導体制
- 日本語学習の支援環境
- 技能評価の実施能力
過去に不正行為や法令違反があった受入れ機関は、一定期間受入れが認められない方針です。これらの適正化された要件や体制を確保した上で、育成就労計画の認定申請が可能となります。
分野によっては、さらに追加の要件が課される可能性があるため、要件の詳細は今後主務省令で定められる最新情報を確認しておきましょう。
育成就労計画の作成と認定
受入れ機関は、外国人材ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けなければなりません。計画作成の際に注意すべきポイントとして、単なる労働力としてではなく、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材に育成する育成プログラムの設計が求められる点が挙げられます。
計画作成のポイントは以下の通りです。
- 職種に応じた段階的な育成カリキュラム
- 月次・年次の到達目標の明確化
- 技能評価の実施時期と方法
- 日本語教育の時間数と内容
- 生活支援や相談体制の具体策
計画は実際の育成状況に応じて柔軟に見直すことも可能です。ただし大幅な変更には再認定が必要となる場合があります。認定を受けた計画に沿って適切に育成を実施しているか、定期的に監理支援機関が監査や指導・助言を行い、外国人育成就労機構が実地検査を行います。計画的な育成は外国人材の成長につながり、企業の生産性向上にも寄与するでしょう。
監理支援機関の役割
監理支援機関は、受入れ機関(育成就労実施者)と外国人材の間に立ち、育成就労の適正な実施を確保する重要な役割を担います。具体的には、育成就労外国人と実施者の間の雇用関係の成立のあっせん、受入れ機関への監理・指導、転籍時の関係機関との連絡調整 など、幅広いサポートを提供します。
監理支援機関の主な業務には以下が含まれます。
- 受入れ機関に対する監理、指導
- 育成就労計画の作成支援
- 国際的なマッチング
- 外国人育成就労機構やハローワークと連携した転籍支援
- 適正な育成就労が実施されているかどうかの監査
- 育成就労外国人への支援・保護、および相談対応
- 試験合格率等の向上に向けた技能向上の支援
監理支援機関自体は許可制となり、許可要件が厳格化されます。特に審査されるのは、職員の配置や財政基盤、相談対応体制、および外部監査人の設置などです。また、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与が制限され、独立性・中立性の担保が図られます。
最終的には、外国人育成就労機構が育成就労計画の認定や実地検査、指導・助言などを担い、国が監督します。企業は、こうした厳格な要件をクリアした優良で信頼できる監理支援機関を選び、密に連携することが、外国人材の受入れから育成までを円滑に進める鍵となるでしょう。
近年、日本の労働市場では人手不足が深刻化しており、特に介護、建設、サービス業などでは慢性的な人材不足が課題となっています。こうした状況の中で注目されているのが、海外からの労働者の活用です。多様な文化や価値観を持つ[…]
日本語能力と技能評価の基準

育成就労制度では、外国人材の日本語能力と技能レベルに明確な基準が設けられています。来日時には一定の日本語能力が求められ、就労期間中も継続的な学習支援が必要です。また技能評価についても、定期的な試験や検定により習得状況を確認する仕組みとなっています。
これらの基準設定は、外国人材が安全に働き、着実に成長できる環境を整えるためのものです。企業にとっては、日本語教育や技能指導の体制づくりが重要な課題となります。適切なサポートにより、外国人材の能力向上と職場でのコミュニケーション円滑化を実現しましょう。
入国時に必要な日本語レベル
育成就労制度で来日する外国人材には、入国時に基礎的な日本語能力が求められます。具体的には日本語能力試験のN5レベル相当、またはA1レベルに相当する能力の証明が必要です。N5は日本語学習の初期段階であり、ひらがなやカタカナの読み書き、簡単な日常会話ができる水準を指します。
ただし分野によっては、より高いレベルが求められる可能性もあります。たとえば介護分野では、利用者とのコミュニケーションが業務の中心となるため、N4レベル程度が望ましいとされるでしょう。一方で製造業など、作業中心の職種では基礎レベルで十分なケースもあります。
多くの場合、送出機関との協力の下で入国前には送出国での日本語教育が実施され、必要な水準に到達してから来日する流れとなります。企業は受入れ後も継続的な日本語学習を支援し、コミュニケーション能力の向上を図る必要があります。日本語能力の向上は、業務効率や職場の安全性向上にもつながるのです。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度及び育成就労制度に係る日本語試験の作成のためのガイドライン
公益財団法人 国際人材協力機構 育成就労制度についてのよくあるご質問
技能試験と評価の仕組み
育成就労期間中には、段階的な技能評価が実施されます。評価方法は分野ごとに異なりますが、技能検定や業界団体が作成する試験が中心となる見込みです。たとえば製造業では技能検定の基礎級や3級、建設業では各職種の技能試験が想定されています。
評価は通常、就労開始から1年後、2年後といった節目に実施されます。合格することで、より高度な業務への従事が認められ、特定技能制度への移行要件も満たせるのです。試験内容は実技試験と学科試験で構成され、実際の業務で必要な能力が総合的に評価されます。
企業には、外国人材が試験に合格できるよう計画的な育成と受験サポートが求められます。模擬試験の実施や、試験対策の時間確保なども効果的でしょう。技能評価は外国人材の成長を可視化し、モチベーション向上にもつながる重要な仕組みです。
継続的な日本語教育と能力向上支援
入国時の基礎的な日本語能力だけでは、職場でのコミュニケーションや日常生活に十分とはいえません。育成就労制度では、受入れ機関に対し継続的な日本語教育の提供が義務づけられています。週に一定時間以上の学習機会を確保し、段階的にN4、N3レベルへの向上を目指すのです。
日本語教育の方法としては、以下のような選択肢があります。
- 外部の日本語学校への通学支援
- オンライン受講用学習プログラムの提供
- 社内での日本語講習の実施
- 監理支援機関が主催する研修への参加
学習内容は日常会話だけでなく、業務で使用する専門用語や安全に関する指示の理解も含めるべきでしょう。また日本語能力の向上は、特定技能制度への移行にも不可欠です。
企業は外国人材の学習意欲を尊重し、勤務時間内での学習機会や費用負担の支援を検討してください。日本語能力の向上により、外国人材は職場により深く溶け込み、長期的な活躍が期待できます。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
日本の多くの会社が直面している最大の課題のひとつは、人手不足です。特に介護や製造、建設などの特定技能分野では、外国人労働者の採用が急速に拡大しており、その事業規模も大きくなっています。しかし、その一方で職場における日本語でのコミュニケーショ[…]
今後のスケジュールと企業が準備すべきこと

育成就労制度は2027年の施行を目指し、現在詳細な制度設計が進められています。この新しい制度の在り方については、様々な角度から議論が行われています。この制度に係る関連省令の策定や、分野別の運用基準の決定が今後行われる予定です。
企業にとってはこの準備期間が、新制度への対応体制を整える重要な時期となります。現在技能実習生を受け入れている場合は、新制度への移行計画も検討しなければなりません。早めに情報収集を始め、社内体制の見直しや必要な投資を計画的に進めることが、スムーズな移行につながるでしょう。制度施行時に慌てることなく、余裕を持って準備を進めてください。
制度施行までの流れと関連省令
育成就労制度の関連法案は2024年に国会で可決・成立し、現在は施行に向けた準備段階にあります。2027年の施行までに、以下のようなスケジュールで制度の詳細が固まっていく見通しです。
【想定されるスケジュール】
- 2025年:省令案の公表と意見募集
- 2026年前半:省令の正式決定と公布
- 2026年後半:受入れ機関や監理支援機関の認定申請開始
- 2027年:制度施行、新規受入れ開始
省令では対象分野の一覧、受入れ人数の上限、育成就労計画の詳細な要件、監理支援機関の認定基準などが定められます。また分野ごとの運用方針や技能評価の具体的な方法も、業界団体との協議を経て決定される見込みです。企業は政府や業界団体が発信する最新情報を定期的にチェックし、制度の全体像を把握しておくことが重要です。
現在の技能実習生への対応方針
育成就労制度の施行後も、既存の技能実習生は在留期間満了まで現行制度で受け入れを継続できます。急に制度が切り替わるわけではなく、段階的な移行期間が設けられる見込みです。ただし新規の技能実習生受入れは、施行時点から育成就労制度へ完全に移行します。
現在受け入れている技能実習生に対しては、以下の対応が考えられます。
- 在留期間満了後、特定技能への移行を支援
- 優秀な人材には長期雇用を前提とした育成計画を提示
- 新制度の内容を丁寧に説明し、今後の選択肢を共有
技能実習から特定技能への移行は現行制度でも可能ですから、企業は該当する外国人材に対し、現行制度と新制度の相違点を踏まえ、試験対策などの支援を強化すると良いでしょう。長期的に活躍してもらうためのキャリアパスを明示することで、外国人材のモチベーション向上にもつながります。
企業が今から始められる準備事項
新制度への移行を円滑に進めるなら、2027年の制度施行に向けて、企業が今から取り組むべき準備は多岐にわたります。早期に着手することで、施行時にスムーズな対応が可能となるでしょう。
- 育成責任者候補の人材育成と実務経験の蓄積
- 社内の育成カリキュラムの見直しと充実化
- 日本語教育の支援体制の構築
- 労働環境や待遇の点検と改善
- 信頼できる監理支援機関の選定と関係構築
- 外国人材受入れに関する社内規程の整備
また業界団体や同業他社との情報交換も有益です。先進的な取り組み事例を学び、自社に適した受入れ体制を設計しましょう。さらに現在の外国人雇用に関する課題を洗い出し、新制度移行を機に解決することも重要です。今から準備を始めることで、育成就労制度を活用した効果的な外国人材受入れが実現できます。
まとめ|育成就労制度を活用した外国人材受入れの成功に向けて

育成就労制度は、技能実習制度の課題を解消し、人材育成と人材確保を明確な目的とする新しい枠組みです。2027年の施行に向け、転籍ルールの柔軟化や権利保護が強化されます。企業には受入れ要件の厳格化が求められますが、適正な運用により長期的な人材確保が可能となるでしょう。
成功の鍵は、早期の情報収集と計画的な準備です。育成就労計画の作成や日本語教育の支援体制など、今後の省令を見据えながら、今から自社の体制を見直しましょう。外国人材が安心して成長できる環境を整えることが、選ばれる企業となり、日本の産業を支える力にもつながります。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しております。