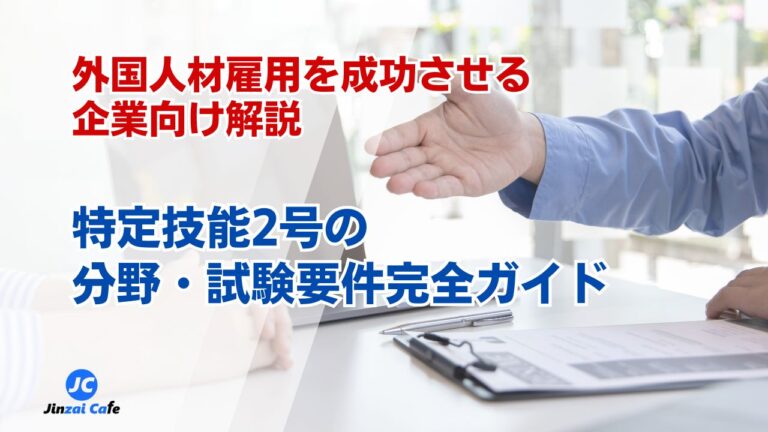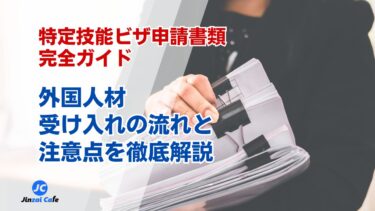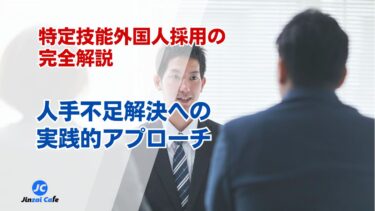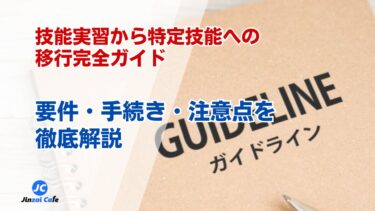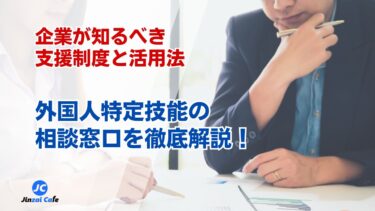外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内容について正確な情報を把握することは容易ではありません。
人材不足が深刻化する中、優秀な外国人材を確保し、企業の成長につなげるためには、特定技能制度の仕組みを正しく理解し、適切な採用戦略を立てることが不可欠です。本記事では、特定技能2号の全体像から具体的な分野別要件、試験内容、企業が知っておくべき実務的なポイントまで、実践的な観点から詳しく解説いたします。
この記事を読むことで、特定技能2号による外国人材の採用を成功させるための知識と具体的な方法を身につけることができ、企業の人材戦略に活かしていただけるでしょう。
特定技能2号制度の概要と基本要件
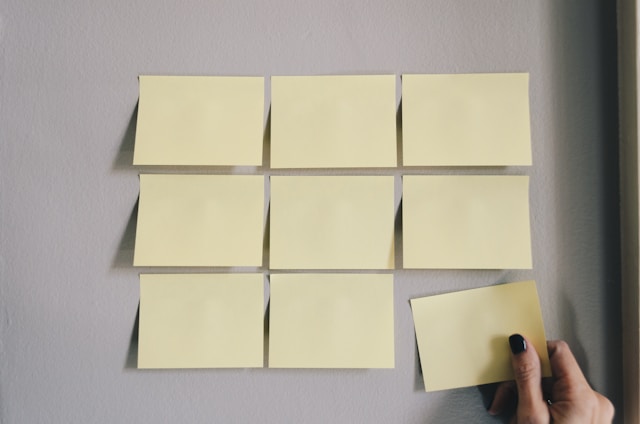
特定技能2号は、「熟練した技能」を有する外国人材が日本の特定産業分野で長期的に就労できる在留資格です。2019年に創設された特定技能制度の一類型であり、特定技能1号よりも高い専門性や、管理者等として業務を遂行できる能力が求められます。
この制度は、日本の産業界における深刻な人手不足を補うと同時に、高度な技能を持つ外国人材の長期定着を促進することを目的としています。特定技能2号の最大の特徴は、在留期間の更新回数に上限がなく、配偶者や子どもの帯同が認められている点です。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和7年11月1日更新)
特定技能2号の基本的な要件と条件
特定技能2号を取得するためには、分野ごとに定められた高度な技能評価試験(または技能検定1級等)に合格することが必須です。特定技能1号として実務経験を積んでから試験に臨むのが一般的ですが、必ずしも1号の在留経験は必須ではなく、試験に合格すれば直接2号の資格を取得することも可能です。
日本語能力については、原則として日本語能力試験(JLPT)やその他の日本語要件は課されていませんが、漁業分野および外食業分野ではJLPT N3以上が必要です。また、技能評価試験自体が日本語で実施されるため、実務上は一定レベルの日本語能力が求められます。
企業は、特定技能2号外国人材の雇用にあたり、労働基準法などの関連法規を遵守し、良好な職場環境を整備することが必要です。なお、特定技能2号には特定技能1号のような法定支援義務はありませんが、日本人と同等以上の報酬を支払うことが条件となっています。
参考:日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
特定技能1号との違いと移行プロセス
特定技能1号と2号の最も大きな違いは、求められる技能レベルにあります。1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」であるのに対し、2号は管理者(例:現場監督)として自らの判断で業務を遂行できるレベルの「熟練した技能」が求められ、多くの場合、他の技能者を指導する能力も評価されます。
特定技能1号から2号への移行は一般的なキャリアパスですが、前述の通り、1号を経ずに直接2号の試験に合格する道もあります。移行プロセスでは、技能測定試験の合格証明書を中心に、実務経験を証明する書類(求められる場合)や雇用契約書などの準備が必要となります。企業は移行手続きにおいて、外国人材の技能向上をサポートし、必要な研修や指導を提供することが重要です。
在留期間と家族帯同の可能性
特定技能2号の大きな特徴は、在留期間の更新回数に上限がないことです。これにより、外国人材は長期的に日本に在留し、キャリアを形成していくことが可能となり、企業にとっても人材の安定確保に直結します。また、特定技能2号取得者は「配偶者」および「子」の帯同が認められており、家族と共に日本で安定した生活基盤を築くことができます。
この制度により、外国人材のワークライフバランスが向上し、企業への定着率も高まることが期待されます。企業側としても、長期的な人材育成計画を立てやすくなり、投資対効果の高い人材活用が可能となります。
2号対象分野と業務内容の詳細解説

特定技能2号の対象分野は、制度開始当初の2分野から大幅に拡大され、現在は11分野が対象となっています。これにより、より多くの産業で熟練した技能を持つ外国人材の長期的な活躍が可能となりました。各分野において、具体的な業務内容や求められる技能レベルが明確に定められており、企業は自社の業務内容と照らし合わせて採用を検討する必要があります。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について
建設分野の業務区分と技能要件
建設分野における特定技能2号では、複数の業務区分が設定されています。土木分野では、現場監督や工程管理、品質管理などの業務に従事することが可能で、建築分野では施工管理や安全管理、技術指導などの業務が含まれます。技能要件としては、建設現場での実務経験に加え、図面の読解能力、安全管理に関する知識、部下や同僚への指導能力などが求められます。
また、建設業界に特定された法規制や安全基準についても十分な理解が必要となります。企業は採用時に、候補者がこれらの要件を満たしているかを慎重に評価し、必要に応じて追加的な研修を提供することが重要です。
参考:国土交通省 建設分野の2号特定技能外国人に求める実務経験等について
造船・舶用工業分野の専門技能
造船・舶用工業分野では、溶接、塗装、鉄工、仕上げなどの専門技能が対象となります。特定技能2号レベルでは、単純な作業の実行だけでなく、工程全体の管理や品質確保、技術的な問題の解決能力が求められます。溶接分野では高度な溶接技術と検査能力、塗装分野では材料の特性理解と品質管理、鉄工分野では精密な製造・加工技術と図面解読能力などが評価されます。
これらの技能は長年の経験と継続的な学習によって習得されるものであり、企業は外国人材の技能向上を支援する体制を整備する必要があります。また、造船業界の国際基準や安全規制についても理解を深めることが重要です。
参考:国土交通省 造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ
拡大された対象分野と今後の動向
制度開始当初は建設業と造船・舶用工業の2分野に限定されていましたが、2023年の制度改正により、対象分野は大幅に拡大されました。新たに追加されたのは、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野です。これにより、合計11分野で特定技能2号の受け入れが可能となり、これまで人材不足に悩んでいた多くの企業にとって、優秀な外国人材を長期的に確保するための新たな道が開かれました。
企業は自社の業界動向を注視し、これらの拡大された分野における受け入れ準備を進めることが重要です。関連する公式サイトや業界団体が主催する説明会からの最新情報を定期的に確認し、よくある質問やQ&Aページも活用して正確な情報収集を行うことをお勧めします。今後、各分野での試験の実施や受け入れ体制の整備が本格化していくため、制度変更に適切に対応することが企業の競争力向上につながります。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について
出入国在留管理庁 特定技能制度に関するQ&A
深刻な人手不足に直面する日本の企業にとって、外国人材の活用は喫緊の課題となっています。特に製造業、建設業、介護分野などでは、即戦力となる人材の確保が企業の存続に関わる重要な経営課題です。2019年4月に創設された特定技能制度は、これ[…]
技能測定試験の内容と合格基準
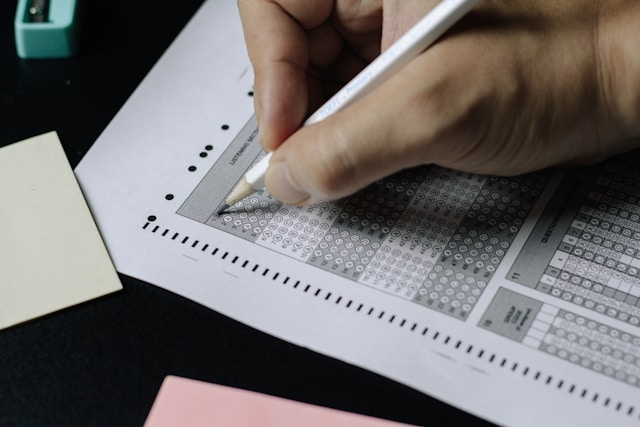
特定技能2号取得のための技能測定試験は、各分野の専門的な知識と実技能力を総合的に評価する試験です。試験内容は分野ごとに異なり、実際の業務で必要となる高度な技能と知識が測定されます。企業は採用候補者の受験をサポートし、合格に向けた準備を支援することで、優秀な人材の確保につなげることができます。
建設分野の技能測定試験概要
建設分野の技能測定試験では、現場管理能力、安全管理知識、技術指導能力などが総合的に評価されます。学科試験では建設に関する法規制、安全基準、品質管理、工程管理などの知識が問われ、実技試験では実際の現場を想定した作業や判断能力が測定されます。
試験は年2回程度実施され、合格水準は各科目で60%以上の得点が必要となります。企業は外国人材の試験準備を支援するため、専門書籍の提供、研修機会の創出、先輩職員による指導などの体制を整備することが重要です。また、試験に関する詳細な資料請求や相談窓口の利用を通じて最新情報を定期的に確認し、候補者に適切な情報提供を行うことで、合格率の向上を図ることができます。
参考:国土交通省 「建設分野特定技能2号評価試験」試験実施要領
造船・舶用工業分野の実技評価基準
造船・舶用工業分野の技能測定試験では、高度な技術力と品質管理能力が重点的に評価されます。溶接分野では精密な溶接技術と検査能力、塗装分野では材料知識と施工技術、鉄工分野では加工精度と図面理解力などが測定されます。実技試験では実際の作業を通じて技能レベルを確認し、学科試験では専門知識と安全管理に関する理解度が問われます。評価基準は国際的な造船業界の標準に準拠しており、高い品質要求に対応できる技能が求められます。
企業は試験対策として、最新の技術動向に関する情報提供、実技練習の機会創出、専門資格取得の支援などを行うことで、外国人材のスキルアップを促進することができます。
参考:国土交通省 造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領
日本語能力要件と評価方法
特定技能2号では、業務上必要な日本語能力が求められますが、特定技能1号ほど厳格な日本語試験の合格は必須ではありません。ただし、現場での円滑なコミュニケーション、技術的な指示の理解、安全管理に関する情報共有などが可能なレベルの日本語能力が必要となります。評価は実際の業務場面での日本語使用能力(Japanese language proficiency in workplace settings)を中心として行い、書面でのやり取り、口頭での報告、緊急時の対応などが総合的に判断されます。
企業は外国人材の日本語能力向上を支援するため、日本語研修の提供、職場でのOJT指導、日本語学習教材の提供などを継続的に実施することが重要です。また、職場内でのコミュニケーション環境を整備し、日本人職員との交流を促進することで、自然な日本語習得を支援することができます。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
企業の受け入れ体制と支援義務

特定技能2号の外国人材を受け入れる企業は、法令を遵守した適切な雇用環境を整備する義務があります。ただし、特定技能1号で必須とされている「1号特定技能外国人支援計画」の策定・実施義務は、特定技能2号では免除されます。
これは、特定技能2号の外国人材が、ある程度自立して日本で生活できる能力を有すると想定されているためです。しかし、外国人材が能力を最大限に発揮し、長期的に定着するためには、企業の自主的なサポートと良好な職場環境づくりが不可欠です。
必要な受け入れ機関の要件
特定技能2号の受け入れ機関となる企業は、1号と同様に労働基準法などの関連法規を遵守し、適切な労働環境を提供する必要があります。具体的には、雇用契約の適正化、賃金の適正支払い、労働時間の管理、安全衛生管理の徹底などが求められます。
また、過去5年間に出入国管理法違反や労働基準法違反がないこと、外国人材に安定した雇用を継続できる財政基盤があることなども条件となります。企業は受け入れ申請前に自社の体制を点検し、これらの要件を満たしているか確認することが重要です。
任意で行う支援と良好な職場環境の構築
特定技能2号の外国人材に対して、法的に定められた生活支援(住居確保のサポート等)の義務はありません。
しかし、企業が任意で実施する支援は、人材の定着と活躍に大きな影響を与えます。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- キャリア形成の支援
- より高度な資格取得の支援や、将来のキャリアパスに関する相談に応じる。
- 円滑なコミュニケーションの促進
- 日本人従業員との交流会を設けるなど、職場に溶け込みやすい環境を整備する。
- 生活上の相談対応
- 家族の帯同に関する手続きや子どもの教育など、生活上の悩みについて相談に応じる体制を整える。
これらの自主的なサポートは、外国人材のエンゲージメントを高め、生産性向上にもつながります。
登録支援機関の任意活用について
前述の通り、特定技能2号では登録支援機関への支援委託は義務ではありません。しかし、企業が独自に手厚いサポートを提供したい場合や、外国人材本人から生活面でのサポートの希望があった場合などには、任意で登録支援機関のサービスを活用することができます。
例えば、「家族帯同に関する手続きのサポート」や「子どもの学校探し」など、専門的な知識が必要な支援をスポットで依頼することも考えられます。企業のリソースや外国人材のニーズに応じて、選択肢の一つとして登録支援機関との連携を検討することは、より良い受け入れ体制の構築に役立ちます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
採用から就労開始までの実務手続き

特定技能2号の外国人材を採用する際の手続きは複雑で、多くの書類準備と段階的なプロセスが必要となります。企業は事前に手続きの流れを把握し、必要な準備を整えることで、スムーズな採用を実現することができます。また、適切な手続きを行うことで、後のトラブルを回避し、安定した雇用関係を築くことが可能となります。
必要書類の準備と申請手順
特定技能2号の在留資格申請には、多数の書類が必要となります。必要書類の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できますが、主なものは以下の通りです。
【企業側で準備する書類】
- 雇用契約書
- 企業の登記事項証明書
- 決算書類
- 受け入れ体制に関する説明書 など
【外国人材側で準備する書類】
- 試験実施機関から発行される技能測定試験の合格証明書
- 実務経験証明書
- パスポート
- 履歴書 など
申請手順では、まず必要書類を収集・作成し、出入国在留管理局に申請を行います。審査期間は通常1か月から3か月程度かかるため、企業は余裕を持ったスケジュールで準備を進める必要があります。書類に不備があると審査が長期化する可能性があるため、事前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。
雇用契約締結時の注意点
特定技能2号の雇用契約では、日本人と同等以上の報酬を支払うことが法的に義務付けられており、この点には特に注意が必要です。契約書には職務内容、勤務地、労働時間、休日、賃金、福利厚生などを明確に記載し、外国人材が内容を十分理解できるよう配慮する必要があります。
また、昇進・昇格の可能性、研修制度、キャリア開発支援などについても明記することで、外国人材のモチベーション向上につなげることができます。契約期間は在留期間と整合性を保ち、更新条件についても明確に定めることが重要です。労働条件の変更が生じる場合は、事前に外国人材と十分な協議を行い、合意形成を図ることで、良好な労使関係を維持することができます。
在留カード取得と各種手続き
在留資格の許可が下りた後、外国人材は在留カードの交付を受ける必要があります。在留カードは身分証明書として重要な役割を果たすため、企業は取得手続きを適切にサポートする必要があります。また、住民登録、国民健康保険への加入、税務関係の手続き等、就労開始に必要な各種手続きを段階的に進める必要があります。
これらの手続きに関する詳細情報は、関連する公的機関のサイトで確認できますが、手続きの複雑さを考慮すると、企業による丁寧なサポートが不可欠です。企業は手続きの流れを整理し、外国人材に対して適切な案内と支援を提供し、手続き上の不明点については相談窓口を活用することで、スムーズな就労開始を実現できます。手続き完了後は、職場でのオリエンテーションを実施し、業務内容、職場ルール、安全管理などについて詳しく説明することで、効果的な職場適応を促進することができます。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
まとめ|特定技能2号を活用した人材戦略の成功に向けて

特定技能2号制度は、高度な技能を持つ外国人材を長期的に確保し、企業の持続的な成長を支える重要な制度です。本記事では、制度の概要から具体的な分野別要件、技能測定試験の内容、企業の受け入れ体制、実務手続きまで、企業の人事担当者・経営者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説いたしました。
特定技能2号の活用を成功させるためには、単に制度を理解するだけでなく、外国人材の視点に立った受け入れ体制の構築と継続的な支援が不可欠です。企業は法的要件を満たすだけでなく、外国人材が能力を最大限発揮できる環境づくりに取り組むことで、人材不足の解決と企業競争力の向上を同時に実現することができます。これは企業の上層部から現場まで、会社全体での取り組みが必要となる重要な課題です。
今後、対象分野の拡大や制度の変更が予想される中、企業は最新の情報収集を継続し、変化に適応できる柔軟な体制を整備することが重要です。適切な準備と継続的な取り組みにより、特定技能2号制度を活用した外国人材の採用を成功させ、企業の発展につなげていただければと思います。この制度は、日本の労働市場における新たな可能性を切り開く重要な選択肢の一つとして、今後さらなる発展が期待されています。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。
深刻な人手不足に直面している企業経営者の皆様、外国人材の活用を検討されていませんか?日本の労働力不足は年々深刻化しており、特に製造業、建設業、介護分野では即戦力となる人材の確保が喫緊の課題となっています。2019年に創設された特定技[…]