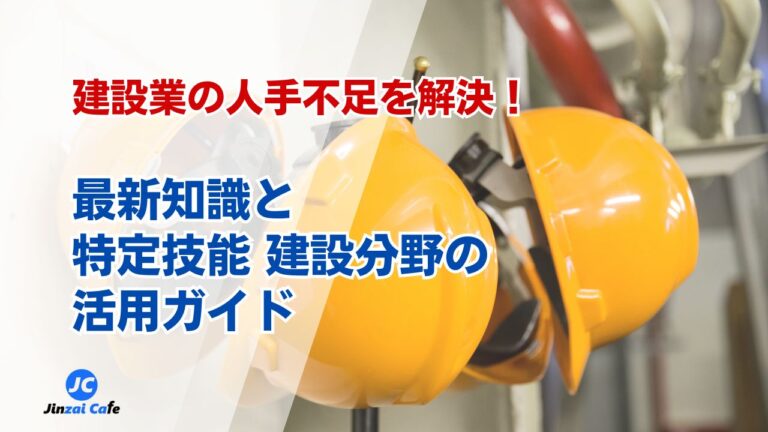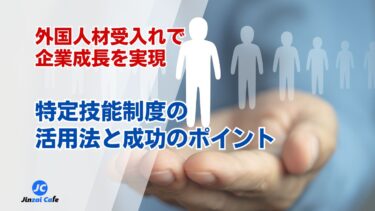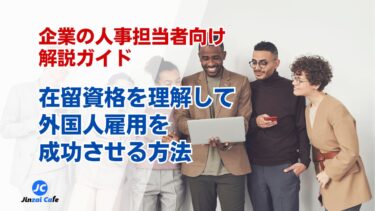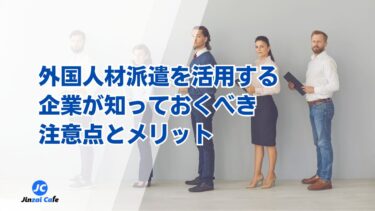近年、建設業界では深刻な人手不足が課題となっています。少子高齢化の影響もあり、若手人材の確保は年々難しくなっており、「このままでは事業の継続が危うい…」と頭を抱える経営者の方も少なくないのではないでしょうか。特に、現場の技能者の高齢化は顕著で、長年培われた技術やノウハウが次世代に継承されにくいという問題も浮上しています。
そんな中、政府が打ち出した解決策の一つが特定技能制度です。この制度は、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。建設分野もその対象であり、この制度を上手に活用することで、貴社の人手不足解消に大きく貢献できる可能性を秘めているのです。
この記事では、特定技能「建設」の概要から、受入れのメリット、具体的な手続き、そして採用を成功させるためのポイントまで、企業経営者の皆さんが知っておくべき最新の情報を網羅的に解説します。
特定技能「建設」とは?基本概要と制度のポイント

特定技能は、日本の労働力不足を補うために2019年4月に創設された在留資格です。特に、建設業は深刻な人手不足に直面している産業分野の一つであり、この制度の活用は急務と言えるでしょう。この在留資格を持つ外国人は、即戦力として日本の建設現場で活躍できるため、企業側にとっても大きなメリットがあります。
特定技能制度の創設背景と目的
特定技能制度が創設された背景には、日本の生産年齢人口(15歳以上65歳未満)の減少があります。特に建設業界では、熟練技能者の高齢化による引退が進む一方で、若年層の入職者数が伸び悩み、構造的な人手不足が深刻化していました。このままでは、日本の社会インフラの維持管理や災害復旧対応、さらには東京オリンピック・パラリンピックに伴う建設需要の後継対応に支障をきたす恐れがあると懸念されていたのです。
こうした状況を踏まえ、政府は2019年4月、国内の労働力不足分野を対象に、即戦力となる外国人材の受入れを可能にする新たな在留資格として「特定技能」制度を創設しました。この制度は、単なる労働力の補完にとどまらず、外国人材が日本社会で安定的に働き、生活できるように、支援措置や受入れ基準も制度化されている点が特長です。まさに、日本の経済・社会基盤を持続可能にするための重要な制度のひとつと位置づけられています。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能「建設」の対象業務と職種
特定技能「建設」において外国人が従事できる業務は、国土交通省が定める特定の分野に限定されています。具体的には、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3分野に大別され、建設現場における多様な作業が対象となります。例として、型枠施工、左官、屋根ふき、電気通信工事、鉄筋施工、配管、内装仕上げ施工、建設機械施工、コンクリート圧送、解体工事などがあり、各種建築設備の設置に係る作業が含まれることもあります。
これらの職種はいずれも、専門的な技能や一定の実務経験を必要とするものであり、外国人が特定技能の資格を取得するためには、所定の技能評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが条件です。これにより、受入れ企業は一定の技能・知識を備えた人材を確保できるため、即戦力として現場に配置することが可能です。こうした制度によって建設分野における技能の担い手を多様化させ、技能振興や人材確保の観点でも、外国人材の活用はますます期待されています。
特定技能1号と2号の違いとは
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格区分があります。これらは在留期間、業務内容、家族帯同の可否などに明確な違いがあります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する「相当程度の知識または経験を要する技能」を必要とする業務に従事する外国人向けの資格で、在留期間は1年・6か月・4か月ごとに更新でき、通算で上限5年となります。家族の帯同は原則として認められていません。建設業界においては、多くの企業が初期段階でこの1号の人材を受け入れています。
一方、「特定技能2号」は、同じく特定産業分野に属するものの、より高度な「熟練した技能」を有する職種が対象であり、在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば永続的な在留と家族の帯同も可能です。2025年現在、建設分野における2号の対象職種は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3分野に限定されていますが、将来的には他の業務への拡大も検討されています。
企業が2号人材の受け入れを活用することで、外国人材のキャリアパスを構築し、長期的な雇用・育成戦略を実現することが可能となります。これは日本人材との協働による技能の継承や、業界全体の持続可能な発展を後押しする上でも重要な方針です。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能1号建設分野の仕事内容
出入国在留管理庁 特定技能2号建設分野の仕事内容
国土交通省 概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】
建設業で特定技能外国人を受け入れるメリット

建設業界にとって、特定技能外国人の受入れは、単なる人手不足の解消に留まらない、多岐にわたるメリットをもたらします。持続可能な事業運営を目指す上で、外国人材の活用はもはや不可欠な要素となりつつあるのです。
深刻な人手不足への具体的な解決策
建設業界が抱える最も大きな課題は、やはり人手不足です。高齢化によるベテラン技能者の引退、若者の建設業離れなど、さまざまな要因が重なり、多くの建設業者が慢性的な人材不足に悩んでいます。特に、現場で実際に作業を行う技能労働者の確保は喫緊の課題と言えるでしょう。
特定技能外国人材は、この深刻な人手不足に対して、具体的な解決策を提供します。彼らは一定の技能水準と日本語能力を有しているため、受入れ後すぐに現場で活躍できる即戦力となることが期待されます。これにより、建設プロジェクトの遅延リスクを減らし、安定した事業運営を維持することが可能になります。また、新規採用が難しい状況下で、質の高い人材を安定的に確保できることは、企業の競争力維持に直結する重要な要素となります。
参考:一般社団法人日本建設業連合会 建設業デジタルハンドブック
若手人材の確保と技術・ノウハウの継承
建設業界の人手不足は、単に「人が足りない」という問題だけでなく、「技術が継承されない」という深刻な課題も内包しています。長年培われてきた熟練の技能やノウハウが、高齢化とともに失われつつある状況は、日本の建設技術全体の低下につながりかねません。
特定技能の外国人材は、全体の中でも20代以上の若年層が大多数を占める傾向にあり、彼らが日本の建設現場で経験を積むことは、新たな人材の育成と技術継承の重要な機会となります。彼らは高い学習意欲と向上心を持っていることが多く、日本の先進的な技能やノウハウを吸収しようと努力します。日本人従業員が外国人材に指導する過程で、改めて自身の技能を見つめ直し、言語や文化の壁を乗り越える中で、社内のコミュニケーションが活性化されるといった副次的な効果も期待できるでしょう。
国際競争力強化と企業イメージ向上
特定技能外国人材の受入れは、企業の国際競争力強化にも貢献します。多文化な背景を持つ外国人がチームに加わることで、多様な視点やアイデアが生まれ、より創造的な問題解決につながる可能性があります。例えば、グローバルな建設プロジェクトへの参加を視野に入れる際、国際的な経験を持つ人材の存在は大きな強みとなるでしょう。
さらに、外国人材を積極的に受け入れ、彼らが働きやすい環境を整備している企業は、社会的な責任を果たす企業として評価され、企業イメージの向上にもつながります。これは、新規の人材採用においても有利に働き、日本人学生からの就職先としての魅力も高まるかもしれません。結果として、企業の持続的な成長と発展に寄与する、まさに一石二鳥の効果が期待できるのです。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
特定技能「建設」外国人の受入れ方法と手続きの流れ

特定技能「建設」の外国人材を受け入れるためには、いくつかの手順を踏む必要があります。複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのプロセスを理解し、適切に行うことで、スムーズな採用が可能です。
受入れ企業に求められる基準と要件
特定技能外国人を受け入れるためには、まず受入れ企業側にいくつかの基準と要件が求められます。これらは、外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう、また不当な扱いを受けることがないよう、国が設定したものです。具体的には、建設業の許可を得ていること、特定技能外国人が従事する業務が建設分野の対象業務であること、雇用契約が適切に締結されていることなどが挙げられます。
また、外国人材に対する支援計画の策定と実施、適切な住居の確保、生活オリエンテーションの実施なども義務付けられています。これらの要件を満たしているか、国土交通省や関係機関のチェックを受けることになります。特に、建設分野の特定技能外国人を受け入れる企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必要となります。これは、建設分野における外国人材の適正な受入れと、技能水準の維持・向上、そしてキャリアアップを総合的に監理し、建設産業の健全な振興を図るための重要な仕組みです。JACの会員となり、そのルールに従って受入れを行うことが求められます。
参考:一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 特定技能外国人制度の概要
在留資格申請から受入れまでのステップ
特定技能外国人を受け入れるまでの主なステップは以下の通りです。
- 外国人材の選定と雇用契約の締結
- まずは、貴社に合った技能と経験を持つ外国人材を探します。人材紹介会社や自社のネットワークを利用することが一般的です。適切な人材が見つかったら、雇用条件や給与などを詳細に記載した雇用契約を結びます。
- 支援計画の策定
- 外国人材が日本での生活にスムーズに適応できるよう、生活オリエンテーションや相談対応、住居確保の支援などを含む「支援計画」を作成します。この計画は、自社で行うこともできますが、専門の「登録支援機関」に委託することも可能です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 雇用契約と支援計画が整ったら、出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。この申請には、雇用契約書、支援計画書、企業側の書類、外国人材のパスポートや履歴書など、多くの書類が必要となります。この際、提出する書類の内容に変更があった場合は、速やかにその変更を届け出る必要があります。
- 来日・就労開始
- 在留資格認定証明書が交付されたら、外国人材がこれを持って現地の日本大使館や領事館でビザ(査証)の申請を行うことで来日します。入国後は、支援計画に基づいたサポートを開始し、いよいよ就労がスタートします。上記の各ステップは、専門の機関や関連団体に相談するとスムーズに進められます。
登録支援機関の役割と選び方
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人材に対して適切な支援を行う義務があります。この支援業務を自社で行うことが難しい場合、登録支援機関に委託することができます。登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された機関であり、外国人材の生活支援や相談対応、日本語学習支援など、多岐にわたるサービスを提供します。
登録支援機関を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。まず、建設分野における受入実績が豊富であるか、提供される支援内容が貴社のニーズに合っているか、費用体系は明確か、などを詳細に確認することが重要です。また、実際に利用している企業からの評判や口コミも参考にすると良いでしょう。良質な登録支援機関を選ぶことで、外国人材が安心して日本で働き続けられる環境が整備され、結果として貴社の人材定着にもつながります。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
特定技能「建設」外国人材の採用を成功させるポイント

特定技能の外国人材を採用する際、ただ手続きを進めるだけでは成功とはいえません。彼らが貴社で長く活躍し、貢献してくれるためには、いくつかの重要なポイントを行う必要があります。
特定技能外国人材の探し方と選び方
特定技能の外国人材を探す方法はいくつかあります。最も一般的なのは、外国人材に特化した人材紹介会社を利用することです。これらの会社は、海外の送り出し機関と提携しており、貴社の求める技能や経験を持つ人材を紹介してくれます。また、地方自治体や業界団体が主催するマッチングイベントに参加するのも有効です。
人材を選ぶ際には、単に技能や日本語能力だけでなく、彼らの日本での就労に対する意欲や、貴社の企業文化に合うかどうかを見極めることが重要です。面接時には、具体的な業務内容や職場環境、給与、福利厚生などを丁寧に説明し、お互いの理解を深める努力が必要です。前向きに仕事に取り組む姿勢も重要でしょう。過去の経験や、技能検定の合格状況なども確認することで、より適正な人材を選択できるでしょう。オンラインでの面接システムを活用すれば、地理的な時間やコストも管理しやすくなります。
日本企業を取り巻く人材不足の深刻化により、多くの企業経営者が自社に合う人材を探し、新たな解決策を模索しています。特に製造業、介護業界、建設業界では、労働力確保が喫緊の課題となっており、従来の採用方法だけでは必要な人材を確保することが困難な状[…]
受入れ後のサポート体制構築の重要性
特定技能の外国人材が日本で安心して働き、定着するためには、受入れ後のきめ細やかなサポートが不可欠です。「雇用したら終わり」ではなく、むしろそこからがスタートと理解しましょう。
例えば、入国時の空港送迎から、市役所での住民登録、銀行口座の開設、携帯電話の契約といった基本的な生活インフラの整備を支援することが求められます。また、病気や災害など、万が一の事態に備えて、連絡体制や相談窓口を明確にしておくことも重要です。これらの支援は、義務付けられているものもありますが、企業が自主的に手厚いサポートを行うことで、外国人材からの信頼を得て、長期的な定着につながるでしょう。この受入に関する支援は、特定技能制度の概要でも重要なポイントとして強調されています。具体的なサポートサービスの内容については、事前に外国人材に案内することも大切です。
日本語教育とキャリアアップ支援
特定技能外国人材が日本の職種で円滑にコミュニケーションをとり、業務の幅を広げていくためには、日本語能力の向上が欠かせません。企業は、時間や場所を選ばずに学習できるEラーニング環境を提供したり、オンライン教材の費用を補助したりするなど、積極的なサポートを行うべきです。
また、外国人材が日本でのキャリアアップを具体的に描けるような支援も重要です。例えば、技能検定の受験を奨励したり、上位の在留資格である特定技能2号への移行をサポートしたりすることで、彼らのモチベーションを上げ、長期的な就労意欲を維持できます。彼らが建設現場での実務経験を積み、専門性を高めることが、ひいては建設産業全体の発展に繋がることを期待しています。
特定技能「建設」を導入した企業事例

実際に特定技能「建設」の外国人材を受け入れて、成功を収めている企業の事例を見ることは、導入を検討している貴社にとって多くの参考となるでしょう。具体的な事例を通じて、制度の有効性とその活用方法を深く理解することができます。
多様な人材活用で新たな価値を創出した事例
高知県の株式会社高知丸高は、四国で外国人技能者が技能講習を受けられる施設が少ないという課題に着目し、独自に多言語対応の建設技能教習センターを設立しました。フォークリフトや玉掛けなど5種類の資格講習をベトナム語・ミャンマー語など5か国語で提供し、外国人労働者の技能向上と安全意識の向上に尽力しています。
さらに特定技能外国人に対する教育手当の支給や福利厚生の充実によるキャリアアップ支援など包括的な取組みにより、2024年度国土交通省「外国人材とつくる建設未来賞」で事業展開賞と外国人材育成賞を受賞しました。このように、多文化人材の活用を通じて企業のみならず地域・業界に新たな価値をもたらした好例と言えます。
参考:
一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 2024年度「外国人材とつくる建設未来賞」<受入企業/団体部門>表彰式レポート
一般財団法人 国際建設技能振興機構 (FITS) 2024年度「外国人材とつくる建設未来賞」
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
まとめ|建設業界の未来を築く、特定技能「建設」の活用

この記事では、建設業界が直面する深刻な人手不足という課題に対し、特定技能「建設」がどのように解決策となるのか、その背景から具体的な受け入れ方法までを解説しました。
特定技能制度は、単に労働力を補うだけではありません。即戦力となる外国人材の受け入れは、現場の課題を解消するだけでなく、社内の活性化や長年培われた技術・ノウハウの継承、さらには企業の国際競争力強化にもつながる大きな可能性を秘めています。
「外国人雇用は初めてで不安」と感じる方もいるかもしれません。しかし、適切な準備とサポート体制を整えれば、スムーズな受け入れは十分に可能です。本記事でご紹介した知識を活用し、登録支援機関や一般社団法人建設技能人材機構(JAC)といった専門機関のサポートを積極的に活用してください。JACの正会員や賛助会員となることで、手厚い支援を受けられる仕組みも整っています。
この在留資格を持つ外国人の皆さんは、現在そして今後の建設分野を支える重要な担い手となることは間違いありません。ぜひ、貴社でも特定技能「建設」の導入を前向きにご検討いただき、持続可能な事業の発展を目指しましょう。
外国人材の雇用についてお困りのことがありましたら、いつでも「人材カフェ」にご相談ください。貴社に最適な外国人材の紹介を通じて、全面的にサポートいたします。