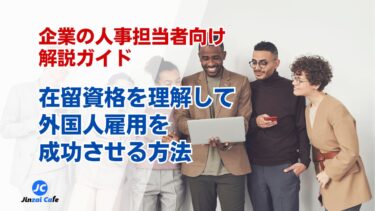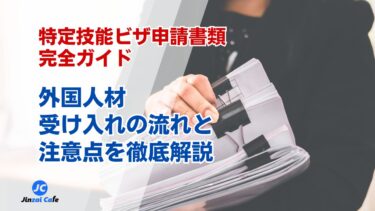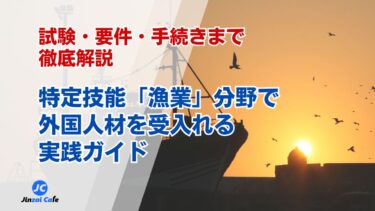自動車整備業界は今、深刻な人手不足に直面しています。ベテラン整備士の高齢化が進む一方で、若手の担い手はなかなか増えません。実際、国土交通省のデータでも有効求人倍率は4倍を超えており、多くの事業所様が「必要な人材が集まらない」という悩みを抱えています。
この厳しい状況を打開する一手として期待されているのが、2022年8月にスタートした「特定技能」の自動車整備分野です。即戦力となる外国人材を雇用できれば、長年の課題である人手不足を解消する大きなチャンスになります。
しかし、「制度が複雑そうで、何から始めればいいのか分からない」とお困りの経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな皆様のために自動車整備分野の特定技能制度を徹底ガイド。受入れの条件から試験内容、採用を成功させるポイントまでを分かりやすく解説します。貴社の事業を未来へつなぐための、確かなヒントとしてお役立てください。
日本社会は今、かつてない規模での外国人材の受入れが進んでいます。政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、多くの企業が外国人材の活用を検討しています。しかし、単に人材を受け入れ[…]
特定技能|自動車整備分野の基本概要

自動車整備分野の特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、2022年8月30日に新たに追加された分野です。この制度の運用の目的は、一定の技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを可能にすることです。
参考:
出入国在留管理庁 自動車整備分野
国土交通省 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ
自動車整備分野が追加された背景
自動車整備業界では、従事者の減少が続いています。日本自動車整備振興会連合会のデータによると、整備要員数は減少傾向にあり、特に若年層の確保が困難な状況です。同時に、自動車の高度化や電子制御システムの複雑化により、より専門性を持った人材が求められています。こうした状況を受けて、即戦力となる外国人材の受入れを可能にする制度として、自動車整備分野が特定技能の対象に加えられました。
参考:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 令和6年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について
在留資格の種類と就労可能な業務範囲
特定技能1号の在留資格では、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備等の業務に従事できます。具体的には、道路運送車両法という法律に基づく認証を受けた整備工場での整備の仕事全般が対象となります。
ただし、自動車整備士の資格を持たない特定技能外国人は、自動車整備士が立ち会いまたは監督する環境での業務に限定されます。そのため、受入れ機関では適切な指導体制の構築が重要です。
受入れ可能な人数と期間の上限
特定技能1号の在留期間は、更新を重ねて通算で上限5年となっています。また、受入れ機関(企業)ごとの人数制限はなく、たとえ数名であっても受入れは可能ですが、適切な指導体制を確保できる範囲内での受入れが求められます。
なお、自動車整備分野は現在、特定技能2号の対象となっています。そのため、5年経過後には特定技能2号への移行が可能です。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
自動車整備分野の特定技能試験と評価方法

外国人材が特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。それぞれの試験の概要と要件について、以下で詳しく見ていきましょう。
技能評価試験の内容と合格基準
自動車整備分野特定技能評価試験は、日本自動車整備振興会連合会が実施機関となり、学科試験と実技試験で構成されています。
学科試験では、自動車の構造・機能、点検・整備の方法、関連法令などの基礎知識が問われます。出題範囲は自動車整備士3級の技能検定と同等の内容で、CBT(Computer Based Testing)形式による四肢択一式で30問出題され、合格基準は65%以上の正答率です。
実技試験は、実際の自動車を用いた作業試験と判定試験が実施されます。エンジン、シャシ、電装品等の基本的な点検・整備作業の実技能力が評価され、安全かつ確実な作業ができることが求められます。
参考:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 特定技能評価試験
日本語能力試験の要件
日本語能力については、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)のN4以上の合格が必要です。自動車整備の現場では、同僚や顧客とのコミュニケーションが重要なため、日常会話レベルの日本語能力が求められています。
試験は読解・聴解・言語知識の各分野から出題され、総合的な日本語運用能力が判断されます。特に、整備作業に関する指示の理解や報告ができる程度の語彙力が重視されます。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
技能実習からの移行条件
技能実習2号を良好に修了した外国人については、上記の試験が免除され、特定技能1号への移行が可能です。移行の条件として、技能実習の職種と特定技能の分野が一致している必要があります。
自動車整備の場合、技能実習の「自動車整備」職種から特定技能の「自動車整備分野」への移行が認められています。特にベトナムやフィリピンなど、既に日本国内で技能実習を行ってきた外国人材も多く、移行手続きでは技能実習修了証明書が適切に発行されているかの確認も必要になります。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
受入れ機関が満たすべき要件と手続き
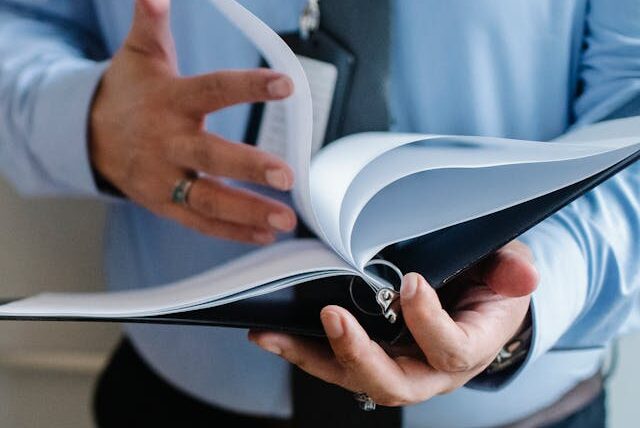
特定技能外国人を受け入れる際には、企業(受入れ機関)は法令で定められた各種要件を満たし、適切な手続きを行っていく必要があります。事前の準備として、様々な書類の提出も求められます。
登録支援機関との連携方法
受入れ機関は、特定技能外国人に対する支援を適切に実施する必要があります。自社で支援体制を整備するか、委託先として登録支援機関を活用することができます。
登録支援機関を活用する場合、出入国在留管理庁長官に登録された複数の機関の一覧から選択し、支援委託契約を締結します。支援内容には、生活オリエンテーション、住居確保支援、日本語学習支援、相談対応といったサービスが含まれます。
多くの企業では、専門知識と経験を持つ登録支援機関への委託を選択しており、初期費用と月額支援費用が請求されますが、これにより法令要求事項を満たした支援を受けることができます。
雇用契約と労働条件の設定
特定技能外国人との雇用契約では、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。労働条件についても、労働基準法第3条(均等待遇)など、関連する各条項を遵守し、適切な労働環境を提供する必要があります。
雇用契約書には、業務内容、勤務地、労働時間、賃金、休日等を記載し、外国人が理解できる言語での説明も求められます。また、社会保険の加入手続きや税務関連の対応も適切に行わなければなりません。
協議会への加入義務と手続き
自動車整備分野では、受入れ機関は「自動車整備分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。この協議会は、国土交通省が事務局となり、地方運輸局の長や業界団体などが構成員となって、適正な受入れと人材育成について協議し推進する役割を担っています。
協議会への加入に係る申請は、初回の特定技能外国人がその機関に所属することになった時から4か月以内に行う必要があります。加入後は、協議会からの定期的な情報提供や連絡、研修への参加など、協議会の活動に協力することが求められます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
自動車整備業務の具体的な作業内容

特定技能外国人が従事できる自動車整備業の業務は、道路運送車両法に基づく整備事業場での各種作業に及びます。実際にどのような業務に活用できるのかを具体的に見ていきましょう。
定期点検・車検業務での活用
12か月点検や24か月点検(車検)では、エンジンルーム、車体下部、室内等の各部位について詳細な点検作業を行います。特定技能外国人は、これらの点検項目について、自動車整備士の指導のもとで実施することができます。
点検作業では、ブレーキの効き具合、ステアリング装置の状態、灯火装置の作動確認など、安全に直結する重要な確認作業が含まれます。そのため、正確な作業手順の理解と、異常を発見した際の適切な報告が不可欠です。
車検の最終検査については自動車検査員の資格が必要ですが、その前段階の点検・整備作業において、特定技能外国人の技能を効果的に活用できます。
一般整備作業における役割
日常的な修理・整備作業においても、特定技能外国人の活用場面は多岐にわたります。オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換など、比較的単純な作業から、エンジン部品の交換や電装品の修理まで、幅広い仕事に従事できます。
ただし、分解を伴う重要な整備作業については、自動車整備士の立ち会いや監督が必要です。作業の複雑さや安全への影響度に応じて、適切な指導体制を確保することが重要になります。
自動車整備士資格との関係性
特定技能外国人も、日本の自動車整備士資格を取得することは可能です。3級自動車整備士の受験資格は実務経験1年以上とされており、特定技能での就労期間もこの実務経験に含まれます。
資格取得により、より高度な整備作業への従事や、将来的なキャリアアップの道筋を描けるようになります。企業としても、長期的な人材育成の観点から、資格取得をサポートする体制を整備することは有効な投資と言えるでしょう。
受入れ成功のためのポイントと注意点

特定技能外国人の受入れを成功させるためには、採用する時に制度要件を満たすだけでなく、実務的な課題への対応も重要です。長期的な視点を持ち、安定した雇用を実現するためのポイントを整理しましょう。
効果的な人材確保の方法
質の高い人材を確保するためには、信頼できる送り出し機関や人材紹介会社との連携が欠かせません。技能評価試験の合格者データベースを活用したり、海外での面接選考会を開催したりするなど、多角的なアプローチが有効です。
また、既に日本で技能実習を経験している外国人材は、日本の職場環境に慣れており、即戦力として期待できます。技能実習実施機関との情報共有により、優秀な人材の確保につながる場合があります。
求人情報の発信においては、給与水準だけでなく、技能向上支援の内容や職場環境の良さをアピールすることで、意欲の高い人材を引きつけることができるでしょう。
生活支援と職場環境の整備
外国人材が安心して働き続けるためには、業務面だけでなく生活面での支援も重要です。住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約など、生活基盤の整備について、手続きの案内や関係機関との調整を含め適切なサポートを提供しましょう。
職場では、日本語でのコミュニケーション支援や、文化的な違いに配慮した指導方法の工夫が必要です。翻訳アプリの活用や、多言語対応のマニュアル作成なども効果的な取り組みとなります。
定期的な面談を通じて、仕事への満足度や生活上の課題を把握し、必要に応じて改善策を講じることで、離職率の低下と生産性向上の両立が期待できます。
長期雇用に向けた工夫
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、この期間を通じて企業と外国人材の双方がメリットを享受できる関係を築くことが重要です。技能向上のための研修機会の提供や、自動車整備士資格取得への支援などを通じて、モチベーションの維持を図りましょう。
また、将来的な他の在留資格への変更可能性も視野に入れ、企業の育成方針として、より高い専門性を身につけられるよう長期的なキャリアパスを提示することで、優秀な人材の定着を促すことができます。企業の成長戦略の中に外国人材の活用を位置付け、持続可能な人材確保システムを構築していくことが求められます。
まとめ|自動車整備分野で特定技能人材を活用しよう

自動車整備分野の特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む企業にとって有効な解決策となり得ます。適切な技能と日本語能力を持った外国人材を受け入れることで、事業の継続性確保と品質向上の両立が期待できるでしょう。
制度の活用にあたっては、いくつかの注意点がありますが、試験制度の理解、受入れ要件の遵守、協議会への加入、在留資格認定証明書の交付申請など、多くの手続きと要件への対応が必要です。しかし、登録支援機関との連携や、経験豊富な専門家のサポートを受けることで、これらの課題は十分にクリアできます。
重要なのは、単なる人手不足の解消にとどまらず、外国人材との共生を通じた職場環境の向上と、自動車整備産業全体の持続可能な事業発展を目指すことです。適切な支援体制の整備と、相互理解に基づく良好な関係構築により、企業と外国人材の双方にとって価値ある雇用関係を実現していきましょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。
外国人材の雇用を検討されている企業の経営者様にとって、特定技能外国人の採用は重要な経営判断の一つです。しかし、「どのような質問をすれば良い人材を見極められるのか」「面接でどうすれば適切な評価ができるのか」「なぜ採用後にミスマッチが起きてしま[…]