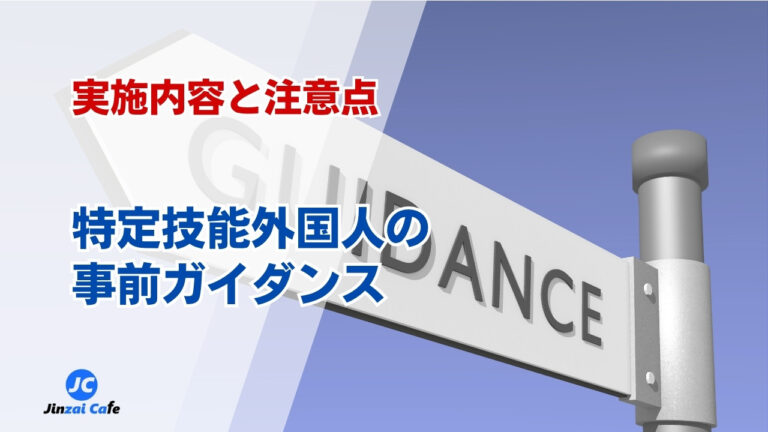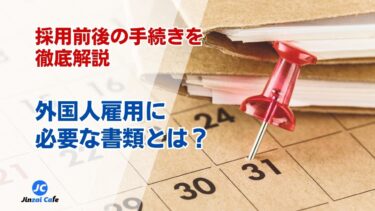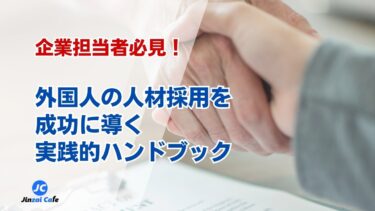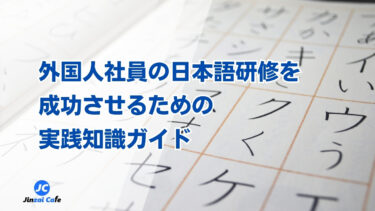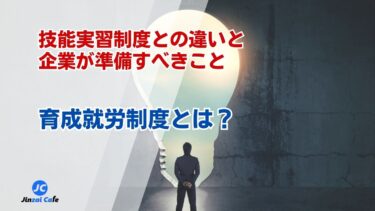特定技能外国人を受け入れる際、企業には様々な支援義務が課せられています。その中でも最初に実施すべきなのが「事前ガイダンス」です。採用活動を経て、入国前に労働条件や生活情報を十分に説明することで、外国人材の不安や悩みを解消し、スムーズな受入れを実現できます。
しかし、何をどこまで説明すればよいのか、どのような方法で実施すべきか、費用負担はどうすべきかなど、初めて外国人を雇用する企業の人事担当者にとっては疑問が多いのではないでしょうか。
今回の記事では、この制度の適切な運用に不可欠な事前ガイダンスの基本から、注意すべき点まで詳しく解説します。適切な支援体制を整え、外国人材が安心して働き続けられる環境を作りましょう。
事前ガイダンスの基本概要
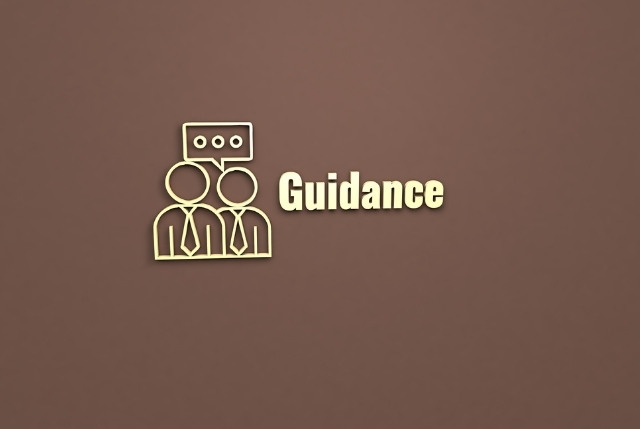
事前ガイダンスは、特定技能外国人を受け入れる前に必ず実施しなければならない義務的支援の一つです。外国人材が日本での生活や業務について十分に理解した上で来日できるよう、雇用契約締結後、入国前に行う重要な手続きとなります。
実施を怠ると在留資格の変更や更新に支障をきたす可能性もあるため、確実に対応することが求められます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
事前ガイダンスとは何か
事前ガイダンスとは、特定技能外国人が来日する前に、受入れ企業または登録支援機関が実施する情報提供活動を指します。労働条件、報酬の内訳、日本での社会生活に関する基本情報、入国手続きの方法などを、外国人材本人が理解しやすく、かつ丁寧な言語で説明します。
この説明は単なる形式的な手続きではありません。技能実習とは異なり、労働者として直接雇用される本制度の特徴として、外国人材が母国を離れ、新しい環境で働き始めるにあたり、不安や疑問を解消するための大切なコミュニケーションの場です。対面またはテレビ電話を通じて、担当者が直接説明することで、信頼関係の構築にもつながります。
義務的支援としての位置づけ
事前ガイダンスは、出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」における義務的支援の一つです。特定技能第1号の在留資格で外国人を受け入れる企業が有する義務として、以下の10項目すべてを実施する必要があります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援
- 生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談または苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらない雇用契約解除時の転職支援
これらの支援の不履行は法律違反と見なされ、在留資格の変更や更新が認められないだけでなく、受入れ企業としての認定が取り消される可能性もあります。今後の外国人材受入れが制限されるなど、企業活動に大きな影響を及ぼします。そのため、事前ガイダンスを含めすべての義務的支援を確実に実施し、その記録を適切に保管することが必須です。
実施が必要なタイミング
事前ガイダンスの実施時期については、雇用契約を締結した後、かつ外国人材が入国する前に行うことが定められています。既に日本国内にいる外国人(例:技能実習生からの移行組等)を雇用する場合でも、在留資格を特定技能に変更する前に行われなければなりません。
具体的なタイミングとしては、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更許可申請前が望ましいとされています。ガイダンス実施後に確認書を作成し、その写しを申請書類と共に提出するため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。遅くとも入国予定日の1か月以内には実施を完了しておくと、その後の手続きがスムーズに進むでしょう。
特定技能外国人労働者を採用する際、多くの企業が「生活オリエンテーション」という言葉を耳にするでしょう。しかし、具体的に何を伝えればいいのか、どのように実施すればよいのか、悩まれる人事担当者の方は少なくありません。生活オリエンテーショ[…]
事前ガイダンスで説明すべき具体的内容

事前ガイダンスでは、外国人材が日本での生活と業務を始めるために必要な情報を網羅的に提供します。出入国在留管理庁が定める要領に基づき、最低でも3時間以上かけて丁寧に説明することが求められています。
説明内容は多岐にわたるため、事前に資料や話す項目の目次のようなものを準備し、項目ごとに漏れなく伝えることが大切です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
労働条件と報酬に関する説明
雇用契約の内容について、外国人材が十分に理解できるよう詳しく説明します。具体的には以下の項目が含まれます。
- 従事する業務の内容と就業場所
- 労働時間、休憩時間、休日の詳細
- 報酬の額とその内訳(基本給、諸手当、控除項目)
- 報酬の支払方法と支給日
- 契約期間と更新の可能性
特に報酬については、金額だけでなく何が控除されるのか、手取り額がいくらになるのかを明示することが重要です。金銭的な問題を避けるため、税金や社会保険料についてもしっかり説明し、実際に支払ってもらう給与額に合意を得ておきましょう。
伝えるべき内容には、同種の業務に従事する日本人と同等以上の報酬水準であることや、日本の労働法令に基づく権利(有給休暇等)を有し適切な労働条件で雇用されることも含まれます。
さらに、作業着や安全用具の支給有無、費用負担についても明確にすることで、後々のトラブルを防止できるでしょう。
日本での生活情報の提供
外国人材が日本で円滑に日常生活を始められるよう、生活に関する基本情報を提供します。
- 住居に関する情報(社宅の有無、家賃の額、設備、通勤方法)
- 日本の気候と適切な服装、持参すべき物
- 生活費の目安(食費、交通費、通信費など)
- 日本の文化や習慣、マナー
- 緊急時の連絡先(企業担当者、支援機関、親族の連絡先確認)
住居については、家賃や光熱費の負担者を明確に示すことが大切です。配偶者や家族との同居が可能かといった質問が出ることも見込まれます。
また、来日してから当面の生活に必要な金額の目安ならびにその主な用途(食費、交通費等)を伝え、どの程度の現金を持参すべきかアドバイスすると親切です。特にベトナムなど気候が大きく異なる国から来る人材には、日本の四季に応じた衣類の準備について触れ、母国との気候の違いを理解してもらいましょう。
入国手続きと必要書類
入国に際して必要な手続きと書類については以下の通りです。
- 在留資格認定証明書の取得プロセス
- 査証(ビザ)申請の方法および管轄の日本大使館・領事館
- 入国時に持参すべき書類(パスポート、在留資格認定証明書、証明写真など)
- 在留カードの交付と重要性
- 入国後に必要な手続き(住民登録、マイナンバー取得など)
特に、本国の日本大使館または領事館での査証申請手続きについては、必要書類や所要日数を具体的に伝えます。企業側でサポートできる範囲も明示し、外国人材が自身で行う手続きと企業が支援する部分を明確に区分しましょう。入国時の空港または港での出迎えの有無、送迎方法についても説明しておくと安心です。
グローバル化が進む現在、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。しかし、多くの人事担当者が「外国人を採用したいけれど、どんな書類が必要なのかわからない」「手続きでトラブルを起こしたくない」といった不安を抱えているのではないでしょ[…]
事前ガイダンスの実施方法と手順

事前ガイダンスは、法令で定められた方法と手順に従って実施する必要があります。適切な実施形態を選び、外国人材が理解できる言語で行うことが基本です。自社で数名の外国人を同時に受け入れる場合でも、一人ひとりの理解度を確認しながら行いましょう。
ガイダンスが適切に行われたことの証明として、実施後には確認書を作成し、双方で署名することが重要です。準備から完了までの流れを把握し、計画的に進めましょう。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援に関する運用要領
対面・テレビ電話での実施要件
事前ガイダンスは、対面またはテレビ電話装置を用いた方法で実施することが義務付けられています。メールでのやり取りや郵送による書面送付のみでの説明は認められていません。
対面での実施が最も望ましいとされていますが、外国人材が本国にいる場合は現実的ではないため、テレビ電話(Zoom、Skype、LINE等)を活用するケースが一般的です。テレビ電話を使用する際は、映像と音声が安定して通信できる環境を整え、双方の表情が見える状態で行うことが求められます。
実施時間は3時間以上を確保し、説明項目すべてについて十分な時間をかけて理解を促しましょう。一方的な説明に終始せず、質問内容を問わず、一つひとつ丁寧に解消することが大切です。
使用言語と担当者の準備
事前ガイダンスは、外国人材が十分に理解できる言語で実施しなければなりません。日本語能力が十分でない場合は、母国語または英語など本人が理解できる言語を使用します。
企業の担当者が該当言語を話せない場合は、通訳者を手配するか、登録支援機関に委託することを検討します。通訳を介する間は、意図が正確に伝わらない可能性もあるため、担当者自身が説明内容を十分に把握し、外国人材との信頼関係構築を意識することが重要です。
事前に説明資料を該当言語で準備し、画面共有しながら進めると理解が深まります。労働条件通知書や雇用契約書の翻訳版も用意し、重要事項を文書で確認できるようにしておくと、後々の確認にも役立ちます。
実施時間と確認書の交付
事前ガイダンスは最低3時間以上かけて実施することが求められています。この時間は、説明だけでなく質疑応答を含めた総時間です。
ガイダンス終了後は、「事前ガイダンスの確認書」を作成します。この確認書には以下の内容を記載します。
- 実施日時と実施方法(対面・テレビ電話の別)
- 実施者の氏名と所属(企業名または登録支援機関の名称)
- 外国人材の氏名と生年月日
- 説明した項目の一覧
- 外国人材が内容を理解したことの確認
確認書は日本語と外国人材の母国語の両方で作成し、双方が署名・捺印します。この確認書の写しは、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の際に提出書類として必要となるため、大切に保管しましょう。これは双方の合意を証明する重要な書類です。
近年、日本の多くの企業が人手不足に直面し、その解決策の一つとして外国人材の採用に注目しています。しかし、採用を始める際には「どの在留資格で働けるのか」「採用の流れや必要な手続きはどう進めるのか」「採用後にどうすれば定着してもらえるのか」とい[…]
事前ガイダンス実施時の注意点

事前ガイダンスを適切に実施するためには、法令で禁止されている行為を理解し、外国人材の権利を守ることが不可欠です。特に費用負担や契約内容に関する事項については、出入国在留管理庁が厳しくチェックしています。
問題を未然に防ぎ、外国人材が安心して来日できる環境を整えるため、以下の注意点を押さえましょう。
費用負担に関する禁止事項
特定技能外国人の受入れにかかる費用について、不当な負担を求めることは法律で禁じられています。具体的には以下の行為が該当します。
- 保証金や違約金を定める契約の締結
- 外国人材の財産を管理する契約
- 入国に要する費用(査証申請、航空券など)の全額を外国人材に負担させること
- 事前ガイダンスの実施費用を外国人材に請求すること
事前ガイダンスに関する費用は、受入れ企業または登録支援機関が負担するのが原則です。通訳費用や資料作成費なども含め、外国人材に請求してはいけません。また、「研修費」などの名目で間接的に費用を徴収することも認められていないため、十分に注意が必要です。
情報提供の十分性確保
事前ガイダンスでは、形式的な説明に終始せず、外国人材が実質的に理解できるよう丁寧に情報を提供することが求められます。
単に資料を読み上げるだけでなく、具体例を示したり、図表を使って視覚的に説明したりする工夫が大切です。特に労働条件や報酬については、誤解が生じないよう詳細に説明し、外国人材から質問があれば誠実に答えます。
また、日本の文化や習慣について説明する際は、外国人材の母国との違いを考慮し、戸惑いそうな点を重点的に取り上げます。それに加え、例えばゴミの分別ルールや、介護など特定の職業・分野におけるコミュニケーションの留意点、騒音に関する注意など、生活上のトラブルを防ぐための実践的な情報を提供しましょう。
登録支援機関への委託時の留意点
事前ガイダンスを登録支援機関に委託する場合でも、受入れ企業の責任が免除されるわけではありません。委託先の支援機関(事業所や事務所)が適切にガイダンスを実施しているか、企業側も確認する必要があります。
委託契約を結ぶ際は、当該支援機関の実績や対応言語、担当者の経験などを確認しましょう。また、ガイダンス実施後は確認書の写しを受領し、内容をチェックすることが大切です。
さらに、委託したからといって企業が外国人材と一切コミュニケーションを取らないのは好ましくありません。ガイダンスの前後で企業の担当者も挨拶を交わし、将来の関係構築に努めると、外国人材の安心感が高まります。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
任意的支援との違いと連携

特定技能外国人への支援には、法令で義務付けられた「義務的支援」と、企業が自主的に行う「任意的支援」があります。事前ガイダンスは義務的支援に該当しますが、任意的支援と組み合わせることで、外国人材がより安心して働ける環境を作れます。
両者の違いを理解し、継続的な支援体制を構築することが、長期的な雇用の成功につながるでしょう。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援に関する運用要領
義務的支援と任意的支援の区別
義務的支援は法令で実施が義務付けられた10項目の支援ですが、それ以外にも企業が自主的に行う「任意的支援」があります。任意的支援は法律で定められていないものの、外国人材の生活向上や職場適応を促進するために有効です。
任意的支援の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 日本語学習の追加サポート(レッスン費用の補助、教材提供)
- 文化体験やそれに関連するイベントの開催(祭りへの参加、観光ツアー)
- 家族の来日支援(住居の拡大、手続きのサポート)
- 母国料理の食材購入サポート
- 帰国時の航空券費用の一部負担
義務的支援は必ず実施しなければなりませんが、任意的支援は企業の判断で柔軟に提供できます。両者を組み合わせることで、外国人材の満足度が高まり、長期的な雇用関係の構築につながるでしょう。
特に同業他社との差別化や、優秀な人材の確保を目指す企業にとって、任意的支援の充実は大きな強みとなります。他社の事例を調べて参考にしてみるのもいいでしょう。
事前ガイダンス後のフォロー
事前ガイダンスは入国前の一度きりの支援ではなく、その後の継続的なサポートの出発点と位置づけることが大切です。来日後は生活オリエンテーションを実施し、実際の生活環境で必要な情報を再確認します。
定期的な面談を通じて、事前ガイダンスで説明した内容と実際の状況に齟齬がないか確認しましょう。もし外国人材が不安や疑問を抱えている場合は、早期に対応することでトラブルを防げます。
相談・苦情対応の窓口を設け、外国人材がいつでも気軽に、そして相談しやすく連絡できる体制を整えることも重要です。担当者の電話番号やメールアドレスを伝え、何か申出があればすぐに対応できるようにしましょう。母国語で相談できる担当者を配置するか、登録支援機関のサポートを活用し、外国人材が孤立しないよう配慮します。
継続的な支援体制の構築
事前ガイダンスを含む義務的支援を確実に実施するとともに、任意的支援を組み合わせることで、外国人材の定着率を高められます。特に以下のような取り組みが効果的です。
- 日本語能力向上のための継続的な学習機会の提供
- 職場の日本人従業員との交流イベント
- 母国の家族との連絡をサポートする環境整備
- キャリアアップの道筋を示す面談
こうした支援は、外国人材のモチベーション向上および長期雇用につながるだけでなく、企業イメージの向上にも寄与し、ひいては会社の運営にも良い影響を与えます。
また、既に働いている外国人材からの紹介で新たな人材を確保できる可能性も広がります。外国人材が「この企業で働きたい」と感じられる体制を、事前ガイダンスの段階から意識して構築していきましょう。
グローバル化が進む中、多くの日本企業が外国人社員を採用するようになっています。しかし、採用後に直面する大きな課題のひとつが「日本語でのコミュニケーション」です。業務の指示が伝わらない、会議で発言が難しい、日常会話に壁を感じるといった問題は、[…]
まとめ|事前ガイダンスで外国人材の安心を確保しよう

特定技能外国人を迎える最初の重要なステップ、それが事前ガイダンスです。これは法律で定められた義務であり、入国前に3時間以上かけ、労働条件や生活情報を本人が理解できる言語で説明し、確認書を取り交わすことが求められます。
特に、保証金や違約金といった不当な費用を本人に負担させないことは絶対条件です。一方的な説明ではなく、対話を通じて実質的な理解を促す姿勢が、後の信頼関係の礎となります。
丁寧なガイダンスは、外国人材の安心なスタートを支え、後のトラブル防止と定着率向上に直結する大切な機会です。適切な支援を確実に行いましょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談サービスをご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。申込みはウェブサイトから簡単に行えます。