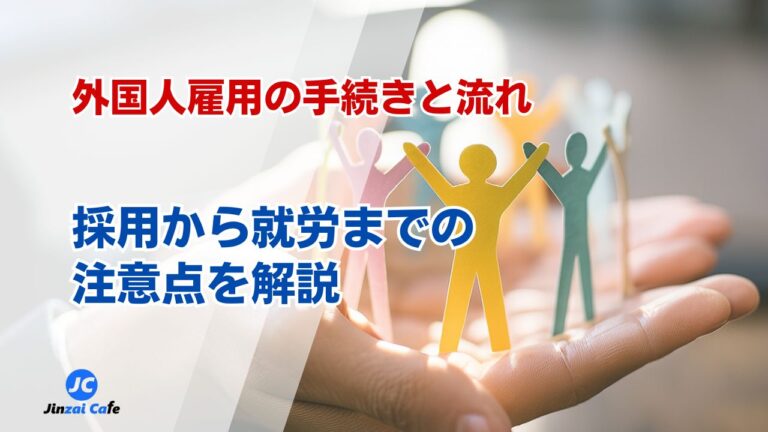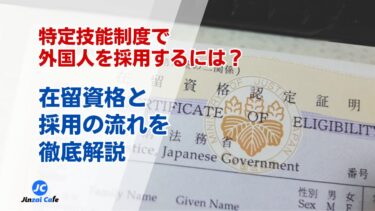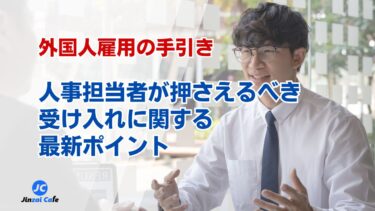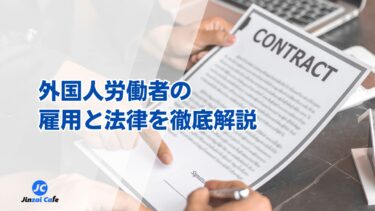外国人材の雇用に興味はあるものの、「どんな手続きが必要なのか分からない」「法令違反が怖い」と感じている企業担当者は少なくありません。特に、これまで外国人を雇った経験がない企業にとっては、在留資格の種類や手続きの流れ、管理体制など、知らなければならないことが多く、不安が先立つのが現実です。
しかし、適切な知識をもって準備をすれば、外国人の雇用は企業にとって大きな戦力となります。人材確保や人材不足の解消、多様性のある組織づくり、新しい市場や視点の獲得といった、多くのメリットを享受できる可能性が広がっています。
この記事では、外国人雇用に関心のある人事担当者に向けて、採用前の基礎知識から手続きの流れ、注意点、制度の理解まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説していきます。これから外国人材の採用を検討する方にとって、「何から始めればいいのか」が明確になるはずです。
外国人を雇用する前に知るべき基本的な知識

外国人労働者を雇用する前に、まず理解しておくべきは「誰を外国人と定義するのか」「どのような条件で働くことができるのか」という法的な前提です。日本人と同じように採用することはできず、在留資格や就労可能な活動内容が日本の法のもとで厳格に定められています。これを誤ると、不法就労を助長するリスクすらあります。ここでは、雇用前に必ず確認しておきたい基本情報を整理します。
外国人の定義と日本での就労の条件
日本の法律において「外国人」とは、日本国籍を持たないすべての人を指します。ただし、「特別永住者」や「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」といった身分に基づく在留資格を持つ外国人は就労に制限がなく、就労ビザの取得も不要なため、日本人とほぼ同様の働き方ができます。一方、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていません。
企業が外国人を雇用する際は、まずその人の在留資格が「就労可能かどうか」を確認する必要があります。
参考:法務省 外国人登録法
主な在留資格の種類と対応業務
外国人が日本で働くためには、「在留資格(就労ビザ)」が必要です。在留資格ごとに許可される業務は大きく異なり、代表的なものには下記があります。
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、貿易、企画、大学での研究職など、一般的なホワイトカラーの仕事 |
|---|---|
| 特定技能 | 16の産業分野で即戦力人材として就労可能(介護、外食、建設、医療など) |
| 技能実習 | 一定期間、技能の習得を目的とした労働が可能 |
ほかにも、インターンシップなどで利用される「特定活動」など様々な在留資格があります。それぞれ活動範囲や在留期間が異なるため、自社の職務内容とマッチしているかをよく確認することが大切です。
参考:
出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
公益財団法人 国際人材協力機構 在留資格「特定技能」とは
公益財団法人 国際人材協力機構 外国人技能実習制度とは
採用前に必ず確認すべきポイント
外国人を採用する前には、下記の確認が必須です。一つでも怠ると大きなトラブルに繋がりかねません。
- 在留カードの内容(在留資格・在留期間)
- 就労可能な業務範囲との一致
- 資格外活動許可の有無(アルバイトやパート等の場合)
以上の点は、本人の自己申告だけに頼らず、公的証明書をもとに十分確認することがトラブル防止につながります。また、「在留カードの裏面」も見落とさず、資格外活動の許可(原則週28時間以内)など重要な情報が記載されているため、必ず両面をチェックしましょう。
近年、日本では多くの産業分野で慢性的な人手不足が深刻な状況となっており、とりわけ介護・建設・農業・外食産業・製造業などの現場では、必要な人材を確保できないことが経営上のリスクとなっています。少子高齢化による労働人口の減少が背景にあることは言[…]
外国人雇用のメリットとデメリット

外国人材を雇用することは、単なる「人手不足解消」にとどまらず、企業にとって多面的な価値をもたらします。一方で、言語や文化の違い、制度面での対応不足がトラブルの火種になるケースも存在します。このセクションでは、外国人雇用における主な利点と課題を整理し、自社の状況に合った判断を後押しします。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 (日本語PDF)
「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 12カ国語版
外国人を採用する主なメリット
外国人材を採用する企業が実感しているメリットには、以下のようなものがあります。
- 人材不足の解消
- 特に介護・建設・製造・外食など、慢性的に人手が足りない業種で即戦力となるケースが多いです。
- 多様性による活性化
- 異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、社内のアイデアや視点に広がりが生まれます。
- 海外展開やインバウンド対応に強くなる
- 母国語や国際的な感覚を活かして、貿易や観光客対応の強化にもつながります。
こうしたメリットは、外国人材を“単なる労働力”ではなく、“価値ある戦力”として育成・定着させる体制が整っていればこそ実現します。
参考:総務省 「令和4年版高齢社会白書」高齢化の推移と将来推計
生じやすい課題とトラブルの例
一方で、外国人雇用には下記のような課題も付きものです。実際のトラブル事例も少なくありません。
- 言語・文化の壁
- 指示が正確に伝わらなかったり、マナーや職場ルールが共有しにくかったりするケースがあります。
- 在留資格の期限・更新管理
- 更新手続きを忘れると不法就労状態になってしまうリスクがあります。
- 職場内の摩擦
- 日本人社員との間にコミュニケーションのズレや待遇面での誤解が生じることもあります。
こうした問題を防ぐには、採用前から受け入れ体制を整え、社内の理解を深めることが重要です。
導入前に検討すべきリスクと対策
外国人雇用の導入にあたっては、事前の調査に基づき、以下のようなリスクへの備えが必要です。
- 制度・法令に対する無理解
- 企業側の誤認が不法就労の助長につながることがあります。法的な義務を事前に確認しておきましょう。
- 支援体制の未整備
- 配属先でのフォローが弱いと、早期離職につながり定着率が低い状態になる可能性があります。
- コストや負担の増加
- 通訳、研修、更新手続きなど、採用後のサポートに一定の手間とコストがかかる点も見逃せません。
とはいえ、こうしたリスクを理解し、あらかじめ体制を整備しておくことで、企業と外国人双方にとって安心で安定した雇用関係を築くことが可能です。職場環境の継続的な改善も求められます。
日本社会は今、かつてない規模での外国人材の受入れが進んでいます。政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、多くの企業が外国人材の活用を検討しています。しかし、単に人材を受け入れ[…]
外国人雇用に必要な手続きの全体像

ここでは、外国人雇用に必要な一連の流れの概要を、具体的な手続きとともに整理して紹介します。外国人を採用する際には、日本人と同じように単に「内定を出して終わり」ではありません。法的な手続き、行政への届出、ビザ取得の支援など、企業として担うべき責任が数多くあります。
参考:厚生労働省 外国人の雇用
採用決定から入社までの流れ
外国人の採用は、面接などを行い、下記のようなステップを踏んで進めるのが一般的です。特に、既に日本に在留している外国人の転職や、留学生の卒業に合わせた採用では、在留資格の変更手続きが必要になるケースもあります。
- 在留資格の確認とマッチング
- 募集している求人内容と候補者の資格が合致しているかをチェックします。
- 雇用契約の締結
- 次に、条件面(職種、勤務時間、給与等の賃金)を明記した雇用契約書を作成・交付します。
- ビザ申請手続きの支援や書類準備
- 必要な資料を揃え、申請サポートを行います。本人を主たる申請者としながらも、企業の協力が不可欠です。手続きをスムーズに進めるためのサポートは定着の観点からもおすすめです。
これらはすべて、適正な雇用と不法就労防止のために必要な準備となります。
行政手続きと必要書類の一覧
外国人雇用において企業側が行う主な手続きには、下記のようなものがあります。各種申請書は厚生労働省、出入国在留管理庁のウェブサイトの該当ページからダウンロード可能です。これらの手続きは遅滞なく行わなければなりません。
- ハローワークへの外国人雇用状況の届出(採用時・離職時)
- 労働条件通知書や雇用契約書の整備・交付(本人に内容を理解してもらうことが重要です)
- 社会保険・雇用保険の加入手続き
- 健康診断の実施(常勤の場合)
必要な書類としては、在留カードの写し、雇用契約書、履歴書、就業条件明示書、在留資格認定証明書などが代表的です。これらに該当する書類は、漏れなく準備しましょう。
就労開始までのスケジュール管理
外国人の就労は、必要な手続きをすべて完了した後でなければ認められません。そのため、スケジュール管理は非常に重要です。
- ビザ申請にかかる期間は1か月から3か月程度が目安(時期や国籍によって異なるため、特に4月入社を予定している場合は早めの準備が必要です)
- 在留カードの発行や入国手続きも含め、余裕を持った計画を立てる必要があります。
- 入社日=就労可能日ではない場合もあるため、開始日は手続き完了後に設定すべきです。
万が一、在留資格の交付が間に合わなかった場合、不法就労となる恐れがあるため、社内全体でスケジュールを共有しておくことが大切です。
近年、日本の労働市場では人手不足が深刻化しており、特に介護、建設、サービス業などでは慢性的な人材不足が課題となっています。こうした状況の中で注目されているのが、海外からの労働者の活用です。多様な文化や価値観を持つ[…]
就労ビザの申請と取得方法

外国人が日本で合法的に働くには、適切な在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得する必要があります。このビザは、単に働くことを認めるだけでなく、どのような業務に従事できるか、どのくらいの期間滞在できるかも定めています。このセクションでは、ビザ申請の種類や流れ、企業が支援すべきポイントを具体的に見ていきましょう。
企業が関与する主要な就労ビザとは
外国人を採用する企業が、所属機関として実際に取得・更新などで関わることの多い就労ビザには、以下の3種類があります。制度理解だけでなく、企業側の準備や申請支援の役割も大きいため、実務的な観点から特徴を把握しておくことが重要です。
| ① 技術・人文知識・国際業務ビザ | いわゆるホワイトカラー系職種(システムエンジニア、通訳、企画など)で最も一般的。 学歴や実務経験などの要件を満たす必要があります。 |
|---|---|
| ② 特定技能ビザ(1号・2号) | 人手不足が深刻な16業種(介護、外食、建設など)で受け入れ可能。 1号は最大5年まで、2号は更新制で永住も可能です。試験や技能評価が要件となります。 |
| ③ 高度専門職ビザ(第1号・第2号) | 学歴、年収、業績などに応じたポイント制で評価されるハイレベルな人材向けの制度。 家族の帯同や永住権の取得でも優遇されるなど、長期雇用を前提とする企業に適しています。 |
※横スクロール→
これらのビザはすべて「在留資格認定証明書」の取得や、更新手続きの際に企業側の書類提出や説明が求められます。制度上の理解に加え、“どう対応すべきか”という視点で準備を進めることがポイントです。
参考:
出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
公益財団法人 国際人材協力機構 在留資格「特定技能」とは
出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請の流れ
申請に必要な書類とポイント
就労ビザの申請には、本人だけでなく受け入れ企業が準備すべき書類も多数あります。主な必要書類は下記の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(本人が外国にいる場合)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 登記簿謄本・決算書類・会社案内等(企業側)
- 卒業証明書・職務経歴書・各種資格証明書(本人側)
書類の整合性・信頼性が審査に大きく影響するため、矛盾がないよう丁寧に作成し、送付前に不備がないか徹底して確認することが重要です。申請ミスや不備による不許可も少なくないため、専門家への相談を行ったうえで、行政書士への依頼を検討するのもよいでしょう。
在留資格認定証明書とは?
「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」は、日本国外にいる外国人がビザを取得して入国する際に必要な書類です。これは出入国在留管理庁が発行するもので、入国目的が適正であると認められたことを示す証明書です。
この証明書を取得してから、日本大使館または領事館で「ビザ」の発給手続きが行われます。なお、COEの有効期間は発行日から3か月間です。企業はこのスケジュールを逆算して準備を進める必要があります。
「少子高齢化による人手不足が深刻化し、事業継続が危うい…」「外国人材の雇用を検討しているが、就労ビザの申請は複雑で何から手をつければいいのかわからない」「不法就労のリスクや、雇用後の管理についても不安がある」もしあなたがこの[…]
採用後に必要な管理・サポート体制

外国人を採用して終わりではありません。むしろ、就労開始後のフォローこそが、外国人雇用の成否を左右します。文化や言語、法制度の違いを踏まえた対応ができていないと、早期離職やトラブルの原因にもなりかねません。ここでは、採用後に企業が果たすべき管理・支援体制について具体的に解説します。
在留資格の更新とその注意点
外国人の在留資格には必ず有効期限があり、就労を継続するためには定期的な更新許可申請が必要です。更新申請は、通常、期限の3か月前から可能で、原則として本人が行いますが、企業側が手続きを支援することで安心感を与えることができます。
更新の際に必要となるのは、雇用契約の継続証明、給与の支払い実績、勤務実態の証明など。これらが不十分だと、「更新不許可」となり、許可がない限り就労継続ができなくなる恐れがあります。不許可となる主な理由には、納税義務の不履行や入管法で定められた届出を怠っていることなども含まれるため注意が必要です。
更新時期を管理する体制を社内で整えることが非常に重要です。
労働条件・就業規則の整備
外国人従業員にも日本の労働法が適用されるため、労働条件や就業規則を整備し、その内容を明確に伝えることが必要です。日本人従業員と同水準の待遇を保証したうえで、特に勤務時間・休日・残業の扱いや、社会保険・雇用保険への加入といった重要な条件は、労働条件通知書の内容として正確に明文化し、本人に理解してもらう必要があります。
加えて、「日本語が得意でない」外国人には、やさしい日本語や母国語翻訳の活用も有効です。誤解を防ぐために、就業規則などの重要書類については、事前に丁寧な説明を行いましょう。
文化・言語への配慮と支援
言葉の壁や文化的な違いは、職場での孤立感や摩擦を生みやすい要因です。そのため、外国人社員の定着には、きめ細やかなサポートが効果的です。例えば、メンターや相談窓口を設けるといった社内サポーター制度の導入や、通訳・翻訳ツール、関連する外部サービスの提供が挙げられます。
さらに、外部セミナーの紹介や社内研修の開催などを通じて日本語教育を支援することも重要です。また、こうした制度的な支援に加えて、「あいさつの文化」や「報連相(報告・連絡・相談)」といった日本ならではの職場ルールも丁寧に伝えることで、相互理解が深まりやすくなります。
外国人雇用に関する法律・制度の理解

外国人を雇用する企業には、法令遵守が強く求められます。違反があれば、企業側に重い責任が問われるだけでなく、外国人本人の在留資格にも影響を及ぼします。ここでは、外国人雇用に関わる主要な法制度の中でも、特に注意すべきルールについて整理し、トラブルを未然に防ぐ知識を提供します。
出入国在留管理庁への届出義務
外国人を雇用した企業は、採用時と離職時に出入国在留管理庁(入管)を通じてハローワークへの届出が義務付けられています。具体的には下記の書類を提出します。他にも、様々な義務が課されていますので注意が必要です。
- 外国人雇用状況届出書
- 在留カードのコピー
提出は、原則として雇入れ日または離職日から14日以内。怠った場合は、30万円以下の罰金が科されることもあります。また、入管への届出とは別に、雇用保険への加入が必要な場合は、所轄の労働基準監督署への手続きも必要です。
雇用主が負う法的責任と罰則
外国人の在留資格に合わない業務を任せたり、無資格のまま就労させたりすると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。これは、以下のような行為が対象です。
- 在留資格を超える活動をさせる
- 就労不可の資格であると知りながら雇用する
- ビザの更新忘れを放置する
この罪に問われた場合、企業側には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
また、重大な違反があれば企業名の公表や、今後の外国人受け入れに制限がかかる場合もあります。意図的でなくとも、知らなかったという不作為が罪に問われるケースもあります。
不法就労のリスクを回避する方法
不法就労を未然に防ぐには、企業の確認・記録・管理が不可欠です。下記のような対策が推奨されます。
- 在留カードの原本確認とコピー保管(裏面も忘れずに)
- 在留期限の社内共有とリマインド体制の整備
- 業務内容と在留資格のマッチング確認
さらに、法制度は頻繁に改正されるため、最新情報の把握も重要です。2027年を目途に技能実習制度の大幅な見直しが予定されているように、制度変更は継続的に行われています。出入国在留管理庁や厚生労働省の公式サイト、各種メディアを定期的に確認し、社内に専門の担当者を設ける、または外部の専門家に相談することも有効な手段です。
近年、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中で、グローバル人材、特に外国人労働者の活用が多くの日本企業にとって喫緊の課題となっています。多様な知識や文化を持つ外国人材を受け入れることは、企業の競争力向上やイノベーション創出につながる一方で[…]
まとめ|外国人雇用を円滑に進めるために必要なこと

外国人材の雇用は、日本人の採用とは異なる制度や文化的な背景があるため、適切な知識と体制がなければトラブルの原因となる可能性があります。しかし、今回本記事で解説した採用前の基礎知識を押さえ、制度に従った手続きを正しく行い、就労後も丁寧なサポート体制を整えることで、外国人材は企業にとって大きな戦力となります。
重要なのは、マッチする在留資格の確認と、手続き・支援体制の整備です。また、制度の変化や最新情報を常にキャッチアップする姿勢も不可欠です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用いただき、ご相談ください。当社では企業様向けに様々な職種の登録外国人材をご紹介しています。詳細はホームページをご覧ください。