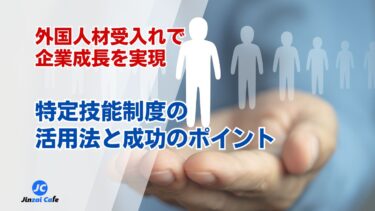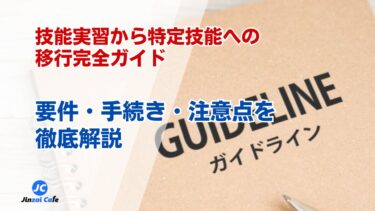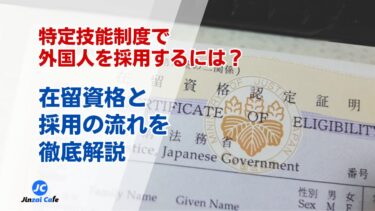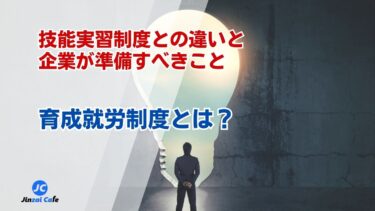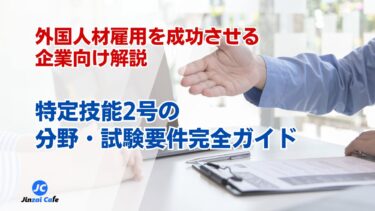日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れを検討する企業が急速に増加しています。2019年に創設された特定技能制度は、人材確保が困難な16分野において、一定の専門性と技能を有する外国人を即戦力として雇用できる在留資格です。
本記事では、特定技能外国人の受け入れを検討している企業の人事担当者向けに、制度の基礎知識から実際の受け入れ手続き、必要な要件まで体系的に解説いたします。特定技能1号・2号の違い、16分野の詳細、受入れ機関としての義務など、実務に直結する情報を網羅的にお伝えします。出入国在留管理庁の情報と成功企業の事例も交えながら、貴社の外国人材活用を成功に導くための実践的な知識となるでしょう。
特定技能制度の基本知識

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格制度です。従来の技能実習制度とは異なり、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人が対象となり、日本国内での就労が可能となる制度です。
特定技能とは何か
特定技能は、国内の人材確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。出入国在留管理庁が所管する制度であり、関連法令や省令で詳細が定められている16の特定産業分野が指定されています。各分野で必要とされる技能水準や日本語能力を満たした外国人が、日本企業と雇用契約を締結して就労できる仕組みです。
受入れ企業は、外国人材に対して日本人と同等以上の報酬を支払う必要があり、適正な雇用環境の整備が求められます。制度創設の背景には、少子高齢化による労働力人口の減少と、特定分野における深刻な人材不足があるでしょう。外国人材の活用が日本経済の持続的成長に不可欠となっている現状を踏まえた制度設計となっています。
参考:公益財団法人 国際人材協力機構 在留資格「特定技能」とは
1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分が存在し、それぞれ要件や在留期間が異なります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年となり、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、1号よりも高度な技能水準が求められます。2号の在留期間は3年・1年または6か月ごとの更新が可能で、更新回数に制限がないため、実質的に長期就労が可能です。また、2号では配偶者や子などの家族帯同が認められている点も大きな違いとなっています。
技能実習との比較
特定技能と技能実習は、外国人を受け入れる制度として混同されがちですが、制度の目的と運用が根本的に異なります。技能実習制度は、開発途上国への技能移転を通じた国際協力を目的としており、最長5年の実習期間中は転職が原則として認められません。
一方、特定技能制度は国内の人手不足解消を目的としており、同一業務区分内であれば転職が可能です。報酬面でも差があり、技能実習では実習生としての待遇となりますが、特定技能では日本人と同等以上の報酬が義務付けられています。また、技能実習を良好に修了した外国人は、技能試験が免除されて特定技能1号への移行が可能です。以下の一覧表で概要をご確認ください。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 |
|---|---|---|---|
| 制度目的 | 人手不足解消 | 人手不足解消 | 技能移転・国際協力 |
| 在留期間 | 通算5年 | 更新制限なし | 最長5年 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 | 不可 |
| 転職 | 同一業務区分内で可能 | 同一業務区分内で可能 | 原則不可 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 | 段階的習得 |
参考:公益財団法人 国際人材協力機構 外国人技能実習制度とは
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
受け入れ可能な16分野

特定技能制度では、人材確保が特に困難と認められる16の産業分野が指定されており、各分野で外国人材の受け入れが可能です。2024年には分野の見直しが行われ、従来の12分野から16分野へと拡大されました。各分野には受入れ見込み数の上限が設定されており、分野ごとに必要な技能水準や試験内容が定められています。
製造業分野の詳細
製造業関連では、2024年の制度改正により工業製品製造業分野として集約されました。従来の素形材・産業機械・電気電子情報関連産業の3分野が統合され、より幅広い製造業務に対応できる体制となっています。工業製品製造業分野では、鋳造や金属プレス加工、機械加工、組立、電子機器製造など多岐にわたる業務区分が設定されており、製造現場での即戦力が求められます。
技能試験と日本語試験の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した外国人については技能試験が免除される仕組みです。製造業分野全体で数万人規模の受入れが見込まれており、日本のものづくり産業を支える重要な人材として期待されています。分野統合により、外国人材の配置転換や業務の柔軟性が向上し、企業にとっても活用しやすい制度となりました。
サービス業分野の特徴
サービス業関連では、介護、ビルクリーニング、外食業、宿泊、自動車整備などの分野が指定されています。介護分野は特定技能制度の中でも特に需要が高く、高齢化社会における人材不足への対応として重要な位置づけです。身体介護や生活支援などの業務に従事でき、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が求められます。
外食業分野では、飲食物調理や接客、店舗管理などの業務が可能となっており、日本の食文化を支える人材として活躍が期待されています。宿泊分野では、フロント業務やレストランサービス、客室管理などが対象業務です。
ビルクリーニング分野は、建築物内部の清掃作業全般を担当する分野であり、技能評価試験の合格が要件となっています。自動車整備分野では、自動車の日常点検整備や定期点検整備などの業務に従事できます。
分野別の受入れ要件
各分野には共通要件と分野特有の要件が存在し、受入れ企業と外国人の双方が満たす必要があります。共通要件として、18歳以上であること、技能試験と日本語試験に合格していること、健康状態が良好であることなどが挙げられます。
分野に係る固有の要件では、建設分野と造船・舶用工業分野において特定技能2号への移行が可能となっており、より高度な技能を持つ人材の長期就労が認められている状況です。
農業分野では、耕種農業と畜産農業の2つの業務区分があり、それぞれに対応した技能試験が実施されます。漁業分野は、漁業と養殖業の2区分に分かれており、海上作業の安全管理に関する知識も必須要件です。
飲食料品製造業分野では、食品製造に関する衛生管理の知識が求められます。航空分野では、空港グランドハンドリング業務や航空機整備業務が対象となり、専門的な技能評価が行われます。
| 分野 | 主な業務内容 | 受入れ見込み数(5年間) | 技能試験 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 身体介護、生活支援 | 約60,000人 | 介護技能評価試験 |
| ビルクリーニング | 建築物内部清掃 | 約37,000人 | ビルクリーニング技能評価試験 |
| 工業製品製造業 | 機械加工、組立、金属加工等 | 約31,450人 | 製造分野特定技能評価試験 |
| 建設 | 型枠施工、左官等 | 約40,000人 | 建設分野特定技能評価試験 |
| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装等 | 約13,000人 | 造船・舶用工業分野特定技能試験 |
| 自動車整備 | 点検整備、分解整備 | 約7,000人 | 自動車整備技能評価試験 |
| 航空 | グランドハンドリング等 | 約2,200人 | 航空分野技能評価試験 |
| 宿泊 | フロント、接客等 | 約22,000人 | 宿泊業技能評価試験 |
| 農業 | 耕種農業、畜産農業 | 約36,500人 | 農業技能評価試験 |
| 漁業 | 漁業、養殖業 | 約9,000人 | 漁業技能評価試験 |
| 飲食料品製造業 | 食品製造加工 | 約34,000人 | 飲食料品製造業技能評価試験 |
| 外食業 | 調理、接客、店舗管理 | 約53,000人 | 外食業技能評価試験 |
| 自動車運送業 | 貨物自動車運送 | 約10,000人 | 自動車運送業技能評価試験 |
| 鉄道 | 鉄道施設の保守管理等 | 約1,000人 | 鉄道分野技能評価試験 |
| 林業 | 造林、伐採等 | 約5,000人 | 林業技能評価試験 |
| 木材産業 | 木材加工、製材等 | 約6,000人 | 木材産業技能評価試験 |
※横スクロールできます→
深刻な人手不足に直面する日本の企業にとって、外国人材の活用は喫緊の課題となっています。特に製造業、建設業、介護分野などでは、即戦力となる人材の確保が企業の存続に関わる重要な経営課題です。2019年4月に創設された特定技能制度は、これ[…]
外国人受け入れの流れ

特定技能外国人を受け入れるには、採用準備から在留資格の申請、就労開始後の支援まで、複数の段階を経る必要があります。各段階で必要な手続きや書類が定められており、適切なプロセスを踏むことが重要です。受入れ企業は、法令で定められた要件を満たしながら、計画的に受け入れを進めることが求められます。
採用前の準備事項
外国人材の受け入れを開始する前に、企業は受入れ機関としての基準を満たしているか確認する必要があります。特定技能外国人支援計画を作成し、適切な支援体制を整備することが求められます。自社で支援を実施できない場合は、登録支援機関に委託することも可能です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働関係法令の遵守 | 労働基準法、最低賃金法などを遵守していること |
| 社会保険関係法令の遵守 | 健康保険、厚生年金保険などに適切に加入していること |
| 非自発的離職者の有無 | 1年以内に特定技能外国人の受入れに関連して非自発的離職者を発生させていないこと |
| 報酬額の適正性 | 日本人と同等以上の報酬を支払うこと |
| 支援計画の作成 | 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援計画を策定すること |
| 支援体制の確保 | 支援責任者と支援担当者を配置すること |
| 登録支援機関の検討 | 自社で支援が困難な場合は登録支援機関への委託を検討すること |
| 雇用契約書の準備 | 雇用条件を明記した契約書を作成すること |
上記の表に挙げた諸事項は、受け入れを円滑に進めるための重要なポイントです。関係部署と連携し、社内組織全体で準備状況を確認しておくことが求められます。
外国人材の雇用を検討されている企業の経営者様にとって、特定技能外国人の採用は重要な経営判断の一つです。しかし、「どのような質問をすれば良い人材を見極められるのか」「面接でどうすれば適切な評価ができるのか」「なぜ採用後にミスマッチが起きてしま[…]
在留資格申請手続き
外国人材の採用が決定したら、在留資格認定証明書の交付申請または在留資格変更許可申請を行います。海外から新規に受け入れる場合は、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を提出します。申請には、雇用契約書や特定技能外国人支援計画書といった各種書類に加え、受入れ機関の概要を示す資料などが必要です。申請から交付までは通常1か月から3か月程度を要しますが、審査の状況によってはさらに時間がかかる場合もあるため注意が必要です。
証明書が交付されたら、外国人本人が現地の日本大使館または総領事館でビザ申請を行い、来日後に在留カードが交付されます。既に日本国内に在留している外国人を雇用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。技能実習から特定技能への移行の場合も、この変更許可申請が必要です。申請に係る詳細な要領は、出入国在留管理庁のウェブサイトでダウンロード可能です。
近年、日本では多くの産業分野で慢性的な人手不足が深刻な状況となっており、とりわけ介護・建設・農業・外食産業・製造業などの現場では、必要な人材を確保できないことが経営上のリスクとなっています。少子高齢化による労働人口の減少が背景にあることは言[…]
受入れ後の支援体制
外国人材の就労開始後は、特定技能外国人支援計画に基づいた支援が義務付けられています。受入れ機関または登録支援機関が責任を持って実施する必要があり、支援計画には、以下の10項目を具体的に記載します。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
受入れ機関は、事前ガイダンスとして、雇用契約締結後、在留資格申請前に労働条件や活動内容などを外国人が理解できる言語で説明します。入国後には、生活オリエンテーションを通じて日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応などを案内することが求められます。
相談・苦情に対しては、職場や生活上の問題を本人が十分に理解できる言語で聞き取り、適切な助言や指導を行う体制が不可欠です。その際、プライバシーへの配慮と個人情報保護も忘れてはなりません。
また、出入国在留管理庁への定期的な届出も受入れ機関の義務であり、受入れ状況や支援実施状況を四半期ごとに報告する必要があります。届出様式や提出方法は、同庁のウェブサイトの該当ページで確認可能です。
特定技能外国人を受け入れる際、企業には様々な支援義務が課せられています。その中でも最初に実施すべきなのが「事前ガイダンス」です。採用活動を経て、入国前に労働条件や生活情報を十分に説明することで、外国人材の不安や悩みを解消し、スムーズな受入れ[…]
特定技能外国人労働者を採用する際、多くの企業が「生活オリエンテーション」という言葉を耳にするでしょう。しかし、具体的に何を伝えればいいのか、どのように実施すればよいのか、悩まれる人事担当者の方は少なくありません。生活オリエンテーショ[…]
受入れ機関の要件と義務

特定技能外国人を受け入れる企業は、受入れ機関として法令で定められた基準を満たす必要があります。適正な雇用環境の確保と外国人への支援体制の整備が求められており、これらの要件を満たさない場合は受入れが認められません。受入れ機関の義務を理解し、継続的にコンプライアンスを維持することが重要です。
受入れ機関の基準
受入れ機関として認められるには、複数の基準をクリアする必要があります。労働関係法令および社会保険関係法令の遵守、適正な報酬の支払い、過去の法令違反がないことなどが求められます。
| 基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働関係法令の遵守 | 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などを遵守していること |
| 社会保険関係法令の遵守 | 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法などを遵守していること |
| 非自発的離職者の不発生 | 過去1年以内に、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと |
| 報酬の同等性 | 特定技能外国人に対して日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払うこと |
| 行方不明者の不発生 | 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと |
| 法令違反の不存在 | 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行っていないこと |
| 欠格事由の非該当 | 禁錮以上の刑に処せられた者、暴力団関係者などの欠格事由に該当しないこと |
| 保証金徴収等の禁止 | 外国人やその親族等から保証金を徴収したり、違約金を定める契約を締結していないこと |
これらの基準は、省令によって詳細な規定が設けられており、受入れ機関はこれらを100%遵守する義務があります。
支援計画の作成方法
特定技能外国人を受け入れる際は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、適切に実施する義務があります。支援計画には、先述の10項目の支援内容を具体的に記載する必要があります。支援責任者および支援担当者を選任し、それぞれの役割を明確にすることが求められるでしょう。
支援責任者は支援計画の統括管理を行う者であり、支援担当者は実際に支援業務を実施する者です。支援を担当する職員は、所属する部署に関わらず、過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有することが望ましいとされています。
支援計画は外国人が十分に理解できる言語で作成し、本人に交付する必要があります。例えば英語(English)版などを用意することが望ましいでしょう。計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに地方出入国在留管理局に届け出なければなりません。
登録支援機関の活用
自社で支援計画の全てを実施することが困難な場合は、登録支援機関に支援業務を委託することが可能です。登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された、特定技能外国人への支援を適正に実施できる機関を指します。
登録支援機関には、支援の全てを委託する「全部委託」と、自社で対応が難しい支援項目の一部を委託する「一部委託」があります。支援を全部委託する場合、受入れ機関は支援体制に関する基準を満たしているものとみなされます。
登録支援機関の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されており、地域や対応分野から検索可能です。自社の事業内容や地域に合った機関を選ぶことが重要です。
| 項目 | 自社で支援を実施 | 登録支援機関に委託 |
|---|---|---|
| 支援体制の基準 | 過去2年間の支援実績等が必要 | 委託により基準を満たすとみなされる |
| 対応言語 | 自社で対応可能な言語に限定 | 多言語対応が可能 |
| 費用 | 人件費等の内部コスト | 月額2万円~4万円程度 |
| 専門性 | 自社でノウハウを蓄積 | 専門機関の知見を活用 |
| 管理負担 | 全ての支援業務を自社で管理 | 実施状況の把握のみ |
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
企業が知るべき最新情報

特定技能制度は運用開始から数年が経過し、制度の改正や運用の見直しが継続的に行われています。2025年時点での最新情報を把握することは、適切な外国人材の受け入れと活用に不可欠です。制度改正の内容、試験情報、成功企業の事例など、実務に役立つ最新動向を理解しておく必要があります。
2025年の制度改正
2024年から2025年にかけて、特定技能制度には複数の重要な改正が実施されました。最も大きな変更点は、受入れ対象分野の拡大です。従来の12分野から16分野へと拡大され、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加されています。
また、製造業関連では素形材・産業機械・電気電子情報関連産業の3分野が工業製品製造業分野として統合され、業務区分の柔軟性が向上しました。特定技能2号の対象分野も拡大されており、建設分野と造船・舶用工業分野に加えて、新たに11分野が追加される方向で検討が進められています。
これにより、熟練した技能を持つ外国人材の長期就労が可能となり、企業にとって人材の定着率向上が期待できるでしょう。在留資格の申請手続きについても、オンライン申請の対象範囲が拡大され、手続きの効率化が図られています。
参考:出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
外国人材の受入れを検討する企業にとって、2027年に施行予定の育成就労制度は見逃せない制度改正です。長年指摘されてきた技能実習制度の課題を解消し、人材育成と人手不足対応を両立させる新たな枠組みとして注目されています。本記事では、育成[…]
試験日程と申込方法
特定技能の取得には、分野別の技能試験と日本語試験の合格が必要です。技能試験は各分野の所管省庁または指定された試験実施機構が実施しており、国内外で定期的に開催されています。2025年の試験日程は、各分野の実施機関のウェブサイトで公開されており、年間を通じて複数回実施される分野が増加している状況です。日本語試験は、国際交流基金が実施する「日本語基礎テスト」または日本語能力試験(JLPT)のN4以上が認められます。
介護分野では、これに加えて介護日本語評価試験の合格も必要となります。試験の申込みは、各実施機関の専用サイトからオンラインで行うことができ、受験料は試験によって異なりますが、技能試験は5,000円から10,000円程度、日本語試験は3,000円から7,000円程度が一般的です。
海外での試験実施国も拡大しており、各国で試験日程が異なるため、最新情報は各機構のウェブサイトで確認する必要があります。ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、タイ、中国、ネパール、モンゴルなど多くの国で受験が可能です。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
成功企業の事例
特定技能制度を効果的に活用している企業の事例から、成功のポイントを学ぶことができます。
参考:
ぐるなびPRO すかいらーくの現場から考える、外国人採用で成功する飲食店の人材戦略
幸ちゃんの家
まとめ|特定技能外国人受け入れの成功へ

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する日本企業にとって、即戦力となる外国人材を確保できる重要な制度です。本記事では、制度の基本知識から16分野の詳細、受け入れの具体的な流れ、受入れ機関としての要件と義務、そして2025年の最新情報まで解説してきました。
特定技能外国人の受け入れを成功させるには、制度の正しい理解と適切な準備が不可欠です。受入れ機関としての基準を満たし、外国人材への支援体制を整備することで、長期的な人材確保と企業の成長につなげることができるでしょう。登録支援機関の活用や、技能実習修了者の継続雇用など、自社の状況に合わせた受け入れ方法を検討することが重要です。
2024年からの制度改正により、対象分野が16分野に拡大され、特定技能2号の範囲も広がっています。これらの変更は、企業にとってより柔軟な外国人材活用の機会を提供するものです。成功企業の事例が示すように、外国人材を単なる労働力ではなく、企業の重要な人材として位置づけ、適切な支援と育成環境を整備することが、定着率向上と企業の競争力強化につながります。
外国人材の雇用に関するご質問やお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。