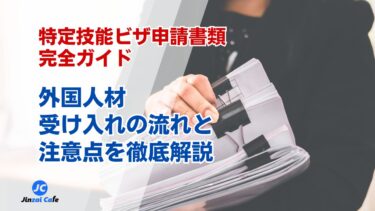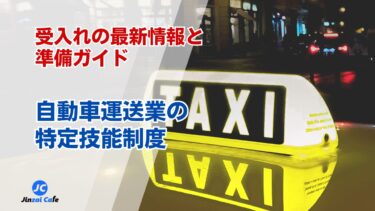日本の鉄道業界では、近年ますます深刻化する人手不足が大きな問題となっています。少子高齢化に伴う労働人口の減少に加え、熟練技術者の引退も進み、特に保守整備や駅業務などの現場では人材の確保が急務です。
こうした状況を受けて、国は即戦力となる外国人材の受け入れを拡大する方針を固め、2019年に「特定技能」制度を創設しました。2024年には新たに「鉄道」分野が制度の対象に追加され、外国人が鉄道関連業務に従事できる道が開かれました。
とはいえ、実際に外国人を雇用するには、制度の概要や対象業務、試験内容、在留資格の取得方法等、企業側が押さえておくべきポイントが多くあります。
本記事では、鉄道分野における特定技能制度の最新情報をわかりやすく整理し、企業がスムーズに外国人材を受け入れるための実務的な知識と手続きを丁寧に解説します。採用ご担当者の参考になれば幸いです。
鉄道分野における特定技能制度の概要

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために2019年に創設されました。2024年には鉄道分野が対象に加わり、保守整備や駅業務などに外国人が従事できるようになりました。人材確保が難しい現場にとって、有力な選択肢の一つとなっています。
特定技能制度の基本構造
特定技能制度には「第1号」と「第2号」の2種類の在留資格がありますが、現在、鉄道分野で認められているのは「特定技能1号」のみです。これは、一定の技能水準と日本語能力を備えた外国人が、通算で最長5年間、日本国内で就労できる制度です。
1号では原則として家族の帯同は認められておらず、純粋な労働力補充を目的とした制度設計がされています。企業は受け入れにあたり、生活支援や職場環境の整備も求められます。
鉄道分野の追加経緯と背景
鉄道分野が特定技能の対象に追加されたのは2024年3月です。背景には、技術職の高齢化、若手人材の確保難、労働集約的な現場業務の継続的な人手不足といった深刻な課題がありました。国土交通省は、日本の運輸インフラの根幹である鉄道事業の安全・安定運行を守るため、技能実習制度だけでは補いきれない人材ニーズに対応する形で、特定技能による外国人の受け入れを認めるに至りました。
これにより、車両や軌道の保守、駅業務など多様な業務で外国人が活躍できる道が開かれたのです。今後も業界全体の持続可能性を支える重要な制度として位置づけられています。
参考:国土交通省 鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
特定技能「鉄道」分野で求められる業務内容と区分

特定技能「鉄道」分野では、受け入れ対象となる業務が制度上、以下の5つの区分に明確に定められています。いずれも鉄道の安全運行を支える重要な実務であり、業務ごとに求められる技能や知識も異なります。
軌道整備
列車の走行や安全を支えるため、線路(軌道)の点検・整備を行う重要な業務です。主な作業として、レールの歪み修正や摩耗部分の交換、枕木や道床(砂利)の整備などが行われます。
これらは高い専門性が求められる分野であり、外国人材が安全に作業できるよう、詳細な作業マニュアルと指導体制が整えられています。安全管理が最優先される現場であり、責任感ある行動と周囲との連携が不可欠です。
電気設備整備
列車の走行や信号の正確な動作を支える電気設備の整備は、安定運行に欠かせない業務です。架線の張力調整や信号装置の検査、電源系統の保守など、作業は多岐にわたります。
特定技能人材には、基礎的な電気知識や工具の扱い方に加え、緊急時の対応力や報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の徹底も求められます。高い専門性と現場経験が必要な仕事です。
車両整備
車両の整備・保守は、鉄道の安全運行を維持するために欠かせない業務です。具体的には、車輪やブレーキの摩耗チェック、各種部品の交換、配線やエンジン機器の点検などが含まれ、マニュアルに基づき定期的かつ精密に実施されます。
特定技能人材には、一定の技術力と慎重さが求められるだけでなく、日本の鉄道特有の精密さと時間厳守の文化を理解し、チームワークを持って作業に臨む姿勢も重要です。
車両製造
鉄道車両そのものや、関連する部品を製造・加工・組み立てる業務です。設計図に基づき、車体の溶接や内装の取り付け、各種機器の搭載などを行います。高品質な車両を安定して供給するため、精密な作業技術と徹底した品質管理が求められる、ものづくりの最前線です。
運輸係員
駅業務における特定技能人材の役割は、主に補助的なポジションに位置づけられます。切符販売機の操作案内、改札業務の補助、構内の案内業務、乗客対応といった業務が含まれます。特にインバウンド観光が多いエリアでは、多言語対応ができる人材として重宝されることもあります。
ただし、対人業務が多いためN3相当以上の日本語スキルが望ましく、混雑時やトラブル発生時には臨機応変な対応が求められるため、現場経験の積み重ねが重要となります。
日本の労働市場では深刻な人手不足が続いており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。この課題を解決する重要な選択肢として外国人材の活用に注目が集まる一方、頻繁に行われる制度変更や言語・文化の壁、複雑な手続きなど、人事担当者の悩みは尽きません[…]
試験制度と評価方法の詳細
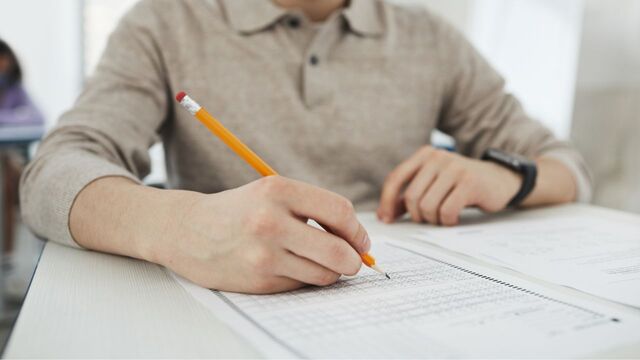
特定技能「鉄道」分野で外国人を受け入れるには、国が定めた技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。試験は専門知識と実務能力を評価するもので、受験方法や評価内容には明確な基準があります。
技能評価試験の内容と実施スケジュール
技能評価試験は、外国人が鉄道分野の業務に的確に従事できるかを評価するために実施されます。試験は「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」「運輸係員」の5区分ごとに分かれており、各業務に必要な実務知識や作業手順、安全管理などについて出題されます。試験方式はCBT(コンピューターを用いた試験)またはペーパーテストで行われ、難易度は日本国内で2年程度の実務経験を有する技能実習生レベルとされています。
試験の実施主体は鉄道分野特定技能協議会などの認定団体で、試験日程や会場情報は専用ウェブサイトで随時発表されています。合格のためには教材を活用した事前学習や模擬試験による対策が推奨されており、合格者には在留資格申請の際に必要となる合格証明書が交付されます。
参考:
国土交通省 特定技能評価試験「軌道整備区分」
一般社団法人日本鉄道施設協会
国土交通省 特定技能評価試験「電気設備整備区分」
一般社団法人 鉄道電業安全協会
国土交通省 特定技能評価試験「車両整備区分」
一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会
国土交通省 特定技能評価試験「車両製造区分」
一般社団法人日本鉄道車輌工業会
国土交通省 特定技能評価試験「運輸係員区分」
一般社団法人日本鉄道運転協会
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
日本語能力試験のレベルと実施スケジュール
日本語能力については、原則として「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」への合格が要件です。N4レベルは日常会話や基本的な指示が理解できる水準ですが、接客・案内等の現場対応が主となる「運輸係員」区分では、より高いコミュニケーション能力が求められるため、N3以上の日本語能力が必要と定められています。
試験の実施スケジュールは、「日本語能力試験(JLPT)」が年に2回(7月と12月)、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は随時開催されるCBT方式で、受験の柔軟性が高いのが特長です。これらの日本語試験と技能評価試験、双方の合格が「特定技能1号」取得の必須条件となります。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
受け入れに必要な手続きと在留資格

外国人を特定技能「鉄道」分野で雇用するには、在留資格の取得に加え、雇用契約や各種書類の提出が必要です。申請から就労開始までには一定のステップがあるため、事前に全体の流れを理解しておくことが重要です。
在留資格「特定技能1号」の取得方法
外国人が日本で特定技能「鉄道」分野の仕事に従事するには、「特定技能1号」の在留資格を取得する必要があります。
所定の試験に合格した後、受け入れ企業との間で雇用契約を締結し、出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請には、雇用条件書や業務内容が明記された契約書、支援計画書などの添付が求められます。無事に認定証明書が交付されたら、ビザ発給を受けて来日し、在留カードが交付されて初めて正式に就労可能となります。
必要な書類と提出先一覧
在留資格を申請する際には、雇用主と外国人本人それぞれから多くの書類提出が求められます。主な提出資料には、雇用契約書、支援計画書、試験合格証明書、身元保証書、受け入れ企業の登記事項証明書や決算報告書などが含まれます。これらの書類は、不備があると審査に時間がかかるため、事前に内容をしっかりと確認することが大切です。
また、フィリピンから人材を受け入れる企業は、MWO申請の手続きが必須です。
提出先は、地方出入国在留管理局であり、オンライン申請システム(出入国在留管理庁のe-申請)を利用することも可能です。提出後の審査期間は1か月から2か月程度が目安とされていますが、時期や混雑状況により前後することもあります。
申請から入社までの流れと期間目安
受け入れまでの一般的な流れは、試験合格 → 雇用契約 → 在留資格申請 → 認定証交付 → ビザ取得 → 来日・入社、という順序になります。全体としては、早くても3か月から4か月、手続きや書類準備に時間がかかる場合は半年程度を見込んでおくとよいでしょう。
中でも時間を要するのが在留資格認定証明書の発行とビザ申請のステップであり、企業側は余裕をもったスケジュール管理が求められます。また、来日前後には生活支援や住居準備、日本での生活ルールの説明なども必要となるため、支援体制の整備も並行して行うことが重要です。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
協議会・支援体制と企業の役割

特定技能「鉄道」分野の受け入れには、国の制度だけでなく、分野ごとの協議会や企業の支援体制が密接に関係しています。企業は適切な環境整備と外国人材への継続的な支援を行う責任を負っています。
鉄道分野特定技能協議会の構成と役割
鉄道分野における特定技能制度の円滑な運用のため、業界団体・関係企業・行政機関などで構成される「鉄道分野特定技能協議会」が設置されています。この協議会は、受け入れ企業へのガイドライン策定、試験内容の検討、制度運用状況をモニタリングし、必要に応じて制度の変更を提言することも担っており、制度の健全性を維持する役割を果たしています。
また、協議会の構成員には鉄道事業者のほか、鉄道車両の製造や施設整備に関わる企業も所属しており、現場の実情を反映した制度設計が行われています。協議会が発信する運用要領やQ&A集は、受け入れ企業にとって実務の大きな助けとなります。
受け入れ企業の義務と注意点
特定技能人材を雇用する企業には、法令上、数多くの義務があります。代表的なものとして、「適切な労働条件の提示」「生活支援計画の策定と実行」「外国人との定期面談の実施」などが挙げられます。また、支援計画の一環として、日本語学習のサポートや相談体制の整備も求められます。
さらに、入国後には行政への報告義務が定められており、違反があった場合には制度の利用停止や罰則が課される可能性もあります。外国人材を「人手」としてではなく、職場の一員として迎え入れる姿勢と、継続的な支援体制の構築が、良好な労働関係と定着につながるのです。
支援機関の利用方法と連携体制
企業が自力で支援体制を整えることが難しい場合、「登録支援機関」を活用するという選択肢があります。登録支援機関は、出入国在留管理庁に認定された民間事業者で、在留資格の申請サポート、生活ガイダンス、日本語教育、行政手続きの代行等、多岐にわたる業務を代行してくれます。
企業は登録支援機関との委託契約を締結することで、自社の負担を軽減しつつ、法令に沿った支援を継続的に提供できます。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、制度や手続きへの理解不足を補いながら安心して運用できるパートナーとなります。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
事例:四国の人材不足解消に向けた取り組み
2024年7月16日、衆議院議員の山本有二氏とJR四国の専務取締役らが、株式会社E-MANと提携するフィリピン・アクラン州立大学を訪問しました。アクラン州は学生の就職難が深刻で、四国地域の労働力不足解消に向けた協力体制の強化を目的とした視察となりました。
背景:就職難と地域の人材不足
アクラン州には17の大学に約7,000名の学生が在籍していますが、卒業後に仕事を見つけられるのは半数以下で、約3,500名が就職難の状況となっています。一方、四国では鉄道の保線作業員などで若手採用が難しく、採用後の離職率も高いなど人手不足の深刻化が続いています。
大学訪問と意欲的な学生の姿勢
訪問時、山本有二議員は学生約100名を前に講演を実施し、日本での就労機会や育成就労制度の説明を行いました。学生の約80%が日本で働く意欲を示し、非常に前向きな反応が得られました。また、アクラン州知事との会談では、両地域の労働市場課題の解決に向けた連携強化が確認されています。
E-MANの役割と今後の展望
株式会社E-MANは、日本語のeラーニングやオンライン授業を通じて学生の日本語能力向上を支援しています。四国地域の企業と連携し、早期からの人材育成と将来的な定着・永住を見据えたトータルサポート体制の強化にも努められています。今後も日本語教育体制の充実と、地域と連携した外国人材の受け入れ推進に注力していく予定です。
まとめ|鉄道業界での外国人材活用に向けて

鉄道業界における人手不足の深刻化を受けて、特定技能制度は即戦力となる外国人材を受け入れる有効な手段となっています。2024年に鉄道分野が追加されたことで、車両整備や駅業務といった重要な現場で外国人の活躍の場が広がりました。
本記事では、特定技能「鉄道」分野の制度概要から試験内容、必要な手続き、協議会や支援体制に至るまで、企業の担当者が知っておくべきポイントを網羅的に解説してきました。これらを正しく理解し、制度を適切に運用することで、企業と外国人双方にとって安心・安全な就労環境が実現できます。
特定技能制度を導入することで、単なる人手補充ではなく、多様性を受け入れた持続可能な職場づくりが可能になります。外国人材の積極的な活用は、鉄道産業の未来を支える重要な選択肢のひとつと言えるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。お電話やメールでのご相談も受け付けております。