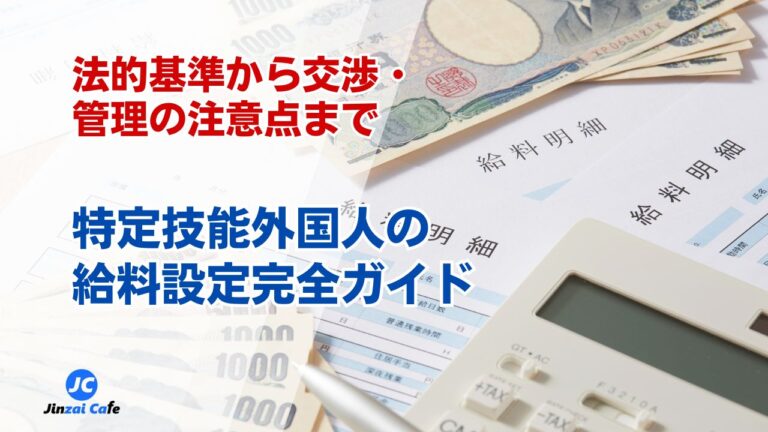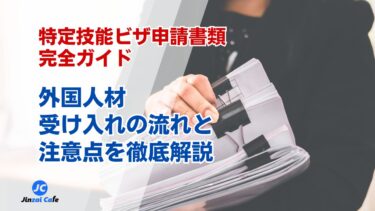人材不足が深刻化する中、特定技能外国人の雇用を検討する企業が増加傾向にあります。しかし、給料設定を誤ると、優秀な人材を確保できないだけでなく、法令違反により在留資格が取り消されるリスクを招くことになります。特定技能制度では「日本人と同等以上の報酬」が義務付けられており、この基準を正確に理解しなければ、採用活動そのものが無駄になるでしょう。
本記事では、給料設定に必要な法的基準から、実践的な交渉術、よくあるトラブル事例と回避策まで、経営者が知っておくべき実務知識を体系的に解説します。適正な給与管理により、外国人材の定着率を高め、企業の競争力強化につなげることが可能です。
特定技能外国人の給料を決める際の法的基準

特定技能外国人の給料設定では、法令遵守が最優先事項となります。入管法や労働基準法に違反すると、在留資格の取消しや罰則の対象となるため、経営者は正確な知識を持つ必要があるのです。特に「日本人と同等以上の報酬」という原則は、単に金額を合わせるだけでなく、職務内容や経験年数を考慮した適切な評価が求められます。
現在、製造業や介護、飲食料品など16の分野で特定技能外国人の受け入れが認められており、それぞれの産業別に適正な待遇を設定することが大切です。ここでは、給料決定に関わる3つの重要な法的基準について詳しく見ていきましょう。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
同等報酬の原則とは
特定技能制度における「同等報酬の原則」とは、外国人労働者に対して、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上の報酬を支払う義務を指します。この原則は、国籍による賃金差別を防ぎ、外国人材の適正な処遇を確保するために定められました。これにより、特定技能という安定した身分で働く外国人の権利が守られています。
具体的には、職務内容、責任の程度、勤務時間、経験年数などを総合的に比較し、日本人従業員の給与水準を下回らないよう設定する必要があるのです。厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」を参考にしながら、自社の給与テーブルと照らし合わせて判断することが重要となります。
同等報酬の原則に違反した場合、特定技能外国人の在留資格が取り消される可能性があるため、慎重な確認が求められるでしょう。このルールは、技能実習生から転職して特定技能に移行する外国人労働者にも同様に適用されます。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度に関するQ&A
厚生労働省 賃金構造基本統計調査
最低賃金と地域別基準
特定技能外国人にも、日本人労働者と同様に最低賃金法が適用されます。最低賃金には、全国一律の「地域別最低賃金」と特定産業に適用される「特定最低賃金」の2種類があり、企業は必ずこれらの基準を満たす給与を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は都道府県ごとに異なり、令和7年10月の改正により東京都では時給1,226円となりました。全国で一番低い高知県、宮崎県、沖縄県でも1,023円となり、この改定で全都道府県で初めて時給1,000円を超えました。給与設定の際は、勤務地の最低賃金を確認し、月給換算で下回らないよう計算することが必要です。
また、残業代や深夜労働の割増賃金も、最低賃金を基準に正確に算出しなければなりません。最低賃金違反は労働基準法違反となり、罰則の対象となるため、毎年10月の改定時には必ず最新の金額を確認し、給与額を見直すことが求められます。
社会保険料の計算方法
特定技能外国人を雇用する企業は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つの社会保険に加入させる義務があります。これらの保険料は、給与額に応じて計算され、企業と従業員が一定の割合で負担する仕組みです。
健康保険と厚生年金保険の保険料率は、標準報酬月額に基づいて決定され、企業と従業員が折半で負担します。雇用保険料は業種によって料率が異なり、労災保険料は全額企業負担となるのです。給与から控除できる項目は法律で厳格に定められており、社会保険料、所得税、住民税以外の控除は原則として認められません。
特に注意が必要なのは、寮費や食費などを給与から控除する場合で、事前に労働者の同意を得た上で、適正な金額設定を行う必要があります。社会保険料の計算ミスや不適切な控除は、トラブルの原因となるため、専門家に相談しながら正確に処理することが重要です。手続きの詳細については、登録支援機関や社会保険労務士などの専門家に気軽に相談することをお勧めします。
外国人労働者の雇用を検討する際、人事担当者が直面する最大の課題は、複雑な法的要件への対応です。在留資格の確認ミスによる不法就労助長、届出義務の不履行、労働条件における差別的取扱いなど、知識不足が重大なコンプライアンス違反を招くリスクがありま[…]
給与交渉で失敗しないための準備と進め方

特定技能外国人との給与交渉は、文化的背景や価値観の違いを理解した上で進めることが成功の鍵となります。日本人との交渉とは異なり、給与に対する考え方や期待値が大きく異なるケースも少なくありません。母国の給与水準や生活費、家族への仕送りなども考慮に入れながら、双方が納得できる条件を提示する必要があるのです。
技能実習から特定技能へ移行する外国人の場合、これまでの経験や技能レベルを適切に評価し、待遇改善の目的を明確に示すことが重要となります。ここでは、交渉を円滑に進めるための具体的な準備方法と実践的なアプローチについて解説していきます。
交渉前の市場調査方法
給与交渉を始める前に、業界や職種ごとの相場を正確に把握することが不可欠です。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や、特定技能制度を扱う登録支援機関が提供する給与データを活用し、自社が提示する金額が市場水準と比較して適正かどうかを確認しましょう。同じ地域で同業種を営む企業の求人情報も参考になります。
また、候補者の出身国における平均給与や物価水準を調べることで、提示額が彼らにとってどの程度魅力的かを判断できるのです。特定技能外国人の多くは、母国の家族への仕送りを前提に日本での就労を希望しているため、手取り額がいくらになるかを明確に示すことが重要となります。
市場調査の結果は資料としてまとめておき、交渉時に根拠として提示できるよう準備しておくと効果的でしょう。製造業、介護、飲食料品など、分野別の相場を詳細に調べることで、より説得力のある提案が可能になります。ダウンロードできる統計資料や一覧表を活用することで、効率的に情報収集を行うことができます。
効果的な給与提示の伝え方
給与を提示する際は、月給の総額だけでなく、基本給、各種手当、残業代の計算方法、社会保険料などの控除項目を明確に説明することが求められます。
特に重要なのは、手取り額がいくらになるかを具体的な数字で示すことです。多くの外国人労働者は、総支給額と手取り額の違いを正確に理解していないケースがあるため、給与明細のサンプルを用いて、控除の概要などを視覚的に説明すると理解が深まります。昇給制度や賞与の有無、支給条件についても明確に伝えましょう。
交渉の場では、候補者の希望額を先に聞き、その金額に至った理由や背景を丁寧にヒアリングすることが大切です。一方的に企業側の条件を押し付けるのではなく、対話を通じて相互理解を深めながら、双方が納得できる着地点を探る姿勢が信頼関係の構築につながります。
技能実習生として働く経験がある外国人の場合、これまでの待遇との違いを明確に示すことで、特定技能への移行のメリットを実感してもらうことができます。
福利厚生を含めた総額提示
給与交渉では、金銭的な報酬だけでなく、福利厚生を含めた総合的な待遇を提示することで、企業の魅力を高めることができます。住宅手当や通勤手当、社員寮の提供、食事補助などは、外国人材にとって大きな価値を持つ福利厚生です。
特に来日直後は住居探しに苦労するケースが多いため、社員寮や住宅サポートがあることは強力なアピールポイントとなるでしょう。以下の表は、福利厚生を金額換算して示した例です。
| 福利厚生項目 | 月額換算額 | 年間価値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 社員寮提供 | 30,000円 | 360,000円 | 市場家賃との差額分 |
| 通勤手当 | 10,000円 | 120,000円 | 実費支給 |
| 食事補助 | 15,000円 | 180,000円 | 昼食代の一部補助 |
| 日本語教育支援 | 5,000円 | 60,000円 | 研修費用の会社負担 |
| 一時帰国費用補助 | – | 100,000円 | 年1回の航空券代補助 |
| 合計 | 60,000円 | 820,000円 | 給与以外の価値 |
このように福利厚生を金額換算して示すことで、給与額だけでは見えない企業の価値を伝えることが可能です。さらに、母国への一時帰国費用の補助や、家族を日本に呼び寄せる際のサポートなど、外国人材特有のニーズに応える制度があれば、積極的にアピールしましょう。
日本語教育や技能向上のための教育プログラム、資格取得支援なども、スタッフの成長を求める外国人労働者にとって大きなメリットとなります。総合的な待遇パッケージとして提示することで、給与交渉をより建設的に進めることができます。様々なサービスを設けることで、企業としての魅力を高めることが可能です。
特定技能外国人を雇用する際、企業には「支援計画」の作成が法律で義務付けられています。この支援計画は、外国人材が日本で安心して働き、生活できるようサポートする具体的な内容を定めたものです。しかし、初めて特定技能外国人を受け入れる企業の[…]
会話トレーニングコースではN5〜N3の日本語レベルに応じて、会話に必要な日本語の使い方を学ぶことで、日常的な会話を理解し…
受け入れ企業が注意すべき給与トラブル事例

特定技能外国人の給与管理において、企業側の認識不足や制度理解の誤りがトラブルを引き起こすケースが後を絶ちません。給与に関連するトラブルは、外国人材の離職や在留資格の取消しにつながるだけでなく、企業の評判を損ない、今後の人材確保にも悪影響を及ぼします。
実際に発生した典型的なトラブル事例を知ることで、同じ過ちを避け、適正な給与管理を実現することが可能です。技能実習から特定技能へ移行する際の待遇変更や、年齢や経験年数に沿った適切な評価など、注意すべき点は多岐にわたります。
ここでは、受け入れ企業が特に注意すべき3つのトラブルパターンと、その予防策について詳しく解説していきます。
違法な給与控除の事例
給与からの控除に関連するトラブルは、特定技能外国人の雇用において最も多く発生する問題の一つです。法律で認められている控除項目は、社会保険料、所得税、住民税のみであり、それ以外の項目を勝手に差し引くことは労働基準法違反となります。
しかし、実際には寮費用や光熱費用、食費用などを事前の同意なく控除したり、市場価格を大幅に上回る金額を請求したりするケースが見られるのです。過去に違法な控除を行った企業が、厳しい行政指導を受けた事例もあります。
- 本人の同意を得ずに寮費用や食費用を控除
- 市場相場の2倍以上の寮費用を徴収
- 制服代や工具代を給与から一方的に天引き
- 研修費用や渡航費用を給与から分割控除
- 罰則名目での控除(遅刻や欠勤に対するペナルティ)
これらの控除を行う場合は、雇用契約書に明記し、労働者の書面による同意を得ることが必須となります。また、控除額は実費相当額に限定し、企業が利益を得るような設定は避けなければなりません。
違法な控除が発覚した場合、未払い賃金として遡って支払う義務が生じるだけでなく、特定技能外国人の在留資格更新が認められない可能性もあるため、慎重な対応が求められるでしょう。技能実習生時代の待遇との違いを明確に説明し、適正な控除のルールを理解してもらうことが大切です。会社として透明性の高い給与管理を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
残業代計算のミス防止策
残業代の計算ミスや未払いは、給与トラブルの中でも深刻な問題に発展しやすい事例です。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う義務があります。さらに、深夜労働(22時から翌5時)には25%、休日出勤には35%の割増が必要です。
特定技能外国人に対しても、日本人労働者と同様に、これらの規定が適用されるため、正確な計算が求められます。時間外労働が月60時間を超える場合は、50%の割増賃金を支払わなければならない点にも注意が必要です。
- 固定残業代制度の説明不足による誤解
- 深夜割増や休日割増の計算漏れ
- 月60時間を超える残業の50%割増適用忘れ
- 休憩時間を労働時間に含めてしまう誤り
- タイムカードと実際の労働時間の乖離
残業代トラブルを防ぐには、勤怠管理システムを導入し、労働時間を正確に記録することが基本となります。また、固定残業代制度を採用する場合は、基本給と固定残業代を明確に分けて表示し、何時間分の残業代が含まれているかを契約書に明記しましょう。
毎月の給与明細には、残業時間数と割増賃金の計算根拠を詳しく記載することで、透明性を確保できます。製造業や介護、飲食料品など、分野によっては長時間労働になりやすい業務もあるため、労働時間管理には特に注意が必要です。会社として適正な労働時間管理を行うことが、トラブル防止の鍵となります。
契約書作成時の注意点
雇用契約書の不備や曖昧な記載が原因で、給与に関連するトラブルが発生するケースも少なくありません。特定技能外国人との契約では、日本語だけでなく、本人が理解できる言語での契約書を用意することが重要です。
入管法では、労働条件を明示した書面の交付が義務付けられており、給与に関連する項目は特に詳細に記載する必要があります。
- 基本給の金額(月給または時給)
- 各種手当の種類と金額(住宅手当、通勤手当など)
- 賞与の有無と支給条件
- 昇給の有無と時期
- 残業代の計算方法と割増率
- 給与の支払い日と支払い方法
- 控除される項目と金額
契約書には、社会保険料や税金の控除により手取り額が総支給額より少なくなることも明記し、概算の手取り額を示すと誤解を防げます。また、契約内容について十分に説明する時間を設け、本人が内容を理解したことを確認した上で署名を得ることが大切です。契約書の写しは必ず労働者に交付し、企業側も適切に保管しましょう。
契約書作成に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。技能実習から特定技能へ移行する際の契約内容の変更点や、待遇改善の詳細を明確に示すことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
登録支援機関が提供する契約書の様式や一覧を参考にすることも効果的です。決め方や手続きの流れを明確にし、透明性の高い契約を行うことが重要です。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
特定技能外国人の給与を適正化する実践ステップ
 給与設定の法的基準や交渉術、トラブル事例を理解した上で、実際に自社の給与制度を構築し運用していくための具体的な手順が必要となります。適正な給与管理は一度設定して終わりではなく、継続的な見直しと改善が求められるのです。製造業、介護、飲食料品など、分野ごとの特性を考慮しながら、自社に最適な給与制度を設計することが大切です。
給与設定の法的基準や交渉術、トラブル事例を理解した上で、実際に自社の給与制度を構築し運用していくための具体的な手順が必要となります。適正な給与管理は一度設定して終わりではなく、継続的な見直しと改善が求められるのです。製造業、介護、飲食料品など、分野ごとの特性を考慮しながら、自社に最適な給与制度を設計することが大切です。
ここでは、給与制度の設計から日常的な運用、定期的な見直しまで、実務で即活用できる実践的なステップを段階的に解説していきます。以下の表は、給与適正化のプロセス全体を示したものです。
| ステップ | 実施内容 | 所要期間 | 担当部署 | チェックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1. 現在状況分析 | 自社の給与水準と市場相場の比較 | 1-2週間 | 人事部・経営企画 | 業界平均との差異確認 |
| 2. 制度設計 | 給与テーブルと昇給ルールの作成 | 2-3週間 | 人事部・経営層 | 法令遵守の確認 |
| 3. 契約書整備 | 雇用契約書と就業規定の更新 | 1-2週間 | 人事部・法務 | 多言語化の実施 |
| 4. 運用開始 | 給与計算と支払いの実施 | 継続的 | 人事部・経理 | 計算ミスの防止 |
| 5. 定期見直し | 年1回の給与水準チェック | 年1回 | 人事部・経営層 | 市場動向の反映 |
※横スクロールできます→
給与テーブルの作成手順
給与テーブルは、職種や経験年数に応じた給与額を体系的に定めたもので、公平で透明性の高い給与制度の基盤となります。
まず、自社の職種を分類し、それぞれに求められるスキルや責任の程度を明確にしましょう。次に、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や業界団体のデータを参考にしながら、各職種の市場相場を調査します。特定技能外国人の場合、同じ業務に従事する日本人従業員の給与を基準として、経験年数や保有資格に応じた給与レンジを設定することが重要です。
給与テーブルには、基本給だけでなく、各種手当の支給基準も明記し、総支給額が明確になるよう設計しましょう。また、地域別の最低賃金を下回らないよう、勤務地ごとに調整を加えることも必要となります。作成した給与テーブルは、労働者に開示することで、評価基準の透明性を高め、モチベーション向上にもつながるのです。
技能実習から特定技能へ移行する外国人労働者の場合、これまでの経験や技能レベルを適切に評価し、昇給のルールを明確にすることが大切です。年齢や経験年数に沿った適切な給与設定を行うことで、長期的な定着を促進できます。給与の決め方を明確にし、様々な職種に対応できる柔軟な制度を構築することが重要です。
昇給制度の設計ポイント
昇給制度は、特定技能外国人の長期定着を促進する上で極めて重要な要素となります。明確な昇給ルールがあることで、労働者は将来の見通しを持って働くことができ、企業への信頼も高まるでしょう。昇給制度を設計する際は、まず昇給のタイミングを決定します。一般的には、年1回の定期昇給が基本ですが、半年ごとの評価制度と連動させることも可能です。
昇給額の決定方法としては、勤続年数に応じた自動昇給と、業績や能力評価に基づく査定昇給を組み合わせる方式が効果的となります。特定技能外国人の場合、日本語能力の向上や資格取得などの成長を評価に反映させることで、スキルアップへの意欲を引き出すことができるのです。昇給率は、業界水準や企業の業績を考慮しながら、年2%から5%程度を目安に設定しましょう。
また、昇給の評価基準は具体的かつ客観的なものとし、評価面談を通じて本人にフィードバックすることが大切です。製造業や介護、飲食料品など、分野ごとの特性に応じた評価項目を設けることで、より実態に即した昇給制度を構築できます。
技能レベルの向上や教育プログラムの修了を昇給の条件とすることで、スタッフの成長を促すことも効果的です。様々な形での評価を組み合わせることで、公平性の高い制度を実現できます。
定期的な見直しの実施方法
給与制度は一度構築したら終わりではなく、市場環境の変化や法改正に応じて定期的に見直すことが必要です。最低賃金は毎年10月に改定されるため、この時期に合わせて自社の給与水準をチェックし、必要に応じて調整を行いましょう。また、年1回は業界の給与相場を調査し、自社の給与水準が市場と比較して適正かどうかを確認することが重要となります。
特定技能外国人からのヒアリングも定期的に実施し、給与に対する満足度や改善要望を把握することで、離職防止につながる施策を講じることができるのです。見直しの結果、給与水準の引き上げが必要と判断された場合は、経営層と協議の上、段階的な改善計画を立てましょう。
給与制度の変更を行う際は、労働者への説明を丁寧に行い、変更の理由や今後の方針を明確に伝えることが信頼関係の維持に不可欠です。見直しプロセスを記録として残し、次回の見直し時に活用することで、継続的な改善サイクルを確立できます。製造業、介護、飲食料品など、産業別の動向を把握し、分野特有の課題に対応することも大切です。
技能実習から特定技能へ移行した外国人労働者の待遇改善の結果を検証し、今後の採用戦略に活かすことも重要となります。会社として継続的に給与制度を改善していく姿勢を示すことで、優秀な人材の確保と定着を実現できます。定期的な見直しの手続きをルール化し、様々な情報源から市場動向を収集することが効果的です。
日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れを検討する企業が急速に増加しています。2019年に創設された特定技能制度は、人材確保が困難な16分野において、一定の専門性と技能を有する外国人を即戦力として雇用できる[…]
まとめ|特定技能外国人の給料管理で企業競争力を高める

特定技能外国人の給料設定は、単なるコスト管理ではなく、優秀な人材を確保し企業の成長を支える戦略的な投資です。本記事では、給与決定に必要な法的基準として、同等報酬の原則、最低賃金の適用、社会保険料の計算方法という3つの重要ポイントを解説しました。これらの基準を遵守しなければ、在留資格の取消しや法令違反のリスクに直面することになります。
また、給与交渉では市場調査に基づく適正な提示額の設定、手取り額を明示した透明性の高い説明、福利厚生を含めた総合的な待遇提案が成功の鍵となるのです。さらに、違法な控除や残業代の計算ミス、契約書の不備といったトラブル事例から学び、予防策を講じることで、労使双方が安心して働く環境を構築できます。
給与テーブルの作成、昇給制度の設計、定期的な見直しという実践ステップを着実に実行することで、外国人材の定着率が向上し、長期的な企業競争力の強化につながるでしょう。
適正な給与管理は、人材不足という経営課題を解決するだけでなく、多様性を活かした組織づくりの基盤を築くものです。製造業、介護、飲食料品など、様々な分野で特定技能外国人を受け入れる企業が増える中、適切な待遇の提供こそが競争優位性を設ける鍵と言えるでしょう。技能実習から特定技能への移行を含め、外国人労働者の生活を支え、家族を安心させる給与制度を構築することは、企業が果たすべき社会的責任なのです。
現在から将来にわたって、持続可能な人材戦略を実現するために、本記事の内容を参考に、自社の給与制度を見直してみてはいかがでしょうか。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。