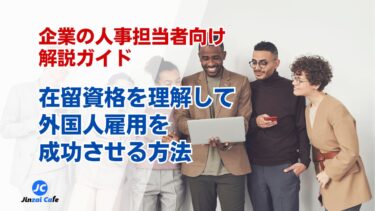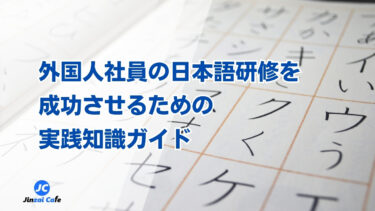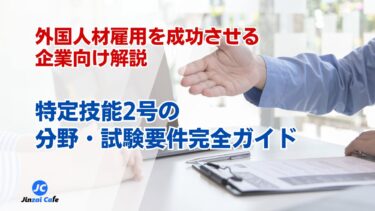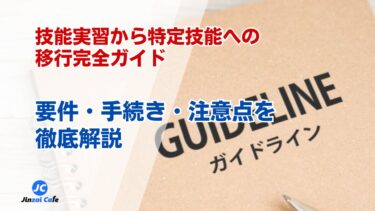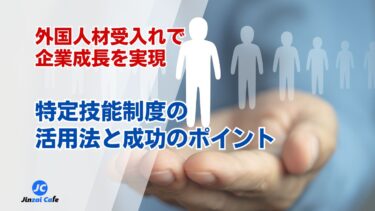造船・舶用工業は日本の産業に欠かせない分野ですが、人材不足が長年の課題になっています。熟練工の高齢化や若手の不足により、現場の負担は大きくなりつつあります。そうした状況に対応する制度として注目されているのが「特定技能2号」です。この制度を活用すれば、必要な技能を持つ外国人材を中長期的に確保することが可能になります。
本記事では、制度の仕組みや対象業務、取得要件、受入れ体制、そして今後の展望を整理し、企業が押さえるべき実務のポイントをわかりやすく解説します。
特定技能2号制度の概要と工業分野の位置づけ

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材の就労を認めるために導入された仕組みです。その中で「特定技能2号」は、一定水準を超えた熟練技能を持つ人材が対象となり、在留更新や家族帯同が可能な点が大きな特徴です。
2023年には造船・舶用工業が対象分野に追加され、産業の基盤を維持するための重要な担い手として期待されています。制度の理解は、今後の人材確保を検討する企業にとって欠かせない要素といえるでしょう。詳細については、関連省庁が公開する公式の資料を参考にすることが重要です。
参考:
出入国在留管理庁 造船・舶用工業分野
国土交通省 造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
特定技能1号との違い
特定技能1号は一定水準の技能を持つ人材が対象で、在留期間が最長5年等の制限が定められています。対して2号はより高度な技能を有する者が対象となり、在留期間の更新を重ねれば永住への道も開かれます。
この違いは企業にとって採用戦略の幅を広げる意味を持ちます。さらに、家族帯同が認められる点も人材の定着に寄与します。造船・舶用工業では長期雇用を前提に技能を継承できる利点があります。
2号の在留資格と永住への道筋
特定技能2号の在留資格は更新が可能で、長期的な就労を希望する外国人材は条件を満たせば永住許可申請へのステップにつながります。とくに造船・舶用工業分野は継続的な技能蓄積が必要であるため、この制度は現場にとって大きな意義があります。
永住が視野に入ることで、外国人材は安定した生活設計を立てやすくなります。その結果、企業も中長期的な人材育成や技能継承を計画的に進められるのです。
造船・舶用工業分野が注目される背景
造船・舶用工業は国際競争の激化や熟練工不足によって人材確保が急務となっています。関連省庁である国土交通省の調査でも、この分野は慢性的な人手不足が続いていることが明らかです。
さらに、大型船舶の建造や舶用機器の整備は高度な技能を必要とするため、即戦力人材の確保が求められます。特定技能2号はこうした背景を踏まえ導入された制度であり、企業にとって活用の意義は極めて大きいでしょう。
日本の造船・舶用工業分野は、世界有数の技術力を誇る一方で、深刻な人手不足に直面しています。特に現場の熟練作業者の高齢化や若手人材の定着難により、製造現場の維持すら困難になっている企業も少なくありません。こうした背景を受け、政府は20[…]
造船・舶用工業分野における対象業務と職種

造船・舶用工業分野で特定技能2号の対象となる業務は、2024年に行われた区分再編により整理されました。従来6つに分かれていた業務区分は、現在「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分に統合されています。
造船所での溶接や鉄工、機械加工に加え、舶用機器の組立てや塗装、電気電子機器の製作・設置なども対象業務として明確化されました。いずれも安全性と精度が求められる重要な作業であり、熟練度の高い外国人材が力を発揮できる領域です。
参考:
国土交通省 造船・舶用工業分野における業務区分再編について(R6.3.29閣議決定)
出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容(造船・舶用工業)
造船業で求められる技能と役割
造船区分には、船体を形づくる鋼材の溶接や鉄工、鋼板の切断・組立てといった基幹業務が含まれます。とくに溶接は船体の強度や耐久性を左右するため、特定技能2号の試験でも重要な評価項目となっています。
また、塗装前の表面処理や溶接後の仕上げといった、品質に直結する作業も重要視されます。造船現場では安全管理や品質管理を徹底しながら作業を進める必要があり、熟練技能を持つ外国人材は即戦力として期待されます。加えて、監督的な役割を担える人材は、工程全体の安定化にも寄与するでしょう。
舶用工業における主要業務区分
舶用工業は「舶用機械」と「舶用電気電子機器」に分けられ、それぞれに重要な業務があります。舶用機械では、エンジンや機関部品の機械加工・組立て、防錆や耐久性を高める整備や配管作業が中心です。
一方、舶用電気電子機器では、配電盤や制御盤の製作・設置、電気機器の組立て、回転電機巻線やプリント配線板製造などが含まれます。いずれの業務も高度な専門性が求められ、現場では機械系と電気系双方の技能を備えた人材が重要な役割を果たすのです。
必要とされる資格・経験の種類
対象業務に従事するためには、2年以上の一定の実務経験や試験合格が必要です。たとえば溶接や鉄工分野では、技能試験の合格が実務従事の条件になります。さらに、日本語での安全指示を理解する力も不可欠です。
技能実習生が実習を修了した末に、特定技能2号へ移行するケースも多く、経験の積み重ねが評価につながります。結果的に、即戦力として配置できる外国人材が増え、現場の生産性が向上するのです。
特定技能2号は、高度な技能を持つ外国人労働者が長期的に働ける在留資格です。取得要件や制度改正のポイントを解説します。…
造船・舶用工業分野での特定技能2号の取得要件と試験制度
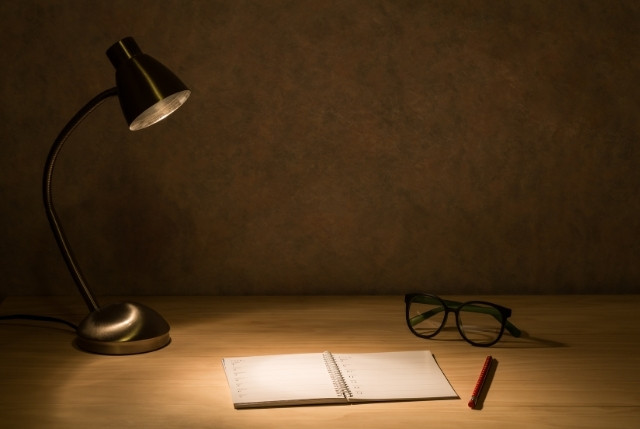
特定技能2号を取得するためには、造船・舶用工業分野における専門的な技能を証明する必要があります。複数の業務区分における実務経験の積み重ねに加え、技能試験や日本語試験の合格が必須です。とくに安全面を重視する現場では、言語理解と実技能力の両立が不可欠とされています。
企業としては、候補者の経歴や試験結果を的確に確認し、適切な人材を選定することが重要です。この点は特定技能に係る制度運用上の大きなポイントになるでしょう。
在留資格と更新条件
造船・舶用工業で働く外国人が特定技能2号を取得すると、在留期間は1年または3年ごとに更新可能です。さらに、条件を満たせば在留資格の更新許可や永住許可の交付申請への道が開ける仕組みです。これにより、長期的な就労が可能となり、技能の継続的な活用が実現します。
更新の際には、雇用契約の安定性や社会保険の加入状況なども審査対象となります。企業にとっても、計画的な雇用と育成を実行しやすい仕組みといえるでしょう。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
実技試験・日本語試験の内容
特定技能2号の資格を得るには、実務に直結する実技試験を突破する必要があります。造船では溶接や鉄工、舶用工業では機械加工や塗装などが試験範囲です。
加えて、日常業務に支障がないレベルの日本語力も求められます。これらの試験は、出入国在留管理庁や国土交通省が関連機関である一般財団法人日本海事協会等に試験業務を委託して実施されるため、信頼性が高いのが特徴です。企業は採用時に試験合格の有無を確認し、配置を検討することが大切になります。
参考:一般財団法人日本海事協会(ClassNK) 造船・舶用工業分野特定技能試験
グローバル化が進む中、多くの日本企業が外国人社員を採用するようになっています。しかし、採用後に直面する大きな課題のひとつが「日本語でのコミュニケーション」です。業務の指示が伝わらない、会議で発言が難しい、日常会話に壁を感じるといった問題は、[…]
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
業種別ソリューション・造船・舶用工業|nihongocafe・日本語カフェ|外国人材教育コスト削減|日本語教育システム・…
技能実習からの移行ルート
技能実習を修了した人材が、特定技能2号へ移行するケースは少なくありません。実習で培った知識や経験が評価され、技能レベルを証明するものとして試験免除の対象になることもあります。
特に造船や舶用工業の分野では、実習での経験がそのまま即戦力として活かせるのが利点です。上記のような制度を理解し、申請要領に沿って手続きを進めることで、所属企業や登録支援機関と連携してスムーズな受け入れが可能になるでしょう。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
造船・舶用工業分野での受入れ体制と支援ポイント

外国人材を受け入れる際には、制度上の要件を満たすだけでなく、現場で安心して働ける環境を整えることが重要です。造船・舶用工業分野では危険を伴う作業が多いため、安全教育や生活支援の充実が欠かせません。
また、登録支援機関が提供するサービスを利用し連携することで、行政手続きや生活面でのフォローも行いやすくなります。適切な受入れ体制を構築することが、長期的な定着や成果につながるでしょう。
受入れ体制の整備と管理責任
造船現場では大規模な設備や重機を扱うため、企業は安全管理の徹底を求められます。具体的には、以下のような労働時間の管理、宿舎の整備、相談窓口の設置や通訳体制の確保などが必要です。これらの対策を徹底して行った結果、トラブルを未然に防げます。
さらに、労務管理においては就業規則や契約書を多言語化する取り組みも有効です。外国人材が不安なく作業に集中できる環境づくりが、業務効率の向上にも直結します。
造船・舶用工業分野の特定技能2号について解説。対象業務、技能要件、試験情報、移行方法、受入れ企業の必要手続きをまとめまし…
外国人材への支援と実務サポート
受入れ企業は、外国人材に対して生活指導や相談窓口の設置といった支援を行うことが求められます。造船・舶用工業では専門用語も多いため、日常的に使える辞書や翻訳ツールの導入も効果的です。
さらに、資格更新や各種申請に関して、数多くの登録支援機関と協力して支援する体制を整えることが欠かせません。実務サポートが充実していれば、人材の定着率が高まり、結果として企業の成長にもつながります。
成功事例に学ぶ効果的な取り組み
因島鉄工株式会社(広島県尾道市)は、「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」において、全国で初めて外国人が3名同時に合格するという成果を挙げました。この成功は、「特定技能外国人受入モデル企業支援事業」の採択を受けての実務的な受け入れ体制の整備によるものです。因島鉄工では県から派遣されたアドバイザーとともに、現場の課題を洗い出し、受験準備だけでなくその後の日本語能力・技術研修・職場環境づくりも含めたプランを構築しました。
また、特定技能2号取得者を、単なる作業員としてではなく、溶接などの専門技能を活かして監督者としての役割を任せるなど、実務上で権限と責任を持った立場で活用しています。このモデルは、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員である多くの企業にとって、人手不足に対する具体的な解決策であるとともに、外国人材の定着とキャリアアップを実現する好例です。
参考:PRTIMES 全国初!「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」に、広島県7内の外国人が合格
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
後の展望と人材確保の戦略

今後の造船・舶用工業分野における特定技能2号制度は、さらに活用が進むと考えられます。国土交通省を中心に制度の運用が強化され、外国人材の定着を後押しする取り組みも拡大中です。
企業にとっては、採用のみにとどまらず、教育・定着・キャリア形成を見据えた人材戦略を構築することが欠かせません。中長期的な人材確保を視野に入れた取り組みが、競争力維持の鍵になるでしょう。
制度運用の最新動向
政府は造船・舶用工業分野の人材不足を背景に、特定技能制度の運用を柔軟化しています。試験の実施回数や受験機会の拡大、制度に関する説明会の開催、支援機関の役割強化などが進められており、随時更新される情報によって外国人材の受け入れやすさは向上している状況です。
さらに、業界団体も協力し、研修や技能評価の基準を整備しています。こうした動向を早めに把握し、制度の変更に合わせて採用戦略を調整することが企業には求められます。
企業にとってのメリットと課題
特定技能2号人材を受け入れることで、熟練作業の継続や人手不足の解消が期待できます。加えて、長期雇用が可能なため技能の定着やチーム力の強化にもつながります。
その一方で、文化や言語の壁をどう克服するかが課題となるでしょう。安全教育や労務管理を徹底する必要があるほか、地域社会との共生も重要な要素です。メリットと課題を理解し、両面に対応する姿勢が欠かせません。
持続可能な人材確保の方法
今後の造船・舶用工業分野では、単なる採用に留まらず「持続可能な人材確保」が求められます。たとえば、外国人材と日本人従業員の共同チームを形成し、技能移転や教育を計画的に進める方法があります。
また、キャリアパスを明確に提示することで、長期的な定着を促すことも可能です。加えて、地域コミュニティとの交流機会を設ける取り組みも効果的です。こうした総合的な戦略が今後の成否を左右します。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
まとめ|造船・舶用工業分野での特定技能2号活用

本記事では、特定技能2号の概要から造船・舶用工業における対象業務、取得要件、受入れ体制、さらに今後の展望までを解説しました。深刻な人材不足を背景に導入されたこの制度は、企業にとって持続的な成長を支える大きなチャンスです。自社の課題に照らし合わせて制度を活用することが、人材確保と技能継承の両立につながるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材を紹介しています。