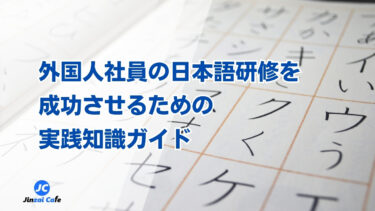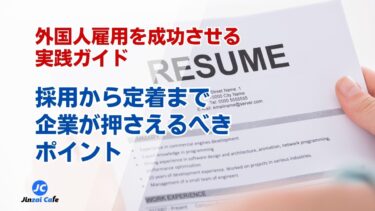飲食料品製造業は、少子高齢化や労働人口の減少により深刻な人手不足に直面しています。特に食品加工や衛生管理などの現場業務は、熟練した人材が不足しており、企業経営者にとって切実な課題です。その一方で、特定技能制度が導入されたことで、外国人労働者の受入れが現実的な選択肢となりました。
しかし、「特定技能2号」については情報がまだ少なく、概要や試験内容、在留資格の更新方法など、制度を正しく理解するのが難しいと感じる者も多いでしょう。本記事では、飲食料品製造業における特定技能2号の制度全体を整理し、試験や支援体制、最新の成功事例を交えながらわかりやすく解説します。
このガイドを読んで、企業としての導入メリットや注意点を確認でき、採用戦略の一助とすることができます。
特定技能2号の概要と制度の位置づけ

特定技能制度は、外国人が一定の技能を持ち、日本の産業に貢献することを目的に設計されています。その中で「2号」は長期的な雇用を可能にする在留資格であり、飲食料品製造業にも大きな影響を与えています。以下に、制度の概要を整理し、企業がとるべき準備や方向性を示します。
特定技能1号との違い
特定技能1号は最長5年間の在留資格で、単純作業を含む幅広い業務に従事できますが、一部の業種で定められた専門的な作業を除く場合があります。一方、2号は熟練した技能を持つ者に付与され、在留資格の更新や家族帯同が認められる点が大きな違いです。飲食料品製造業では、技能実習を修了した人材が2号へ移行するケースもあり、長期的な戦力としての受け入れが可能になります。
在留資格と更新条件
2号の在留資格は、更新に制限がなく、条件を満たせば長期滞在が可能です。更新には、従事する業務が制度に定められた分野であることや、適切な雇用契約が結ばれていること等が必要です。これにより、外国人労働者と企業の双方に安定した雇用関係が築かれます。
飲食料品分野での制度導入の背景
農林水産省や厚生労働省の報告によると、飲食料品製造業は慢性的な人材不足にあり、特定技能制度の対象分野として位置づけられました。食品安全や衛生管理を確保するためにも、技能を持つ外国人の受け入れが求められており、外国からの労働力に期待が寄せられているのが現状です。
人材不足が深刻化する現代の日本社会において、外国人材の活用は企業の持続的成長に欠かせない重要な戦略となっています。共生社会の実現に向けた具体的な取り組みを解説します。外国人材との共生を推進し、多様性を活かした組織づくりを行うことで、[…]
飲食料品製造業における特定技能2号の重要性

飲食料品製造業は、食品加工、包装、品質管理など多様な工程を含むため、安定した人材確保が求められます。業界のトップレベルの品質を維持するためにも、特定技能2号は長期雇用を前提としており、企業が外国人労働者と共に中長期的な計画を立てられる点で重要な役割を担います。また、技能の蓄積や継続的な改善が期待できることから、産業全体の競争力強化にもつながります。
参考:農林水産省 飲食料品製造業における外国人の受入れについて
業界の人材不足の実態
飲食料品製造業は、季節や需要に応じて人手が大きく変動する分野です。とりわけ繁忙期には、地元の労働力だけでは対応が難しくなっています。厚生労働省の調査でも、製造業の中でも食品関連は有効求人倍率が高く、慢性的な人手不足が明らかです。こうした背景から、技能を有する外国人材の受け入れは欠かせない対策とされています。
企業にとっての導入メリット
特定技能2号を活用することで、企業は長期的な人材確保が可能になります。1号と異なり在留資格更新の制限がないため、熟練度が上がるにつれて現場力の向上も見込めます。また、採用や教育のコストが分散され、結果として生産性の向上や品質の安定につながります。導入企業の中には、外国人スタッフが外国の文化や視点をもたらす効果を感じている事例もあります。
外国人労働者の役割と可能性
外国人労働者は、単なる人手不足の補填ではなく、企業の成長を支える重要な戦力です。特に2号の対象者は、既に技能実習や1号で1年以上の経験を持つ場合が多く、彼らがこれまで行ってきた努力が現場の力となります。こうした人材は衛生管理や品質測定など専門性が高い作業も担うことができ、現場の効率化や安全性の確保に寄与します。
「人手不足が深刻化する中、外国人材の採用を検討すべきか悩んでいる」「外国人労働者を雇用するメリットやデメリット、その理由を詳しく知りたい」。このような課題を抱える企業の人事担当者は少なくないでしょう。厚生労働省の調査によると、202[…]
特定技能2号の試験と評価基準

特定技能2号を取得するには、専門的な知識と技能を証明する試験に合格する必要があります。飲食料品製造業における評価基準は厳格に定められており、現場の作業者としてだけでなく、管理者としての能力を有することを証明しなくてはなりません。この高いハードルをクリアした人材だからこそ、企業は安心して中核業務を任せることができます。
試験の構成と評価内容
特定技能2号の試験は、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」と呼ばれ、「学科試験」と「実技試験」で構成されています。これらは単なる作業能力だけでなく、管理者としての資質を多角的に評価する内容です。
- 学科試験
- HACCPに沿った高度な衛生管理、品質管理、食品表示に関する専門知識に加え、労務管理や生産性向上に関わる工程管理といった、現場リーダーや管理者に求められるマネジメント能力が問われます。
- 実技試験
- ペーパーテスト形式で行われ、複数の製造ラインや作業工程を管理・監督する場面を想定した課題が出題されます。作業員への適切な指示の出し方や、トラブル発生時の的確な判断力など、より実践的な管理能力が試されるのが特徴です。
また、独立した日本語試験はありませんが、試験問題はすべて日本語(漢字にはふりがな付き)で出題されるため、日本語能力試験(JLPT)N3相当以上の読解力や専門用語の知識がなければ合格は困難です。この試験は、農林水産省の監督のもと、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施し、合格者には合格証明書が発行されます。
参考:
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
受験資格と合格基準
特定技能2号の試験を受験するには、原則として「飲食料品製造業分野の特定技能1号として、通算2年以上の実務経験」が必要です。この経験を通じて、現場のリーダーや管理者として必要な技能の基礎を習得していることが前提となります。
合格基準は、「複数の従業員に対して指導・監督を行いながら、自らも模範となる技能レベルで業務を遂行できる能力」を有しているかどうかで判断されます。この高い基準をクリアすることで、外国人は在留期間の更新に制限のない資格を得られ、企業も安心して中核人材として雇用を継続できます。
試験に向けた学習・支援体制
高度な知識が問われる2号試験の合格には、企業側の支援が不可欠です。成功している企業では、登録支援機関と連携して専門的な勉強会を開催したり、管理者層が模擬面談を行うなど、従業員が試験を突破できるよう手厚い体制を整えています。
OTAFFの公式サイトでは、学習用の公式テキストや過去問題のサンプルといった資料が公開されており、誰でもダウンロードが可能です。試験の数ヶ月前からこれらの資料を活用し、計画的に学習を進めることも有効な手段です。
参考:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 外食業と飲食料品製造業の国内・国外試験情報
グローバル化が進む中、多くの日本企業が外国人社員を採用するようになっています。しかし、採用後に直面する大きな課題のひとつが「日本語でのコミュニケーション」です。業務の指示が伝わらない、会議で発言が難しい、日常会話に壁を感じるといった問題は、[…]
企業が行うべき受入れ準備と支援体制

特定技能2号の外国人材を受け入れる際、企業は単なる採用活動にとどまらず、労務管理や生活支援を含めた体制整備が求められます。円滑な受入れのために、企業は様々な準備を行う必要があります。
登録支援機関の活用方法
多くの企業にとって、特定技能制度の手続きや申請業務は複雑に感じられるでしょう。そこで活躍するのが「登録支援機関」です。これらの機関は、在留資格に関する書類作成、行政への申請代行、さらには生活支援までを包括的にサポートします。委託契約を結ぶことで、企業は法令違反のリスクを減らし、採用後の管理負担も軽減できます。農林水産省の公式一覧から信頼できる支援機関を確認し、自社に合ったパートナーを選ぶことが重要です。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
衛生管理と労務管理の注意点
飲食料品製造業では、食品衛生法に基づいた衛生管理が欠かせません。外国人労働者に対しても、手洗いや異物混入防止などのルールを徹底する教育が必要です。また、労務管理の面では、労働時間の遵守や安全な作業環境の提供が求められます。
受け入れ計画と更新手続きの実務
特定技能2号は長期雇用を前提とするため、受け入れ計画の作成が欠かせません。計画には、業務内容、指導方法、更新時の確認事項などを明記し、企業として責任を持って実施する必要があります。これらを丁寧に運用し、継続的な戦力として外国人材が企業に根付くことを受け、長期的な発展が期待できます。
人手不足が深刻化している現代において、中小企業を含め多くの企業が新たな労働力確保の方法を模索しています。特に建設業、介護業界、製造業では、国内での人材確保が困難になっているのが現状です。そうした中で注目されているのが、外国人雇用という選択肢[…]
飲食料品製造業での成功事例と最新情報

実際に特定技能2号を導入した企業では、人手不足解消だけでなく、品質管理の向上や生産効率アップといった成果が報告されています。ここでは、代表的な成功事例や農林水産省からの最新情報を整理し、導入の参考となるポイントを紹介します。
成功事例の紹介|責任ある品質管理で2号取得に
ウィルオブ・ワークのベトナム出身特定技能外国人は、兵庫県神戸市の食品製造を請け負う事業所で従事しています。特定技能1号として「生産・品質管理」の業務に加え、ベトナム人スタッフの管理やライン管理者としてのリーダー業務も担う、責任あるポジションを任されました。その実績を背景に、2024年3月に実施された第1回「特定技能2号技能測定試験」に合格し、8月には特定技能2号の在留資格を取得しました。これにより在留期間の制限がなくなり、家族帯同も可能となったため、昇給後も継続して同事業所で活躍しています。
同社は今後も、外国人のキャリア形成支援と特定技能2号取得促進に注力していく予定です。
参考:PR TIMES ウィルオブ・ワークが雇用する特定技能外国人が飲食料品製造業の在留資格「特定技能2号」を初取得!
政府・農林水産省の発表情報
農林水産省は、飲食料品製造業における外国人材の受け入れ状況を定期的に公表しています。最新の発表では、受け入れ人数が年々増加しており、今後も制度の拡充が予定されています。また、技能測定試験の実施スケジュールや評価基準についても公式サイトで随時更新されているため、企業は常に情報を確認する必要があります。
参考:農林水産省 飲食料品製造業における外国人の受入れについて
今後の制度拡充の見通し
政府は、特定技能制度の拡充を段階的に進めています。飲食料品製造業でも、受け入れ可能な業務範囲の拡大や試験制度の改善が議論されています。さらに、業界の協議会が中心となり、その構成員である企業や団体と共に教育プログラムの作成も進められています。外食業や介護、漁業など他の分野とは異なる工業的な特性を持つ業種であるため、関連する協議の詳細にも注目が必要です。
まとめ|特定技能2号の活用で人手不足を解消する

飲食料品製造業は、日本の生活を支える重要な産業でありながら、人手不足という深刻な課題に直面しています。本記事で説明したように、特定技能2号は在留資格の長期化や家族帯同を可能とする制度であり、企業にとっては安定した人材確保の手段となります。
成功事例に見られるように、特定技能外国人は単なる労働力ではなく、責任ある立場で品質管理やリーダー業務を担うなど、企業の成長を支える存在となり得ます。農林水産省や支援機関の情報を常に確認しながら、登録支援機関の活用や受け入れ計画の整備を行うことが、円滑な制度運用のカギとなるでしょう。
人材不足に悩む経営者にとって、特定技能2号制度は未来の経営基盤を支えるチャンスです。制度の正しい理解と計画的な導入により、企業は持続可能な発展を目指せます。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談サービスをご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。