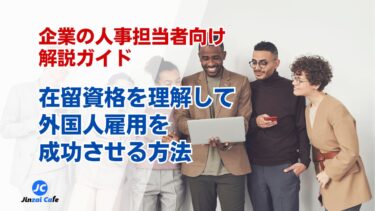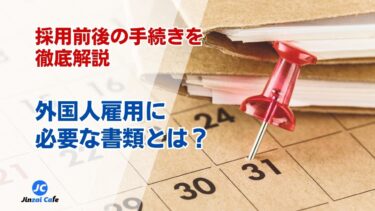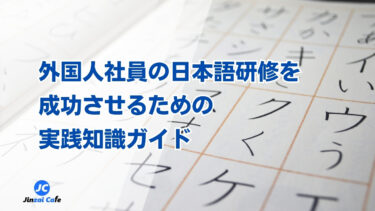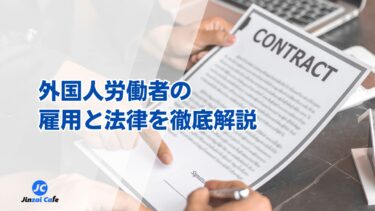製造業では深刻な人手不足が続いており、企業は持続的な雇用確保に悩んでいます。その中で注目されているのが「特定技能2号」という在留資格です。特定技能1号と異なり、更新制限がなく長期的な雇用が可能なため、熟練した外国人労働者を安定的に受け入れる仕組みとして期待されています。この記事では、制度の概要から試験内容、受入れ要件、支援体制まで、製造業の現場で活用できる実用的な情報を解説していきます。
日本の製造業は、長年にわたり人手不足という大きな課題に直面してきました。特に工業製品製造の現場では、少子高齢化に伴う労働力の確保が困難になっており、生産ラインの維持すら危ういという声も少なくありません。こうした背景のなかで注目を集め[…]
特定技能2号制度の概要

特定技能2号は、日本の労働市場で高度な技能を持つ外国人材を長期的に受け入れるために設けられた制度です。特定技能1号からの移行が可能で、更新回数に制限がない点が大きな特徴です。特に製造業分野では、熟練した技能を持つ人材が安定的に働く仕組みとして注目されています。ここでは、制度全体の特徴と製造業における位置づけを整理し、導入を検討する企業に必要な基礎情報をまとめます。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
特定技能1号との違い
特定技能1号は相当程度の技能を要する業務が対象で、在留期間は通算5年まで、原則として家族帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は熟練度の高い業務に従事でき、在留資格に更新上限がない点が大きな違いです。また、2号資格では家族帯同も特別な形で認められるため、外国人材の生活基盤が安定し、長期的に企業に定着する効果が期待できます。これにより、製造業のような継続的な人材ニーズが高い分野での活用が進んでいます。
対象分野と製造業の位置づけ
特定技能2号の対象分野は、当初は建設分野と造船・舶用工業分野(一部の溶接区分に限る)でしたが、2023年8月31日の省令改正により、製造業、自動車整備、農業、漁業、外食業、宿泊、ビルクリーニング、航空の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全ての全11分野に拡大されています。
製造業では素形材、産業機械、電気・電子情報、飲食料品製造などが含まれ、数多くの企業で技能実習や1号から2号への移行が進むと予想されます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
在留資格と更新制度の特徴
特定技能2号の在留資格は、制度上、更新回数に制限がなく、事実上の長期雇用が可能です。更新時の在留期間は3年または5年等が付与され、これは特定技能1号の「通算5年まで」という制約と大きく異なる点です。
また、資格取得には試験合格や実務経験が求められ、技能水準の高さが保証されます。さらに、家族帯同が認められることで、外国人材が生活の安定を得やすくなり、結果として企業への定着率が高まります。
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
製造業分野での受入れ要件

製造業で特定技能2号の外国人材を受け入れるには、以下に挙げるような法律で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、受入れ対象の業務区分が明確に定められており、企業はそれに合致する業務を提供しなければなりません。
また、在留資格の変更申請の際には必要書類の提出や、労働条件が適正であることの確認も求められます。さらに、外国人材が安心して働ける環境を整えることも企業の責任とされています。
受入れ可能な業務区分一覧
製造業に関連する特定技能2号の業務区分は、金属加工(溶接、塗装、表面処理など)、産業機械・機械組立て、電気・電子機器関連、自動車整備等、多岐にわたります。
これらは高度な技能や知識を必要とするため、単純労働ではなく、実務経験を積んだ外国人材が活躍できる領域となります。企業は、自社の業務がこれらの区分に含まれているかを確認し、必要に応じて制度利用を検討すると良いでしょう。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容(工業製品製造業分野)
必要書類と申請の流れ
申請手続きでは、受入れ企業は雇用契約書、労働条件通知書、技能証明書等の資料を提出する必要があります。これらの書類は、外国人材が適切な在留資格で就労できるかを判断する重要な素となります。
申請は出入国在留管理庁を通じて行われ、内容に不備があると審査に時間がかかる場合があります。申請後、許可が下りるまでの期間も考慮しましょう。そのため、事前に公式サイトのページで必要な資料を確認したり、登録支援機関の利用を検討することが有効です。
受入れ企業に求められる条件
受入れ企業には、外国人労働者の生活支援や労働環境整備といった責務が課せられています。たとえば、日本語教育の支援や、労働時間・給与が法律に準じているかの確認が必要です。サービスとして相談窓口を設けることも有効でしょう。
さらに、ハラスメント防止や安全管理体制の整備も求められます。これらを怠ると、受入れ資格を失う可能性があるため、企業は制度遵守と適切な体制構築を徹底しなければいけません。
グローバル化が進む現在、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。しかし、多くの人事担当者が「外国人を採用したいけれど、どんな書類が必要なのかわからない」「手続きでトラブルを起こしたくない」といった不安を抱えているのではないでしょ[…]
試験制度と評価方法

特定技能2号の取得には、一定の技能レベルを証明するための試験に合格することが求められます。製造業関連の分野では、実務に直結した内容が出題され、受験者の知識や経験を客観的に評価する仕組みが整っています。
試験は日本国内外で実施されており、受験方法や評価基準が公開されています。企業は採用時に合格証明書の発行を確認することで、即戦力となる外国人材を確保できるでしょう。
参考:
経済産業省 製造分野特定技能評価試験実施要領
特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト 製造分野特定技能評価試験
試験内容と出題範囲
試験内容は、金属加工、機械組立て、電子機器、自動車関連など製造業特有の分野を網羅しています。出題範囲は基礎知識から実務的な技能まで幅広く、図面の読み取りや工具の使用方法、工程管理の理解等が含まれます。
これにより、単なる座学ではなく現場での実践力が測定される仕組みです。特定技能1号から移行する場合でも、2号に必要な高度な知識が問われます。
受験方法とスケジュール
試験は原則として日本語で行われ、筆記試験と実技試験に分かれています。受験者は国内外の試験会場で受験可能で、実施日程は出入国在留管理庁や関連のポータルサイトで公開されています。
スケジュールは業種ごとに異なり、定期的に更新されるため、企業は採用計画に合わせて情報を確認する必要があります。受験料や申請手続きも事前に整理しておくとスムーズでしょう。
評価基準と合格率の傾向
合格判定は、筆記・実技それぞれの基準点をクリアする必要があります。評価基準は公開されており、技能の正確性や安全管理について一定程度の理解度も重視されます。
近年の傾向として、実技試験の合格率は比較的高い一方、専門知識を問う筆記試験で苦戦する受験者が多いと言われています。そのため、企業は候補者に事前学習の支援を行い、合格までのプロセスを伴走することが効果的です。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
製造業における活用事例

特定技能2号は、すでに製造業分野で導入が進んでおり、人材不足の解消に貢献しています。実務経験を積んだ外国人労働者が長期的に働けるため、品質維持や生産効率の向上につながる点が大きな特徴です。
ここでは、金属加工分野と、技能実習からの移行事例を取り上げ、企業が制度を活用する具体的なイメージを紹介します。
金属加工分野の成功事例
和歌山県紀の川市に本社を置く協和プレス工業株式会社では、特定技能2号人材を積極的に受け入れています。技能実習修了者の採用やジョブフェアを通じ、多国籍の人材を登用しており、金属プレス加工や工場板金といった高度な業務に従事しています。
日本語教育や資格取得支援を会社が全面的にバックアップし、合格者には手当を支給する制度を導入している点も特徴です。外国人材は日本人社員と同等の役割を担い、後輩指導も行っています。
その結果、人手不足解消に加え教育コスト削減や生産性向上を実現しました。社員同士の交流も工夫され、社内報で外国人の母国紹介を掲載するなど、文化の共有も進んでいます。
参考:経済産業省 製造業における特定技能外国人材受入れ事例(15ページ)
技能実習から特定技能への移行に向けた取り組み事例
大阪府門真市のマルイチエクソム株式会社では、技能実習を修了した人材や他社から転職してきた特定技能1号人材を受け入れています。プラスチック成形や組立、検査などの現場で外国人が活躍しており、従業員の約半数を占める多国籍な環境です。
2023年には特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級の合格者が生まれ、2号資格への移行を進めています。日本語力向上を促す仕組みや、マネジメント勉強会の実施など、キャリア形成にも積極的に取り組んでいます。外国人材は日本人と同様にリーダー役を担い、長期雇用へ移行するモデルケースとなっています。
参考:経済産業省 製造業における特定技能外国人材受入れ事例(39ページ)
企業が押さえるべき支援体制

特定技能2号人材を安定的に雇用するには、採用後の職場定着を支える仕組みが不可欠です。製造業の現場では、高度な技能を持つ外国人労働者が活躍する一方、言語や生活環境の壁が課題となる場合があります。
そこで企業は、生活支援や日本語教育、スキル向上の仕組みを整えるとともに、法令遵守を徹底する必要があります。これにより、外国人材の能力を最大限に発揮させられるでしょう。
生活支援と職場環境整備
外国人材が安心して働けるためには、生活面での支援が欠かせません。住居の確保、医療機関の案内、生活相談窓口の設置など、日常生活に密着したサポートが求められます。
加えて、製造業の現場では安全管理体制や作業マニュアルの整備も重要です。快適で安心できる環境を用意することで、外国人労働者が長期的に定着し、企業の戦力として活躍する可能性が高まります。
日本語教育とスキル向上支援
特定技能2号の外国人は高い技能を持ちますが、日本語力に不安を抱える場合もあります。そのため、企業が日本語教育を提供し、円滑なコミュニケーションを支援することは有効です。
また、製造業に必要な最新技術や工程管理の研修を行うことで、人材のスキルアップにつながります。教育投資を行うことで、従業員のモチベーション向上と企業全体の生産性改善が期待できるでしょう。
グローバル化が進む中、多くの日本企業が外国人社員を採用するようになっています。しかし、採用後に直面する大きな課題のひとつが「日本語でのコミュニケーション」です。業務の指示が伝わらない、会議で発言が難しい、日常会話に壁を感じるといった問題は、[…]
法的遵守とトラブル回避のポイント
外国人労働者を雇用する際には、労働基準法や入管法をはじめとする関連法規を守ることが必須です。労働条件通知書の明示、残業管理、適正な賃金支払いはもちろん、ハラスメント防止の体制づくりも求められます。
違反が発覚すると、受入れ資格を失うだけでなく企業の信用を大きく損なう可能性があります。定期的なチェックと、登録支援機関等の専門家による客観的な確認を導入すると安心でしょう。
近年、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中で、グローバル人材、特に外国人労働者の活用が多くの日本企業にとって喫緊の課題となっています。多様な知識や文化を持つ外国人材を受け入れることは、企業の競争力向上やイノベーション創出につながる一方で[…]
まとめ|製造業の未来と特定技能2号

特定技能2号制度は、製造業における人手不足を根本的に解決する可能性を秘めています。更新制限がなく、熟練した外国人労働者を長期的に雇用できる点は、企業にとって大きな強みです。
さらに、生活支援や教育体制を整備することで、人材が安心して働き続けられる環境が実現できます。今後の製造業において、特定技能2号を活用することは企業の競争力維持に直結するでしょう。ぜひ本記事を参考に、制度導入を検討してみてください。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。