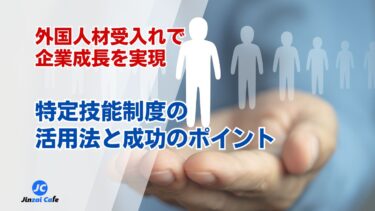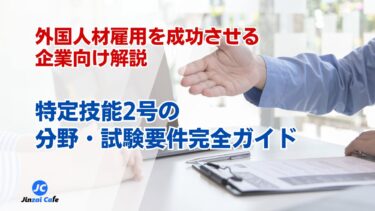日本の豊かな食文化を根底から支える飲食料品製造業は、私たちの食卓に欠かせない重要な産業です。しかし近年、その現場では少子高齢化の進行と若者の製造業離れを背景に、深刻な人手不足が恒常的な課題となっています。特に地方の工場や中小企業では、採用が思うように進まず、既存の従業員の負担が増加し、事業の継続自体が危ぶまれるケースも少なくありません。
こうした中で注目されているのが「特定技能制度」を活用した外国人材の受け入れです。この制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、労働力を確保するだけでなく、組織の活性化にも繋がる優秀な人材を安定的に確保することが可能になります。
本記事では、特定技能制度の概要から試験や手続き、実際の導入事例までを網羅的に解説します。外国人材を受け入れる前に制度の全体像を深く把握することで、採用の第一歩を確かなものにするヒントが得られるはずです。
飲食料品製造業における人手不足と課題

日本の飲食料品製造業は、高品質な加工食品や惣菜、冷凍食品などを安定して供給する社会インフラとしての役割を担っています。しかし、その現場では構造的な人手不足という大きな課題に直面し、生産体制の維持が困難になりつつあります。特に農業や外食業といった関連産業と同様に、労働集約的な側面が強く、年間を通じて安定した労働力の確保が経営の最重要課題となっています。この課題解決なくして、業界の持続的な発展は難しい状況です。
現場で求められる業務内容と人材像
飲食料品製造業では、食材の加工作業やライン作業、検品・包装といった反復的かつ正確さが求められる業務が中心です。そのため、一定の日本語能力とマニュアル遵守力、体力を兼ね備えた人材が求められています。関連業務の経験があれば即戦力として期待できますが、未経験者でも比較的短い時間で技能を習得できる業務が多いのも特徴です。近年はHACCPに沿った衛生管理が義務化されており、そのルールを正確に理解し、他の人と協力して品質と安全を守るチームワークも不可欠な資質となっています。
参考:厚生労働省 食品製造におけるHACCP入門のための手引書
人手不足が及ぼす経営への影響
慢性的な人材不足は、生産量の低下や納期遅延、従業員の過重労働といった形で企業経営に直接的な悪影響を及ぼします。人手が足りない状態が続くと、受注そのものを断らざるを得なくなるケースもあり、競争力の低下を招きます。また、新たな設備投資や商品開発といった未来への投資機会を逃したり、原材料の安定調達に支障をきたしたりするなど、経営戦略全般に影を落とします。熟練従業員の退職が相次ぐ中で技術の継承が滞り、せっかくの事業拡大のチャンスを逃してしまうことも、企業の持続可能性を揺るがす深刻な問題です。
他業界との人材獲得競争の実態
近年では物流業界や介護業界、漁業などでも深刻な人手不足が問題となっており、飲食料品製造業はこれらの業界と人材獲得競争を強いられています。給与面や就業環境で劣ると判断されれば、他業種に人材が流れてしまい、ますます採用が難しくなるという負のスパイラルに陥ります。求人広告費の高騰や採用担当者の負担増も無視できません。特に、求人サイト上での見せ方やSNSを活用した情報発信など、企業の魅力を積極的にアピールする工夫がなければ、多くの候補者の中から選ばれることは難しくなっています。
日本社会は今、かつてない規模での外国人材の受入れが進んでいます。政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、多くの企業が外国人材の活用を検討しています。しかし、単に人材を受け入れ[…]
特定技能制度の概要と対象分野

特定技能制度は、2019年に開始された在留資格制度で、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材の就労を認めるものです。食料品製造業もその対象に含まれており、制度を活用することで安定的な人材確保が可能となります。この制度は、日本の食文化を支える重要な産業を維持するため、国際的な人材流動を促進するという側面も持っています。企業にとっては、グローバルな視点で人材戦略を考える良い機会となるでしょう。
在留資格「特定技能1号」と「2号」の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。1号は原則として在留期間が最長5年で、比較的簡単な業務への従事を想定しています。一方、2号は熟練した技能が必要な分野で、家族帯同が可能な上、在留期間の更新に制限がありません。2024年以降、飲食料品製造業でも2号の受け入れが可能となりました。
飲食料品製造業が対象となる理由と範囲
農林水産省が所管する飲食料品製造業は、深刻な人材不足が続いている分野の一つです。特に、弁当・惣菜の製造、冷凍食品、菓子類、飲料、茶(緑茶等)の加工・包装などの工程が対象業務となっており(酒類を除く)、品質や衛生管理に係る一定の判断を伴う業務も含まれます。単なる単純作業だけでなく、日本の「食の安全」を支える責任ある役割を担うことが期待されています。具体的には、マニュアルや工程図を正確に理解し、機械の基本操作や日常点検を行う能力も求められます。
参考:農林水産省 飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について
制度の背景と導入目的
特定技能制度は、日本国内での人材確保が困難な状況に対応するために導入されました。従来の技能実習制度(技能実習2号を良好に修了した者は特定技能試験が免除される特例あり)とは異なり、労働力確保を主目的としており、即戦力としての外国人材受け入れを可能にしています。これにより、業界の生産性維持と事業継続が図られており、制度開始以降、多くの企業で導入が進んでいます。企業側は、受け入れ人材の即戦力化と定着を両立させるためのマネジメントが求められます。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
外国人材の採用に必要な手続きと条件

特定技能外国人を雇用するには、制度上の要件や必要書類を正しく理解し、適切な準備を行うことが不可欠です。法令に則った採用手続きと、受け入れ体制の整備が求められます。手続きは複雑なため、出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を直接確認したり、行政書士などの専門家に相談したりすることが推奨されます。特に初めて受け入れる企業は、事前の情報収集を十分に行うことが成功の鍵となります。
企業に求められる基準と責任
受け入れ事業者は、労働条件や職場環境の整備はもちろん、外国人が安心して働けるよう生活面の支援も求められます。また、社会保険への加入義務、定期的な報告義務や法令遵守も重要で、該当する義務を怠った場合には受け入れ許可が取り消されることもあります。労働環境全般にわたる包括的な配慮と責任ある対応が不可欠です。特に、報酬については、同等の業務に従事する日本人従業員と同等額以上であることが法律で定められており、不当な差別的取扱いは固く禁じられています。
必要な申請手続きと書類一覧
外国人を採用するには、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請が必要です。提出書類には、以下のようなものが含まれます。
- 雇用契約書
- 業務内容説明書
- 受入れ体制の概要
- 支援計画書
上記の書類作成は正確性が求められ、不備があると審査に時間がかかります。申請受付から許可が下りるまでには数ヶ月を要することもあり、スムーズな手続きを望むなら、出入国在留管理庁の公式サイトから申請様式をダウンロードし、事前に専門家に相談するのも有効な選択肢です。
出入国在留管理庁との関係と対応
採用後も、定期的な報告書の提出や在留状況の管理が義務付けられています。さらに、受け入れ企業は「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です。この協議会の構成員として、在留許可が下りてから在留期間が満了するまでの間、制度の適正な運用に協力することが求められます。協議会は単なる義務ではなく、業界の課題や優良事例を共有する貴重な情報交換の場であり、その公式サイトで公開される情報や研修会に積極的に参加し、自社の体制を改善していくことが不可欠です。
参考:農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
そのほかの事例とフィリピンから飲食料品製造業の人材を受け入れる場合のMWO申請
試験・研修・日本語能力の確認方法
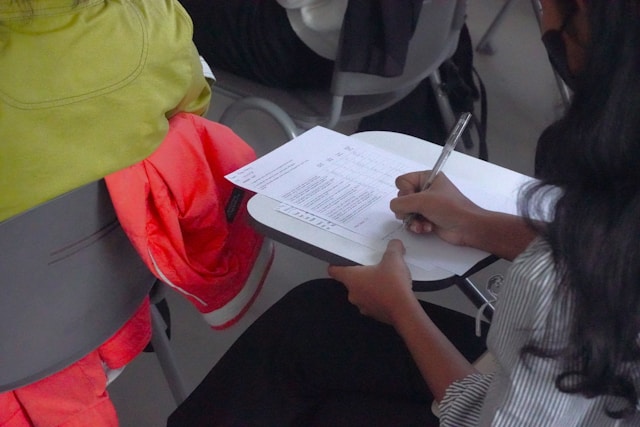
特定技能制度では、外国人が対象分野で働くために、一定の技能水準と日本語能力を有していることが求められます。これらは所定の試験で測定され、企業はその結果をもとに採用可否を判断します。試験は国内だけでなく国外でも実施されており、企業はどちらで合格した人材を採用するか戦略を立てる必要があります。国外試験合格者を新規に呼び寄せるか、国内在住の留学生などを採用するか、それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
飲食料品製造業向け特定技能評価試験とは
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(略称:otaff)が評価試験を実施しています。試験内容は、食品衛生、安全管理など実務に関する知識を問うもので、公式サイトでは学習用の動画や図解資料も公開されています。試験は、知識を問う学科試験と作業手順を確認する実技試験で構成され、多くは大学のテストセンターなど、指定された会場のコンピューターで解答するCBT方式が採用されており、受験者は画面の指示に従って解答を進めます。
試験合格のためには、HACCPなどの専門知識や、現場での安全衛生に関する日本語の理解が求められます。飲食料品製造業に特化したオンライン試験対策コース「特定技能飲食料品製造業合格コース」を活用し、採用候補者の学習を支援することが合格への近道です。
参考:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号・2号技能測定試験
日本語能力試験と学習支援の重要性
特定技能1号の取得には、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金が実施する日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。どの程度の日本語能力が必要かというと、日常会話や業務連絡が可能な水準です。企業としても、公式テキスト等を活用した学習支援に加え、業務で使う専門用語リストを作成することが望まれます。公式サイトから学習用のテキストがダウンロードできる場合もありますので、積極的に活用を促し、入社後のスムーズなコミュニケーションを後押ししましょう。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
外国人スタッフのJLPT N4合格をオンラインで支援。10週間の短期集中、11ヵ国語対応。充実の動画と模擬試験で93%の…
試験実施スケジュールと申し込み手順
試験の実施予定は、公式サイトで定期的に公表されます。申し込みの際には、各国語対応のWebサイトから手続きを行います。試験の受付期間は短く、先着順の場合が多いため、新着情報をこまめにチェックすることが重要です。試験の詳細な内容や応募資格については、必ず公式サイトの募集要項を確認しましょう。事前にマイページ(アカウント)を作成しておく必要があり、受付開始と同時にスムーズに申請できるよう準備しておくことが肝心です。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
特定技能人材の支援体制と定着支援

外国人材の雇用には、働きやすさだけでなく「暮らしやすさ」を整えることが重要です。そのためには、法定支援と独自支援の両方をバランスよく設計し、定着率を高める工夫が必要です。画一的な支援ではなく、外国人材一人ひとりの希望や文化的背景に応じて柔軟に対応することが、信頼関係の構築と長期的な定着につながります。支援は、彼らが日本社会の一員として自立していくためのサポートであるという視点が大切です。
支援計画の策定と実施内容
企業は、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、銀行口座の開設や携帯電話の契約といった生活に必要な手続きの案内、生活オリエンテーションなどを含む10項目の「支援計画」を策定し、実施する義務があります。この計画は、受け入れる人材一人ごとに内容を調整し、定期的な面談を行って見直すことが重要です。計画の形骸化を防ぐためには、支援担当者を明確にし、計画の進捗状況や外国人材の満足度を確認し、必要に応じて内容を見直すサイクルを確立することが大切です。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
登録支援機関の役割と選び方
支援の一部またはすべてを外部の「登録支援機関」に委託することも可能です。登録支援機関は、出入国在留管理庁の認定を受けた民間企業や団体で、専門的なサービスを提供します。選ぶ際は、実績だけでなく、電話やメール、オンラインでの相談など、各種コミュニケーション手段への対応力やレスポンスの速さも確認しましょう。支援を委託するなら、事前に複数の機関から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。安さだけで選ぶのは避けるべきです。
生活支援・相談対応の工夫と事例
多言語対応の相談窓口、定期面談、生活ルールの翻訳資料の提供など、支援の質を高める企業が増えています。例えば、日本人社員との交流イベントを定期開催することで、外国人材の孤立防止と所属意識の醸成に成功しています。また、地域の国際交流センターや多文化共生センターと連携し、日本の税金や社会保障制度に関する勉強会を開くといった事例もあり、彼らが職場の外でも安心して生活できるようなサポートが定着率の向上に繋がります。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
導入事例と実際の企業の声

実際に特定技能制度を活用している企業は増加傾向にあり、その成果や課題から多くの学びを得ることができます。ここでは実例を通して、制度導入の効果や現場のリアルな声を紹介します。他社の成功事例で紹介されている工夫や、現場での具体的な取り組みを参考にすることで、自社の状況に合わせた最適な運用方法を模索していきましょう。
現場での活躍と企業の満足度
麺類の製造を行う株式会社ヤマヲでは、200名を超える特定技能外国人が在籍し、うち9名が特定技能2号として管理業務を担っています。人材紹介はリファラルを中心に行い、製造から出荷、教育まで幅広く活躍中です。社内講座や個別指導による試験支援も充実しており、外国人材の長期定着とキャリア形成が進んでいます。特定技能2号の取得者はリーダーや教育係として現場を支え、生産性や品質の向上、職場の活気づくりにも貢献しています。公平な環境づくりにも力を入れており、組織全体の底上げにつながっています。
参考:株式会社JTB 外国人材受入総合支援事業 受入れ事例紹介
導入にあたっての課題と工夫
制度導入初期は、書類作成の煩雑さや社内理解の浸透に苦労する企業も多くあります。しかし、企業のトップが率先して受け入れ方針を明確にし、社内説明会を行って理解を求めるなどの工夫で、スムーズな運用に移行した事例も増えています。言葉の壁に対しては、翻訳アプリや、指示内容を図やピクトグラムで示すなどの工夫が有効です。また、文化的な背景の違いを社内で共有しておくことで、無用な誤解や衝突を避け、円滑な人間関係を構築できます。
受け入れ企業が得た経営的メリット
人材の定着により採用コストの削減が進み、安定した生産体制を確保できたという声も聞かれます。また、多様な価値観が社内に入ることで、現場の改善意識や教育制度の見直しにつながるといった「副次的効果」も確認されています。日本人従業員にとっても、異文化理解が深まり、組織全体の活性化に貢献しています。さらに、受け入れた人材の母国への海外展開を将来予定している企業にとっては、彼らが重要な架け橋となる可能性も秘めています。
まとめ|特定技能で飲食料品製造業の人手不足を解消

飲食料品製造業が抱える人手不足の課題に対し、特定技能制度は有効な解決策のひとつです。本記事で紹介した制度の概要、試験、支援体制、導入事例を通じて、外国人材の受け入れに対する理解が深まったのではないでしょうか。
制度の運用には正しい理解と適切な準備が不可欠ですが、ポイントを押さえれば中小企業でも無理なく導入可能です。今後の人材戦略として、またグローバル化に対応する組織づくりの一環として、特定技能制度をぜひ検討してみてください。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。