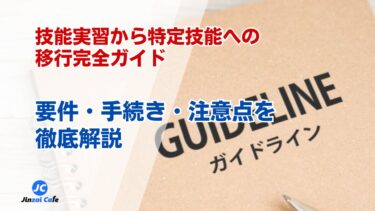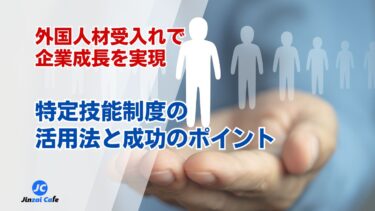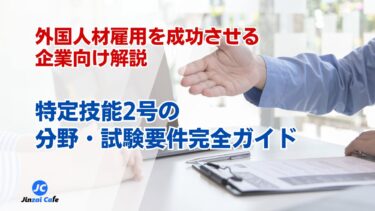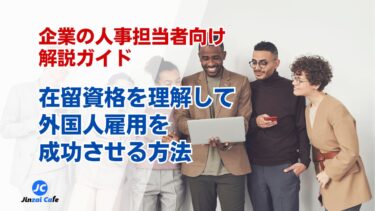日本の農業分野では、深刻な人材不足が続いています。高齢化の進行と若年層の農業離れにより、多くの農業事業者が労働力の確保に頭を悩ませているのが現状です。そんな中、2019年に新設された「特定技能」制度は、外国人材の活用という新たな選択肢を提供しています。
特定技能制度における農業分野は、16の対象分野の中でも特に注目度が高い分野です。しかし、制度の詳細や受入れ要件について正確に把握している企業は意外に少ないのではないでしょうか。外国人材の雇用を検討するにあたって、「どのような手続きが必要なのか」「どんな支援が求められるのか」といった疑問をお持ちの経営者も多いことでしょう。
この記事では、特定技能農業分野での外国人材雇用について、基本的な制度概要から具体的な受入れ手続きまで、企業が知っておくべき情報を網羅的に解説します。読み進めることで、自社での外国人材活用の道筋が明確になり、適切な人材確保戦略を立てられるようになるでしょう。
特定技能農業分野の制度概要と重要性

特定技能制度は、人材不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。農業分野は、この制度の対象となる16分野の一つであり、日本の食料安全保障の観点からも極めて重要な位置づけとなっています。
農林水産省によると、農業従事者の数は年々減少傾向にあり、2024年時点で約111万人となっています。この数字は10年前と比較して約60万人の減少を示しており、労働力不足の深刻さを物語っています。特に、収穫期などの繁忙期には、必要な労働力を確保できない農業事業者が全国で続出しているのが実情です。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度 農業分野
農林水産省 在留資格「特定技能」について (農業分野)
農林水産省 農業労働力に関する統計
育成就労制度の創設と特定技能2号の拡大
特定技能制度を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えています。注目すべきは、2024年の法改正による「育成就労制度」の創設です。これは、従来の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と育成を明確な目的として新設される制度です。
この育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて外国人材を育成し、特定技能1号の水準まで引き上げることを目指しています。これにより、将来的には特定技能への移行がよりスムーズになり、企業は計画的に人材を育成・確保しやすくなる見込みです。
さらに、2023年には農業分野でも「特定技能2号」の受入れが可能となりました。これにより、熟練した技能を持つ人材が在留期間の上限なく就労し、家族を帯同することも可能になりました。これらの制度変更は、農業分野における外国人材雇用が、短期的な労働力確保から、長期的なキャリア形成を視野に入れた人材戦略へとシフトしていることを示しています。
農業分野における外国人材受入れの背景
農業分野での外国人材受入れには、単なる労働力不足の解消以上の意味があります。近年の農業は、ICT技術の導入や6次産業化の推進により、事業の多角化が進み、従来の農作業だけでなく、幅広い技能が求められるようになりました。特定技能制度では、こうした現代農業に対応できる技能を持つ外国人材の受入れを可能にしています。
また、グローバル化の進展により、農産物の輸出拡大も重要な課題となっています。外国人材の雇用は、将来的な海外展開の基盤づくりという観点からも注目されています。彼らの母国での農業事情や消費者ニーズを理解することで、輸出戦略の策定にも活かせるでしょう。
参考:農林水産省 農業分野における外国人材の受け入れ、「農業分野における外国人材の受け入れ (令和7年10月)」 PDF
特定技能1号と2号の違い
農業分野では、特定技能1号・2号の両方が運用されています。特定技能1号は通算5年までの在留が可能で、主に一定の知識や経験を必要とする業務に従事します。一方、特定技能2号は、1号を修了した、より高度な技能を有する外国人材を対象とします。在留期間の上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も認められるため、管理者候補としての長期的な人材確保の選択肢が大きく広がっています。
技能実習制度との主な違い
特定技能制度と技能実習制度は、目的や仕組みが大きく異なります。従来の技能実習制度は国際貢献を目的とした技能移転の制度であったのに対し、特定技能制度は日本の労働力不足解消を目的とした就労制度です。
特定技能では、同一業務区分内での転職の自由が認められており、受入れ企業との直接雇用が基本となります。給与についても、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられており、より対等な雇用関係を築けるのが特徴です。
なお、前述の通り、技能実習制度は「育成就労制度」へと移行します。これにより、特定技能制度との連携がさらに強化され、人材育成から長期就労までの一貫したキャリアパスが構築されやすくなります。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
農業分野の対象業務と受入れ要件

農業分野での特定技能外国人材が従事できる業務は、農林水産省告示により詳細に規定されています。単純な農作業だけでなく、現代農業に必要な幅広い業務が対象となっているのが特徴です。
対象業務は大きく「耕種農業」と「畜産農業」の2つに分類されます。各種農作物の栽培に関する業務が含まれ、畜産農業では、養豚、養鶏、酪農に関する業務が対象となります。これらの業務に従事する外国人材は、一定の技能水準と日本語能力を有していることが前提となります。人的リソースの確保という観点からも、これらの業務範囲を正確に把握することが重要です。
参考:法務省・農林水産省 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-
耕種農業の具体的業務内容
耕種農業分野では、栽培管理、収穫・調製、選別・梱包・出荷準備などの業務が対象となります。施設園芸においては、ハウス内での温度・湿度管理、潅水システムの操作、病害虫の防除作業なども含まれます。これらの業務は、単純な肉体労働というよりも、植物の生育状況を判断し、適切な管理を行う技能が求められます。各種作物に対応した専門技能の習得も必要です。
畑作・野菜分野では、土壌管理、播種・定植、除草・間引き、収穫作業などが主な業務となります。近年では、GPSを活用した精密農業や、ドローンを使った農薬散布なども普及しており、これらの新技術に対応できる技能も重要になってきています。
果樹分野では、剪定、摘果、収穫、選果・梱包などの専門的な技術が要求されます。特に剪定作業は、果樹の収量や品質に直結する重要な技術であり、経験と知識を要する業務です。
畜産農業の業務範囲
畜産農業分野では、飼養管理、繁殖管理、衛生管理などが主要な業務となります。養豚では、豚舎の清掃・消毒、給餌・給水、発情・分娩管理、出荷準備などが含まれます。これらの業務には、動物の健康状態を観察し、異常を早期に発見する技能が必要です。農業という産業の特性上、家畜の状態を的確に判断する能力が求められます。
養鶏業務では、鶏舎管理、採卵・集卵、鶏の健康管理などが対象となります。現代の養鶏業では、自動化された設備の操作や、コンピューター管理システムの活用も一般的になっており、こうした技術への対応も求められています。
酪農分野では、搾乳作業、牛舎の清掃・消毒、飼料給与、繁殖管理などが主な業務です。特に搾乳作業は、乳質の確保と牛の健康管理の両面から、高い技術と責任感が要求される業務です。
受入れ企業の基本要件
特定技能外国人材を受け入れる農業事業者は、以下の基準を満たす必要があります。
まず、労働関係法令を遵守していることの確認が前提となり、過去5年以内に労働関係法令違反がないことが求められます。また、適切な雇用管理体制を整備し、外国人材に対する支援計画を策定する必要があります。
財政的基盤についても要件が設定されており、外国人材の適切な処遇を継続的に確保できる経営状況である必要があります。さらに、外国人材が従事する業務について、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
受入れ企業は、外国人材の技能向上や日本語学習の支援、生活相談への対応なども求められます。これらの支援は、企業が直接実施するか、登録支援機関に委託することが可能です。別の選択肢として、地域の農業関連団体と連携した支援体制の構築も検討できます。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
特定技能農業分野の試験と合格基準

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人材が「技能」と「日本語能力」において所定のレベルに達していることを試験で証明する必要があります。特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれで求められる試験や基準が異なります。
また、技能実習制度からの移行など、特定の条件を満たす場合には試験の一部または全部が免除される特例措置も設けられています。ここでは、1号と2号それぞれの試験要件と、特例措置について詳しく解説します。
特定技能1号を取得するための要件
特定技能1号の在留資格を得るには、原則として「①技能測定試験」と「②日本語能力試験」の両方に合格する必要があります。
① 農業技能測定試験(1号)
特定技能1号に必要な技能水準を測る試験です。
| 試験名 | 農業技能測定試験(1号) |
|---|---|
| 実施機関 | 全国農業会議所 |
| 試験区分 | 「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2区分。従事する業務に応じた区分の試験に合格する必要があります。 |
| 試験内容 | 各区分において、栽培管理や飼養管理、安全衛生など、農業現場で即戦力として働くための基本的な知識と技能が問われます。 |
| 試験形式 | 知識を問う「学科試験」と、実際の作業能力を測る「実技試験」で構成されます。 |
| 合格基準 | 各試験区分で60%以上の得点。 |
| 実施場所 | 日本国内および主要な送出国(国外)で年に複数回実施されています。 |
② 日本語能力試験
業務や日常生活に必要な日本語能力を証明するため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | A2レベル以上で合格 |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N4以上で合格 |
N4レベルは「基本的な日本語を理解することができる」水準です。農業現場では、農薬使用や農業機械操作など安全に関わる指示を正確に理解する必要があるため、この日本語能力は極めて重要です。
参考:
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
特定技能農業の技能測定試験合格を目指す外国人材向けコースは、1号、2号の耕種・畜産に対応。8言語解説動画と圧倒的問題量で…
特定技能2号へ移行するための要件
2023年6月の制度改正により、農業分野でも特定技能2号の受入れが開始されました。特定技能2号は、1号を修了した外国人材が対象となり、熟練した技能を持つ人材として、より長期の就労や家族帯同が可能になります。
1号から2号へ移行するためには、「農業技能測定試験(2号)」に合格する必要があります。
農業技能測定試験(2号)
特定技能2号に求められる、より高度な技能水準を測る試験です。
| 試験名 | 農業技能測定試験(2号) |
|---|---|
| 試験内容 | 複数の作業工程を管理する能力や、他の作業者に対して指導・監督ができる管理者レベルの熟練した技能が問われます。 |
| 日本語能力 | 2号への移行に際して、日本語能力試験は免除されます。これは、1号取得の段階で基礎的な日本語能力が証明されているためです。 |
特定技能2号農業合格コース。耕種・畜産分野に対応した動画、ワークシート、演習問題の3ステップで網羅的に学び最短合格を目指…
試験が免除される特例措置
特定の要件を満たす外国人は、上記の技能試験や日本語能力試験が免除されます。最も一般的なケースが、技能実習からの移行です。
技能実習2号を良好に修了した者
日本の技能実習制度で「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、特定技能1号に必要な「技能測定試験」と「日本語能力試験」の両方が免除されます。
- 条件
- 技能実習時の職種・作業内容と、特定技能で従事する業務内容に関連性があることが必須です。農業分野の技能実習(耕種農業・畜産農業)を修了していれば、この条件を満たします。
- メリット
- この特例により、既に日本の農業現場で実務経験と日本語能力を培った人材を、試験を経ずに継続して雇用できます。企業にとっては、即戦力をスムーズに確保できる非常に有効な手段です。
なお、技能実習修了者が特定技能2号を目指す場合も、まずは特定技能1号へ移行し、その後2号の技能試験に合格する必要があります。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
外国人材受入れの手続きと支援体制

特定技能外国人材の受入れには、複雑な手続きと継続的な支援が必要です。出入国在留管理庁への在留資格申請から、日常的な生活支援まで、企業が担うべき責任は多岐にわたります。これらの手続きや支援を適切に行うことで、外国人材の定着率向上と生産性向上を両立できます。
受入れ手続きは、まず外国人材の選考から始まります。海外から直接採用する場合は、現地での面接や書類選考を通じて、自社の業務に適した人材を見つける必要があります。または、ベトナムなどの送り出し機関と連携して人材の紹介を受ける方法もあります。
信頼できる機関を選ぶことが、優秀な人材の確保に繋がります。国内で技能実習を修了した外国人材を雇用する場合は、技能実習実施機関や監理団体からの紹介を受けることが一般的です。
在留資格申請の流れと必要書類
在留資格「特定技能1号」の申請は、外国人材が海外にいる場合と国内にいる場合で手続きが異なります。海外からの呼び寄せの場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書を取得した後、外国人材が現地の日本領事館等で査証申請を行います。
申請に必要な資料は多岐にわたり、特定技能雇用契約書、雇用条件書、企業の概要書、支援計画書などが必要です。また、外国人材の試験合格証明書や日本語能力証明書、健康診断書なども提出する必要があります。これらの書類は、正確性と完全性が求められるため、事前の準備が重要です。
フィリピンから農業人材を受け入れる場合は、日本の在留資格申請とは別に、フィリピン政府へのMWO申請の手続きが必要となるため、十分な準備期間が必要です。
申請から許可までの期間は、通常1か月から3か月程度かかります。この期間中に、外国人材の受入れ準備を進めることが効率的です。住居の確保、業務研修の計画、生活オリエンテーションの準備などを並行して進めることで、スムーズな受け入れが可能になります。
支援計画の策定と実施
特定技能外国人材を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を策定し、実施することが義務付けられています。支援計画には、入国前の事前ガイダンス、入国時の空港等での出迎え、住居確保の支援、生活に必要な契約手続きの案内や支援などが含まれます。
支援の内容は10項目にわたり、それぞれについて具体的な実施方法を定める必要があります。日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進なども支援項目に含まれており、外国人材の職場定着と地域社会への統合を促進することが目的です。
これらの支援は、企業が直接実施することも可能ですが、登録支援機関に委託することも認められています。農業分野では、農業協同組合や農業関係団体が登録支援機関として活動している場合が多く、専門知識を持つ機関による支援を受けることができます。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
登録支援機関の活用方法
登録支援機関は、特定技能外国人材の受入れ企業に代わって、支援業務を実施する機関です。出入国在留管理庁に登録された機関であり、専門的な知識と経験を持つスタッフが支援を行います。農業分野では、全国農業会議所や各地の農業協同組合が登録支援機関として活動しています。
登録支援機関を活用することで、企業は本業に集中しながら、外国人材への適切な支援を確保できます。支援機関は、複数の企業から受入れ支援を受託しているため、ノウハウの蓄積があり、効率性の高い支援を期待できます。
支援機関の選定においては、農業分野での実績や地域での活動実績、料金体系などを総合的に評価することが重要です。また、支援機関との連携体制を構築し、外国人材の状況を共有することで、より効果的な支援が可能になります。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
企業の人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの業界で注目を集めています。特に製造業や介護、IT、飲食といった現場では、即戦力となる外国人労働者の採用が進んでいます。こうした動きは報道でも頻繁に取り上げられるようになり、外国人材が日本[…]
農業分野での外国人材活用の成功事例

農業分野での特定技能外国人材の活用は、全国各地で成功事例が報告されています。これらの事例を分析することで、自社での外国人材活用の参考とできるでしょう。成功の要因は、受入れ前の準備や適切な支援体制、継続的なコミュニケーションにあります。さらに、外国人材の意見を積極的に取り入れて作業効率の向上を図ったり、個々の能力を最大限に活かす体制を整えたりすることが、成功のカギとなっています。
施設園芸での活用事例
北海道長沼町の株式会社三木田では、特定技能外国人5名を含む多国籍22名の外国人材を受け入れ、長ネギやトマトなどの通年栽培と加工業務に従事しています。技能実習から特定技能への移行により安定的な雇用を実現し、日本語学習支援や運転免許取得費用の全額補助など、キャリア形成も積極的に支援しています。
宿舎や食事の提供、休憩時の飲料支給など、生活面のサポートも充実しています。地域住民とも良好な関係を築いており、受け入れ開始から売上は2倍に増加しました。今後も多国籍人材の採用を拡大し、農業分野での持続的な人材活用を目指していく方針です。
参考:一般社団法人全国農業会議所 農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集【令和6年度版】(4ページ〜9ページ)
畜産業での成功パターン
群馬県安中市の有限会社タカハシファームでは、特定技能外国人を14名雇用し、養豚や酪農の現場で重要な戦力として活躍しています。特定技能の導入は人手不足の解消を目的としており、日本語力や即戦力性を評価して採用が進められています。支援機関と連携し、雇用契約や生活支援、昇給制度を整備することで、長期的な就労環境を構築しています。
寮は農場近隣に整備され、Wi-Fiや送迎も完備されています。給与は時給1,000円から1,200円で、能力に応じた手当も支給されており、30万円以上を得る従業員もいます。キャリアアップ支援として、運転免許取得費用の補助やリーダー制度の導入も実施しています。
外国人材の受け入れにより、労働力が大幅に強化され、「外国人材がいなければ経営継続できなかったと考えている」と述べられており、制度の意義を実感している事例です。
参考:一般社団法人全国農業会議所 農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集【令和6年度版】(55ページ〜59ページ)
まとめ 特定技能農業分野での外国人材雇用を成功に導くために

特定技能制度を活用した農業分野での外国人材雇用は、日本の農業が直面する労働力不足の解決策として、大きな可能性を秘めています。しかし、単に人手不足を補う手段として捉えるのではなく、長期的な視点で人材育成と組織運営を考えることが重要です。
成功のポイントは、外国人材を貴重な戦力として位置づけ、適切な支援体制を整備することにあります。技能測定試験や日本語能力試験をクリアした外国人材は、即戦力となる可能性を持っています。企業としては、彼らの能力を最大限に活かせる環境を整備し、継続的な成長を支援することが求められます。
また、外国人材の受入れは、企業の国際化や新たな市場開拓のきっかけにもなります。多様な文化的背景を持つ人材との協働により、従来の発想にとらわれない革新的なアイデアが生まれる可能性があります。農業分野でのイノベーション創出という観点からも、外国人材の活用は有効な戦略といえるでしょう。これにより、次の事業展開への足がかりとすることも可能です。
制度面も大きな転換点を迎えています。特に2024年の法改正による「育成就労制度」の創設と、農業分野での「特定技能2号」の運用開始は、今後の外国人材雇用を考える上で極めて重要です。育成就労制度は特定技能へのスムーズな移行を前提としており、特定技能2号は熟練人材の長期雇用を可能にします。企業としては、これらの大きな制度変更の動向を正確に把握し、育成就労からの受入れや、1号から2号へのステップアップを見据えたキャリアパスを整備するなど、中長期的な人材戦略を立てることが重要です。
外国人材の雇用を成功させるためには、事前の準備と継続的な支援が欠かせません。在留資格の申請手続きから日常的な生活支援まで、多岐にわたる対応が必要になりますが、適切な支援体制を構築することで、企業にとって大きなメリットをもたらします。登録支援機関の活用や地域との連携により、効率的な支援システムを構築することも可能です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。