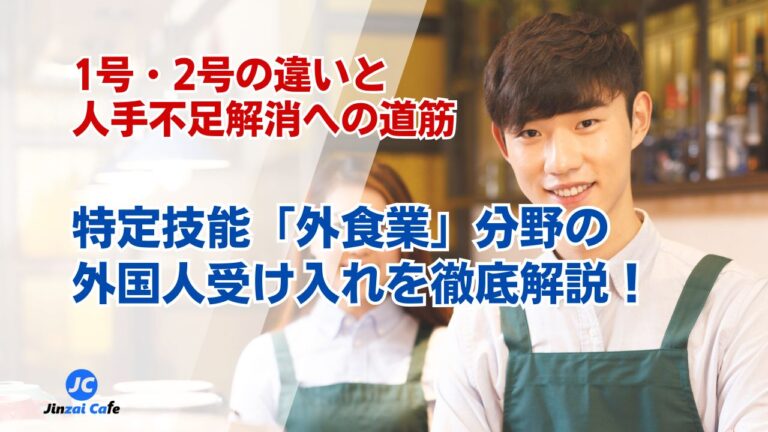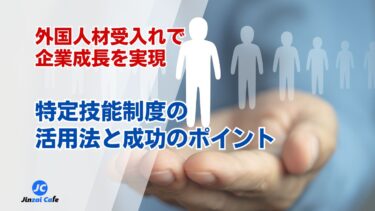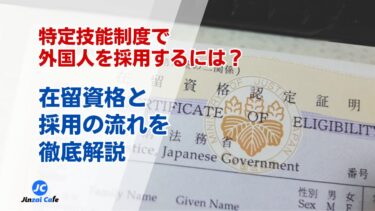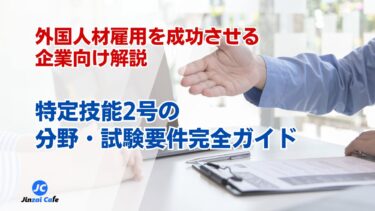飲食店を経営されている方なら、「求人広告を出しても、なかなか人が集まらない」「せっかく採用しても、すぐに辞めてしまう」といった悩みを経験されたことがあるでしょう。飲食業界は今、深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。この状況は、単に店舗運営が忙しくなるというレベルではありません。サービスの質が低下したり、営業時間を短縮せざるを得なくなったりと、経営そのものを揺るがしかねない深刻なリスクなのです。
このような厳しい状況を打開する解決策として注目されているのが、在留資格「特定技能」を活用した外国人材の受け入れです。とはいえ、「特定技能って、なんだか難しそう」「うちのような中小企業でも受け入れられるのだろうか」といった不安や疑問をお持ちの方も多いはずです。
そんな皆さんの疑問にお答えするため、この記事では外食業分野における特定技能制度について、その基本から受け入れに必要な要件、1号と2号の具体的な違い、そして採用に至るまでの手続きまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事をお読みいただければ、貴社の人手不足を解消し、未来の成長へとつなげるための道筋が見えてくるでしょう。
特定技能「外食業」分野の基本情報

特定技能という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な内容を把握している方はまだ少ないかもしれません。この制度は、日本の人手不足を解消するために創設された、比較的新しい在留資格です。特に外食業分野では、その活用が事業の継続・発展の鍵を握ると言っても過言ではありません。ここではまず、特定技能制度の基本的な概念と、外食業でなぜこれほどまでに必要とされているのか、その背景に迫ります。
そもそも在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」とは、外食業のほか、介護や農業など、国内人材の確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された就労目的の在留資格です。2019年4月にスタートしたこの制度は、即戦力となる人材の確保を目的としており、技術や知識の移転を目的とする「技能実習」とは根本的に異なります。
特定技能外国人は、企業と直接雇用契約を結び、日本人従業員と同様に労働基準法などの適用を受けることになります。まさに、人手不足に悩む産業分野にとって、頼れる新たな担い手として期待されている存在なのです。
外食業で特定技能外国人の受け入れが急がれる背景
なぜ、外食業でこれほどまでに特定技能外国人の力が必要とされているのでしょうか。その背景には、日本の社会構造の変化が深く関わっています。少子高齢化による生産年齢人口の減少は、多くの産業に影響を与えていますが、特に労働集約型である外食産業への打撃は深刻です。
これに加え、近年のインバウンド需要の回復などが追い風となり、お客様は戻ってきたものの、サービスを提供するスタッフが足りないというジレンマに陥る企業が後を絶ちません。こうした状況下で、就労意欲の高い外国からの人材は、外食業の活気を取り戻し、サービスを維持・向上させるための不可欠な存在となっているのです。
参考:農林水産省 外食業分野における特定技能外国人制度について
企業が特定技能人材を受け入れるメリット
特定技能人材を企業が受け入れることには、単なる人手不足の解消にとどまらない、いくつものメリットが存在します。最大の利点は、技能試験と日本語能力試験に合格した「即戦力」となる人材を確保できる点でしょう。基礎的な業務知識やコミュニケーション能力を備えているため、ゼロから教育するコストと時間を大幅に削減できます。
また、特定技能外国人は原則としてフルタイムでの就労が可能ですから、安定したシフトの構築にも寄与します。さらに、多様なバックグラウンドを持つ人材が職場に加わることで、新たな視点やアイデアが生まれ、事業全体の活性化につながる「ダイバーシティ推進」という側面も、見逃せない大きなメリットと言えるでしょう。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
特定技能1号「外食業」の受け入れ要件

特定技能の制度を活用しようと考えたとき、まず基本となるのが「特定技能1号」です。この資格を持つ外国人材を受け入れるためには、受け入れる企業側(特定技能所属機関)と、働く外国人材側の双方が、定められた要件をクリアする必要があります。ここでは、具体的にどのような条件が求められるのか、そして、彼らがどのような業務に従事できるのかを詳しく見ていきましょう。
参考:農林水産省 外食業分野における外国人材の受入れについて
受け入れ企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件
外国人材を受け入れる企業は、「特定技能所属機関」として、以下に挙げるような重要な条件を満たさなくてはなりません。まず大前提として、労働基準法や社会保険関連法規といった各種法令を遵守していることが求められます。加えて、外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう支援する体制を整える必要があり、そのための「支援計画」の策定が義務付けられています。
さらに、外食業分野特有のルールとして、農林水産省が組織する「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です。この協議会は、制度の適正な運用を図るための情報共有や連絡調整を行う組織であり、加入しなければ特定技能外国人を雇用することはできません。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度「受入れ機関の方」
農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
対象となる外国人材がクリアすべき条件
一方、特定技能1号の在留資格を得る外国人材側にも、満たすべき条件があります。まず、年齢が18歳以上であることが基本です。そして最も重要なのが、国が定める技能と日本語の試験に合格し、業務に必要な能力を証明することです。これらの試験の具体的な内容やレベルについては、後の章「特定技能の『試験』に関する必須情報」で詳しく解説します。
これにより、企業は採用時点で一定のスキルととコミュニケーション能力を期待できます。なお、日本での「技能実習2号」を良好に修了した外国人材については、これらの試験が免除される場合があり、スムーズな移行が可能となっています。
特定技能1号外国人が従事できる業務の範囲
特定技能1号「外食業」の資格を持つ外国人は、外食業における幅広い業務に従事することが可能です。具体的には、「飲食物の調理」「接客」、そして仕入れや売上管理といった「店舗管理」の3つが主な業務内容として定められています。
これは、厨房での調理作業から、ホールでのオーダー対応や配膳、さらには店舗運営に関わる業務まで、レストランや飲食店における一連の作業全般をカバーすることを意味します。ただし、デリバリー業務や、接待を伴う業務は対象外です。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で規定される「接待飲食等営業」を営む店舗では、受け入れが認められていない点に注意が必要です。
参考:農林水産省 外食業分野における特定技能外国人制度について
近年、日本では多くの産業分野で慢性的な人手不足が深刻な状況となっており、とりわけ介護・建設・農業・外食産業・製造業などの現場では、必要な人材を確保できないことが経営上のリスクとなっています。少子高齢化による労働人口の減少が背景にあることは言[…]
特定技能の「試験」に関する必須情報

特定技能外国人を受け入れる上で、企業が最も関心を寄せるのが「彼らは一体どれくらいのスキルを持っているのか?」という点でしょう。その能力を客観的に証明するのが、国が定める「技能測定試験」と「日本語能力試験」です。これらの試験に合格していることが、特定技能1号の在留資格を得るための大前提となります。ここでは、外食業分野における試験の具体的な内容やレベル、そして学習に役立つ情報について解説します。
外食業技能測定試験の概要と試験内容
外食業分野の技能レベルを測る試験は、正式名称を「外食業技能測定試験」と言い、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。この試験は、外食業で働く上で必要不可欠な知識を問うもので、大きく分けて「衛生管理」「飲食料品の調理」「接客全般」の3つの科目から構成されています。
例えば、衛生管理では食中毒予防やHACCPの考え方、調理では食材知識や調理方法、接客では基本的なサービスマナーやクレーム対応など、非常に実践的な内容の問題が出題されます。この試験に合格しているということは、即戦力として現場で活躍できるだけの基礎知識を有している証左と言えるでしょう。
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 衛生管理 | 一般衛生、HACCP、食中毒予防など |
| 飲食物調理 | 食材、調理、機器の知識 |
| 接客全般 | サービスマナー、多様化対応、クレーム処理など |
参考:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1・2号技能測定試験
日本語能力を測る2種類の試験(JLPT/JFT-Basic)
業務を円滑に進めるためには、日本語でのコミュニケーション能力が欠かせません。特定技能では、その能力を証明するために、以下のいずれかの試験に合格することが求められます。一つは、国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」、もう一つは同じく国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上です。
JFT-Basicはコンピューターを使って受験する形式で、JLPTのN4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルに相当します。どちらかの試験に合格していれば、職場で最低限の指示を理解し、簡単な報告ができる日本語力があると判断できます。試験日程や申し込み方法は、各公式サイトで早めに確認しましょう。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
試験対策用の学習テキストや参考資料
「外国人材はどのように試験対策を行うのか」と気になる方も多いかもしれません。特定技能「外食業」分野の技能測定試験に関する公式学習テキストは、一般社団法人日本フードサービス協会(JFNET)のホームページで無料公開されています。このテキストは、日本語だけでなく、英語やベトナム語など複数言語で提供されており、サイト上の一覧から誰でも必要な資料をダウンロードして学習に活用できます。
企業側も、採用予定の外国人材がどのような知識やスキルを身につけているかを把握するため、これらの公式テキストに目を通しておくことが推奨されます。これにより、入社後の教育計画の立案にも役立ちます。また、テキストは定期的に内容が見直され、最新バージョンが協会の公式サイトを通じて配信されているため、常に最新情報を確認することが重要です。
参考:一般社団法人日本フードサービス協会 外食業技能測定試験学習用テキスト
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
【最新情報】外食業でも特定技能2号の受け入れが可能に

特定技能制度に、大きな転換点が訪れました。2023年6月の閣議決定により、これまで一部の分野に限られていた「特定技能2号」の対象分野が拡大され、ついに「外食業」もその仲間入りを果たしたのです。これは、外食業界で働く外国人材にとって、そして彼らを受け入れる企業にとって、極めて重要な意味を持ちます。熟練した人材に、より長く日本で活躍してもらう道が開かれたことで、企業の採用戦略や人材育成計画は新たなステージへと進むことになります。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
特定技能2号とは?1号との決定的な違い
特定技能2号は、1号の上位資格にあたり、その違いは非常に大きいものです。最も決定的な違いは「在留期間」にあります。通算5年という上限が設けられている1号に対し、2号には在留期間の更新に上限がありません。これは、要件を満たし続ける限り、実質的に永続的な日本での就労が可能になることを意味します。
さらに、「家族の帯同」が認められる点も大きな特徴です。配偶者と子供を日本に呼び寄せ、共に生活できるようになります。また、企業に義務付けられていた「支援計画」の策定・実施も、2号人材に対しては不要となります。まさに、より自立した熟練労働者としての位置づけなのです。
参考:出入国在留管理庁 「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
外食業で特定技能2号へ移行するための要件
外食業で働く外国人材が特定技能1号から2号へ移行するためには、当然ながら、より高いレベルの技能が求められます。具体的には、「外食業特定技能2号測定試験」に合格することが必須要件となります。この試験は、単なる調理や接客のスキルだけでなく、複数の従業員を指導・監督しながら作業を行う能力や、店舗の管理業務を遂行できる能力など、いわば現場のリーダーや管理者に求められる高度な技能を測るものです。
加えて、副店長やサブマネージャーなど管理的役割で、複数の従業員を指導・監督しながら店舗管理業務を補助する実務経験が2年以上あることが必須とされています。企業は、将来の管理者候補として1号人材を育成していく視点が重要になるでしょう。
企業が2号人材を受け入れるメリットと準備
企業にとって、特定技能2号の人材を受け入れるメリットは計り知れません。最大の利点は、長年の経験で培われた高度なスキルを持つ人材を、永続的に確保できることです。彼らは現場のリーダーとして他の従業員を指導・育成する役割を担い、組織全体のスキルアップに貢献してくれるでしょう。これにより、人材が定着し、採用や教育にかかるコストを長期的に削減できます。
その一方で、企業側には準備も必要です。2号人材の働きぶりを正当に評価し、その高度なスキルに見合った待遇(役職や給与)を用意することが重要です。彼らがキャリアを築いていける明確なキャリアパスを示すという採用方針が、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための鍵となります。
企業のための特定技能受け入れ手続きと全流れ

特定技能制度の魅力は理解できたけれど、実際に外国人材を受け入れるには、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。一見すると複雑に思えるかもしれませんが、全体の流れをステップごとに把握すれば、計画的に進めることが可能です。ここでは、採用候補者を見つけるところから、実際に入社して業務を開始するまでの具体的な手続きの全貌を、分かりやすく解説していきます。
ステップ1:採用候補者の決定と雇用契約の締結
すべての始まりは、採用したい候補者を見つけることからです。国内に在住する留学生や技能実習修了者を探す方法もあれば、人材紹介会社から紹介を受ける方法もあります。
候補者が決まったら、次に行うのが雇用契約の締結です。この際、最も重要な注意点は「日本人従業員と同等以上の報酬」を支払うことを明確に定めることです。これは不当な低賃金労働を防ぐためのルールであり、契約書に明記する必要があります。
また、業務内容や労働時間、休暇などの条件も、外国人材が十分に理解できる言語で説明し、双方合意の上で契約内容を確認することが不可欠です。
ステップ2:1号特定技能外国人支援計画の策定
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、彼らが日本で安心して働き、生活するための「支援」を行う義務があります。その支援内容を具体的にまとめたものが「1号特定技能外国人支援計画」です。この計画には、日本に入国する前の事前ガイダンス、空港への送迎、住居の確保やライフラインの契約支援、日本語学習の機会提供など、法律で定められた10項目の義務的支援を盛り込む必要があります。当然、支援の過程では個人情報保護に関する法令を遵守しなくてはなりません。
これらの支援をすべて自社で行うのが難しい場合は、国の認定を受けた「登録支援機関」に支援計画の全部または一部を委託することも可能です。多くの企業がこの登録支援機関を活用しています。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
ステップ3:出入国在留管理庁への在留資格申請
雇用契約を結び、支援計画を策定したら、いよいよ行政手続きの段階に入ります。管轄の出入国在留管理庁(入管)に対して、在留資格の申請を行います。海外から新たに人材を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、日本にすでに在留している外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
フィリピンから人材を受け入れる場合には、もう一つの手続き、MWO申請が必要です。
申請書を含む多数の資料を準備する必要があります。審査には通常1〜3ヶ月程度の期間を要するため、入社時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが肝心です。
ステップ4:査証(ビザ)発給と入国・就労開始
無事に入管の審査を通過し、「在留資格認定証明書」が交付されたら、ゴールはもうすぐです。この証明書を海外にいる本人へ送付し、本人が現地の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の発給申請を行います。ビザが発給されれば、日本へ入国し、就労を開始することができます。
空港では支援担当者が出迎え、市区町村での住民登録や銀行口座の開設などをサポートします。入社後は、業務のオリエンテーションと並行して、支援計画に基づいた生活面のサポートを継続的に行っていくことが、外国人材の早期定着と活躍につながる重要なポイントです。
「少子高齢化による人手不足が深刻化し、事業継続が危うい…」「外国人材の雇用を検討しているが、就労ビザの申請は複雑で何から手をつければいいのかわからない」「不法就労のリスクや、雇用後の管理についても不安がある」もしあなたがこの[…]
まとめ|特定技能で外食業の人手不足を解消し、未来へつなぐ

本記事では、深刻な人手不足に悩む外食業の経営者様に向けて、解決策の切り札となりうる「特定技能」制度を、その基本から1号・2号の違い、具体的な手続きに至るまで徹底的に解説してまいりました。即戦力となる人材を確保できる特定技能1号、そして熟練した人材の長期雇用を可能にする特定技能2号は、どちらも貴社の大きな力となるはずです。
制度を正しく理解し、計画的に受け入れを進め、入社後の支援体制を整えること。これが成功への鍵となります。特定技能制度の活用は、もはや単なる人手不足対策ではありません。意欲と能力のある多様な人材を迎え入れ、共に成長していくことは、これからの時代を生き抜くための重要な経営戦略です。この記事が、貴社の新たな一歩を後押しするきっかけとなれば幸いです。
もし外国人材の雇用でお困りなら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。お電話やメールでも結構です。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。