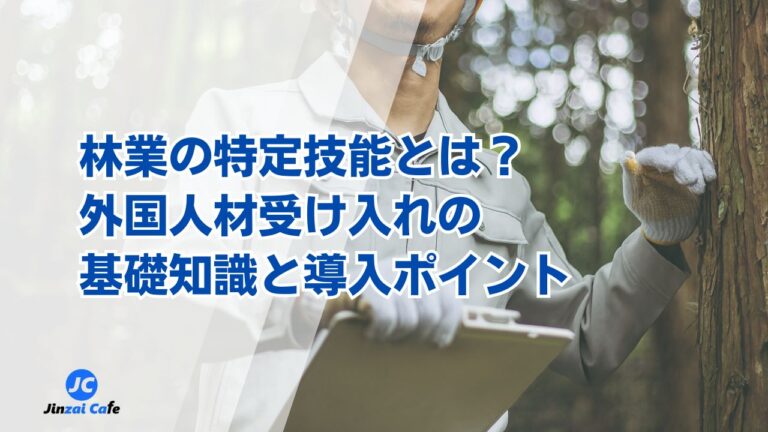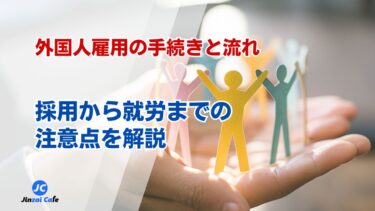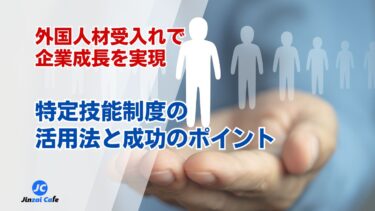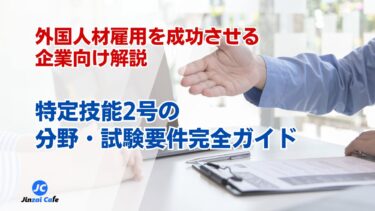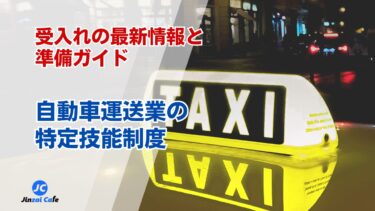日本の林業は今、大きな課題に直面しています。高齢化や担い手不足の影響で、国内の森林資源を十分に活用した木材生産が難しくなり、作業現場の人手は常に足りない状態が続いています。林業は自然を相手にした厳しい労働環境である一方で、日本の山林管理や木材という素材供給の根幹を担う重要な産業です。しかし、その持続性が危ぶまれているのが現状であり、この問題は各種調査でも明らかになっています。
このような背景から、政府は「特定技能」という新たな在留資格を設け、外国人材の受け入れを促進する方法を打ち出しました。中でも林業分野は2019年から制度対象となり、外国人が専門的な技能を持って働けるようになりました。これは、慢性的な人手不足を解決する一手として注目を集めています。
本記事では、林業分野における「特定技能」制度の概要、必要な要件、受け入れの具体的な準備、試験制度、導入時の注意点までを丁寧に解説します。林業に携わる企業の経営者や人事担当者が、「制度は聞いたことがあるけれど、実際にどう進めればいいのか分からない」という疑問を解消し、実践への第一歩を踏み出せる内容になっています。
特定技能「林業」分野の制度概要

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する産業分野において、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする新しい在留資格制度です。2019年に導入され、現在は介護や建設など、いくつかの分野が追加され16の産業分野が対象となっており、林業もそのひとつです。
外国人が日本の現場で一定期間働くには、在留資格(通称:就労ビザ)を取得することが必要です。従来の技能実習制度は「人材育成」を目的としたものであり、就労の自由度が低いという課題がありました。これに対し、特定技能制度は「即戦力の確保」を目的としており、労働力不足を補う現実的な手段として注目されています。
ここでは、特定技能制度の目的や背景、林業分野が対象となった経緯を見ていきましょう。
特定技能制度の目的と背景
特定技能制度が誕生した背景には、日本の労働人口の減少と、それに伴う産業全体の人手不足問題があります。とりわけ現場作業を伴う一次産業や建設業、介護業などでは、人材の確保が急務となっていました。
この制度は、外国人が専門的な技能を活かして即戦力として働けるようにすることで、産業の持続的な発展と、地域経済の活性化を図ることを目的としています。また、受け入れる企業には生活支援や指導体制の整備が求められるため、外国人材が安心して働ける環境を整えることも制度の重要な柱です。
林業が対象分野となった理由
林業分野が特定技能の対象となったのは、農林水産省や林野庁が管轄する日本の森林資源の約6割が人の手を必要とする人工林であり、その管理や伐採といった木材生産を担う人材が大幅に不足しているからです。特に若年層の新規就業者が定着しづらく、現場は高齢化の一途をたどっていました。
また、林業は災害防止や環境保全にも関わる公共性の高い分野であるため、外国人材の導入が社会的にも意味を持つと判断されました。こうした背景から、林業は特定技能「1号」の対象に含まれるようになりました。この資格では、通算で最長5年間の就労が可能です。
参考:林野庁 林業労働力の動向
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
林業分野で求められる技能と業務内容

特定技能「林業」分野での外国人材受け入れは、「即戦力」としての活躍が前提となります。林業特有の作業は、単に体力を要するだけでなく、安全管理、機械の操作、現場判断力など多くのスキルを必要とします。ここでは、外国人が従事可能な業務の種類や求められる専門性について詳しく解説します。
参考:林野庁 林業分野における特定技能外国人材受入れの手引き
従事可能な業務一覧と特徴
特定技能「林業」分野においては、主たる業務として「育林」「素材生産」「林業用種苗の育成(育苗)」「原木生産を含む製炭作業」などが定められています。これらの業務は、林業技能測定試験の合格により確認された技能を必要とし、森林の維持・管理や木材生産に直接関わるものです。
また、これらの主たる業務に従事する日本人が通常行う関連業務として、「林産物の製造・加工」「副産物を利用した製造・加工」「林業用機器や装置等の保守管理」「資材の管理・運搬」「事業所の清掃作業」等も従事可能です。全ての業務において、安全管理を徹底し、現場での指示に従い適切に作業できることが求められます。
求められる専門性と技能の水準
特定技能で求められるのは、実際に作業を遂行できるだけの「技能水準」を有していることです。この技能水準を測定・評価するために試験が実施されます。たとえば、チェーンソーの取り扱いや伐倒技術に関しては、安全に配慮しながら適切な作業が行えるかが評価されます。
また、林業機械の操作においても、単に操作するだけでなく、現場環境に応じた判断や簡易なメンテナンスができることも重要です。こうしたスキルは、評価試験を通じて確認されます。
企業側も、外国人がスムーズに現場で働けるよう、必要に応じて事前研修やOJTの仕組みを整えておくことが望まれます。
即戦力人材としての位置づけ
特定技能1号の目的は「即戦力の確保」であり、林業分野でもこれは変わりません。つまり、外国人材は補助要員ではなく、現場の一員として戦力となることが期待されています。
そのため、作業の一部だけを担うのではなく、主たる業務にしっかりと従事することになります。受け入れる企業には、業務内容を明確にし、外国人労働者の役割を正しく設定する責任があります。
また、制度上は転職も可能であるため、企業にとっても「選ばれる職場づくり」が重要です。待遇面だけでなく、コミュニケーションや教育体制も含めた“働きやすさ”が問われる時代になっています。
外国人材の雇用に興味はあるものの、「どんな手続きが必要なのか分からない」「法令違反が怖い」と感じている企業担当者は少なくありません。特に、これまで外国人を雇った経験がない企業にとっては、在留資格の種類や手続きの流れ、管理体制など、知らなけれ[…]
外国人受け入れの要件と準備事項

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるには、企業側にも一定の条件や準備が求められます。制度は単なる労働力確保の手段ではなく、外国人が安心して働き、生活できるような環境整備が前提となっています。ここでは、受け入れ企業に課される主な要件や、雇用契約、支援体制について詳しく解説します。
受け入れ企業の要件と登録制度
特定技能外国人を雇用するには、企業は「特定技能所属機関」として認められなければなりません。そのためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 関連法令の遵守(労働基準法や入管法等に違反歴がないこと)
- 財務面の安定性(直近の決算で債務超過でない等)
- 適正な雇用体制(常勤職員が在籍している等)
さらに、必要に応じて「登録支援機関」に支援計画の実施を委託し、協力して生活支援や行政手続きのサポートを行う体制も構築する必要があります。林業のような地方・山間部では、生活面の不安が大きくなりがちなため、どのような支援サービスが提供されるか、その質が重要になります。
雇用契約・支援計画に必要な内容
外国人を特定技能で雇用する際には、一般の雇用契約とは異なる配慮が必要です。具体的には以下の点が求められます。
- 同一業務に従事する日本人と同等以上の報酬水準
- フルタイム勤務(週40時間が基本)
- 一定の福利厚生の整備
- 契約内容の母国語での説明・関連する資料の交付
加えて、雇用と並行して「支援計画」の作成が義務づけられています。この計画には、生活ガイダンス、住居確保、行政手続き同行、日本語学習機会の提供など、外国人が日本社会に適応できるような施策を盛り込む必要があります。契約内容に変更が生じる際には、改めて本人に説明し、合意を得なければなりません。
受け入れ体制と指導方針の整備
現場での受け入れ体制もまた、制度運用の鍵を握ります。林業は危険を伴う作業が多いため、安全面の指導や作業ルールの徹底が不可欠です。
そのため、以下のような準備が求められます。
- 母国語による安全教育の実施
- 作業指導員の配置(できれば外国人と意思疎通可能な職員)
- 相談窓口の整備とトラブル時の対応フローの策定
また、地域社会との関係性も重要です。山間部における外国人の生活は孤立しがちなため、地域ぐるみでの受け入れや、自治体との協力体制の構築も効果的です。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
特定技能「林業」分野の試験制度と合格基準

特定技能1号として外国人が林業分野で働くには、一定の知識・技能を有していることを証明する必要があります。これを評価するために設けられているのが「林業技能評価試験」と「日本語能力試験」です。ここでは、各試験の概要、実施機関、合格基準、そして申請までの流れについて整理します。
林業技能評価試験の概要と実施機関
林業技能評価試験は、外国人が日本で林業の仕事に従事する能力を測定・評価するための試験です。林野庁の協力のもとで策定されており、主に以下の能力を評価します。
- チェーンソーなど林業機械の基礎的操作
- 安全衛生管理に係る知識
- 現場作業に関する基礎知識(伐採・造林・集材など)
この試験は、林業技能実習評価試験協議会(FLC)が実施しており、日本国内に加え、フィリピンやインドネシアなどの海外会場でも実施されています。基本的に筆記と実技を組み合わせた形式で行われ、一定の点数をクリアすることで合格となります。
参考:
林野庁 林業特定技能協議会
一般社団法人林業技能向上センター 林業技能測定試験(林業分野特定技能1号評価試験)とは
日本語能力要件と対応試験
特定技能制度においては、業務に支障がない程度の日本語能力も求められます。原則として、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格が条件となります。
| JLPT N4 | 日常会話がある程度理解できるレベル |
|---|---|
| JFT-Basic | CEFR A2相当の日本語力を測るテスト。海外での受験も可能 |
ただし、技能実習2号を修了している外国人については、日本語試験が免除されることもあります。採用時には、実際の業務で求められる日本語力とのバランスを考慮し、支援体制を整えることも大切です。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
試験スケジュールと申請方法
試験の開催頻度は、国や地域によって異なります。日本国内では年数回程度、海外では不定期に実施されることが多いため、詳細は公式サイト(FLCまたは出入国在留管理庁)での確認が必須です。
試験の申込は、基本的にオンラインで行われます。申請に係る書類は、公式サイトからダウンロードできる場合もあります。合格後は、在留資格を取得するための重要な資料として、合格証の原本またはデジタル証明が必要になります。受け入れ企業側も、採用予定者の受験スケジュールを把握し、早めに準備を始めることが成功のカギとなります。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
林業分野の人材受け入れの注意点と成功事例

特定技能制度を活用することで、林業の人手不足解消に一定の効果が期待されますが、実際の運用にあたっては注意すべきポイントも多く存在します。外国人材を受け入れた企業が安心して制度を活用するためには、事前にリスクや課題を把握し、適切に対応する姿勢が求められます。また、すでに導入して成果を上げている企業の事例も参考にするとよいでしょう。
運用時の注意点とトラブル防止策
外国人材を受け入れるにあたり、トラブルにつながりやすいのは以下のようなケースです。
- 雇用契約と実際の労働条件が異なる
- 支援体制が不十分で生活面の不安が放置されている
- 作業内容や安全指導が曖昧で事故が発生
これらを防ぐためには、雇用契約に係る各種資料の多言語化、支援内容の可視化、事前研修や安全教育の徹底が不可欠です。また、特定技能制度には定期報告や監査もあるため、法令順守の視点を常に持って運用し、制度変更にも注意を払うことが重要です。
外国人とのコミュニケーションの工夫
林業現場では、安全性や効率性の向上の面からも、外国人労働者との円滑なコミュニケーションが重要です。ただし、日本語能力には個人差があるため、すべてを言語でカバーするのは難しい場面もあります。
そのため、以下のような工夫が効果的です。
- 作業マニュアルや注意書きをピクトグラム(絵や図)で示す
- 翻訳アプリや指さし会話表を導入する
- 日々のミーティングで簡単な日本語の反復学習を取り入れる
- 文化や宗教への配慮も含めた職場ルールの共有
また、定期的な面談を通じて不安や不満を吸い上げ、改善につなげる姿勢も信頼関係の構築には欠かせません。
地域連携と特定技能導入の成功事例紹介
福島県南会津地域では、特定技能を活用した外国人労働者の受け入れにより、林業の成長産業化に成功した好事例が見られます。地元のNPO法人や町が連携し、森林資源の地域内循環の構築を目指し、高性能林業機械の導入によって素材生産量・生産性の向上、さらに地元製材所での町産材利用率も大幅にアップしました。
町の公共建築物や住宅に町産材を積極的に活用するだけでなく、広葉樹材供給ステーションを活用した新たな流通やネット販売の実践により、林業の高付加価値化と地域経済への還元が進んでいます。
さらに、支援機関と連携し、地元自治体の日本語教室や地域交流会に外国人労働者が積極的に参加することで、地域とのつながりもスムーズになったという報告もあります。こうした事例は「外国人雇用=ハードルが高い」というイメージを払拭し、制度を前向きに活用する企業や地域に大きな励みとなっています。
参考:林野庁 令和3年度林業成長産業化地域の取組の分析・評価等に係る調査委託事業報告書
まとめ|林業の特定技能は制度理解と準備が成功のカギ

林業分野の人手不足を補う手段として、特定技能制度は非常に有効です。
成功のカギは、制度の概要や受け入れの方法・要件、試験内容といった制度面を事前にしっかり把握し、スムーズな導入の土台を作ることです。その上で、現場で活躍する外国人材との信頼関係を築くには、生活やコミュニケーションといった側面での支援も重要となります。このように、準備を怠らず、実情に合わせた受け入れ体制を整えることこそが、制度活用の成功につながるのです。
外国人材の採用やビザ取得でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談サービスをご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材に関する詳細な情報をご提供しています。