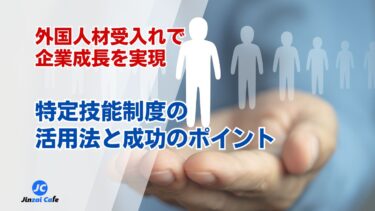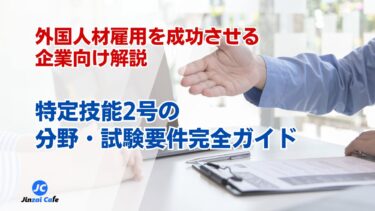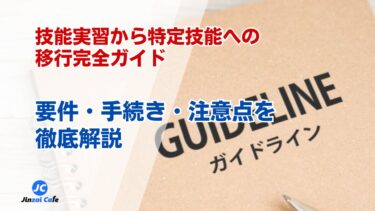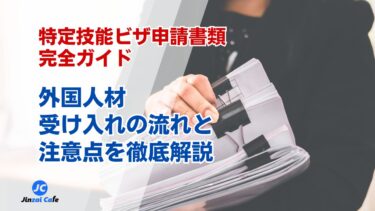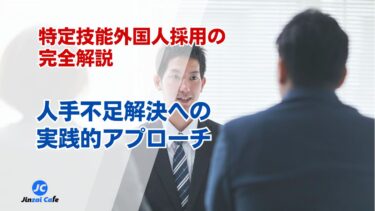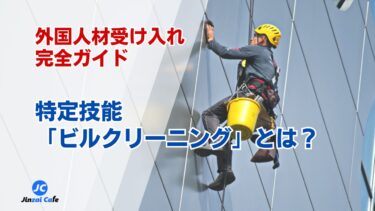日本の製造業は、長年にわたり人手不足という大きな課題に直面してきました。特に工業製品製造の現場では、少子高齢化に伴う労働力の確保が困難になっており、生産ラインの維持すら危ういという声も少なくありません。
こうした背景のなかで注目を集めているのが、外国人材を対象とした「特定技能」制度です。2019年に新たに新設されたこの制度は、即戦力となる外国人を受け入れるための枠組みとして、多くの企業にとって救世主的な存在となりつつあります。
この記事では、その中でも「工業製品製造業分野」に特化して、制度の概要、受入れ可能な職種、必要な手続き、試験内容などをわかりやすく解説します。外国人材の雇用や採用を検討している製造業の経営者や人事担当者にとって、有益な情報を詳細に網羅しています。読み進めることで、自社にとって何から始めれば良いのか、導入の可能性や今後の人材戦略のヒントが見つかるはずです。
特定技能制度における工業製品製造業分野の概要

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を背景に、2019年に導入された新しい在留資格(通称:ビザ)制度です。その目的は、一定の専門性や技能を持つ外国人材を、即戦力として受け入れることにあります。対象となる業種は、介護、農業、宿泊など多岐にわたりますが、そのうちの一つが「工業製品製造業分野」です。
この分野では、主に製造業の中でも機械、電子機器、金属加工など、多様な工業製品の製造に携わる業務が対象となります。中小企業から大手メーカーまで、幅広い業態・事業規模に適用可能であり、現場の労働力を支える選択肢として注目されています。
また、特定技能のうち「1号」は就労可能な在留資格であり、取得には原則として「分野別の技能試験」と「一定水準の日本語試験」への合格が必要です。ただし、修了した場合は試験が免除されるなど、いくつかのルートがあります。
※各試験の具体的な要件や内容については、後の章で詳しく解説します。
以下で、この制度の工業製品製造業分野における定義や、他の制度との違いについて詳しく見ていきましょう。
工業製品製造業分野の定義と対象業務
工業製品製造業分野とは、機械や金属製品、電子機器、電気製品などの製造に関連する業務全般を指します。具体的には、部品の組立て、加工、溶接、塗装、検査、梱包といった一連の作業が含まれます。
この分野の特徴は、業務が多岐にわたる点です。例えば、金属部品の精密加工を行う現場もあれば、電気製品の組立ラインで作業するケースもあります。いずれも一定の技能が求められるため、単純労働とは異なり、外国人にとってもやりがいのある職種として人気があります。
対象業務の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトなどで発表されているガイドラインに基づいて定められています。企業は自社の業務内容が対象に該当するかを事前に確認することが重要です。
他の外国人雇用制度との違い
特定技能制度は、従来の技能実習制度や高度専門職制度とは異なる性質を持ちます。
技能実習制度は「技能の移転」を目的としたもので、基本的に母国への還元を前提としています。対して、特定技能は「即戦力としての労働力確保」が目的であり、労働者としての正当な処遇が求められる制度です。
また、高度人材に比べると日本語力や学歴要件は緩やかで、現場業務に特化した採用が可能です。こうした違いから、製造業の多くの現場では特定技能制度がより現実的な選択肢として受け入れられています。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
受入れ可能な業務区分と業務内容

特定技能制度における工業製品製造業分野では、2025年現在、10の業務区分が受け入れ対象となっています。これらの区分は多彩な製造現場をカバーしており、正確な作業と安全管理が求められるため、一定の技能を持つ外国人材の受け入れが重要です。
各区分では専門的な作業が中心ですが、マニュアルや現場でのOJTが整備されていることから、技能習得の環境も整っています。付随する資材搬送や機械運転などの業務も含まれますが、これらのみを専業とすることは認められていません。
| 業務区分 | 主な業務内容(例) |
|---|---|
| 機械金属加工区分 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、溶接、板金、仕上げ、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、工業包装、プラスチック成形、金属熱処理など |
| 電気電子機器組立て区分 | プリント配線板製造、電子機器組立て、はんだ付け、動作テスト、機器保全など |
| 金属表面処理区分 | めっき、アルミニウム陽極酸化処理 |
| 紙器・段ボール箱製造区分 | 紙器・段ボール箱の裁断、折り、組立て |
| コンクリート製品製造区分 | コンクリート製品の成形、加工 |
| RPF製造区分 | 固形燃料(RPF)の製造 |
| 陶磁器製品製造区分 | 陶磁器製品の成形、乾燥、焼成、検査 |
| 印刷・製本区分 | オフセット印刷、グラビア印刷、製本 |
| 紡織製品製造区分 | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品・カーペット製造 |
| 縫製区分 | 婦人・紳士服、子供服、下着類、寝具、帆布製品、座席シートの縫製 |
参考:
出入国在留管理庁 特定技能1号の各分野の仕事内容(工業製品製造業分野)
出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容(工業製品製造業分野)
特定技能試験の要件と合格への道筋

特定技能制度において外国人材が就労するには、一定の技能水準と日本語能力が必要です。これを客観的に評価するために、各分野ごとに設定された「特定技能評価試験」が実施されています。製造業・工業製品分野においては、試験の合格が原則的な受入れ条件となります。
ただし、技能実習2号を良好に修了したと認定された外国人であれば、試験免除で特定技能1号への移行が認められるケースもあります。ここでは、評価試験や日本語能力の要件、技能実習からの移行条件について詳しく解説します。
製造分野特定技能1号評価試験の内容
製造分野で求められるのは、「産業機械製造業」「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」「金属製品製造業」「プラスチック成形業」などの職種に対応した技能です。
この分野の評価試験は、一般財団法人国際人材協力機構(JITCO)などが関連する各業界団体によって実施されています。試験は筆記(CBT形式)および実技で構成されており、主に以下の能力が問われます。
- 加工・組立て・検査などの作業に関する基礎知識
- 安全管理や作業手順に関する理解
- 基本的な工具・機械の使用方法
試験は海外・国内の両方で実施されており、合格者は特定技能1号の在留資格を取得できる第一歩を踏み出せます。
参考:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト 製造分野特定技能評価試験
日本語能力試験の要件
外国人が日本で特定技能1号の在留資格を得るには、日本語能力も重要な要素です。一般的には「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格が求められます。
N4レベルは「日常生活に必要な基礎的な日本語を理解できる」水準であり、読み書きや会話の基礎がある程度身に付いていることが前提です。JFT-Basicも、簡単な指示や案内を理解し、職場内のやりとりが可能かどうかを判断するためのテストです。
なお、技能実習2号からの移行者には、日本語試験が免除される場合があります。企業側としても、受け入れる人材の日本語能力を事前に把握し、配属後のサポート体制を整えておくことが求められます。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
技能実習からの移行条件
特定技能制度の設計上、技能実習制度と連携したスムーズな人材移行が意図されています。技能実習2号を「良好に修了した」と認定された外国人は、特定技能1号の試験を免除され、直接移行することが可能です。
「良好な修了」とは、計画通りに実習を終え、技能評価試験や出席率、勤務態度、違法行為の有無などが基準を満たしていることを意味します。企業側としては、過去に実習生を受け入れていた経験がある場合、特定技能へのスムーズな切り替えを視野に入れるとよいでしょう。
移行制度を活用することで、教育コストや採用手続きの一部を省略でき、即戦力の確保が現実的になります。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
人材受入れの手続きと必要書類

特定技能制度で外国人材を受け入れるには、企業側が一定の手続きを正しく踏む必要があります。制度に則った受入れを行うためには、事前の準備、関係機関への届出、在留資格の申請など、複数のステップを順序立てて実行しなければなりません。
また、行政機関への書類提出や登録支援機関との連携も必要であり、実務を担当する人事・総務部門にとっては正確な知識とスケジュール管理が不可欠です。不明点があれば、専門の行政書士事務所などに連絡・相談することも有効です。ここでは、代表的な3つの手続きと、それぞれに必要な書類について解説します。
協議会への加入と届出手続き
特定技能制度を利用する企業は、分野ごとに設置されている「分野別運用方針」に基づいて、該当する業界の協議会へ加入する必要があります。工業製品製造業に該当する場合は、「製造業分野特定技能協議会」などが該当します。
協議会への加入により、受入れ企業としての情報が政府に登録され、適切な監督・支援を受けることが可能になります。併せて、法令改正など重要事項に関する連絡も受けられるようになります。
- 協議会加入申込書
- 支援計画書(登録支援機関と連携する場合)
- 受入れ企業情報の登録様式 など
参考:経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)
在留資格申請の流れ
外国人を日本に呼び寄せる、あるいは国内在住の外国人を雇用する場合、出入国在留管理庁での「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」が必要です。いずれの場合も、企業が主たる申請人(受入れ機関)として手続きを行います。
おおまかな流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理庁への申請書提出
- 審査・交付(通常1か月から2か月程度)
- 外国人材の入国、または在留資格の変更手続き完了
参考:
出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請
人手不足解消の切り札「特定技能」制度について解説。金属表面処理、陶磁器製品製造などの業務区分に分かれている、工業製品製造…
受入れ機関が準備すべき書類
企業が特定技能外国人を受け入れるに際し、準備すべき書類の一覧は多岐にわたります。誤りや漏れがあると申請が受理されなかったり、手続きに大幅な遅延が生じることもあるため、事前準備が非常に重要です。
- 雇用契約書(条件明示書を含む)
- 支援計画書(自社実施 or 登録支援機関の支援内容)
- 給与支払証明・住居確保計画
- 労働条件通知書・36協定届(残業がある場合)
これらに加え、受け入れにあたっての説明資料や研修マニュアルの提出が求められることもあります。実務負担を軽減するために、経験豊富な行政書士法人や支援機関といった外部サービスとの連携を活用する企業も少なくありません。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
工業製品製造業における支援体制と注意点

特定技能人材の受入れは、採用して終わりではありません。実際に就労を始めてからの支援体制や就労環境の整備が、定着率や生産性の向上に直結します。特に文化や言語、生活習慣の異なる外国人材が所属する企業にとっては、きめ細かなサポートが不可欠です。
企業には、職場での指導・育成はもちろんのこと、生活支援、相談対応、母語での案内といった支援義務が課されることもあります。ここでは、受入れ後に重要となる3つのポイントを解説します。
登録支援機関の活用方法
企業が特定技能人材を受け入れる際、自社で十分な支援体制を整えることが難しい場合には、「登録支援機関」と連携することができます。これは、出入国在留管理庁に登録された専門機関で、外国人への生活支援・行政手続き支援などを代行・補助してくれる存在です。
- 住居の確保・生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談窓口の設置(母語対応)
- 定期的な職場訪問・定着状況の報告
中小企業などでは、これらの支援をすべて自社で担うのは現実的に難しいため、外部機関をうまく活用することが制度運用のカギになります。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
労働条件と待遇面での配慮事項
特定技能人材は、労働者としての権利が国内の労働法令によって守られています。日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられており、待遇格差があってはなりません。
また、過度な残業や休日出勤、差別的な取り扱いなどは大きなトラブルにつながるため、以下のような配慮が必要です。
- 日本人従業員との均等待遇(昇給・福利厚生等)
- 安全衛生教育・作業マニュアルの整備
- 外国人向けの就業規則の翻訳
実務上では、労働基準監督署の調査や協議会のモニタリングなどもあるため、法令遵守と情報共有の徹底が求められます。
長期雇用に向けた育成計画
特定技能1号の在留期間は最長5年と定められており、期間満了前には在留期間の更新手続きが必要です。一定の条件を満たせば、特定技能2号へ移行し、長期就労や家族帯同が可能となるケースもあります。
このような制度的制約の中でも、企業が長く戦力として活用するには、次のような育成が有効です。
- 定期的なスキル評価とキャリアパスの提示
- 日本語力向上支援や資格取得支援
- チーム内でのローテーションやリーダー候補育成
育成によってモチベーションと定着率が向上し、結果的に人材不足の慢性化を防ぐことができます。将来的に制度が拡充された際の対応準備としても、有意義な事業投資といえるでしょう。
深刻な人手不足に直面している企業経営者の皆様、外国人材の活用を検討されていませんか?日本の労働力不足は年々深刻化しており、特に製造業、建設業、介護分野では即戦力となる人材の確保が喫緊の課題となっています。2019年に創設された特定技[…]
まとめ|特定技能制度を活用した製造業の人材確保戦略

製造業を取り巻く人手不足の問題は、今後ますます深刻さを増していくと予想されています。その中で「特定技能制度」は、即戦力となる外国人材を受け入れるための現実的かつ有効な手段として、多くの企業に注目されています。
本記事では、工業製品製造業分野における特定技能制度の概要から、対象職種、試験内容、手続き、受入れ後の支援体制までを一通り解説しました。これにより、制度の全体像と実務上のポイントをつかみ、自社での導入可否を判断する手がかりが得られたのではないでしょうか。
特定技能制度は単なる労働力補充にとどまらず、現場に新しい視点や活力をもたらす可能性も秘めています。人材の多様性は、企業の競争力を支える重要な資源です。今こそ制度を正しく理解し、自社の人材戦略に組み込んでいくことが求められます。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材を紹介しています。