日本の介護業界は今、かつてない人材不足の危機に直面しています。高齢化の進行とともに介護サービスの需要は急激に増加している一方で、介護職員の確保は年々困難になっているのが現状です。
この深刻な課題を解決する有効な手段として注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れです。2019年に創設された特定技能制度は、介護分野においても多くの企業で導入が進み、現場の人手不足解消に大きく貢献しています。
本記事では、介護分野での特定技能外国人材受け入れを検討している企業の経営者に向けて、制度の概要から具体的な採用手続き、支援体制の構築方法まで、実践的な情報を網羅的に解説します。読み終えた後には、自社での外国人材受け入れに向けた具体的なアクションプランが描けるでしょう。
介護分野の人手不足の現状

介護業界が直面している人材不足の現状を、具体的な数値データとともに詳しく見ていきましょう。厚生労働省の発表資料や業界団体の調査結果から、その深刻さが浮き彫りになります。この現状を正確に把握することで、特定技能外国人材受け入れの必要性とメリットがより明確になるでしょう。
介護職員の需要と供給のギャップ
厚生労働省が2024年7月に公表した最新の推計によると、2026年度には約240万人の介護職員が必要とされる一方、2022年度時点の介護職員数は約215万人にとどまっており、約25万人の増員が必要とされています。さらに2040年度には、必要な介護職員数は約272万人に達し、2022年度比で約57万人の増加が求められる見通しです。
この数字が示すのは、単なる一時的な人手不足ではなく、構造的で長期的な課題だということです。団塊の世代が75歳以上となる2025年問題を目前に控え、介護サービスの需要は今後も継続的に増加していくでしょう。一方で、少子化による労働人口の減少により、日本人のみでこの需要を満たすことは現実的ではありません。
実際に、介護事業所の約6割以上が人材不足を感じており、特に利用者の自宅への訪問を主とする事業所では8割を超える事業所で人材確保が困難な状況となっています。この状況は、サービス提供時間の制限や新規利用者の受け入れ困難など、直接的に事業運営に影響を与えています。多くの事業所では、在留資格の更新手続きを含む外国人材の活用を真剣に検討せざるを得ない状況にあります。
参考:厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
離職率と人材確保の課題
介護業界の離職率は令和4年度(2022年度)で14.4%となっており、ここ数年は減少傾向にあります。離職理由としては、身体的負担の大きさ、夜勤を含むシフト勤務の不規則さ、他業種と比較して低い賃金水準などが挙げられます。
さらに深刻なのは、新規参入者の確保の困難さです。介護職員初任者研修の受講者数は減少傾向にあり、若い世代の介護職への関心は低下しています。実際に、介護職員の平均年齢は上昇し続けており、将来的な人材供給の見通しは決して明るいものではありません。
こうした状況下で、多くの介護事業所では既存職員の負担増加、サービス品質の低下、事業拡大の困難などの問題が顕在化しています。これらの課題を解決するためには、従来の採用手法だけでなく、新たな人材確保の手段を模索する必要があるでしょう。関係省庁や業界団体との協議も活発化しており、業界全体での取り組みが求められています。
参考:公益財団法人介護労働安定センター 令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について
将来予測と対策の必要性
現在、日本の総人口は1億2,340万人(2025年4月1日現在、概算値)で、前年同月比で約60万人減少しています。65歳以上の高齢者人口は3,624万人で、総人口に占める割合は29.3%と過去最高を記録しています。15歳未満の人口は1,379万人、生産年齢人口(15歳から64歳)は7,374万人で、いずれも減少傾向が続いています。
今後もこの傾向は続き、2065年には65歳以上の高齢者人口は約3,274万人、高齢化率は38.4%に達すると推計されています。また、生産年齢人口は約4,535万人まで減少し、現在の約6割の水準になる見込みです。
つまり、介護サービスの需要は今後さらに増加する一方で、それを支える労働力人口は大幅に減少していくという、極めて厳しい社会状況が想定されています。こうした現実を踏まえると、外国人材の活用はもはや選択肢の一つではなく、介護業界の持続的発展のために不可欠な戦略といえるでしょう。特定技能制度は、こうした長期的な人材需要に対応するための重要な制度として位置づけられており、今後ますます積極的な活用が求められます。出入国在留管理庁のウェブサイトでも、この制度の詳細な情報が提供されており、企業の具体的な検討を後押ししています。
介護分野の特定技能制度とは

特定技能制度は、2019年4月に創設された新しい在留資格制度で、深刻な人手不足に対応するために導入されました。この制度は、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。介護分野も対象の一つであり、介護現場で実際に働ける人材の確保を可能にしています。従来の技能実習制度が「研修的」な色合いを持つのに対し、特定技能は雇用労働の即戦力化を強く意識した制度設計となっています。
特定技能1号の概要と目的
特定技能1号は、生産性向上や国内人材確保のための努力を行ってもなお人材不足が解消できない産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。介護分野では、介護技能評価試験、日本語能力試験(N4以上)、介護日本語評価試験に合格した外国人が対象となります。技能実習2号修了者などは試験が免除される場合もあります。
在留期間は1年、6か月、または4か月ごとの更新で、通算5年が上限です。家族の帯同は原則認められていませんが、介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」に移行し、長期在留や家族帯同も可能となります。2025年4月からは、一定の条件を満たせば訪問介護業務にも従事できるようになりました。
特定技能1号の大きな特徴は、同一の業務区分内であれば転職が可能な点です。適切な手続きを経れば、他の受入れ機関へ移ることができ、外国人材にとって柔軟な働き方が実現されています。
このように、特定技能制度は介護分野における人材確保の新たな柱として、現場の即戦力となる外国人材の受け入れを支えており、その円滑な運用には受入れ機関と支援機関の密な連携が求められます。
参考:厚生労働省 介護分野における特定技能外国人の受入れについて
介護分野が対象となった背景
介護分野が特定技能制度の対象となったのは、慢性的かつ深刻な人手不足が続いていること、そして一定の技能と日本語能力を持つ外国人材が即戦力として活躍できると判断されたためです。
従来、介護分野では経済連携協定(EPA)による外国人介護福祉士候補者の受け入れや、技能実習制度での受け入れが行われてきました。しかし、EPAは対象国が限定されており、技能実習制度は主に人材育成を目的としているため、即戦力となる人材の安定的な確保には限界がありました。こうした背景から、介護現場の人手不足に直接対応できる新たな制度として、特定技能制度が導入されました。
特定技能制度では、介護分野で働く外国人に対し、介護技能評価試験や日本語能力試験(N4以上)、介護日本語評価試験の合格が求められます。これにより、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人材を即戦力として受け入れることが可能となり、現場の人手不足解消に直接的な効果が期待されています。実際、2024年12月末時点で特定技能「介護」の在留外国人数は44,367人と、年々増加傾向にあります。
特定技能外国人材の受け入れ要件

特定技能外国人材を受け入れるためには、企業側・外国人材側の双方が一定の要件を満たす必要があります。出入国在留管理庁が定める基準をクリアすることで、安全で適切な雇用関係を構築できます。ここでは、受け入れに必要な条件を体系的に整理して解説します。
受入れ機関の基準と条件
特定技能外国人を受け入れる機関(企業)は、まず日本人と同等以上の報酬を支払うこと、適切な労働時間の設定、社会保険の加入など、労働関係法令や社会保険関係法令を遵守した雇用契約を締結する必要があります。また、過去5年間に出入国管理法や労働関係法令等に重大な違反がないこと、そして財務状況が健全であることを確認することも重要な条件です。
介護分野特有の要件として、介護保険法に基づく指定を受けた事業所であることが求められます。さらに、受入れ機関は初めて特定技能1号外国人を受け入れた日から4カ月以内に、介護分野における特定技能協議会の構成員になることが義務付けられています。また、外国人支援計画の策定・実施や日本語学習支援体制の整備も必要です。
受け入れ人数については、常勤介護職員数と同数までが上限とされています。加えて、介護分野では派遣形態での受け入れは認められておらず、直接雇用が必須です。訪問介護業務に従事させる場合は、介護職員初任者研修修了と原則1年以上の実務経験など、追加要件が設けられています。
これらの要件を満たすことで、外国人材が安心して働ける環境を提供できるとともに、受入れ機関には定期的な届出義務や適切な管理体制の構築が求められます。
参考:公益社団法人全国老人福祉施設協議会 外国人介護人材受入れ制度早わかりガイド2025
介護福祉士との違いと将来性
特定技能外国人材と介護福祉士では、業務範囲やキャリアパスに違いがあります。介護福祉士は国家資格であり、身体介護を中心とした専門的な業務を行うことができます。一方、特定技能外国人材も身体介護・生活援助等の業務に従事できますが、医療的ケアなど一部の業務には制限があります。
特定技能外国人材は在留中に介護福祉士国家資格の取得を目指すことが可能です。合格すれば「介護」の在留資格に変更でき、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も認められるようになります。なお、2025年7月時点で介護分野は特定技能2号の対象外であり、現時点では移行はできません。
多くの特定技能外国人材が介護福祉士の取得を目指していることから、受入れ機関としても国家試験対策の支援を行うことで、優秀な人材の長期的な定着を図ることができます。これは、投資対効果の観点からも有効な戦略と言えるでしょう。
人材確保の方法と採用手続き

特定技能外国人材の採用には、複数のルートと段階的な手続きが存在します。事前の準備から実際の採用まで、適切なプロセスを踏むことで、優秀な人材を確保できます。ここでは、実際の採用活動で役立つ具体的な手法と注意点を詳しく説明します。
採用ルートと人材確保の選択肢
特定技能外国人材の確保には複数のルートがあります。最も一般的なのは、人材紹介会社や登録支援機関を通じた採用です。これらの機関は、海外での人材募集から面接の調整、ビザ申請のサポートまで一貫したサービスを提供しています。自社の採用計画に合わせて、最適なルートを選択することが重要です。
海外での現地採用も可能ですが、この場合は企業自身が現地での面接や選考を行う必要があります。語学力や現地の法制度への理解が求められるため、初回の受け入れでは専門機関の活用が現実的でしょう。
また、既に日本国内にいる外国人材の採用も検討できます。技能実習を修了した外国人や、留学生で特定技能への在留資格変更を希望する者などが対象となります。これらの人材は既に日本での生活経験があるため、適応が比較的スムーズに進む可能性があります。
在留資格申請の流れと必要書類
特定技能外国人材の在留資格申請には、海外から呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」と、既に日本にいる外国人の「在留資格変更許可申請」があります。
申請には多くの書類が必要となります。主なものとして、雇用契約書、特定技能雇用契約に係る説明書、事前ガイダンスの実施記録、支援計画書などがあります。事前に必要書類の一覧を作成し、準備を進めましょう。また、外国人材の技能証明書類や日本語能力証明書類も必要です。各種申請書の作成には専門知識が必要で、適切な書類準備が成功の鍵となります。
フィリピン国籍の介護人材を採用する場合、日本の在留資格申請とフィリピン政府へのMWO申請が必要です。
申請から結果通知までは通常1か月から3か月程度かかりますが、書類の不備があると更に時間を要する場合があります。そのため、申請前の書類準備には十分な時間を確保し、行政書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
入国から就労開始までの手続き
外国人材の入国後は、速やかに住居の確保、住民登録、銀行口座開設などの生活基盤の整備を行う必要があります。これらの手続きは、受入れ機関が支援することが義務付けられています。
職場での受け入れ準備も重要です。同僚職員への事前説明、業務マニュアルの多言語化、指導担当者の選任などを行い、外国人材がスムーズに職場に適応できる環境を整えましょう。
また、入国後の生活オリエンテーションの実施も法的義務となっています。日本での生活ルール、労働関係法令、相談窓口の案内など、包括的な情報提供を行うことで、外国人材の不安を軽減し、長期的な定着を促進できます。
外国人材への支援体制と義務

特定技能外国人材を受け入れる際には、法律で定められた支援義務があります。これらの支援は、外国人材が日本で安定して働き続けるための重要な基盤となります。適切な支援体制を構築することで、外国人材の定着率向上と企業の持続的発展の両立が可能になります。
義務的支援の具体的内容
特定技能外国人材を受け入れる機関は、法律により10項目の支援を実施することが義務付けられています。これらの支援は、外国人材が日本で安心して働き、生活できる環境を整備するために不可欠なものです。
具体的な支援内容として、まず事前ガイダンスの実施があります。これは雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件や生活環境、支援内容について説明するものです。
入国後の支援では、出入国する際の送迎、住居確保の支援、生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーションの実施などが含まれます。法で定められた義務的支援以外にも、受入れ機関が独自のサポートを行うことで、より良い関係を築くことができます。また、定期的な面談の実施、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応なども継続的に行う必要があります。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
登録支援機関の役割と選び方
受入れ機関は、支援業務の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された機関で、特定技能外国人への支援に関する専門的な知識と経験を有しています。
登録支援機関を選ぶ際は、その機関の実績、対応可能な言語、支援内容の充実度、費用などを総合的に検討することが重要です。また、介護分野での支援経験があるかどうかも重要な選択基準となります。
優良な登録支援機関であれば、法定支援だけでなく、外国人材の長期定着に向けた独自の支援プログラムを提供している場合があります。例えば、介護福祉士国家試験の受験支援や、キャリアアップ研修の実施などです。これらの付加価値も考慮して選択するとよいでしょう。
生活支援と職場環境整備
外国人材の定着には、職場環境の整備が不可欠です。言語面での配慮として、重要な文書の多言語化、通訳サービスの提供、日本語学習支援の実施などが効果的です。
文化的な違いへの理解も重要です。宗教的な配慮、食事の配慮、休暇制度の柔軟性などを検討し、外国人材が働きやすい環境を創出することが求められます。また、日本人職員に対する異文化理解研修の実施も、職場全体の受け入れ体制強化に繋がります。
住居面では、適切な住環境の提供が重要です。プライバシーの確保、生活に必要な設備の整備、交通の便の良さなどを考慮し、外国人材が安心して生活できる住居を提供しましょう。これらの支援は、外国人材の満足度向上と長期定着に直結する投資と言えます。
特定技能に必要な試験と技能水準
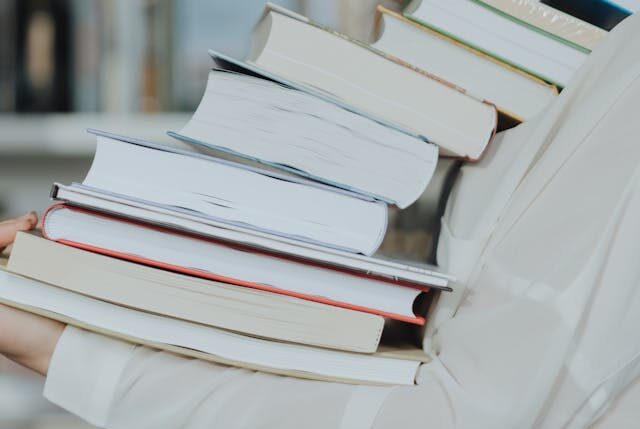
特定技能外国人材には、介護現場で即戦力として活躍できる技能水準と日本語能力が求められます。これらの要件を満たしていることを証明するために、複数の試験が設けられています。ここでは、必要な試験の全体像とそれぞれの内容について詳しく解説します。
介護技能評価試験
介護分野における専門的技能を測定するための試験です。試験は「介護の基本」「こころとからだのしくみ」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」の4分野から出題され、学科試験と実技試験で構成されます。合格基準は、学科・実技ともに総得点の60%以上です。
この試験は、現在インドネシア、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、ネパール、カンボジア、タイ、モンゴルの8か国および日本国内で実施されています。各国での実施頻度は異なりますが、年間を通じて複数回の受験機会が提供されています。国別の合格率には差があり、各国の介護教育制度や文化的背景の違いが影響していると考えられます。
特定技能介護合格コースは、最大10ヵ国語対応のオリジナル解説動画と豊富な過去問で外国人スタッフの特定技能の習得を後押しし…
日本語能力を証明する2つの試験
介護業務を円滑に行うためには、一定の日本語能力が不可欠です。特定技能「介護」では、以下の2つの日本語試験への合格が必要です。
- 基礎的な日本語能力を測る試験
- 「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかに合格する必要があります。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。
- 介護現場に特化した日本語試験
- 上記に加えて、「介護日本語評価試験」への合格も必須です。この試験は、介護現場で実際に使用される語彙や表現、利用者とのコミュニケーション能力など、より実践的な日本語能力を測定します。
これらの日本語要件は、利用者との適切なコミュニケーションを確保し、介護サービスの質と安全性を担保するために設定されています。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
出入国在留管理庁 「介護日本語評価試験」試験実施要領
試験の免除規定について
以下のいずれかの条件を満たす者は、上記の「介護技能評価試験」および「日本語関連の試験」の全部または一部が免除されます。
- 日本の介護福祉士養成施設を修了した者
- 技能実習2号を良好に修了した者
- 経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士候補者としての研修を修了した者
これらのケースに該当する人材は、試験を受けることなく特定技能の申請が可能となるため、よりスムーズな採用が期待できます。
特定技能外国人材受け入れ成功事例

実際に特定技能外国人材を受け入れて成功している企業・団体の事例を紹介します。これらの成功事例から、効果的な受け入れ方法や長期定着のポイントを学ぶことができます。具体的な取り組み内容や成果を通じて、自社での受け入れ戦略の参考にしていただくことができるでしょう。
社会福祉法人伍福会ふるさとにおける外国人介護職員の支援事例
社会福祉法人伍福会(福岡県八女市)は障害者向け生活介護施設「ふるさと」を運営する法人です。将来の人材不足に備え、2022年4月に特定技能でベトナム人介護職員1名を採用しました。本人の「日本で長く働きたい」という希望を受け、長期就労できる環境づくりに取り組んでいます。言葉の壁を考慮し、日本人職員と現場に入るOJTを取り入れ、地域の日本語教室も紹介するなど日本語習得を支援しました。生活面でも常に気を配り、特にコロナ感染時には職員総出で飲食物を届けるなどのサポートを行いました。日本語力が向上した結果、コミュニケーションが円滑になり、現在では後輩を指導できるほどに成長しました。長期勤務を促すため、一定期間勤務した外国人が数週間母国に帰省できる特別休暇(航空券代補助付き)など新たな支援策も検討されており、得た経験を母国で活かしてほしいと期待されています。
参考:公益社団法人 国際厚生事業団 介護分野における特定技能受入れ事例集
社会福祉法人愛心会の取り組みと成果
徳島県にある社会福祉法人愛心会・特別養護老人ホーム千歳苑では、2019年より外国人介護職員の受け入れを開始し、現在では40名以上が在籍しています。法人では、外国人職員の専門性向上を目指し、介護福祉士国家試験の受験支援を積極的に実施しています。2023年度には、ミャンマー出身のティンさんが法人初の外国人合格者として在留資格「介護」へ移行し、活躍を続けています。学習支援や生活面でのフォロー、日本人職員の協力体制が整っており、外国人職員と日本人職員が共に学び合う好循環が生まれています。
参考:公益社団法人 国際厚生事業団 介護分野における特定技能受入れ事例集
成功事例から学ぶ受け入れのコツ
成功事例から見えてくる共通のポイントは、まず経営陣の強いコミットメントです。外国人材の受け入れを単なる人手不足対策ではなく、組織の国際化と発展のための重要な方針として位置づけることが重要です。
次に、継続的な教育・研修体制の構築が挙げられます。日本語教育だけでなく、介護技術、日本の文化や慣習、キャリア開発など、多角的な支援プログラムを提供することで、外国人材の成長と定着を促進できます。
また、受け入れ側の日本人職員への教育も不可欠です。異文化理解研修や外国人とのコミュニケーション研修を実施し、職場全体で外国人材を受け入れる土壌を作ることが成功の鍵となります。さらに、外国人材の声を聞く仕組みを作り、継続的な改善を行うことも重要なポイントです。
まとめ|特定技能外国人材で介護現場の課題解決を

深刻化する介護業界の人手不足に対し、特定技能制度は、即戦力となる外国人材を確保するための極めて有効な解決策です。複雑そうに見える特定技能制度ですが、成功の鍵はいくつかのポイントに集約されます。
- 制度の理解:即戦力確保のための仕組み
特定技能「介護」は、技能・日本語試験に合格した外国人を、身体介護を含む即戦力として最大5年間受け入れられる在留資格です。技能実習制度とは異なり、明確な「雇用」を目的としています。 - 受入れ要件:企業と外国人が満たすべき基準
受け入れる企業は、介護事業所の指定を受けていること、日本人と同等以上の雇用条件を提示すること、そして外国人への支援計画を策定・実施することが必須です。一方、外国人材は「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(N4レベル+介護日本語評価試験)」の両方に合格する必要があります。 - 採用と手続き:専門機関の活用が成功の鍵
採用は、国内外の人材紹介会社や登録支援機関を通じて行うのが一般的です。在留資格の申請は手続きが複雑なため、行政書士などの専門家の支援を得ながら、計画的に進めることが推奨されます。 - 支援体制の構築:定着に不可欠な法的義務
受け入れ企業には、住居確保や公的手続きの支援、日本語学習の機会提供など、法律で定められた10項目の支援義務があります。これらの支援は、専門知識を持つ「登録支援機関」に委託することも可能です。 - 長期的な視点:キャリアパスの提示と組織への好影響
特定技能外国人材が在留中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留期間の制限がない在留資格「介護」へ移行でき、長期的な活躍が期待できます。資格取得支援は、優秀な人材の定着に繋がる重要な投資です。成功事例が示すように、外国人材の受け入れは単なる人手不足の解消に留まらず、組織の活性化や多様な文化理解を促し、職場全体に良い影響をもたらします。
これらの要点を押さえ、計画的に受け入れ準備を進めることが、特定技能制度活用の成功に直結します。将来、外国人材との協働が当たり前になる時代を見据え、早期に受け入れ体制を整備し、ノウハウを蓄積することが、企業の持続的な成長を支えるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。












