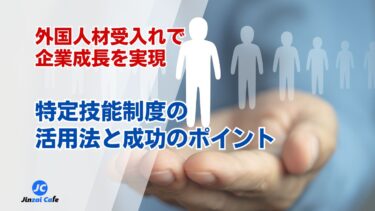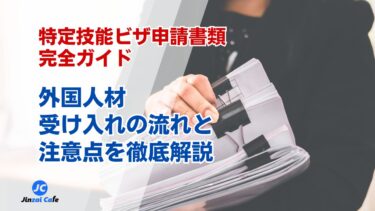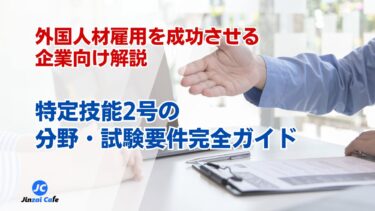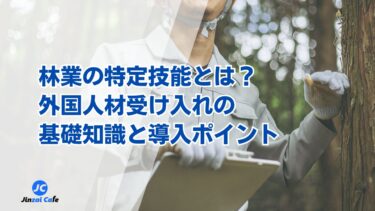日本の造船・舶用工業分野は、世界有数の技術力を誇る一方で、深刻な人手不足に直面しています。特に現場の熟練作業者の高齢化や若手人材の定着難により、製造現場の維持すら困難になっている企業も少なくありません。
こうした背景を受け、政府は2019年から「特定技能制度」を導入しました。外国人労働者を受け入れることで、即戦力となる人材を確保し、現場の生産性を維持・向上させる取り組みが本格化しています。なかでも、造船・舶用工業分野はその対象業種として明確に位置づけられており、多くの企業が制度の活用を検討・開始しています。
本記事では、この「造船・舶用工業分野における特定技能制度」について、制度の概要、対象業務、受入れ要件、試験内容、実務上の注意点まで、経営者や人事担当者の方が実際に活用できるよう、実務目線で詳しく解説していきます。
「何から始めればよいかわからない」という方でも、この記事を読み終える頃には、制度の全体像と具体的な進め方がはっきりと見えてくるはずです。
造船・舶用工業分野における特定技能制度の全体像

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる目的で2019年4月に創設された在留資格です。数ある対象分野の中でも「造船・舶用工業分野」は、製造業のなかでも特に人手不足が深刻な産業として位置づけられており、多くの企業が制度活用による人材確保を進めています。
本制度を活用することで、企業は国内人材だけでは補えない製造・組立・修理といった重要な工程を支える人材を確保できるようになります。ただし、制度の対象業務や条件は細かく定められており、経営者や人事担当者の方は正確な理解と準備が不可欠です。
参考:
出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
出入国在留管理庁 造船・舶用工業分野
制度創設の背景:深刻化する人手不足への対応
特定技能制度が創設された直接的な背景には、日本の急速な労働力不足があります。特に造船・舶用工業では、現場を支える熟練工の高齢化と、若年層の採用難という構造的な課題を長年抱えてきました。その結果、人手が回らず受注に応じきれない企業も増え、事業の継続すら危ぶまれるケースも少なくありません。
このような状況を受け、政府は従来の国際貢献を主目的とした「技能実習制度」とは別に、明確に「労働力の確保」を目的とする本制度を設け、企業側の積極的な活用を促す方針を打ち出しました。
「育成就労制度」への移行と「特定技能」の位置づけ
外国人材の受け入れ制度は、大きな転換期を迎えています。2024年6月、「技能実習制度」に代わる「育成就労制度」の創設が決定されました。
従来の技能実習制度が「技能の移転」を目的としていたのに対し、特定技能は「労働力の補完」を目的とする、より実務的・即戦力重視の制度です。新設される育成就労制度は、この両者の橋渡し役を担います。3年間の就労を通じて外国人を育成し、特定技能1号の水準の人材へと引き上げることを目的としており、外国人材は「育成就労」から「特定技能」へとスムーズに移行し、日本でより長期的なキャリアを築きやすくなります。
長期就労を可能にする「特定技能2号」への対象拡大
企業にとって大きなメリットとなるのが、2023年6月の閣議決定による「特定技能2号」への対象分野拡大です。特定技能1号の在留期間が「通算で上限5年」であるのに対し、熟練した技能を持つと認められる2号は、在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。
これまで以上に外国人材が定着しやすくなるため、企業は腰を据えて人材育成に取り組み、長期的なパートナーとして活躍してもらうことが可能となりました。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
特定技能「造船・舶用工業」で対象となる業務

特定技能「造船・舶用工業」分野で受け入れ可能な業務は、2024年3月29日の閣議決定等により、従来の6区分から以下の3つの業務区分へと再編・統合されました。これに伴い、対象となる作業範囲が整理・拡大されています。各区分には、船体建造をはじめとしたさまざまな実作業が含まれており、即戦力となる外国人材の受け入れが制度上明確に位置付けられています。
参考:国土交通省 造船・舶用工業分野における業務区分再編について(R6.3.29閣議決定)
区分1:造船
この区分では、主に船体の建造や修理に必要な溶接、鉄工、塗装などの工程が対象となります。船の骨格や外板の加工・組立てから各種仕上げ塗装まで、船舶製造における中核的な作業全般を担います。
- アーク溶接・ガス溶接等による船体部材の接合や組立て
- 厚板や鋼板の切断、穴あけ、曲げ加工などの部品製作
- 船体外板・構造物への防食塗装、防汚塗装・仕上げ塗装(ハケ・ローラー・スプレー等の各方法を含む)
区分2:舶用機械
この区分では、船舶に搭載されるエンジンや各種機械部品の製造・組立および精密加工といった業務を中心に、部品の仕上げや取り付けなど機械関連の様々な作業が含まれます。
- エンジン部品やプロペラ軸などの精密金属部品の機械加工
- 工作機械を用いた旋盤・フライス盤加工
- 部品の仕上げ、バリ取り、防振材・断熱材の取り付け など
区分3:舶用電気電子機器
この区分では、船舶に必要な配電盤や制御盤、照明器具などの電気電子機器の製造、組立、配線、取り付け作業などが対象となり、船舶の電装関連工事全般を担うことになります。
- 配電盤や制御盤の組立・配線作業
- 船舶内の照明や航海計器等の結線・取付け
- 各種ワイヤリング作業
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
受け入れ企業の条件と申請手続き

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるには、企業側にも厳格な条件と申請手続きが求められます。ただ人手が足りないという理由だけでは制度は適用されず、労働環境やサポート体制、労務管理の整備状況などもチェックされます。
具体的には、適正な雇用契約の締結、労働・社会保険への加入、生活支援計画の作成などが義務付けられています。これらはすべて、「外国人が日本で安定的に働ける環境を提供できるかどうか」を判断するためのものです。
申請手続き自体も多くの書類と確認事項があり、提出先である出入国在留管理庁や、必要に応じて国土交通省海事局が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」との協力が不可欠です。受け入れ事業者は、この協議会の構成員となる必要があり、協議会が主催する定期的な会への出席を通じて制度の適正な運用に努めます。
参考:
出入国在留管理庁 受入れ機関の方
国土交通省 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領
受入れ企業の要件と雇用管理体制
受入れ企業には、次のような要件が課されています。
- 特定技能外国人と適切な雇用契約を締結していること(期間・賃金・業務内容の明記)
- 自社に所属する日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 労働基準法、労働安全衛生法などに基づいた環境整備ができていること
- 外国人への生活支援(希望に応じた住宅の確保、相談窓口の設置等)を行うこと
また、外国人の就労状況を定期的に報告する義務もあり、これらを怠ると制度からの除外や不許可の可能性が生じます。
申請に必要な書類と手続きの流れ
申請手続きは、以下のような流れで行われます。
- 外国人材の選定(技能試験・日本語試験の合格確認)
- 雇用契約の締結
- 必要書類の準備と提出(在留資格認定証明書交付申請)
- 出入国在留管理庁の審査
- 入国または在留資格変更
提出書類には、雇用契約書、支援計画書、誓約書、申請理由書、企業情報などが含まれ、記載内容や他の関連資料との整合性が重要視されます。申請から証明書の交付まで1か月から2か月程度を要するのが一般的です。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
外国人材に必要な試験・資格・語学力
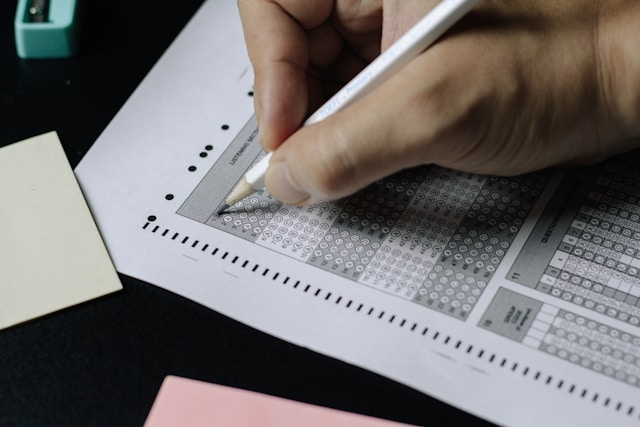
特定技能「造船・舶用工業」分野で外国人材を受け入れるには、あらかじめ決められた試験と語学基準を満たしていることが必要です。これは、現場で即戦力として働けるかどうかを見極めるための重要な指標となります。
なお、現行の技能実習制度における2号技能実習を良好に修了している場合、将来的に予定されている「育成就労制度」が施行された後に、特定技能1号への移行時に技能試験や日本語試験の一部または全部が免除される可能性があります。ただし、2025年8月時点では育成就労制度はまだ施行されておらず、これらの免除措置は現段階では適用されていません。
技能試験の概要と評価基準
技能試験は、「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分ごとに、外国人材が現場の即戦力として必要な知識と技術を有しているかを評価する目的で実施されます。試験は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が主管しており、試験内容は学科試験と実技試験の2つに大別されます。
学科試験では、作業に必要な専門知識や安全衛生、使用工具・素材についての基本的理解が問われます。
実技試験では、実際の現場と同様に溶接や金属加工、組立てなどの作業を通じて、技能面や安全意識、正確な手順遂行能力などを総合的に審査します。
合格基準は、学科ではおおむね正答率60%以上、実技も所定の合格基準をクリアすることが条件です。
試験申込はインターネット経由でも受け付けており、受験地・機材・日時の自由度が高いことも特徴です。いずれの区分も「現場技能の証明」を重視しており、不合格の場合は再受験も可能です。各試験の詳細は日本海事協会の最新案内で随時確認できます。
参考:一般財団法人日本海事協会(ClassNK) 造船・舶用工業分野特定技能試験
日本語能力試験(JLPT・JFT-Basic)の基準
外国人材は、日本語でのコミュニケーション力も一定程度求められます。具体的には以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。
- JLPT(日本語能力試験)N4以上
- JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2レベル以上
これらのレベルでは、簡単な日常会話や業務指示が理解できることが想定されています。なお、作業指示や安全教育は日本語で行われるため、企業側としても語学力の確認は必須です。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
支援機関・制度活用と実務運用の注意点

特定技能外国人を受け入れる際、企業は登録支援機関との連携を通じて、生活面や業務面のサポートを行う義務があります。企業はこれらの支援業務を登録支援機関に委託するか、自社で直接実施するかを選択できますが、初めて外国人材を雇用する企業にとっては、支援機関の存在が制度運用の成否を分ける重要なポイントとなります。
また、制度の運用にあたっては、実務上でのトラブルやミスも起こりがちです。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、事前準備と運用ルールの明確化、社内体制の整備が欠かせません。
参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
登録支援機関の選定と役割
登録支援機関は、外国人材の生活支援や相談対応など、企業に代わって支援業務を担う専門組織です。支援内容は法令で定められており、以下のような項目が含まれます。
- 日本語学習や地域生活に関する支援
- 医療機関の案内や緊急時対応の支援
- 生活ルールや就労マナーに関するオリエンテーションの実施
- 外国人との定期面談および出入国在留管理庁への報告
支援機関を選ぶ際は、業界経験や多言語対応の有無、提供するサービス内容、各種サポートの実績数などを確認し、自社の業務内容や地域特性に合った機関を選ぶことが重要です。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
現場でよくあるトラブルと対応策
特定技能人材を受け入れた企業では、次のようなトラブルが起こるケースがあります。
- 想定していた業務以外への配置(制度違反の恐れ)
- 言語の壁による作業ミスや指示誤解
- 文化の違いによる職場内の人間関係の摩擦
- 寮や通勤環境に対する不満
こうした問題に備えて、事前に外国人向けの業務マニュアルを整備したり、社内に相談窓口を設置したりすることが有効です。また、定期的に面談やアンケート調査を実施する方法で、早期に課題を把握することができます。
制度活用の際にありがちなミスとその回避法
特定技能制度はルールが細かく、理解が不十分なまま運用するとトラブルにつながる可能性があります。ありがちなミスとしては以下のとおりです。
- 「育成就労(旧技能実習)」と「特定技能」を混同して運用してしまう
- 雇用契約の内容が制度上の要件を満たしていない
- 変更届や報告書の提出を失念する
- 受入れ人数の上限(事業所規模により異なる)を超えてしまう
これらのミスは、厚生労働省や出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されている特定技能運用要領や最新の情報を随時確認し、参考にすることで回避できます。公式サイトでは必要書類の一覧や詳しい説明も掲載されていますので、制度変更や通達に迅速に対応しましょう。実際に多くの企業が行ってきたように、支援機関や社労士と密に連携することも有効な手段です。
日本の労働市場では深刻な人手不足が続いており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。この課題を解決する重要な選択肢として外国人材の活用に注目が集まる一方、頻繁に行われる制度変更や言語・文化の壁、複雑な手続きなど、人事担当者の悩みは尽きません[…]
【導入事例】特定技能の活用で現場の活気を取り戻した中小造船所のケース
ここでは、特定技能制度を活用して人手不足の解消に成功した、ある地方の中小造船所の事例をご紹介します。
課題:熟練工の退職と深刻な人手不足
従業員50名ほどのA造船株式会社では、長年現場を支えてきた熟練の溶接工たちが次々と定年退職し、深刻な人手不足に悩まされていました。ハローワークに求人を出しても若手の応募はほとんどなく、採用できてもすぐに辞めてしまう状況が続き、受注した船の納期遅延が常態化し、会社の将来に大きな不安を抱えていました。
解決策:特定技能「造船」分野での外国人材採用
経営者が解決策を探す中で特定技能制度を知り、登録支援機関に相談しました。すると、海外での実務経験が豊富な人材を紹介できると聞き、フィリピンから特定技能「造船」区分の溶接経験者2名の採用を決定しました。
受け入れにあたり、会社は登録支援機関と連携して住居としてアパートを借り上げ、生活に必要な家具・家電も一式用意しました。また、現場の日本人リーダーには、指示が伝わりやすい「やさしい日本語」の研修や、異文化理解に関する勉強会を実施し、スムーズに業務を開始できる環境を整えました。
成果:生産性の向上と職場環境の活性化
来日した2名は、期待通りの高い溶接技術を持つ即戦力でした。すぐに現場に溶け込み、彼らが加わったことで生産ラインの遅れは解消されました。納期を守れるようになっただけでなく、その真摯な仕事ぶりが他の日本人若手社員にも良い刺激となり、職場全体に活気が戻りました。
現在、2名は特定技能2号への移行を目指して技術を磨いており、会社としても長期的なキャリアプランを支援しています。A造船の社長は、「彼らはもはや単なる『助っ人』ではなく、会社の未来を共に創る大切な仲間です」と語っています。
まとめ|外国人材活用で人手不足を解消するために

造船・舶用工業分野における人手不足は、業界全体の課題として深刻化しています。こうした状況の中で、「特定技能制度」は、企業にとって即戦力となる外国人材を確保するための有効な手段です。
本記事では、制度の概要から最新の業務区分、受け入れ手続き、実務運用のポイントまで、実際に制度を活用するうえで押さえておくべき事項を網羅的にご紹介しました。
特定技能2号への対象拡大や育成就労制度の開始により、外国人材がより長期的に活躍できる環境が整いつつあります。制度を正しく理解し、支援体制を整えることで、外国人材も企業も安心して長期的なパートナーシップを築いていけるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。