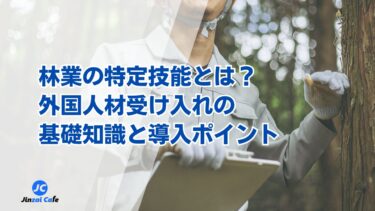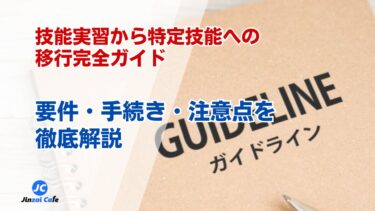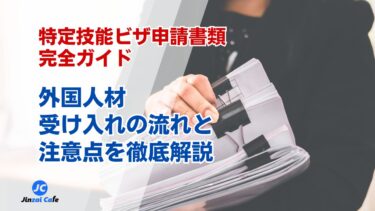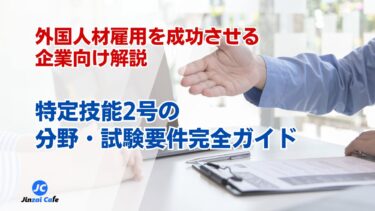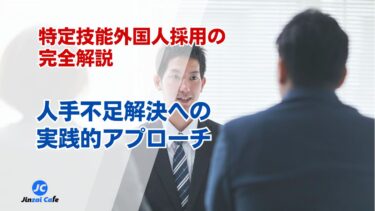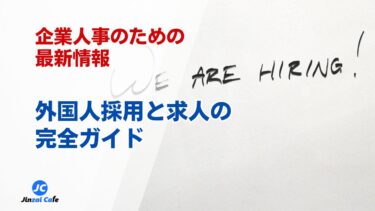日本の木材産業は、住宅建築や家具製造など幅広い分野を支える重要な産業です。しかし現場では、長年にわたり深刻な人手不足が続いています。高齢化による熟練労働者の引退や、若手人材の就業離れが進み、製材・加工・出荷などの工程で十分な人員を確保できない状況が常態化しています。その影響は、生産性の低下や納期遅延、品質管理の難化といった形で顕在化しています。
こうした課題の解決策として注目されているのが「特定技能制度」です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることで、現場の即戦力として活躍してもらうことが可能になります。ただし、制度を有効に活用するには、対象業務や受け入れ要件、試験制度、定着支援などを正しく理解し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
本記事では、木材産業における特定技能制度の概要から、受け入れ方法、試験制度、定着促進のポイントまでをわかりやすく解説します。最後までお読みいただくことで、自社の人材戦略にこの制度をどう組み込むべきか、具体的な方向性を描けるはずです。
日本の林業は今、大きな課題に直面しています。高齢化や担い手不足の影響で、国内の森林資源を十分に活用した木材生産が難しくなり、作業現場の人手は常に足りない状態が続いています。林業は自然を相手にした厳しい労働環境である一方で、日本の山林管理や木[…]
特定技能と木材産業の現状

木材産業は、日本の住宅建築や家具製造を支える重要な分野ですが、現場では慢性的な人手不足が続いています。高齢化や若手離れにより労働力の確保が難しく、生産効率や納期管理にも影響が出ています。こうした課題を背景に2019年、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れる「特定技能制度」が導入されました。制度活用により、現場の即戦力確保や持続的な生産体制の構築が可能になります。
木材産業の人材不足の背景
林野庁の統計によると、木材関連事業(林業)の就業者のうち、65歳以上の高齢者が25%を占めており、全国的な全産業平均(15%)に比べても高齢化が顕著です。さらに、35歳未満の若年層は17%にとどまり、若手人材の参入は減少傾向にあります。木材産業の現場では、体力を要する屋外作業や大型機械の操作など厳しい作業環境が多く、令和2年(2020年)における林業従事者数は44,000人と、1985年からの35年間で約35%減っています。
また、地方では人口減少や都市部への流出が進み、採用活動を行っても応募がほとんどない企業も少なくありません。これらの要因が重なり、木材産業は構造的な人手不足に陥っています。この問題を解消するための実践的な策の一つが、特定技能人材の受け入れです。
参考:林野庁 林業労働力の動向
特定技能制度の概要と目的
特定技能制度は、2019年4月に新設された在留資格「特定技能1号・2号」に基づき、即戦力となる外国人労働者を特定の産業分野で雇用できる制度です。2024年3月29日の閣議決定により、木材産業分野(製材・加工・合板製造など)が正式に対象に追加されました。これにより、木材産業でも特定技能制度を活用して外国人労働者を受け入れられるようになりました。
受け入れ対象者は所定の技能試験や日本語試験に合格している必要がありますが、試験の詳細については後の章で解説します。特定技能1号は最長5年間の在留が可能で家族帯同は認められていません。一方、特定技能2号は在留期限がなく家族帯同も認められますが、木材産業分野では現在1号のみが対象です(2号の適用は今後検討されています)。
この制度の目的は、深刻な人手不足を補い、木材産業の現場で即戦力を確保するとともに、産業の持続的発展に寄与する点にあります。政府は2024年度から5年間で、木材産業分野に最大5,000人の特定技能外国人を受け入れる計画を進めています。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
出入国在留管理庁 木材産業分野
林野庁・農林水産省の最新発表と動向
林野庁や農林水産省は、木材産業における特定技能制度の円滑な運用を推進しています。現在、関係省庁や業界団体が構成員となる協議会が設置され、現場の状況を共有し円滑な運用に関する協議が行われています。協議会では受け入れ拡大に向けた方針も示されており、企業向けガイドラインの整備や試験実施体制の拡充等が進められています。
農林水産省の公式ホームページでは、対象業務や試験日程、各種申請手続きに関する最新情報が随時更新されており、資料もダウンロードできますので、企業は参考として常に確認することが求められます。
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
木材産業での特定技能の対象分野と業務内容

特定技能制度で木材産業が対象となるのは、製材、木材加工、合板製造などの工程です。これらの業務は大型機械の操作や精密な加工技術を必要とし、安全管理の徹底も欠かせません。外国人材が現場で即戦力として活躍するためには、試験で求められる技能水準や作業手順を理解していることが重要です。制度の対象業務を把握することで、企業は採用計画をより具体的に立てられます。
参考:林野庁 木材産業分野 特定技能外国人 受入れマニュアル
製材・加工などの具体的作業
製材工程では、丸太を用途に応じたサイズに切断し、乾燥や表面仕上げを行います。加工工程では、住宅用建材や家具部材の製造、組み立て前のパーツ加工が中心です。これらの作業には大型丸鋸、プレーナー、フォークリフトなどの機械を扱う技能が必要です。特定技能人材は、こうした作業を即戦力として担うことが可能で、現場の生産性向上や納期短縮に直結します。特に人手不足が深刻な中小規模の製材所では、その効果が顕著です。
安全管理と技能要件
木材加工現場は、回転刃や高温乾燥機など危険を伴う設備が多く、安全管理は最優先事項です。特定技能試験では、機械の安全操作、保護具の着用、緊急時の対応など安全関連の知識が問われます。さらに、正確な寸法測定や加工精度を維持する技能も重要です。受け入れ企業は、採用前に人材の技能レベルを確認するとともに、入社後の安全教育や技能研修を徹底することで、事故防止と品質確保を両立させる必要があります。
技能実習との違いと移行の流れ
技能実習は「技能習得」が目的で、所属する監理団体の下で計画に沿った実習を行います。一方、特定技能は「即戦力としての就労」が目的で、より実務的な業務に従事できます。技能実習修了者が特定技能に移行する場合、関連業務での実務経験があれば技能試験が免除されるケースもあります。この方法により、すでに日本での生活や業務に慣れた人材を継続雇用できるため、教育コストを削減しつつ、現場戦力を維持できるという利点があります。
外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます[…]
特定技能人材の受け入れ要件と申請手続き

特定技能人材を木材産業で受け入れるには、制度で定められた条件を満たし、所定の申請手続きを行う必要があります。受け入れ機関としての登録、適正な雇用契約の締結、在留資格の取得が主な要件です。申請には技能試験・日本語試験の合格証明や、雇用条件書、支援計画書などの書類が必要となります。これらを正しく準備することで、受け入れがスムーズに進みます。
受け入れ機関の登録と要件
企業が特定技能人材を雇用するためには、「受け入れ機関(特定技能所属機関)」として法務省に登録される必要があります。登録要件には、適正な労働条件の確保、社会保険への加入、過去5年間に出入国・労働法令違反がないこと等が含まれます。
また、外国人材に対する支援計画の策定と実施が義務づけられており、この支援業務の全部または一部を、国に登録された「登録支援機関」に委託することも可能です。支援内容には以下に挙げる事前ガイダンス等が含まれ、法令遵守と継続的な支援体制が求められます。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
在留資格申請の流れと必要書類
在留資格「特定技能1号」の取得に係る申請は、地方出入国在留管理局に対して行います。申請に必要な書類は多岐にわたるため、事前に法務省のホームページ等で一覧を確認し、漏れなく準備することが重要です。主な提出資料は以下の通りです。
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 会社概要資料等
審査では、雇用契約が基準を満たしているか、支援体制が整っているかが確認されます。書類不備や支援計画の不十分さは不許可の原因となるため、注意が必要です。
雇用契約と労働条件の確認ポイント
特定技能人材の雇用契約は、日本人労働者と同等以上の労働条件でなければなりません。賃金、労働時間、休日、保険加入状況などを明確に記載し、契約書は本人が理解できる言語で交付します。
また、安全教育や労働災害防止措置の実施も重要です。契約内容が不十分だと、後のトラブルや離職につながります。受け入れ企業は、契約締結の際に通訳や支援機関を同席させ、条件の相互理解を確保することが望まれます。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
試験制度と日本語能力要件
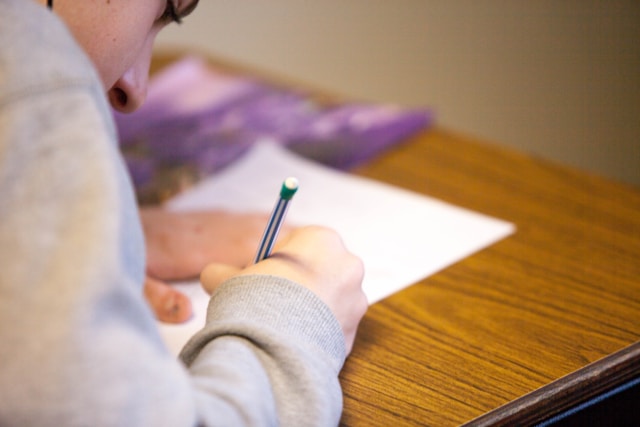
特定技能人材として木材産業で働くには、技能試験と日本語試験の双方に合格する必要があります。技能試験は、製材や加工などの実務能力を評価し、日本語試験は業務に必要な言語理解力を確認します。これらは国内外で実施され、合格証明が在留資格申請の必須条件です。適切な試験対策と合格後のスケジュール管理が、受け入れを円滑に進める鍵となります。
技能試験の科目と実施機関
木材産業分野の技能試験(テスト)では、製材、木材加工、合板製造に関する知識と実技能力が問われます。試験内容は、寸法測定、機械操作、安全管理、品質確認など多岐にわたり、実際の現場作業を想定した形式で行われます。この分野は、いわゆる林業とは異なり、主に製造業に分類される業務が対象です。
試験は国内外で実施され、実施機関は農林水産省が指定した団体です。企業側は受験者のスケジュールや受験会場の情報を事前に確認し、受験費用や渡航費の支援も検討することで、採用候補者の合格を後押しできます。
参考:一般社団法人全国木材組合連合会 木材産業分野特定技能制度
日本語能力試験(JLPT・JFT-Basic)の水準
日本語能力は、安全な作業指示の理解や職場コミュニケーションの円滑化に不可欠です。特定技能1号の取得には、国際交流基金と日本国際教育支援協会が共催する「日本語能力試験(JLPT)」でN4以上に合格するか、国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」で一定の合格基準を満たす必要があります。
これらのテストは、日常会話や業務の基礎となる指示を理解できるレベルを測るもので、現場での安全確保にも直結します。企業は受験希望者に試験情報を提供し、学習教材やオンライン講座等を利用して事前学習をサポートすることが望まれます。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
試験対策と合格者の傾向
試験合格者の多くは、受験前に専門知識や日本語を重点的に学習しています。特に技能試験では、安全管理や機械操作の理解が不足すると不合格になりやすいため、模擬試験や現場体験を通じた実践的な訓練が効果的です。日本語試験対策では、業務で使う用語や指示文に慣れることが重要です。企業が受験者支援を行えば、合格率向上だけでなく、採用後の即戦力化にもつながります。合格後は速やかに在留資格申請を行い、入国準備を進めます。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
受け入れ後の支援と定着促進策

特定技能人材を受け入れた後は、職場環境への適応と長期的な定着を促す支援が不可欠です。法令で定められた生活支援や安全教育に加え、社内コミュニケーションの工夫、技能向上研修などを行うことで、離職率を下げられます。受け入れ企業は、業務面だけでなく生活面のサポートにも注力し、外国人材が安心して働ける環境を整えることが重要です。
生活支援と相談体制の構築
特定技能人材が日本で安定して生活するためには、住居の確保、役所手続きのサポート、医療機関の案内など多面的な生活支援が必要です。
また、生活や業務上の悩みを相談できる窓口を社内外に設置し、通訳や多言語対応も整えると安心感が高まります。相談体制を整えることは、早期離職防止だけでなく、職場の信頼関係構築にもつながります。支援計画は受け入れ前から準備し、入社初日から実行に移すことが理想です。
安全教育と技能向上研修
木材産業の現場は大型機械や高所作業など危険を伴う業務が多いため、受け入れ直後の安全教育は必須です。機械操作マニュアルや作業手順を多言語で用意し、実地研修を通して理解度を確認します。
加えて、長期的には技能向上研修を計画的に実施し、製品品質の向上や作業効率化を目指します。技能向上の機会を提供することで、従業員のモチベーション維持や定着率の向上にも効果が期待できます。
国際交流や社内コミュニケーションの工夫
外国人材が職場に溶け込みやすくするためには、国際交流イベントや社内交流の場を定期的に設けることが有効です。例えば、文化紹介や多国籍料理の持ち寄り会などは、お互いの理解を深め、チームワークの向上につながります。
また、業務連絡ではシンプルで明確な表現を心がけ、必要に応じて翻訳アプリや社内用語集を利用します。こうした地道な協力体制の構築が、職場全体の雰囲気改善や長期的な人材定着を後押しします。
深刻な人手不足に直面している企業経営者の皆様、外国人材の活用を検討されていませんか?日本の労働力不足は年々深刻化しており、特に製造業、建設業、介護分野では即戦力となる人材の確保が喫緊の課題となっています。2019年に創設された特定技[…]
【導入事例】技能実習から特定技能への移行による人材定着の成功例
ここでは、地方の製材所が技能実習から特定技能制度への移行によって人材の定着と技術継承の課題を乗り越えた事例をご紹介します。
課題:技能定着を阻む「3年間の壁」
従業員30名ほどのある製材所では、長年インドネシアから技能実習生を受け入れてきました。しかし、技能実習制度は原則3年間(条件を満たせば最長5年)で帰国が必要なため、ようやく仕事を覚えて一人前になったタイミングで離職してしまう「3年間の壁」が課題となっていました。また、日本人の熟練社員の高齢化も進み、技術継承が大きな経営課題となっていました。
解決策:特定技能制度への移行
このような状況の中、技能実習2号を良好に修了した実習生は、技能試験を受けずに「特定技能1号」へ移行できる制度があることに着目しました。実習期間終了間近の優秀な実習生2名に、引き続き特定技能人材として働いてもらうことを提案。日本での生活や仕事に慣れ、長期間働くことを望んでいた2名はこれを受け入れ、会社は在留資格変更の手続きを支援しました。
成果:即戦力人材による現場改善
特定技能に移行した2名はすでに業務内容や職場環境に精通しており、教育にかける時間やコストを大幅に抑えて現場に復帰しました。技能実習時代の経験を生かして他の技能実習生の指導も担うようになり、現場の重要な存在へと成長しています。
これにより、最長5年間継続勤務できる環境が整い、若手日本人社員の育成にもより多くの時間を割けるようになりました。事業者は「技能実習から特定技能への移行は、本人にも事業所にも良い選択だった。今後対象分野の拡大や特定技能2号の適用が進めば、さらに長期的な活躍を期待できる」と話しています。
まとめ|木材産業における特定技能活用の意義

木材産業の現場は、日本の暮らしを支える重要な役割を担っていますが、構造的な人手不足の中で持続的な発展を遂げるには、新たな労働力確保の手段が欠かせません。特定技能制度は、必要な技能と日本語力を備えた外国人材を受け入れられる実践的な枠組みとして、多くの企業で注目されています。
本記事で解説したように、制度の対象業務や受け入れ要件、試験制度、申請手続き、そして定着支援のポイントを押さえれば、採用活動は格段に進めやすくなります。特に、受け入れ後の生活支援や社内コミュニケーションの工夫は、長期的な雇用継続に直結します。
特定技能2号への移行も見据え、長期的なキャリアパスを描ける環境を整えることが、これからの木材産業の持続的発展の鍵となります。外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに各種職種の外国人材をご紹介しています。