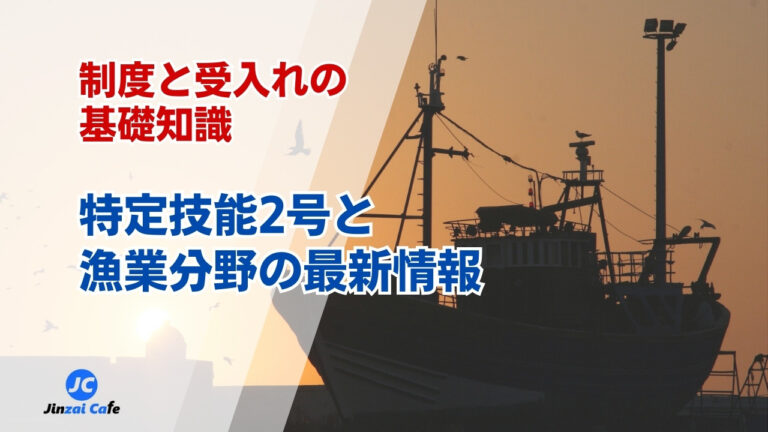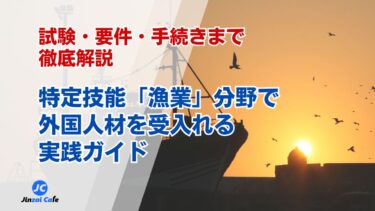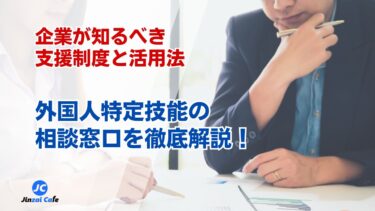日本の漁業は、後継者不足や高齢化が深刻化しており、担い手の確保が大きな課題となっています。そこで注目されているのが「特定技能2号」です。特定技能制度は、外国人が一定の技能と経験を持つことで在留資格を得て働ける仕組みであり、漁業分野もその対象に含まれています。
特に2号資格は在留期間の更新制限がなく、家族帯同も可能であるため、長期的な人材確保に直結します。本記事では、漁業における特定技能2号の概要や取得要件、受入れ体制、導入事例を整理し、自治体や企業担当者が制度を理解・活用するためのポイントを解説します。
特定技能2号と漁業分野の概要

特定技能2号は、高度な技能を持つ外国人材が日本で長期的に就労できる在留資格です。漁業分野が対象に含まれている背景には、慢性的な人手不足や水産業の国際競争力低下があります。漁業は漁船の操業から養殖業まで幅広い作業があり、担い手不足が続けば地域経済や食料供給にも影響を及ぼすでしょう。
そのため、政府は特定技能制度を導入し、外国人材の活用によって持続可能な漁業運営を目指しています。制度を理解することは、地域振興や安定した漁業経営につながる重要な第一歩です。
参考:
水産庁 令和6年度 水産白書概要
出入国在留管理庁 特定技能「漁業分野」
漁業での人材不足と制度導入の経緯
漁業分野では高齢化が進み、若年層の就業希望者が減少しています。その結果、漁船の操業や養殖現場では労働力不足が顕著になりました。こうした状況を背景に、2019年に創設された特定技能制度が活用されるようになり、漁業も対象分野として位置づけられました。外国人材の受入れは一時的な人手補充ではなく、漁業の持続性を確保する戦略の一環として進められています。
特定技能1号との違いと2号の特徴
特定技能1号は基本的に在留期間が上限5年で、家族帯同は認められていません。一方で2号は更新制限がなく、家族も帯同できるため、長期的な生活基盤を築けます。
この違いにより、2号を取得した人材は企業にとって安定的な労働力となりやすいのです。漁業においても、技能実習や1号で経験を積んだ人材が、2号へ移行することで地域社会に長期的に貢献できるようになります。
漁船・養殖業における活用範囲
特定技能2号の対象業務は、漁船における操業や水産加工、養殖業での作業など幅広く設定されています。具体的には、網の管理、魚の選別、餌やり、漁獲物の取り扱いといった実務に従事できます。
これらは高い技能と経験を必要とするため、2号取得者は現場で即戦力となることが期待されています。外国人材が担う役割は、単なる作業員にとどまらず、漁業全体の効率化や安定化にも直結します。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容(漁業)
日本の漁業界では、高齢化の進行と若年層の離職により、深刻な人手不足が続いています。水産庁の調査によると、漁業就業者数は2003年の約24万人から2023年には約12万人まで減少しており、この傾向は今後さらに加速すると予測されています。現在、[…]
特定技能2号の取得要件と試験制度

特定技能2号を取得するには、一定の実務経験や技能水準を証明することが不可欠です。漁業分野では、技能測定試験や日本語能力試験を通じて専門性と生活能力が確認されます。さらに、1号での就労経験を積んだうえで移行するケースが多く、段階的なキャリア形成を経て2号に到達する仕組みです。
在留資格の許可が交付されると、長期的な在留と家族帯同が可能になり、地域に根差した人材育成につながります。受入れ企業や自治体は、試験制度と要件を正しく理解し、円滑な手続きを進める必要があります。
必要な実務経験と技能水準
漁業分野の2号取得者は、一定の実務経験を持ち、高度な作業を独立して行える水準が求められます。たとえば、漁船の操業工程を理解し、安全管理を徹底できることや、養殖業での作業を計画的に進められる能力などです。技能実習や特定技能1号で培った経験が評価対象となり、現場での即戦力として活躍できる人材であることが条件となります。
技能測定試験と日本語能力要件
2号資格を得るには、分野ごとに設定された技能測定試験に合格する必要があります。漁業の場合、操業技術や養殖に関する知識・技能を問う実技・筆記試験が実施されます。
加えて、日本語能力試験(JLPT)や国際交流基金の日本語基礎テストにより、生活や業務に必要な日本語力が確認されます。こうした試験を通じて、専門性とコミュニケーション力を兼ね備えた人材を選抜しているのです。
参考:
一般社団法人大日本水産会 漁業技能測定試験
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
在留資格更新と家族帯同の条件
特定技能2号は、在留期間に上限がなく、更新を繰り返すことで長期滞在が可能です。また、家族の帯同も認められるため、生活基盤を築きながら地域社会に根付くことができます。
ただし、受入れ先が安定した就労環境を提供し続けることが前提条件です。更新時には引き続き技能の継続性や所属機関における雇用の安定性が確認されるため、企業や自治体には適切なサポートと管理が求められます。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
漁業分野での受入れ体制と管理ポイント

また、法務省が管轄する出入国在留管理庁や農林水産省、水産庁と連携し、制度に則った適切な管理を行う必要があります。自治体や漁業協議会が積極的に関わることで、外国人材が地域社会に定着しやすくなり、漁業経営の安定にも寄与するでしょう。
漁船運用と安全確保の基準
漁船での就労は、天候や海上状況によって危険が伴うため、安全基準の徹底が求められます。具体的には、救命具の常時着用、労働時間の適正管理、操業時の指導などが挙げられます。
外国人労働者には日本語での安全教育だけでなく、母語や図解を活用した研修を導入することで理解度を高める工夫も有効です。こうした取り組みによって、事故防止と安心できる労働環境の整備が可能となります。
漁業協議会や関係省庁との連携
漁業分野での受入れは、個別企業だけでなく地域全体の協力体制が不可欠です。漁業協議会を通じて情報共有を図り、出入国在留管理庁や農林水産省など関係機関と連携することが求められます。
制度変更や試験要領の改訂に対応するためにも、最新情報を常に確認する仕組みが重要です。こうしたネットワークを活かすことで、制度運用の透明性を高め、不適切な受入れを防ぐ効果も期待できます。
従事者への支援体制と生活サポート
受入れ人材が長期的に働くためには、職場だけでなく生活環境の整備も大切です。住居の確保、日本語教育、地域との交流イベントなどが、定着を促す有効な支援策です。
また、外国人従業員が困ったときに相談できる窓口を設けたり、必要に応じて登録支援機関へ支援を委託したりすることで、不安を軽減し安心して働ける環境を整えられます。生活支援は結果的に職場の安定にもつながり、企業や自治体にとっても大きなメリットとなります。
実際の事例と導入効果
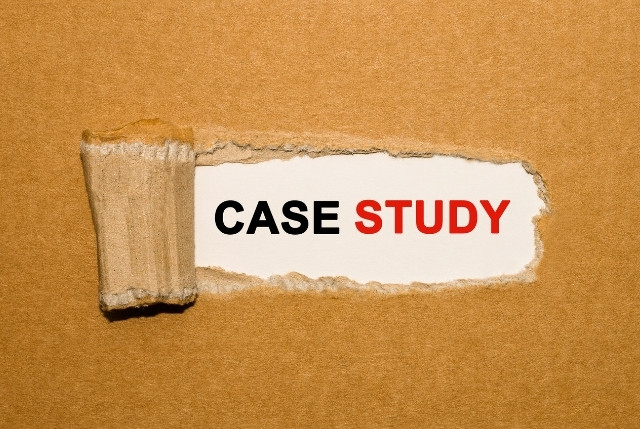
特定技能2号は、既に全国の漁業現場で導入が進み、一定の成果を上げています。技能実習や特定技能1号を経て2号に移行した外国人材は、熟練の作業者として漁業経営を支えています。漁船操業や養殖業の現場では、外国人材の活躍によって労働力不足が改善され、生産効率が向上しました。
さらに、地域社会に長期的に居住することで地域振興にも寄与しています。こうした事例は、自治体や企業が制度を積極的に活用する大きな後押しとなっています。
技能実習から特定技能2号への移行事例
多くの外国人材は、技能実習を経て特定技能1号に移行し、さらに経験を積んで2号へとステップアップします。例えば、技能実習で養殖業務に従事していた人材が、現場での指導経験や管理業務を任されるまでに成長し、2号資格を取得したケースがあります。このような移行は、本人のキャリア形成だけでなく、受入れ事業者にとっても安定的な人材確保につながります。
養殖業での外国人材活用例
養殖業では、給餌や水質管理、稚魚の育成といった継続的な作業が必要です。外国人材が2号として定着することで、これらの作業を安定的に担うことが可能となります。
たとえば、地方の養殖業者がベトナム出身の技能実習生を採用し、数年後には2号資格を取得してチームリーダーとして活躍している事例もあります。安定した労働力の確保は、事業拡大や品質管理の強化にも直結します。
地域活性化につながる取り組み
外国人材の長期定着は、単なる労働力補充にとどまらず、地域社会への貢献にもつながります。地域イベントへの参加や学校との交流を通じて、外国人と地域住民の関係が深まり、国際的な交流の場が生まれています。
さらに、家族帯同によって子どもが地域の学校に通うことで、新しい文化の交流が進み、地域の活性化につながる好循環が生まれています。
自治体・企業が活用する際の課題と解決策

特定技能2号の活用は有効な人材確保策ですが、導入時には課題も多く存在します。特に、手続きの煩雑さ、法務や労務管理の不慣れさ、生活支援の不足などが指摘されています。これらを放置すれば、外国人材が定着せず、地域や事業者にとって逆効果となる可能性もあります。
そのため、企業と自治体が協力し、実務的な解決策を講じることが求められます。制度の円滑な運用は、現場の安定と地域活性化を実現する重要な基盤となるでしょう。
手続き・書類提出の注意点
特定技能2号の受入れには、出入国在留管理庁や農林水産省への書類提出が必要です。申請書類の不備や提出期限の遅延は、許可交付の遅れにつながります。
そのため、手続き要領を事前に確認し、専門家や行政書士と連携することが効果的です。申請内容を正確に整備することで、円滑に在留資格を取得でき、企業の負担軽減にもつながります。
受け入れ事業者が直面する問題と改善策
受け入れ事業者は、言語の壁や文化の違いによるコミュニケーション不足に悩むことが少なくありません。改善策としては、日本語研修の実施や、同国籍の先輩社員をメンターとして配置する方法が有効です。
また、勤務シフトや労働環境を柔軟に整えることで、外国人材の働きやすさを高められます。現場での小さな工夫が、長期的な人材定着に直結するのです。
地域全体での人材定着支援方法
外国人材の定着には、職場だけでなく地域社会の協力が欠かせません。自治体やNPOが主催する交流イベントや生活相談窓口を整備することで、安心して暮らせる環境を提供できます。
また、地域住民との交流を促進することで相互理解が深まり、外国人材が「地域の一員」として受け入れられるようになります。こうした取り組みは、漁業の持続的な発展と地域振興の両立に寄与します。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は重要な選択肢の一つです。しかし、複雑な制度内容や手続きに関して「どこに相談すればよいのか分からない」「適切な支援を受けられるのか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も多いの[…]
まとめ|特定技能2号と漁業の未来

本記事では、特定技能2号が漁業分野にもたらす可能性と、その取得要件、受入れ体制、事例、課題と解決策を整理しました。
漁業の人手不足は全国的な問題ですが、制度を正しく理解し、自治体と企業が協力して受入れ環境を整えることで、持続可能な漁業経営が実現できます。さらに、外国人材の長期定着は、地域社会の国際化や活性化にもつながります。
これから特定技能2号の活用を検討する際は、制度情報の確認と生活支援の充実を意識し、安心して働ける環境づくりを進めることが大切です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。