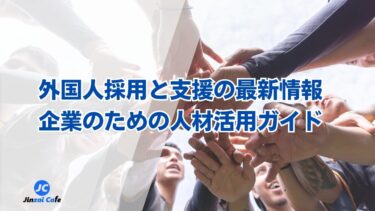人手不足が深刻化する中、鉄道業界では安全運行や車両整備といった業務を安定的に維持するための「人材の確保」が急務となっています。少子高齢化が進む日本では、日本人だけで必要な人員をまかなうのが難しくなっており、鉄道会社にとっても大きな課題です。
このような背景のもと、近年注目されているのが「特定技能制度」を活用した外国人採用です。鉄道分野が制度の対象として新たに追加されて以降、現場では外国人の受け入れに向けた動きが加速しつつあります。制度の内容や受入れ要件を理解し、的確に活用することが、企業の持続的な成長に直結するのです。
本記事では、鉄道会社が特定技能の仕組みをどう活用できるのか、導入の流れや注意点、成功事例などを交えてわかりやすく解説していきます。これから外国人材の採用を検討される方にとって、有益な情報となることを目指します。
鉄道業界の人手不足とその影響

鉄道業界では近年、運転士や車両整備士、駅係員といった現場の担い手が深刻に不足しています。社員の高齢化や若年層の採用難に加え、技術職の人材育成に時間がかかることから、多くの鉄道会社が慢性的な人手不足に悩まされています。
特に地方の中小規模の鉄道会社では、退職による人員の自然減に加えて、新規採用の確保が追いつかず、日々の運行維持や安全対策に支障が出ている例も見られます。こうした背景の中、鉄道分野が2024年に特定技能制度の対象に追加されたことを受け、外国人材の受け入れを模索する動きが広がってきました。
単なる人員補充ではなく、将来の安定運営を見据えた「戦略的な人材確保」として、制度の活用に注目が集まっています。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能「鉄道分野」
国土交通省 鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
少子高齢化による構造的な人材不足
日本の労働人口減少は、鉄道業界にも大きな影響を及ぼしています。特に、運転・保守といった鉄道の根幹を担う職種では、若手のなり手が少なく、社員の高齢化が進行中です。
技術や安全管理の知見を持つベテラン社員が次々と退職する一方で、新人の採用や育成が思うように進まないため、知識・技能の断絶が起きつつあります。結果として、現場では人手と経験の両面でギリギリの状態が続いているのが実情です。
鉄道会社が直面する業務継続のリスク
人材の不足は、鉄道の根幹である安全運行や安定運行の継続性に直結します。運転士が足りずに列車の本数を減らしたり、整備スタッフが不足して車両検査のスケジュールが遅延したりといったケースも、各地で報告されています。
こうした状況は、社員への負担増を招くだけでなく、鉄道サービス全体への信頼低下にもつながりかねない深刻な問題です。企業としては、従来の日本人採用に加え、より柔軟な人材戦略の再構築が求められています。
特定技能制度導入への関心の高まり
政府が整備した特定技能制度において、鉄道分野は新たな対象業種として加わりました。この制度では、一定の日本語能力と職務技能を有する外国人材の採用が可能となり、慢性的な人材難を抱える企業にとって有力な選択肢となっています。
すでに制度に対応した準備を進めている鉄道会社もあり、今後の採用方針を固める上で、外国人材の戦力化に向けた実務的な関心が着実に高まっています。今後の制度活用の成否は、社内での理解促進と現場体制の整備にかかっているといえるでしょう。
特定技能制度の概要と鉄道分野への適用

鉄道会社が外国人を採用するにあたって、中心的な制度となるのが「特定技能制度」です。この制度は、人手不足が深刻な業種に限り、一定の技能と日本語能力を有する外国人を即戦力として受け入れるために整備された制度であり、従来の技能実習制度とは異なる実務ベースの仕組みとして注目されています。
鉄道分野は、2024年に新たに制度対象として追加されました。すでに複数の鉄道会社が導入準備を進めており、今後は制度を活用した採用が本格化すると見込まれます。
制度の正確な理解と、それに対応できる社内体制の構築は、外国人材を受け入れる上での第一歩です。
特定技能とは何か?制度の仕組みと目的
特定技能制度とは、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」に基づき、日本の人手不足分野に即戦力となる外国人を受け入れる制度です。これまで対象は介護、外食、建設など12分野でしたが、2024年3月の閣議決定により鉄道分野を含む4分野が加わり、現在は全16分野に拡大しています。
この制度では、受け入れ企業が外国人と直接雇用契約を結びます。在留期間は原則5年までで、一部の例外を除いて配偶者などの帯同は認められていません。受け入れに際しては、「技能試験」と「日本語試験」に合格する必要があり、制度上の透明性と一定のスキル保証が図られています。
目的は単なる労働力の補充ではなく、即戦力としての人材活用です。企業はこの意図を理解したうえで、制度を効果的に活用することが求められます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
鉄道分野が追加対象になった背景と意義
鉄道分野が制度対象に追加された背景には、現場の極端な人手不足とそれに伴う安全運行への懸念があります。運転士や駅係員、車両の検査・整備スタッフなど、多岐にわたる業務において人材が不足しており、特に地方路線や中小鉄道会社では業務維持そのものが困難な状況に直面していました。
こうした声を受けて、政府は業界団体や関係機関と協議を重ねたうえで、鉄道分野を2024年に追加しました。外国人にとっても、専門性があり長期的なキャリア構築が見込める分野として魅力があり、双方にとって意義のある制度追加となっています。
制度利用のメリットと注意点
制度を利用する最大のメリットは、一定のスキルと語学力を備えた人材を雇用できることです。たとえば、車両整備の経験がある外国人や、駅での接客経験がある人材を受け入れることで、研修コストや戦力化までの期間を短縮できます。
一方で、注意点もあります。特定技能人材は「労働者」として受け入れるため、企業は日本人と同等の待遇と労務管理を行う必要があります。また、日本語能力が一定以上あっても、現場では方言や業界用語への対応、文化的な違いからコミュニケーションギャップが生じることも想定されます。
これらを補うためには、受け入れ後の教育体制やフォローアップ体制を整備し、長期的に定着できる環境づくりが欠かせません。
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
鉄道会社が採用できる職種と要件

特定技能制度を活用して外国人を採用する場合、鉄道会社は制度で明示された対象職種と要件に基づいて雇用する必要があります。制度上は自由な職種設定が認められているわけではなく、定められた範囲内での受け入れとなるため、事前の確認が必須です。
また、職種ごとに求められるスキルや日本語能力の水準も異なり、採用後の適正配置や研修設計にも影響を及ぼします。ここでは、採用可能な主な職種と必要な要件について詳しく解説します。
採用対象となる業務と職種の一覧
鉄道分野において特定技能で採用が認められている業務区分は、以下の5つに分類されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 軌道整備区分 | 線路の点検・補修、枕木やレールの交換作業など、鉄道の安全運行を支える保守業務 |
| 電気設備整備区分 | 信号設備、変電設備、通信ケーブルなどの点検・整備・更新作業 |
| 車両整備区分 | 列車の定期点検、部品交換、ブレーキや台車の整備など、安全に直結する整備作業 |
| 車両製造区分 | 新造車両の組立・製造に関わる金属加工、電装、溶接、塗装といった工程 |
| 運輸係員区分 | 駅務業務(案内・改札・切符販売)や列車内での接客・安全確認業務など、利用者と直接関わる接客的職務 |
彼らが担うこれらの仕事はすべて、鉄道業務の中核をなす領域であり、一定の専門性と責任感が求められるのが特徴です。採用にあたっては、それぞれの区分に応じた試験合格と、業務内容への理解が不可欠です。
日本語能力・実務経験などの求められる条件
採用対象となる外国人には、原則として日本語能力試験(JLPT)N4以上の日本語力が求められ、業務に関する基本的な理解力も不可欠です。特に「運輸係員」(駅務や接客を含む職種)においては、より高い日本語能力が求められており、目安として日本語能力試験N3以上が必要とされています。
また、制度上の要件として、該当職種ごとに定められた技能評価試験に合格することが求められます。この試験は業務に関連した筆記および実技で構成されており、実務に直結した知識と技能を評価します。技能実習2号の良好な修了者は、一部試験や日本語要件の免除が認められる場合があります。
企業は、採用時に応募者の日本語能力や試験合格証明、業務理解度を確認し、入社後も長期的な育成計画のもとで支援を行うことが重要です。
参考:日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
試験制度と合格基準の概要
鉄道分野における特定技能試験は、国土交通省の管轄で開発・実施されており、2025年から本格運用が始まりました。駅務、整備、軌道保守などの分野ごとに、筆記と実技が組み合わされた評価形式となっています。
試験は国内外で定期的に開催されており、外国人が受験できる体制が整備されつつあります。合格基準は分野ごとに異なるものの、即戦力として求められる水準を想定しており、内容は実務に直結した実践的な項目が多く含まれています。
試験に合格した者には、該当分野での「特定技能1号」在留資格の取得申請が可能となります。企業側は採用前に、受験者の合格証明書や技能レベルをきちんと確認することが重要です。
参考:国土交通省 鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
日本の鉄道業界では、近年ますます深刻化する人手不足が大きな問題となっています。少子高齢化に伴う労働人口の減少に加え、熟練技術者の引退も進み、特に保守整備や駅業務などの現場では人材の確保が急務です。こうした状況を受けて、国は即戦力とな[…]
外国人採用における課題と成功事例

制度導入だけで成果が保証されるわけではありませんが、実務的に成果が見え始めている事例も出てきています。制度の活用にあたっては、課題の見える化と対応策の整備が成否を分けます。ここでは、特定技能制度を活かした外国人材の採用・定着支援に関する最新事例を通じて、成功の秘訣を探ります。
教育制度の整備と制度移行のスムーズ化
JR東日本は2025年2月から3月に行った「特定技能人材育成研修」を試行的に実施した結果、研修を受けた25名中24名が評価試験に合格し、96%もの驚異的な合格率を達成しました。この結果を踏まえ、2025年度からは年間100名規模の育成に拡大し、他の鉄道事業者も参加可能なオープンな教育プラットフォームとして運用を強化しています。
さらに、2025年6月には技能実習生が特定技能1号へ移行する事例も生まれました。ベトナム人研修生3名が車両整備区分で試験に合格し、在留資格を切り替えたうえで鉄道業務に就労できるようになるなど、制度間のスムーズな連携もうかがえます。
参考:
東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本ニュース(2025年7月15日)
外国人雇用新聞 JR東日本が拓く!鉄道分野の外国人雇用最前線~業界全体の未来を創造する新モデル~
課題への対応—教育・フォロー体制とモデルの提示
制度を活用するうえで見えてきた課題としては、以下が挙げられます。
- 専門用語や技術教育の難しさ
- 現場とのコミュニケーションギャップ
- 外国人社員の定着・キャリアパス設計の必要性
一方、JR東日本の取り組みでは、研修プログラムにビジュアル資料や日本語指導を組み込むなど、教育体制の充実に注力しています。また、研修の企画だけでなく、日本での生活支援や雇用契約までをカバーする一貫した受け入れ体制が整備されています。
このような取り組みが、外国人材の早期戦力化と定着率の向上につながっており、業界内での良きモデルケースとして注目されています。
業界全体への波及と今後への期待
JR東日本がオープン型の研修プラットフォームとして他社にも門戸を開いたことで、制度活用のハードルが下がり、鉄道業界全体の外国人採用促進に寄与する構造が見え始めました。
また、政府も鉄道分野への外国人材受け入れを促進しており、2028年度までに最大3,800人の受け入れを見込んでおります。これは非常に前向きな数字であり、地方の鉄道会社にとっても制度導入の追い風となる可能性があります。
採用までの流れと必要な手続き

特定技能制度を活用して外国人材を鉄道会社で採用するには、法令に基づいた手続きと適切な段取りが必要です。制度は整っていても、受け入れ企業側がその流れを把握していなければ、手続きに時間がかかったり不備が生じたりするおそれがあります。
このセクションでは、外国人材を採用する際に必要となる基本的なステップを、事前準備から在留資格の取得、採用後の対応まで時系列で整理します。
受入れ企業の登録と事前準備
まず、外国人材を受け入れる鉄道会社は、出入国在留管理庁への申請による「受入れ機関」としての登録が必要です。これは、外国人の雇用に関して適切な体制を整備していることを示す重要なステップです。
登録にあたっては、以下のような条件が求められます。
- 社会保険・労働保険への加入
- 外国人と日本人社員の待遇同等性の確保
- 支援責任者の配置と外国人支援計画の策定
- 過去に不適切な雇用歴がないこと
また、受け入れ企業は必要に応じて、登録支援機関との契約も検討するとよいでしょう。社内で十分な支援体制を構築するのが難しい場合は、外部の関連機関の活用により、外国人本人の生活・職場適応支援をスムーズに進められます。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
在留資格取得と申請の手順
次に行うのが、「特定技能1号」在留資格の取得手続きです。外国人本人が、技能試験と日本語試験の両方に合格している必要があります。
手続きの主な流れは以下の通りです。
- 企業が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出
- 入管が審査し、交付(約1ヶ月から2ヶ月が目安)
- 交付された証明書をもとに、本人が在外日本大使館などで査証(ビザ)申請
- 日本入国後、在留カードを取得し就労開始
外国にいる外国人材を採用する場合だけでなく、すでに日本国内にいる元技能実習生などが特定技能に移行する場合もあります。その際は「在留資格変更許可申請」の提出が必要です。
採用後の教育とフォローアップ
採用後は、スムーズに現場で業務ができるよう、初期研修と継続的な支援体制の整備が不可欠です。たとえば、以下のような取り組みが効果的です。
- 配属前の安全教育とビジネスマナー研修
- わかりやすい多言語マニュアルの整備
- メンター制度による個別フォローアップ
- 日本語学習支援や生活相談窓口の設置
また、定期的に面談や評価を実施することで、外国人社員の不安やストレスを早期に察知し、長期的な定着と成長につなげることができます。
企業がこのような体制を整えておくことで、受け入れ側・働く側の双方にとって安心できる関係が構築され、制度を最大限に活かした人材活用が可能となります。
「少子高齢化による人手不足が深刻化し、事業継続が危うい…」「外国人材の雇用を検討しているが、就労ビザの申請は複雑で何から手をつければいいのかわからない」「不法就労のリスクや、雇用後の管理についても不安がある」もしあなたがこの[…]
まとめ|鉄道会社に求められる外国人採用戦略

鉄道業界では、深刻な人手不足と高齢化を背景に、即戦力となる外国人材の採用が現実的な解決策として注目されています。2024年に特定技能制度の対象分野に鉄道が追加されたことで、制度を活用した採用が可能となり、すでにJR東日本などが先行して取り組みを進めています。
本記事では、制度の概要、対象職種、採用までの流れ、現場での課題と解決策、そして成功事例に至るまでを網羅的に解説しました。企業にとって重要なのは、「単に人手を補う」のではなく、中長期的に現場を支え、育成し、戦力化していくためのビジョンと体制の構築です。
今後の鉄道会社には、制度理解に加え、社員・外国人双方にとって安心できる受け入れ環境を整える努力が求められます。そして、それが業界全体の信頼と安全性の向上にもつながっていくのです。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。