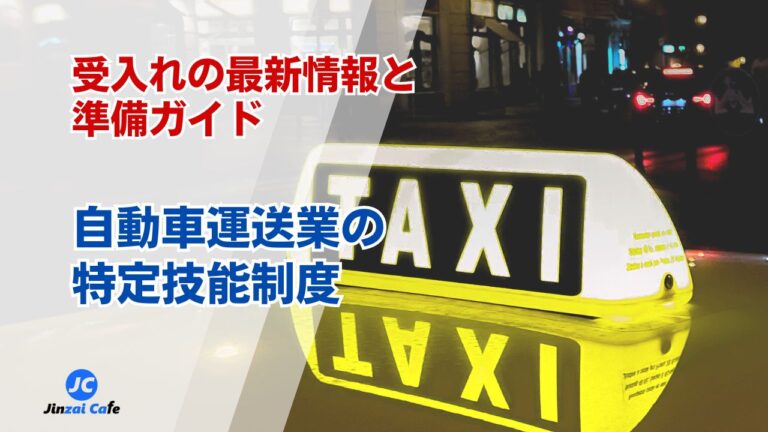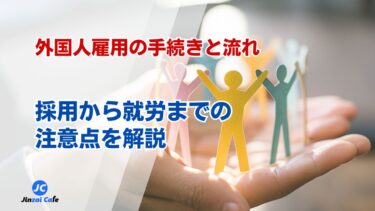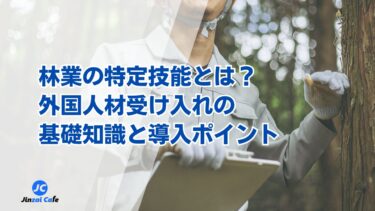「ドライバーが足りない」。
これは今や多くの運送業経営者が直面する切実な課題です。特に中小企業においては、既存の日本人労働者だけで業務を回すのが難しい状況が続いており、物流の安定性そのものが揺らいでいます。
こうした状況を受けて、2024年3月29日に政府で閣議決定され、同年4月19日に公式発表されたとおり、日本政府は「特定技能」の対象分野に新たに「自動車運送業」を追加しました。これにより、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を、合法的かつ体系的に受け入れる道が開かれたのです。
本記事では、この特定技能制度が自動車運送業にどのような影響を与えるのか、その詳細について、導入の流れや必要な準備、試験制度、定着支援までを一貫してわかりやすく解説します。外国人材の活用を検討している運送事業者の方にとって、実践的かつ信頼できる情報源となることを目指します。
自動車運送業における特定技能制度の概要

特定技能制度とは、深刻な人手不足が生じている分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が即戦力として働くことを認める在留資格制度です。2019年に創設され、もともとは介護や外食、建設などが対象でしたが、2024年3月29日に「自動車運送業分野」が新たに追加されました。これにより、トラック・バス・タクシーなどの運転業務においても、特定技能外国人の採用が可能になりました。制度の対象範囲や目的、導入の背景について理解を深めることが、円滑な受け入れの第一歩となります。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
出入国在留管理庁 自動車運送業分野
制度の成り立ちと目的
特定技能制度は、少子高齢化による労働力不足を背景に、日本国内で特に人材が不足している業種を支援する目的で導入されました。
「特定技能第1号」は、一定の試験に合格すれば、日本国内で最長5年間の就労が可能となる制度で、外国人は「技能実習」と異なり、即戦力人材として位置付けられています。
自動車運送業においても、業界全体の高齢化や若年層の離職率増加により、深刻なドライバー不足が発生しており、物流の安定確保の観点から、特定技能制度の対象に加えられたのです。
運送業が対象分野に追加された背景
国土交通省が発表した統計資料によると、2022年時点での貨物自動車運送業のドライバー平均年齢は48.9歳。10年後には多くのベテランドライバーが定年を迎えると予測され、後継者不足が明白になっています。
この状況に歯止めをかけるため、業界団体や自治体からの強い要望を受け、政府は特定技能の対象分野として「自動車運送業」を2024年に追加しました。バス・タクシー・トラックといった公共・物流インフラの維持を支えるための決断でした。
対象となる業務と職種一覧
特定技能「自動車運送業分野」における主な対象職種は、以下の3つに分類されます。
- 貨物自動車運転業務(トラック・配送ドライバーなど)
- 旅客自動車運転業務(路線バス・観光バスなど)
- タクシー運転業務(タクシー、ハイヤーなど)
これらの業種で、点検・日常メンテナンス・車両管理などの業務は、日本人運転者が通常職務の一環として行う範囲に限り、付随的に従事することが許されています。ただし、自動車整備や検査などの専門資格が必要な業務は対象外です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能1号自動車運送業分野の仕事内容
少子高齢化が加速する中、日本の多くの業界では深刻な人手不足に直面しています。特に介護、建設、外食、製造業など、現場の担い手が慢性的に不足しており、事業継続すら危ぶまれるケースも増えています。こうした背景のもと、2019年4月に新たに[…]
外国人材受入れの流れと準備事項

特定技能制度を活用して外国人ドライバーを採用するには、制度理解だけでなく、法的手続きや社内体制の整備が不可欠です。
この章では、実際に受け入れを進める中で、企業が準備すべきポイントをわかりやすく整理します。制度上の要件を満たすことはもちろん、外国人材が安心して働ける環境づくりも成功のカギとなります。
事業者に求められる体制整備
外国人材を雇用する事業者は、単に労働力を確保するだけでなく、就労と生活の両面で支援体制を整える必要があります。
たとえば、以下のような準備が求められます。
- 日本語が不自由な人への業務指導体制
- 住居や生活インフラの案内
- 労働時間・賃金の適正管理
- ハラスメント防止の方針明示
これらは、登録支援機関が提供する支援サービスに委託することも可能ですが、生活全般のサポートを含め、事業者としての責任は免れません。事前に役割分担を明確にし、受け入れ体制全体を社内で共有しておくことが重要です。
必要な書類と申請フローの確認
外国人を特定技能として雇用するには、「在留資格認定証明書交付申請」など、出入国在留管理庁への申請に係る提出書類が多数必要です。主な書類には次のようなものがあります。
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 企業概要書
- 特定技能所属機関届出書類
- 登録支援機関との委託契約書(該当する場合)
申請はオンラインでも可能ですが、書類の不備や記載漏れは審査遅延の原因となるため、必ず最新の申請要領をご覧ください。申請の詳細については、国土交通省や出入国在留管理庁の専用ページから、各種資料(PDF形式)をダウンロードして確認しましょう。
フィリピンからドライバーを受け入れる場合は、日本の在留資格申請とは別に、フィリピン政府へのMWO申請という特別な手続きが必要となるため、十分な準備期間が必要です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
協議会・登録支援機関との連携の重要性
特定技能制度では、分野ごとに設置された協議会が制度運用に関与しており、自動車運送業では、分野の健全な運用について協議を行う「自動車運送分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。
また、生活支援を外部に委託する場合は、出入国在留管理庁に認定された「登録支援機関」と契約する必要があります。
これら関係機関との連携は、受入れ企業が制度に則って円滑に採用を進めるための重要なパートナーとなります。申請前から事前に相談し、運用ルールや支援内容をすり合わせておくことで、トラブルの回避にもつながります。
参考:
国土交通省 自動車運送業分野特定技能協議会規約
出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
外国人材の雇用に興味はあるものの、「どんな手続きが必要なのか分からない」「法令違反が怖い」と感じている企業担当者は少なくありません。特に、これまで外国人を雇った経験がない企業にとっては、在留資格の種類や手続きの流れ、管理体制など、知らなけれ[…]
特定技能の試験と取得条件
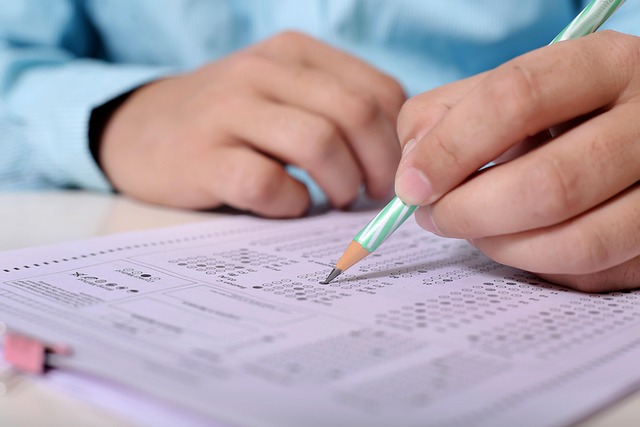
特定技能「自動車運送業分野」で外国人が働くためには、定められた技能試験と日本語能力試験に合格しなければなりません。
これらの試験は、外国人材が実務に必要な知識や言語力を有しているかを確認するもので、採用後のトラブルを防ぐためにも重要なプロセスです。
この章では、試験の種類や内容、実施機関、評価方法、試験合格後の流れについて具体的に解説します。
技能試験の内容と実施機関
「自動車運送業分野」の技能試験は、運転や運行管理、安全知識などを評価する筆記試験です。現在は、公益財団法人 運行管理者試験センターなどが実施主体として指定されています(2025年現在)。
試験内容は次の通りです。
- 安全運転の知識(道路交通法、危険予測など)
- 運送業務の基本(積荷、車両点検、運行管理)
- 職業倫理・マナー(接遇、安全意識など)
試験は日本語で実施されるため、読み書きの基礎能力も必要です。今後、国内外での受験会場拡大も予定されています。
参考:
公益財団法人運行管理者試験センター
一般財団法人日本海事協会(ClassNK) 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
日本語能力試験とその基準
日本語能力は、就労や日常生活に支障がないレベルであることが求められます。
具体的には、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上のいずれかに合格している必要があります。
| JLPT N4 | 日常的な場面で使われる基本的な日本語が理解できるレベル |
|---|---|
| JFT-Basic A2 | 生活に必要な日本語をある程度使いこなせるレベル(会話中心) |
運転業務では安全確保のため、日本語による指示理解が欠かせないため、試験合格だけでなく、実践的なコミュニケーション能力にも注目すべきです。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
評価試験合格後の流れと注意点
試験に合格した外国人材が実際に日本で働くためには、次の手続きを経る必要があります。
- 雇用契約の締結
- 特定技能1号の「在留資格認定証明書」申請
- 出入国在留管理庁による審査・発行
- 入国・在留カード取得後の就労開始
注意すべき点として、試験合格=自動的な就労許可ではないこと。企業側も「特定技能所属機関」として要件を満たしていなければ、雇用は成立しません。
また、受け入れ後の「支援計画の実施」も義務であり、これを怠ると在留資格の更新に影響する可能性があります。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
外国人運転者の採用と職場定着のポイント

外国人ドライバーの採用が制度上可能になったとはいえ、「採って終わり」では成功しません。
むしろ、採用後にいかにスムーズに業務に馴染み、長く働き続けてもらえるかが、特定技能制度の本当の価値を左右します。
この章では、採用直後から定着までのプロセスで重要となる支援や工夫、実務上のポイントについて解説します。
新任ドライバー向けの研修・OJT体制
採用直後の外国人ドライバーに対しては、業務に係る知識や日本特有の運転マナーなどを体系的に伝える研修を行い、スムーズな業務開始をサポートします。
たとえば:
- 道路交通法と安全運転に関する座学研修
- 実車を用いた運転OJT(同乗指導付き)
- 接客・積荷・顧客対応に関するロールプレイ
言葉の壁がある場合は、イラスト付きのマニュアルや翻訳アプリの併用も効果的です。初期段階での手厚い教育が、その後のミス防止と自信の醸成につながります。
文化・言語ギャップを乗り越える支援策
外国人材が日本の職場に馴染むうえで大きな障壁となるのが、「文化」と「言語」の違いです。
以下のような配慮が、定着率向上に直結します。
- 休日の取り方や宗教上の配慮(食事・礼拝など)
- わかりやすい日本語での声かけ(早口を避ける)
- 通訳やメンター社員の設置
- グループ懇親会や相談窓口の設置
会社側がこうしたサポートを通じて歩み寄る姿勢を見せることで、外国人ドライバーも安心して働くことができ、トラブルの予防にもなります。
定着率を高める職場づくりとは?
離職防止には、「働きやすさ」と「やりがい」の両方が重要です。特定技能の外国人ドライバーも、評価され、必要とされる職場であれば長く働きたいと考えています。
そのために有効なのが、
- スキルや成果に応じた昇給制度
- 母国語で読める社内掲示物や安全ルール
- 定期的な面談とフィードバック
- 社内イベントへの積極的な参加促進
こうした環境整備は、日本人社員にとってもプラスになり、結果として組織内全体の活性化にもつながります。
申請・管理体制の整備と注意点

特定技能制度に基づく外国人の受け入れは、採用して終わりではありません。
就労開始後も、適切な管理体制のもとで在留資格の維持や支援実施状況の報告など、継続的な運用が求められます。
ここでは、特定技能の申請から在留中の管理に至るまで、企業が押さえておくべき注意点と実務上のポイントを紹介します。
出入国在留管理庁への申請・報告義務
外国人ドライバーを雇用する企業は、出入国在留管理庁(通称:入管)に対し、複数の申請や届出を適切に行う必要があります。
- 就労前の「在留資格認定証明書」交付申請
- 就労開始後の「所属機関に関する届出」
- 支援実施状況の四半期ごとの報告
- 雇用終了時の離職届
これらの報告を怠ると、罰則だけでなく次回以降の受け入れにも支障が出る可能性があります。専任担当者の配置や業務マニュアルの整備が望ましいでしょう。
個人情報保護と雇用管理の実務ポイント
外国人従業員の在留カード番号やパスポート情報などは、個人情報保護法の観点からも厳重な管理が求められます。
情報漏洩を防ぐためには、以下の対応が重要です。
- 紙ベースの情報は鍵付き保管
- デジタルデータはアクセス制限付きで管理
- 社内教育による情報リテラシー向上
また、出勤簿や賃金台帳など、労務関連書類も3年間は保存が義務づけられており、外国人であっても日本人と同様の管理が求められます。
更新・変更・修了時の対応フロー
特定技能1号の在留資格は、原則1年ごとの更新が必要です。
更新に際しては、以下のような準備が必要となります。
- 継続雇用の意思確認
- 雇用契約書の更新と添付
- 支援計画の見直し
- 再申請書類の提出(更新は90日前から可能)
また、本人が別の企業への転職を希望する場合や、やむを得ず契約終了となる場合も、「変更届」や「修了届」などの提出が必要です。
最新の運用ルールや様式は、出入国在留管理庁の公式ページで必ず確認しましょう。
参考:出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
「少子高齢化による人手不足が深刻化し、事業継続が危うい…」「外国人材の雇用を検討しているが、就労ビザの申請は複雑で何から手をつければいいのかわからない」「不法就労のリスクや、雇用後の管理についても不安がある」もしあなたがこの[…]
【導入事例】業界団体の支援を活用した中小運送会社の挑戦
ここでは、特定技能制度の活用を検討する企業がどのように情報を集め、準備を進めたのか、ある中小運送会社の事例を通じてご紹介します。
課題:2024年問題とベテランの引退で窮地に
関東近郊で地域配送を手掛けるA運送株式会社は、2024年問題による労働時間規制の強化と、長年会社を支えてきたベテランドライバーの相次ぐ引退が重なり、配送キャパシティは限界に達していました。求人広告費を増やしても応募はほとんどなく、社長は事業の縮小も考え始めていました。
解決策:全日本トラック協会のセミナーが転機に
そんな中、社長が藁にもすがる思いで参加したのが、全日本トラック協会が主催する「特定技能制度活用セミナー」でした。そこで制度の概要や、国が作成した手引き、信頼できる登録支援機関の見つけ方など、具体的な情報を得ることができました。社長は「業界団体からの正確な情報がなければ、リスクを感じて一歩を踏み出せませんでした」と語ります。
セミナーをきっかけに登録支援機関と契約し、母国で中型トラックの運転経験が豊富な、ベトナム出身の特定技能人材2名の採用を決定しました。
成果:計画的な受け入れ準備と現場の活性化
A運送では、登録支援機関のアドバイスを受けながら、受け入れ準備を計画的に進めました。住居の手配はもちろん、運行管理者を中心にOJT計画を策定しました。現場の日本人ドライバーには、翻訳アプリの使い方や、文化の違いを尊重するコミュニケーションについて事前に説明会を開きました。
採用された2名は、3ヶ月間の同乗指導を経て、今では担当ルートを一人で任されるまでに成長しました。真面目で安全意識の高い仕事ぶりは、他の社員にも良い刺激となり、職場全体の雰囲気が明るくなりました。A運送は、今後も特定技能人材の採用を継続していく予定です。
まとめ|特定技能制度で物流業界の未来を切り拓く

深刻化する人手不足への対応として、自動車運送業における「特定技能制度」の導入は、極めて実用的かつ現実的な解決策となり得ます。
本記事では、制度の概要から受入れの準備、試験内容、採用後の運用・支援体制までを一貫して解説してきました。
重要なのは、「制度がある」ことではなく、「制度を正しく理解し、実行に移す」ことです。特定技能外国人の活用は、単なる労働力の補填ではなく、持続可能な経営への一歩とも言えます。
ドライバー不足に悩む企業にとって、いまがまさに動き出す好機。適切な支援と環境整備を行っていけば、外国人材は信頼できる戦力として、物流の未来を共に支えてくれるはずです。
外国人材の雇用に係る総合的なサポートをご希望でしたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。