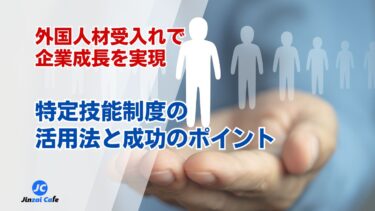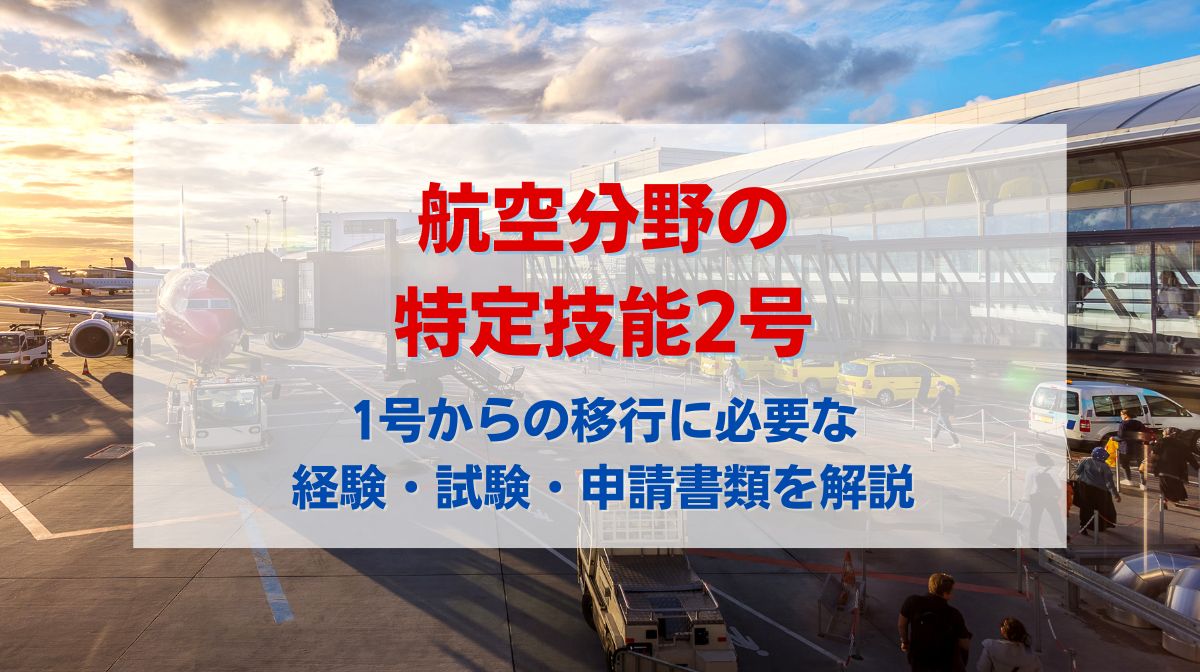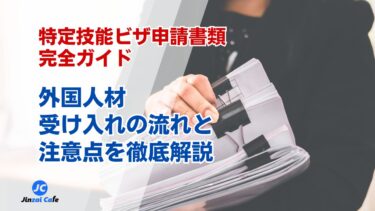近年、日本の航空分野では深刻な人材不足が課題となっています。航空機整備や空港でのグランドハンドリング業務は安全運航を支える基盤ですが、国内人材の確保が難しくなっているのが現状です。こうした状況を背景に、外国人材の活躍を促進するために導入されたのが「特定技能制度」です。
その中でも特定技能2号は、長期的な就労やキャリア形成を可能にする在留資格として注目されています。本記事では、航空分野における特定技能2号の仕組みや対象業務、取得条件、企業が知っておくべき注意点を解説します。制度を理解することで、受入れ体制の整備や採用計画に役立てられるでしょう。
特定技能制度の概要と航空分野の位置づけ

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を補うために2019年4月から始まった新しい在留資格制度です。14分野でスタートしましたが、その後の労働需要を調査した結果を踏まえて航空分野も対象に加わりました。航空業界は海外からの旅客需要も高く、国際的な競争が激しく、安全性や迅速性を求められるため、専門性を持つ人材の確保が急務となっています。
特定技能2号は特定技能1号よりも長期在留が可能であり、永住への道も開かれている点が特徴です。この記事では、この制度の枠組みと航空分野の位置づけという基礎を理解し、採用や活用の基盤知識を整理していきます。
特定技能制度の基本構造
特定技能制度は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の二段階構造です。1号では一定の技能と日本語能力を有する外国人が最長5年間働けます。これに対し2号は熟練した技能を持つと認められた人材が、在留期間の更新制限なく就労可能で、家族帯同も認められるのが大きな違いです。
制度全体は出入国在留管理庁が管理し、各分野ごとに国土交通省や関係協会が監督しています。航空分野の場合、整備や地上業務など高い専門性を伴う職種が対象となり、即戦力としての貢献が期待される仕組みです。なお、本制度は受入れ機関と外国人材との直接雇用が原則とされており、安定した労働環境の確保が図られています。
航空分野が追加された背景
航空分野が特定技能制度に追加された理由は、人材不足の深刻化と内外からの国際需要の高まりにあります。航空機整備士や空港スタッフは高度な安全管理を担いますが、日本国内では資格取得者の高齢化や人材流出が進み、新たな人材の確保が追いつかない状況です。
そのため国土交通省は、技能試験や研修制度を整備し、外国人材が日本の航空現場で活躍できる環境を整えました。特定技能2号の枠組みにより、経験豊富な外国人が長期的に雇用され、空港運営や航空安全の基盤を支える役割を果たすことが狙いとされています。
参考:
日本政府観光局 訪日外客数(2025 年 4 月推計値)
国土交通省 航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
1号と2号の違いと移行条件
特定技能1号と2号の最大の違いは「在留期間」と「技能水準」です。1号は最長約5年で、一定の試験合格が条件となります。2号は熟練技能が求められ、在留更新に上限がなく、将来的に永住申請も可能です。
移行には、技能実習制度とは異なり、長期的なキャリア形成を見据えたプロセスが用意されており、1号として一定期間勤務し、上記の条件を満たすために追加の技能評価試験や実務経験を経て認められるプロセスが必要となります。
航空分野では、整備士やハンドリング業務で実務を積んだ人材が対象です。この仕組みにより、外国人材が短期労働力にとどまらず、組織の中核人材へと成長できる道が用意されているのです。
日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]
航空分野における対象業務と必要技能

航空分野の特定技能2号で対象となる業務は、大きく「航空機整備」と「空港グランドハンドリング」の2つの区分に分けられます。どちらも安全運航に直結する専門的な仕事であり、即戦力としての高度な技能が期待されます。
企業は採用にあたり、それぞれの業務範囲や求められる技能水準を正しく理解し、適切に人材を配置することが重要です。ここでは、各区分で定められている具体的な業務内容と、それに付随する関連業務について整理して解説していきます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容(航空)
航空機整備区分で求められる技能と資格
航空機整備区分では、航空機の機体や装備品等の整備業務が中心となります。特定技能2号の人材には、自らの判断で業務を遂行できる熟練した技能が求められます。
主な業務には、空港に到着した航空機に対して次のフライトまでに行う「運航整備」、通常1年から1年半毎に約1週間から2週間かけて機体の隅々まで点検する「機体整備」、そして航空機から取り下ろされた脚部や計器類、エンジン(原動機)等を整備する「装備品・原動機整備」が含まれます。これらの業務を的確に行うため、自身の技能を証明する整備士資格や豊富な実務経験が不可欠です。
空港グランドハンドリング区分の業務範囲
空港グランドハンドリング区分では、空港の地上支援業務全般が対象となります。特定技能2号の人材に期待されるのは、単なる作業員としてではなく、指導者やチームリーダーとして工程を管理しながら業務を遂行する役割です。具体的には、航空機の地上走行を支援する業務、お客様の手荷物や貨物を取り扱う業務、それらを航空機へ搭降載する業務などが含まれます。
日本航空のような大手航空会社の事業を支えるのも、こうした地上スタッフの働きがあってこそです。空港全体のオペレーションを円滑に進めるため、正確な判断力とチームをまとめるリーダーシップが重視される分野です。
清掃・貨物取扱いなど周辺業務
上記の専門業務以外にも、特定技能では関連する周辺業務への従事も想定されています。例えば、空港グランドハンドリング区分には、航空機内外の清掃整備業務も主要な業務として含まれています。
さらに両区分に共通して、安全で効率的な作業環境を維持するための「作業場所の整理整頓や清掃」、各種手続きに伴う「事務作業」、また積雪地域においては「作業場所の除雪」といった業務も担うことがあります。これらの業務も、一見補助的に見えますが、航空輸送全体の品質と安全性を支える重要な役割を果たします。
人手不足が深刻な日本の航空業界で注目される「特定技能2号」。本記事では、特定技能1号との違いや、2号への移行に必要な試験…
在留資格と試験制度の詳細
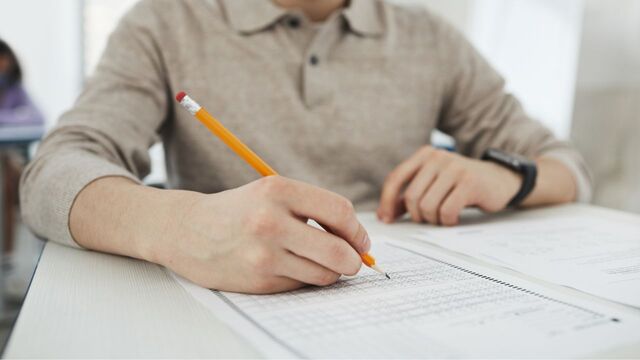
特定技能2号の在留資格を取得するには、制度で定められた条件を満たす必要があります。特に航空分野では、高度な実務経験と技能評価試験への合格が必須です。また、日本語能力の確認も重要で、業務上の安全や同僚との円滑なコミュニケーションに直結します。
企業側は、採用時に必要要件を十分理解し、候補者が条件を満たしているかを確認する責任を負います。ここでは、在留資格に係る取得の流れ、技能試験の内容、日本語要件の3点に分けて解説します。
在留資格「特定技能2号」の取得条件
特定技能2号を取得するには、まず特定技能1号で一定期間従事し、実務経験を積むことが前提となります。そのうえで、航空分野特有の技能評価試験に合格する必要があります。
在留期間は更新制限がなく、家族帯同も認められるため、長期的なキャリア形成が可能です。企業にとっては即戦力を安定的に確保できる利点がありますが、雇用契約や労働環境が適切であるかを提出する書類で示さなければなりません。事業者は条件を正しく理解し、雇用体制を整備しておくことが成功の第一歩になるでしょう。
航空分野における技能試験と評価方法
航空分野の技能試験は、整備・グランドハンドリングなど対象業務ごとに区分され、実技と筆記で評価されます。実技テストでは、工具や機材を使った作業手順、安全確認、緊急時対応の正確さが問われます。筆記では、航空法令や機材の知識、作業工程に関する理解度がチェックされます。
評価は公益社団法人や関係協会が実施し、基準を満たした者のみが合格できます。実務経験がある外国人材にとっては、知識の整理と実践力が問われる試験です。企業側は候補者に対して事前学習や模擬試験を支援することで、採用活動を円滑に進められるでしょう。
参考:
国土交通省 「航空分野(航空機整備区分)特定技能2号評価試験」試験実施要領
国土交通省 「航空分野(空港グランドハンドリング区分)特定技能2号評価試験」試験実施要領
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
日本語能力の要件と確認方法
航空分野での特定技能には、日本語能力も欠かせません。安全に直結する業務であるため、指示や注意喚起を正確に理解できるレベルが必要です。多くの場合、日本語能力試験(JLPT)N4以上が目安とされますが、業務内容によってはそれ以下でも特定の条件に該当すれば認められる場合があります。
確認方法としては、公式の日本語試験結果に加え、面接や現場シミュレーションでの応答を通じた評価も有効です。特にグランドハンドリングでは即時対応が求められるため、指示の誤解を防ぐ訓練が欠かせません。企業は採用段階で十分に言語スキルを確認し、必要に応じて教育体制を整備することが大切です。
参考:日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
日本の多くの会社が直面している最大の課題のひとつは、人手不足です。特に介護や製造、建設などの特定技能分野では、外国人労働者の採用が急速に拡大しており、その事業規模も大きくなっています。しかし、その一方で職場における日本語でのコミュニケーショ[…]
企業による受入れの流れと注意点

外国人材を航空分野で受け入れるには、法令に基づく適切な手続きを踏むことが求められます。受入れ計画を作成し、出入国在留管理庁への申請や関連機関との確認が必要です。
また、雇用後も労働条件や生活支援を適切に提供しなければなりません。特に航空業務は安全に直結するため、教育・研修の充実が不可欠です。ここでは、企業が実際に行う流れと注意点を3つの視点から整理します。
受入れ計画と出入国在留管理庁への申請
受入れを開始するには、まず雇用計画を作成し、必要な資料や書類を揃えて出入国在留管理庁へ申請します。計画書には、業務内容・配置予定の部署・労働条件・教育体制などを明記する必要があります。
申請の際には、国土交通省が設置する協議会と事前に協議を行い、その承認を受けることが必要です。この協議会は関係省庁や事業者団体の構成員からなり、業界全体の秩序を保つ役割を担います。
また、これらの複雑な手続きや支援計画の実施について、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に業務を委託することも可能です。申請に用いる資料に不備があれば認定が遅れるため、準備段階から国土交通省や関係機関のガイドラインを参考にし、法令や制度を十分に確認することが重要です。
参考:国土交通省 航空分野特定技能協議会の開催状況・協議会からのお知らせ
航空分野の特定技能2号について解説します。在留資格2号の対象業務(グランドハンドリング、航空機整備)、1号との違い、試験…
受入れ企業に求められる体制整備
外国人材を受け入れる会社には、単なる採用だけでなく、長期的に働ける環境を提供する責任があります。航空分野は専門性が高いため、現場での安全教育や資格取得支援が求められます。
また、企業への所属意識を高めるためにも、適切な社会保険への加入はもちろん、住居や宿泊場所の確保といった生活支援、相談窓口の設置など、生活基盤を整える取り組みも不可欠です。特に文化や言語の違いから生じる摩擦を防ぐため、自社内研修や多文化共生の仕組みを導入し、日本人従業員との間で良好な関係を築くことが望まれます。
トラブル防止のための管理とサポート
航空分野での受入れでは、労働条件や職場環境に起因するトラブルを防ぐことが重要です。たとえば、残業時間や休日取得が不適切であれば、早期離職や法的問題につながりかねません。そのため、雇用契約内容を明確にし、本人が希望するキャリアパス等について定期的な面談で状況を確認することが有効です。
また、生活サポートとして日本語学習機会を提供する企業も増えています。トラブル防止は「予防的管理」が鍵であり、外国人材との信頼関係を築くうえでも欠かせない要素です。サポート体制の充実が、安全で持続的な雇用につながるでしょう。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
航空分野での外国人材活用の展望

航空業界では、外国人材の受入れが現場の即戦力確保だけでなく、企業の営業基盤を支える中長期的な人材戦略にも直結しています。特定技能2号により熟練した人材が定着できることで、企業は人手不足を補うと同時に、技術やノウハウの継承にもつなげられます。
さらに、日本人従業員との協働が進むことで、多文化共生や国際的な対応力も高まります。ここでは、活用の具体像を事例・協働・将来展望の観点から整理して紹介します。
成田空港におけるグランドハンドリング業務での成功事例
成田空港を拠点とする地上支援現場では、多国籍の特定技能人材がグランドハンドリング業務で力を発揮しています。手荷物や貨物の搭載、航空機誘導、プッシュバックなど高度な作業を担い、日本人社員と同等の条件で勤務しています。
特定技能1号から経験を積み、2025年には2号試験合格者も誕生しました。2号取得により、これまでの実績を活かしてリーダーとして後輩指導や工程管理を担えるようになり、安全性とサービス品質の向上に寄与しています。
語学力を活かした外国人旅客対応も評価され、定着率の高さと組織活性化が成果として示されており、このような成功事例は全国の空港でその数を増やしています。
日本人従業員との協働と教育
外国人材が現場で力を発揮するには、日本人従業員との協働が不可欠です。文化や言語の違いがある中で、双方が理解し合える環境をつくることが大切です。例えば、経験豊富な日本人スタッフの指導の下で、研修で安全規則や業務手順を分かりやすく共有したり、実際に現場で行ってきた作業を想定したチーム単位でのロールプレイを行うことで、誤解やトラブルを防げます。
また、日本人スタッフにとっても、多様な背景を持つ人材と働く経験は貴重で、国際感覚やマネジメント力を養う機会になります。教育や研修を修了した人材同士の協働が、航空分野全体の安全性と効率性を高める鍵となるでしょう。
将来的な制度変更や拡大の可能性
特定技能2号の制度は、社会情勢や業界のニーズに応じて見直される可能性があります。航空分野では、今後さらに対象業務が拡大することや、試験内容の変更が行われることも考えられます。例えば、現在議論されているように、6月の制度改定で新たな職種が追加されるといった動きも想定されるところです。
さらに、国際的な人材獲得競争が激化するなかで、日本が制度をいかに柔軟に運用できるかどうかが、企業にとって大きな影響を及ぼします。上記のような制度変更を正しく把握し、将来を見据えた採用戦略を検討するためにも、公式サイトのサイトマップを検索する等の継続的な情報収集が成功のポイントです。
日本社会は今、かつてない規模での外国人材の受入れが進んでいます。政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、多くの企業が外国人材の活用を検討しています。しかし、単に人材を受け入れ[…]
まとめ|航空分野の特定技能2号を活用するには

航空分野の特定技能2号は、人材不足を補うだけでなく、長期的な人材育成や国際競争力の強化につながる制度です。整備やグランドハンドリングといった専門業務を担える即戦力を確保できる点は、企業にとって大きな魅力でしょう。
一方で、受入れには法令順守や生活支援、教育体制の整備が不可欠です。制度の特性を理解し、実務に活かす準備を整えることで、外国人材と日本人従業員が協力し合える環境を築けます。今後の制度変更も視野に入れ、継続的な情報収集と体制強化を行うことが、成功への近道です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。