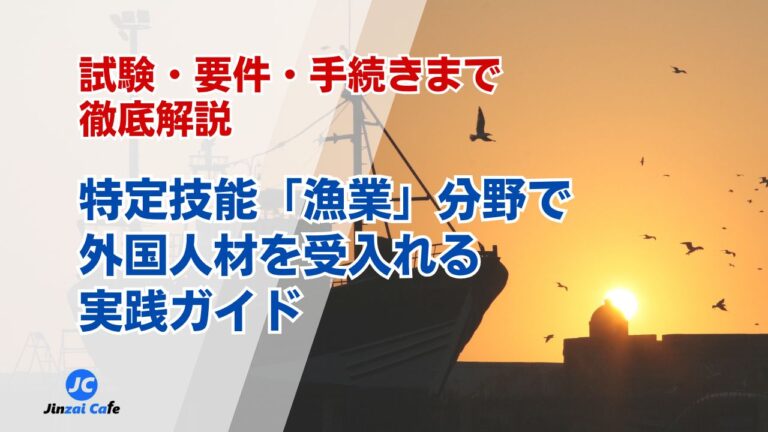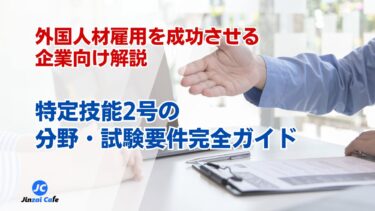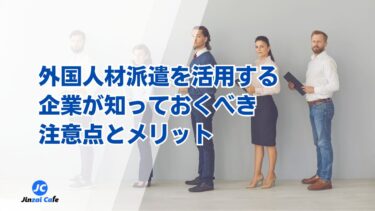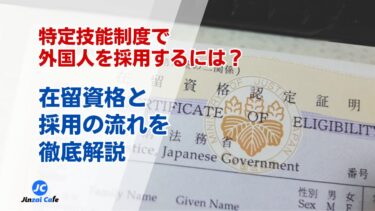日本の漁業界では、高齢化の進行と若年層の離職により、深刻な人手不足が続いています。水産庁の調査によると、漁業就業者数は2003年の約24万人から2023年には約12万人まで減少しており、この傾向は今後さらに加速すると予測されています。現在、特に沿岸漁業や養殖業では、作業の担い手確保が喫緊の課題となっているのが現状です。
こうした状況を受けて2019年4月に設立された特定技能制度は、漁業分野においても外国人材の受入れを可能にしました。この制度を活用することで、技能を持つ外国人労働者を最長5年間雇用でき、人手不足の解決と事業の継続性確保が期待できます。
本記事では、特定技能「漁業」分野での外国人材受入れを検討されている経営者の皆様に向けて、制度の概要から具体的な手続き、受入れ後の管理まで、実務に必要な情報を詳しく解説していきます。適切な準備と理解により、貴社の人材確保戦略の一助となれば幸いです。
特定技能「漁業」分野の基本概要と制度の仕組み

特定技能制度における漁業分野は、従来の技能実習制度との大きな違いとして、即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。この制度を理解するためには、まず対象となる業務範囲と基本的な要件を把握することが重要でしょう。
漁業分野での特定技能制度は、日本の水産業界が直面する構造的な人手不足に対応するため、一定の技能水準を満たした外国人材に就労機会を提供する仕組みです。受入れ上限は2019年度から2024年度までの5年間で最大9,000人とされており、その後は2029年度までの第2期で最大17,000人への拡大が計画されています。段階的な規模拡大を通じて、安定した労働力の供給を目指しています。
参考:
水産庁 令和6年度 水産白書概要
出入国在留管理庁 特定技能「漁業分野」
漁業分野で受入れ可能な業務内容
特定技能「漁業」分野では、主に「漁業」と「養殖業」の2つの区分で外国人材を受入れることができます。
漁業(漁労)においては、漁具の設置・操作・修理や補修、水産動植物の探索・漁獲(捕獲)、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保などが対象業務となります。具体的には、定置網や刺網などの漁具設置作業、魚群探知機を使った探索業務、漁獲後の選別・処理作業などが含まれるのです。これらの仕事は漁船での作業が中心となるため、海上での安全管理に関する知識も必要とされます。
一方、養殖業では、養殖資材の設置・管理・修理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、養殖場の維持・管理などが対象です。陸上養殖施設での作業も多く、魚類の給餌管理、水質管理、収穫時の選別作業などが主な業務内容の一つとなります。
在留資格「特定技能第1号」の基本要件
特定技能第1号の在留資格を取得するには、「技能水準」と「日本語能力水準」の両方において、国が定める基準を満たす必要があります。
これらはそれぞれ所定の試験に合格することで証明されますが、詳細は後述の「試験制度と技能測定の詳細解説」で詳しく説明します。
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される特例措置があります。
養殖業と漁船漁業の区分と特徴
特定技能「漁業」分野では、養殖業と漁船漁業それぞれに特有の要件と特徴があります。
養殖業では、陸上や海面での養殖施設において、魚類・貝類・海藻類などの育成から収穫まで一連の作業に従事します。作業環境は比較的安定しており、定期的な給餌や水質管理、施設のメンテナンスなどが主な業務となるでしょう。季節性はあるものの、年間を通じて継続的な作業が必要で、長期雇用に適した分野といえます。
漁船漁業の場合は、沿岸漁業や沖合漁業での漁獲作業が中心です。天候や漁況に左右されやすく、早朝からの作業や夜間操業もあるため、より過酷な労働環境となることが一般的です。その分、高い技能と体力が求められますが、漁獲高によって収入が変動する可能性もあります。
試験制度と技能測定の詳細解説

特定技能制度において、外国人材が適切な技能を有していることを確認するための試験制度は、制度の根幹をなす重要な仕組みです。上記の区分で働くためには、漁業分野では専門的な知識と実践的な技能の両方が求められるため、試験内容も多岐にわたります。
試験制度の理解は、受入れ企業にとっても重要な意味を持ちます。なぜなら、どのような技能レベルの人材を受入れることができるのか、また受入れ後にどの程度の指導が必要になるのかを事前に把握できるからです。
漁業技能測定試験の内容と実施機関
漁業技能測定試験は、一般社団法人大日本水産会が指定された実施機関として運営しており、学科試験と実技試験の2部構成で実施されます。
学科試験では、漁業および養殖業に関する基礎知識、安全衛生、日本の漁業関連法令、環境保護などの分野から出題されます。具体的には、漁具の種類と特徴、魚類の生態、海洋環境、労働安全衛生法に関する基礎事項などが含まれます。試験時間は50分前後で、真偽式や多肢選択式のCBT(コンピュータによる試験)形式で行われ、合格基準は正答率おおむね65%以上とされています。
実技試験は試験区分(漁業または養殖業)に応じて内容が異なり、漁業区分では漁具の取り扱いやロープワーク、魚の選別・処理などの実技が求められます。一方、養殖業区分では養殖施設の管理、給餌作業、収穫作業などが評価対象です。試験時間はおおむね20分から30分程度で、実際の作業を模擬した課題に取り組む形式となっています。
試験は年に3回から4回程度、国内外で開催され、受験料は学科・実技合わせて約8,000円(国内の場合)です。
日本語能力試験の要件と水準
特定技能1号での就労には、一定レベルの日本語能力が必要とされており、これは職場でのコミュニケーションを円滑に行うための重要な要件です。
日本語能力の証明方法として、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格証明書の提出が求められます。JFT-Basicは特定技能制度のために新設された試験で、日常生活で必要な日本語能力を測定します。一方、JLPT N4は従来から実施されている試験で、基本的な日本語を理解できるレベルとされています。
実際の職場では、作業指示の理解、安全に関する注意事項の把握、同僚との基本的なコミュニケーションなどができる程度の日本語力が必要です。特に漁業分野では安全管理が極めて重要であるため、緊急時の指示や注意喚起を理解できる日本語能力は不可欠といえるでしょう。
受入れ企業としては、採用予定者の日本語レベルを事前に把握し、必要に応じて追加的な日本語学習支援を検討することが重要です。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
技能実習からの移行パターン
技能実習制度から特定技能への移行は、多くの漁業事業者にとって現実的な選択肢となっています。
技能実習2号を良好に修了した外国人については、漁業技能測定試験と日本語能力試験が免除される特例措置が設けられています。「良好な修了」とは、技能実習計画に従って技能実習を行い、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験に合格していることを指します。
この移行パターンのメリットは、すでに一定期間日本で働いた経験があり、基本的な作業技能と日本語能力を身につけていることです。また、職場環境や日本の労働慣行にも慣れているため、特定技能として受入れた後も比較的スムーズに業務を継続できる可能性が高いでしょう。
ただし、技能実習生として受入れていた企業が、そのまま特定技能として継続雇用する場合には、雇用条件や待遇の見直しが必要になることがあります。特定技能では日本人と同等以上の報酬支払いが求められるため、給与水準の調整が必要になる場合もあります。
外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]
外国人材受入れ機関の要件と手続き

特定技能外国人を受け入れる企業は、「受入れ機関」として様々な要件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。これらの要件は、外国人材の適切な処遇と円滑な就労を確保するために設けられており、違反すると受入れ停止などの重い処分を受ける可能性があります。
受入れ準備の段階で要件を正しく理解し、必要な体制を整備することは、その後の円滑な外国人材活用の基盤となります。また、継続的な要件遵守により、長期的に安定した人材確保が可能になるでしょう。
受入れ機関が満たすべき基準と注意点
受入れ機関には、財政的基盤、適切な雇用実績、法令遵守などの厳格な基準が設けられています。自社がこれらの基準を満たしているか、事前の確認が不可欠です。
まず財政的基盤について、直近2年間の決算において債務超過でないこと、適切な事業規模を維持していることなどが求められます。また、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険の適用事業所であること、労働関係法令及び関連要領を遵守していることも必須要件です。
人的な要件としては、自社に所属する常勤職員で、外国人材への適切な指導ができる者を配置することが求められます。この職員は5年以上の実務経験を有し、外国人材の指導・教育に責任を持てる人材である必要があります。漁業分野では、海上での安全管理や漁具の取り扱いなど専門的な指導が必要なため、経験豊富な指導者の存在は特に重要です。
事業所の設備面では、適切な作業環境の確保、安全設備の整備、外国人材が使用する宿舎の確保なども要件となります。宿舎については、プライバシーに配慮した個室の提供、適切な共用設備の設置などが求められるでしょう。
協議会への加入と水産庁との連携
漁業分野で特定技能外国人を受入れる機関は、「漁業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。
この協議会は水産庁が事務局を務め、受入れ機関、監理団体、関係行政機関などで構成されています。協議会の目的は、制度の適正な運用確保のための協議や情報共有、課題解決などであり、四半期ごとの定期的な報告や研修会への参加が求められます。
協議会への加入手続きは、特定技能外国人の受入れ開始後4か月以内に行う必要があります。加入に際しては、事業概要、受入れ予定人数、支援体制などを記載した申請書の提出が必要です。また、年会費の支払いや定期的な活動報告も義務付けられています。
水産庁との連携では、受入れ状況の四半期報告、問題が発生した場合の速やかな報告、指導があった場合の改善報告などが求められます。これらの報告は、制度全体の適正な運用を確保するために重要な役割を果たしています。
支援計画の作成と登録支援機関の活用
受入れ機関は、特定技能外国人に対する支援計画を作成し、適切な支援を実施する義務があります。
支援計画には、事前ガイダンス、在留資格認定証明書交付後の手続き支援、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援(これに係る手続きのサポートも含む)、定期的な面談などが含まれます。これらの支援は、外国人材が日本での生活と就労を円滑に行うために不可欠な要素です。
特に漁業分野では、海上での作業に伴う特殊な安全管理、季節による作業内容の変化、地域コミュニティとの関係構築などについても、きめ細やかな支援が求められます。
支援計画の実施については、受入れ機関が自ら行うか、登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は出入国在留管理庁から認定を受けた専門機関で、外国人材の支援業務に精通しているため、特に初回受入れの場合には活用を検討すべきでしょう。委託費用は発生しますが、こうした専門機関の協力を得ることで、適切な支援体制の確保と事務負担の軽減という観点から、多くの受入れ機関で活用されています。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
雇用形態と労働条件の設定ポイント

特定技能制度における雇用条件の設定は、単なる法的要件の充足にとどまらず、外国人材の定着率や生産性向上に直結する重要な要素です。適切な条件設定により、優秀な人材の長期雇用が可能になり、結果的に事業の安定化と発展につながります。
漁業分野特有の労働環境や季節性を考慮しつつ、日本人労働者と同等以上の処遇を確保することが、制度の趣旨に沿った運用といえるでしょう。
給与水準と日本人との同等性確保
特定技能制度では、外国人材に対して日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが法的に義務付けられています。
給与水準の設定にあたっては、同一地域・同一職種の日本人労働者の賃金水準を十分に調査し、それを下回らない金額を設定する必要があります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や各都道府県の最低賃金などを参考に、適切な水準を判断することが重要です。
漁業分野では、基本給に加えて漁獲量に応じた歩合制を導入している事業所も多くあります。この場合、外国人材についても同様の歩合制を適用し、漁況の良い時期には相応の収入を得られるような仕組みを構築することが望ましいでしょう。ただし、漁況不良時の最低保証額についても、法定最低賃金を上回る水準で設定することが求められます。
賞与や各種手当についても、日本人労働者に支給している場合は、外国人材にも同等の支給を行う必要があります。これには通勤手当、住宅手当、危険作業手当なども含まれるため、雇用契約書には支給条件を明確に記載することが重要です。
労働時間と安全管理の留意点
漁業は天候や潮汐に左右される産業特性があるため、労働時間の管理には特別な配慮が必要です。
労働基準法では、1日8時間、週40時間が法定労働時間とされていますが、漁業については一定の特例措置があります。ただし、特定技能外国人についても日本人労働者と同様の労働時間管理を行い、時間外労働が発生する場合は適切な割増賃金の支払いが必要です。
特に重要なのが海上作業における安全管理です。外国人材に対しては、入職時に海上での安全規則、緊急時の対応方法、救命胴衣の着用方法などについて、理解できるまで十分な指導を行わなければなりません。また、定期的な安全教育の実施、安全設備の点検・整備、気象情報の共有なども欠かせません。
労働災害が発生した場合の対応についても、事前に明確な手順を定めておく必要があります。特に外国人材の場合は、言語の問題もあるため、緊急連絡先の多言語表示、通訳の手配、医療機関との連携などを事前に準備しておくことが重要です。
参考:
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
首相官邸政策会議 農漁業において労働者を雇う場合の労働基準法の適用について
派遣労働の制限と直接雇用の重要性
特定技能制度では、外国人材の適切な処遇を確保するため、労働者派遣は原則として認められていません。
受入れ機関は、特定技能外国人と直接雇用契約を締結し、自らの事業所で就労させることが基本原則です。これは、派遣労働では雇用責任が曖昧になりやすく、適切な労働条件の確保や支援の実施が困難になる可能性があるためです。農業分野など一部の特例を除き、漁業分野では直接雇用が原則です。
このような場合でも、一時的な作業量の減少を理由とした安易な雇用調整は避け、年間を通じた安定的な雇用を維持することが求められます。作業量が少ない時期には、漁具の修理・整備、施設のメンテナンス、技能向上のための研修などを実施し、継続的な雇用を確保することが重要です。
直接雇用により、受入れ機関は外国人材の能力や適性を直接把握できるため、より効果的な人材育成や配置が可能になります。また、外国人材にとっても安定した雇用環境が確保され、長期的なキャリア形成を図ることができるのです。
日本企業の多くが直面している人手不足問題。特に製造業や介護業界、建設業などでは、慢性的な労働力不足が深刻化しています。そんな中、注目を集めているのが外国人材の活用です。しかし、外国人材の派遣を検討する際、「在留資格の確認はどうすれば[…]
受入れ後の管理と支援体制

特定技能外国人の受入れは、採用がゴールではありません。むしろ受入れ後の適切な管理と継続的な支援こそが、制度活用の成否を分ける重要なポイントといえるでしょう。
効果的な支援体制を構築することで、外国人材の早期戦力化、定着率の向上、そして最終的には事業の持続的な発展につなげることが可能です。また、適切な管理により法令違反のリスクを回避し、長期的に制度を活用し続けることができます。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
生活支援と日本語学習のサポート
外国人材が日本での生活に早期に適応できるよう、包括的な生活支援体制の構築が不可欠です。
住居の確保については、単に部屋を提供するだけでなく、生活に必要な家電製品の設置、インターネット環境の整備、近隣施設(病院、買い物施設、公共交通機関など)の案内なども重要な支援項目となります。特に地方の漁業地域では、都市部と比べて生活インフラが限定的な場合があるため、より丁寧なサポートが必要です。
金融機関での口座開設、携帯電話の契約、各種保険の加入手続きなどの行政手続きについても、初期段階での支援が必要です。これらの手続きは日本人にとっても煩雑な場合があるため、外国人材にとっては大きな負担となる可能性があります。
日本語学習については、業務に必要な専門用語や安全に関する指示を理解できるよう、継続的な学習機会を提供することが重要です。一般的な日本語能力の向上に加え、漁業特有の用語や表現についても体系的に学習できる環境を整備しましょう。地域の日本語教室への参加支援や、職場での日本語指導時間の設定なども効果的です。
技能向上と長期雇用への道筋
特定技能制度を効果的に活用するためには、外国人材の継続的な技能向上を図ることが重要です。
入職時の基本的な技能から、より高度で専門的な技能へのステップアップを支援することで、外国人材のモチベーション向上と定着率改善を実現できます。具体的には、新しい漁法の習得、機械操作技能の向上、品質管理手法の学習などが考えられるでしょう。
技能向上の成果については、適切に評価し処遇に反映させることも大切です。技能レベルに応じた昇給制度の導入、責任ある業務への登用、リーダー的役割の付与などにより、外国人材の成長実感と将来への希望を醸成できます。
長期雇用に向けては、5年間の在留期間終了後の選択肢についても早期から情報提供を行うことが望ましいでしょう。特定技能2号への移行可能性(在留資格変更許可申請が必要となります)、永住権取得の道筋、帰国後のキャリア活用方法などについて、透明性の高い情報提供を行うことで、外国人材の将来設計を支援できます。
転職防止と定着率向上の施策
外国人材の転職は、受入れ機関にとって大きな損失となるため、効果的な定着率向上施策の実施が重要です。
職場環境の改善については、外国人材の意見や要望を定期的に聴取し、可能な限り反映させることが基本となります。月1回程度の個別面談を実施し、業務上の悩みや生活上の困りごとについて相談できる体制を整備しましょう。また、日本人従業員との良好な関係構築を促進するため、歓迎会や懇親会などの交流機会の設定も効果的です。
待遇面での配慮も重要な要素です。法定要件を満たすだけでなく、地域相場を上回る給与水準の設定、福利厚生の充実、有給休暇の取得促進などにより、他社との差別化を図ることができます。特に漁業分野では危険を伴う作業もあるため、安全手当や健康診断の充実なども検討すべきでしょう。
キャリア開発の機会提供も定着率向上に寄与します。外部研修への参加機会、資格取得支援、他部署での経験機会の提供などにより、外国人材の成長を支援し、やりがいを感じられる環境を構築することが重要です。
近年、日本では多くの産業分野で慢性的な人手不足が深刻な状況となっており、とりわけ介護・建設・農業・外食産業・製造業などの現場では、必要な人材を確保できないことが経営上のリスクとなっています。少子高齢化による労働人口の減少が背景にあることは言[…]
まとめ|特定技能漁業分野での人材確保を成功させるために

本記事では、特定技能「漁業」分野での外国人材受入れについて、制度の基本的な仕組みから具体的な手続き、受入れ後の管理まで幅広く解説してまいりました。
漁業界が直面する深刻な人手不足を解決するため、特定技能制度は有効な選択肢となり得ます。しかし、制度を成功させるには適切な理解と準備、そして継続的な支援体制の構築が不可欠です。試験制度や受入れ要件を正しく理解し、外国人材にとって魅力的な職場環境を整備することで、優秀な人材の確保と定着が可能になるでしょう。
特に重要なのは、単なる労働力の確保ではなく、外国人材を新たなパートナーとして位置づけ、共に成長していく姿勢です。適切な処遇と支援により、外国人材の能力を最大限に活用し、事業の発展につなげていくことが求められます。
制度活用にあたっては、法令遵守はもちろんのこと、外国人材の人権と尊厳を尊重し、互いにとってメリットのある関係を構築することが重要です。そのためには、継続的な情報収集と制度理解、そして柔軟な対応姿勢が必要となるでしょう。関連する公的機関のウェブサイトは情報が多岐にわたるため、サイトマップを活用して必要な情報を効率的に見つけることをお勧めします。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。