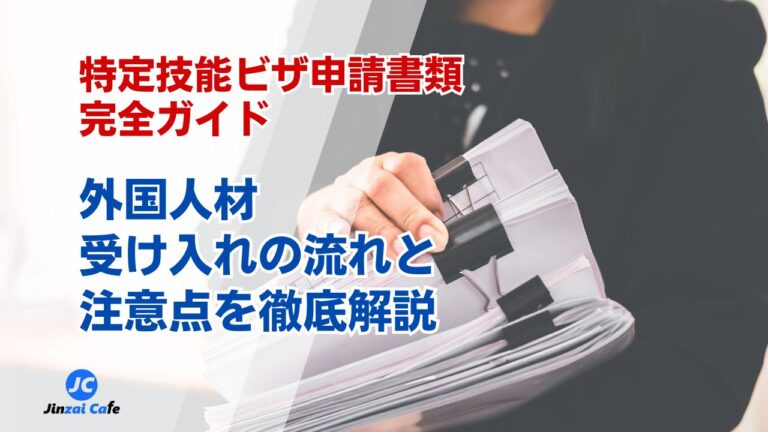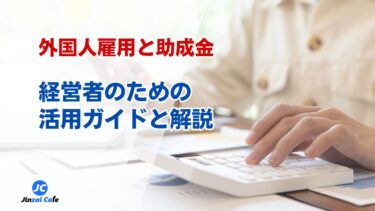人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れを正確に把握することは簡単ではありません。
申請書類の不備や提出漏れは、審査期間の延長や許可申請の却下につながる可能性があります。企業にとって外国人材の受け入れ時期の遅れは、人材確保計画全体に大きな影響を与えかねません。この記事では、特定技能ビザ申請に必要な書類を体系的に整理し、企業の人事担当者が安心して外国人材の受け入れを進められるよう、実務的な観点から詳しく解説いたします。
特定技能制度の基本概要と在留資格の仕組み

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持った外国人を国内に受け入れるのを目的に、2019年にスタートした在留資格制度です。この制度を利用することで、外国人は特定技能1号もしくは2号の在留資格を得て、日本国内で就労することが可能となります。
特定技能1号の場合、日本に滞在できる期間は合計で最大5年と定められており、原則として、家族を日本に呼び寄せることは許可されていません。一方、特定技能2号は在留期間の更新に制限がなく、要件を満たせば配偶者や子供といった家族を呼び寄せることも許可されており、より安定した就労環境を提供できます。
現在、16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が対象となっており、各分野で受け入れ見込み数の上限が設定されています。
特定技能1号と2号の違いと対象分野
特定技能1号と2号は、それぞれ特徴が異なります。1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験が求められる仕事に携わる外国人のための在留資格です。滞在できる期間は1年・6か月・4か月のいずれかで、都度更新を行う必要があり、日本に滞在できるのは通算5年間までです。技能水準としては、即戦力となるために必要な知識や経験を要求されますが、熟練した技能までは求められません。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を対象としています。1号と異なり、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば永続的に日本に滞在することも可能です。また、配偶者や子などの家族の帯同も認められており、より安定した就労環境を提供できます。2025年11月現在、2号は建設、造船・舶用工業、介護、農業、飲食料品製造業など11分野で受け入れが可能です。
受け入れ機関としての企業の役割と責任
特定技能の資格を持つ外国人を雇用する企業は、出入国在留管理庁から「受け入れ機関」として認定される必要があります。受け入れ機関は単に雇用するだけでなく、外国人が日本で安定的に働き、生活できるよう包括的な支援を提供する責任を負います。
具体的には、外国人との雇用契約を適正に結び、日本人従業員と同水準以上の給与を保証することや、安全衛生に関する教育を行うこと、社会保険への加入を代行したり、生活に関する案内や住まい探しをサポートしたりすることが要求されます。加えて、本人が理解可能な言語で情報を提供したり、日本語を学ぶ機会を設けたり、日々の質問や相談に応じたりすることも求められます。こうしたサポート業務を登録支援機関にアウトソースする選択肢もありますが、受け入れ機関としての責任は継続します。
申請から許可までの基本的な流れ
特定技能ビザの申請プロセスは、外国人が国内にいるか海外にいるかによって手続きが異なります。技能実習2号を終えた外国人が特定技能1号へ切り替えるケースでは、在留資格変更許可申請を行います。一方、海外から新たに人材を招く際は、まず在留資格認定証明書の交付を申請するところからスタートし、次に査証申請、入国手続きという流れになります。
申請から許可までの標準的な審査期間は、在留資格の変更許可申請にはおよそ2か月から4か月、在留資格認定証明書の交付申請には約1か月から3か月かかると言われています。ただし、書類の不備がある場合や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。企業は余裕を持ったスケジュールで申請手続きを進めることが重要です。
深刻な人手不足に直面する日本の企業にとって、外国人材の活用は喫緊の課題となっています。特に製造業、建設業、介護分野などでは、即戦力となる人材の確保が企業の存続に関わる重要な経営課題です。2019年4月に創設された特定技能制度は、これ[…]
ビザ申請に必要な基本書類一覧
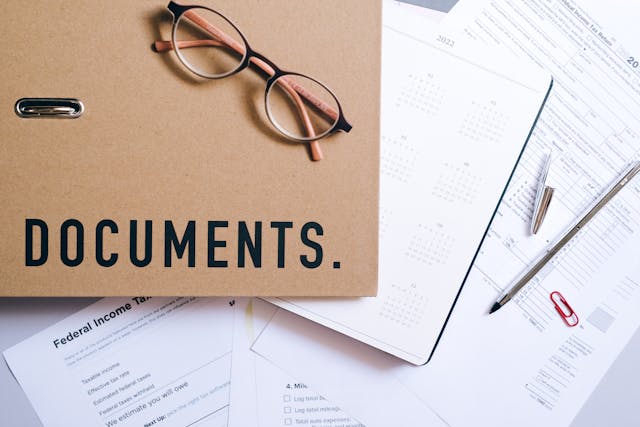
特定技能ビザの申請に係る書類には、外国人本人と受け入れ機関である企業の双方に関する書類を揃えなければなりません。申請に必要な文書は非常に数が多いため、事前に整理して準備することが重要です。以下に、必要書類を体系的に分類して解説いたします。
基本的な申請書類としては、在留資格変更許可申請書、もしくは在留資格認定証明書交付申請書、並びに特定技能外国人の給与に関する説明書や、特定技能外国人との雇用契約を交わした書類のコピー、雇用条件書の写し、事前ガイダンスの確認書などがあります。上記に加えた分野別の追加書類もあるため、不備がないよう十分に確認する必要があります。
申請人(外国人)に関する必要書類
外国人本人が準備する書類として、まず在留資格変更許可申請書、もしくは在留資格認定証明書交付申請書を準備します。この申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードでき、公式サイトの記入例も参考にしながら、氏名、生年月日、国籍、現在の在留資格、勤務先情報、日本での活動内容などを正確に記載する必要があります。
パスポートの写しは全ページのコピーが必要で、特に出入国のスタンプが押印されているページは鮮明にコピーする必要があります。在留カード(既に日本に在留している場合)の表裏両面の写しも必要です。また、証明写真(4cm×3cm、無帽、正面、無背景)を申請書に貼付します。技能試験合格証明書や日本語試験合格証明書(技能実習2号修了者は免除)、健康診断書(指定項目を満たした健康診断個人票)なども重要な書類となります。これらの書類には外国人のプライバシー情報が深く関わるため、個人情報保護の観点からも取り扱いに十分な注意が必要です。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
受け入れ機関(企業)が準備する書類
受け入れ機関である企業が準備する書類は多岐にわたります。まず、特定技能雇用契約書と雇用条件書は、外国人との労働条件を明確に定めた重要な契約書面です。給与水準は日本人従業員と同等かそれ以上であることが絶対条件で、労働時間、休日、社会保険の取扱いなどを詳細に記載し、その待遇を証明する資料を提示する必要があります。
企業の基本情報を証明する書類として、登記事項証明書(法人の役員構成などがわかるもの)、決算書類の写し(直近年度分)、納税証明書(法人税、消費税、源泉所得税等)、社会保険料納付証明書などが必要です。これらの書類により、企業の適法性と経営の安定性を示します。あわせて、特定技能外国人向けの支援計画書や、1号を対象とする支援計画の概要書、支援責任者及び支援担当者の氏名や所属部署、そして法令違反がないことを誓う誓約書なども提出が求められます。
分野別特有の書類と要件
特定技能の各分野では、業界特有の要件に応じて追加の書類提出が求められることがあります。例えば、建設分野では建設業許可証のコピーに加え、受け入れ対象の外国人が携わる建設工事のあらましを記した書面が求められます。介護分野では、介護施設の許可証や指定証の写し、サービス内容を説明する書類の提出が求められます。
製造業分野では、工場の概要や製造品目、外国人が従事する具体的な業務内容を詳細に記載した書類が必要です。農業分野では、農地の使用権を証明する書類や、作物の栽培計画、農業経営の概要などを提出します。分野ごとに監督官庁や業界団体が定める特別な要件もあるため、該当する分野の最新情報を確認することが重要です。
「少子高齢化による人手不足が深刻化し、事業継続が危うい…」「外国人材の雇用を検討しているが、就労ビザの申請は複雑で何から手をつければいいのかわからない」「不法就労のリスクや、雇用後の管理についても不安がある」もしあなたがこの[…]
申請手続きの詳しい流れと審査のポイント

特定技能ビザの申請手続きは、準備段階から許可取得まで複数のステップを経る必要があります。各段階で適切な対応を行っていくことで、スムーズな審査進行と許可取得が期待できます。手続きの流れを理解し、計画的に進めることが成功の鍵となります。
審査では、外国人の技能水準、企業の適格性、雇用契約の適正性、支援体制の整備状況などが総合的に評価されます。特に、虚偽申請や過去の法令違反がないか、外国人への適切な支援が提供できるかという点は厳格にチェックされます。
事前準備と書類作成のポイント
申請書類の作成は、正確性と完全性が最も重要です。申請書の各項目は空欄を残さず、該当しない項目には「該当なし」や「なし」と記載する必要があります。数字や日付は正確に記入し、特に報酬額や労働時間については雇用契約書と整合性を保つ必要があります。
書類の翻訳が必要な場合は、公的機関や専門業者による正式な翻訳を用意する必要があります。翻訳者の氏名、資格、連絡先を明記した翻訳証明書も添付します。また、各書類の有効期限にも注意が必要で、特に指定のないものを除き、証明書類は発行から3か月以内のものが通常は必要ですが、対象分野ごとに要件が違うケースもあるため、最新の情報を確認してください。書類の不備や記載漏れは審査の遅延につながるため、提出前には複数人でのチェックを実施することをおすすめします。
出入国在留管理庁での審査過程
出入国在留管理庁での審査は、書類審査を中心に行われますが、必要に応じて追加資料の提出や面接が実施される場合があります。審査官は、提出された書類の内容を詳細に検討し、外国人の在留資格該当性、企業の受け入れ体制、支援計画の妥当性などを総合的に判断します。
審査期間中に疑義が生じた場合は、出入国在留管理庁から追加資料の提出や説明を求められることがあります。この際は、速やかに対応することが重要で、回答の遅れは審査期間の延長につながります。また、申請内容に重大な不備が発見された場合は、申請の取り下げや再申請を求められることもあるため、初回申請時の精度向上が極めて重要です。
審査結果の通知と許可後の手続き
審査が完了すると、許可または不許可の結果が通知されます。許可が下りた場合、在留資格認定証明書が発行されるか、在留カードが交付・更新されることになります。海外から初めて日本に入国する外国人のケースでは、取得した在留資格認定証明書を母国の日本領事館などに持って行き査証申請を行い、その後入国手続きを経て日本での就労が開始されます。
特にフィリピン国籍の方を採用する場合、ビザ申請とは別に、フィリピン政府へのMWO申請が必須となります。
許可後も企業には継続的な義務があります。支援の実施状況に関する記録を適切に保管し、外国人の活動状況や支援実施状況を定期的に出入国在留管理庁に報告する必要があり、特定技能外国人受け入れに関する届出書の提出が義務付けられています。また、雇用契約の変更や外国人の転職、一時帰国などが生じた場合は、速やかに必要な手続きを行わなければなりません。
申請時の注意点とよくある失敗事例

特定技能ビザ申請において、多くの企業が陥りがちな失敗パターンがあります。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、申請の成功率を大幅に向上させることができます。失敗事例から学び、同様のミスを避けることが重要です。
申請書類の不備は最も頻繁に発生する問題の一つです。特に、代表的な失敗例として3つ挙げられます。それは、記載内容の矛盾、書類の有効期限切れ、そして署名・押印の漏れです。これらの問題は事前チェックで防げるものが多いため、組織的な確認体制を整備することが有効です。
書類不備による申請遅延の回避方法
書類不備を防ぐためには、まず申請書類のチェックリストを作成し、全ての必要書類が揃っているかを段階的に確認することが重要です。特に、申請書の記載内容と添付書類の内容が一致しているか、日付や数字に誤りがないか、必要な署名・押印が全てなされているかを入念にチェックする必要があります。
また、各書類の有効期限管理も重要なポイントです。証明書類は一般的に発行から3か月以内のものが求められますが、分野によって異なる場合があるため、最新の要件を確認する必要があります。翻訳書類については、翻訳者の資格確認と翻訳証明書の添付を忘れずに行い、原文と翻訳文の対応関係を明確にしておくことが必要です。
雇用契約と支援体制に関する留意事項
雇用契約書は特定技能ビザ申請の核となる重要書類です。報酬の支払いについては、同じ業務に携わる日本人従業員の給与水準と比較できるデータを用意することが求められます。労働時間、休日、有給休暇の取扱いについても、労働基準法等の関係法令に適合していることを確認する必要があります。
支援体制については、1号特定技能外国人向けの支援計画を作成することが法律で義務付けられています。支援計画には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談とその記録の保管などの10項目の支援が含まれます。これらの支援を自社で行っていくのか、それとも登録支援機関に依頼するのかをはっきりさせ、具体的な実施方法を詳細に記載する必要があります。
分野別技能試験と日本語能力の要件確認
特定技能1号の取得には原則として技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。ただし、技能実習と同じ業務区分の特定技能へ移行する場合、技能実習2号を良い成績で終えた外国人に関しては、これらの試験を受ける必要がありません(受験が不要となります)。技能試験は各分野の業界団体等が実施しており、試験内容や実施時期、受験資格などが分野ごとに異なります。
日本語能力については、国際交流基金が実施する日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT(日本語能力試験)のN4以上の合格が求められます。介護分野については、さらに介護日本語評価試験の合格も必要です。企業は受け入れ予定の外国人がこれらの要件を満たすか事前に確認し、不足している場合は試験受験の支援を行う必要があります。試験の実施状況や合格率なども考慮して、採用計画を立てることが重要です。
参考:
日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)
費用と期間の目安
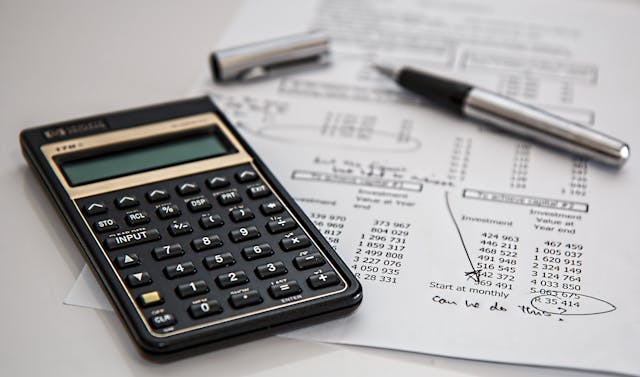
特定技能外国人の受け入れには、ビザ申請に関わる各種費用と相当な期間を要します。企業は事前にこれらのコストと時間を適切に見積もり、予算と人材確保計画に反映させる必要があります。費用については、申請手数料だけでなく、書類作成や翻訳、支援業務委託など幅広い項目を考慮する必要があります。
期間については、申請から実際の就労開始まで数か月を要するのが一般的です。とりわけ海外から新たに人材を迎えるケースでは、在留資格認定証明書の発行や査証の申請、入国審査といった複数のステップを踏むため、より長期間の準備期間が必要となります。
申請にかかる各種手数料と関連費用
特定技能ビザ申請の基本的な手数料として、在留資格変更許可申請の手数料は2025年4月1日以降、窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円に改定されています。一方、在留資格認定証明書の交付申請自体は手数料がかかりません。しかしながら、これらは出入国在留管理庁への支払いが必要な最小限の費用であり、実際の受け入れには多くの関連費用が発生します。
書類作成や翻訳にかかる費用は、依頼する業者や書類の分量によって大きく異なりますが、一般的に10万円から30万円程度を見込んでおく必要があります。行政書士等の専門家に申請取次を依頼する場合は、20万円から50万円程度の報酬が必要です。また、外国人の技能試験や日本語試験の受験費用、健康診断費用なども企業が負担するケースが多く、これらも考慮しておくべき費用項目です。
登録支援機関への委託費用
多くの企業が、特定技能外国人に対するサポート業務を登録支援機関に依頼しています。その際の費用は支援機関によって異なりますが、月額2万円から5万円程度が一般的な相場です。年間では24万円から60万円程度の費用が継続的に発生することになります。
委託する支援内容によっても費用は変動し、基本的な支援のみの場合と、日本語学習支援や生活相談なども含む包括的な支援では費用に差が生じます。また、外国人が来日した際の空港への出迎えや住まい探しの手伝い、また緊急時のサポートなどには追加の料金がかかることがあるほか、地域の国際交流センターなどが提供する支援サービスも活用できます。複数の登録支援機関から見積もりを取得し、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。
申請から就労開始までの期間見積もり
特定技能ビザの申請から実際の就労開始までの期間は、申請の種類や外国人の所在地によって大きく異なります。国内にいる技能実習生が特定技能1号に移行する場合は、在留資格変更許可申請から許可まで約2か月から4か月程度を要します。
海外から新たに受け入れるケースでは、さらに長い期間を見込む必要があります。在留資格認定証明書の交付申請には、1か月から3か月ほどかかり、その後の査証申請と入国手続きに1か月程度を要するため、全体で3か月から5か月程度の期間を見込んでおく必要があります。ただし、書類の不備による再申請や追加資料の提出が必要な場合は、さらに期間が延長される可能性があります。企業は余裕を持ったスケジュールで人材確保計画を立て、複数の候補者を並行して進めることでリスクを軽減することが重要です。
近年、日本の労働市場において外国人雇用の重要性が急速に高まっています。少子高齢化や人材不足が深刻化する中で、多くの企業が外国人労働者の採用を検討・実施するようになり、グローバル人材の確保はもはや選択肢ではなく戦略となりつつあります。この国際[…]
2025年の制度変更と動向

2025年4月1日から特定技能制度に重要な変更が実施されており、企業の受け入れ体制にも影響を与える内容が含まれています。主な変更点として、在留手続きの手数料改定、届出制度の見直し、オンライン申請の拡充などが挙げられます。これらの変更は、外国人材の受け入れをより効率的にする一方で、企業の管理責任も強化される内容となっています。
届出制度の簡素化と新たな要件
2025年4月より随時届出制度が大幅に見直され、これまで対象外だったケースも届出対象に追加されています。一方で、定期届出については年4回から年1回への簡素化が実施され、企業の事務負担軽減が図られています。ただし、定期届出の初回提出は2026年4月1日から5月31日までとされており、移行期間中の対応が必要です。
新しい届出制度では、受け入れが困難になった場合の届出様式も変更されており、より詳細な情報提供が求められるようになりました。企業は新しい届出要件を正確に理解し、適切なタイミングでの届出実施体制を整備することが重要です。さらに、支援を登録支援機関に依頼しているケースでも、企業として届出内容を把握し、責任を持って確認する必要があります。
参考:出入国在留管理庁 特定技能制度における運用改善について
オンライン申請の活用メリット
制度変更に伴い、オンライン申請の対象範囲が拡大され、手数料の割引適用も受けられるようになりました。オンライン申請を活用することで、申請手続きの効率化と費用削減の両方を実現できます。特に複数の外国人材を継続的に受け入れる企業にとって、大きなメリットとなります。
オンライン申請では、書類の電子化により提出書類の管理が容易になり、申請状況の確認もリアルタイムで行えます。ただし、システムの操作方法や必要な電子証明書の準備など、事前の準備が必要です。企業は担当者の教育やシステム環境の整備を進め、オンライン申請のメリットを最大限活用することをお勧めします。
今後の制度展望と企業の対応策
特定技能制度は継続的に見直しが行われており、2022年の対象分野拡大に続き、2024年には「育成就労」制度の創設も決定されています。これらの制度変更は、外国人材の受け入れ環境をより整備し、企業にとってより活用しやすい制度とすることを目的としています。企業は最新の制度動向を常に把握し、柔軟に対応する体制を構築することが重要です。
今後は、デジタル化の推進、支援の質的向上、地域との連携強化などが重点課題となると予想されます。企業は単なる労働力確保の手段として特定技能制度を捉えるのではなく、外国人材の長期的な定着と活躍を支援する総合的な取り組みが求められます。制度変更への適切な対応により、企業の競争力強化と外国人材の満足度向上の両立を目指していくことが重要です。
まとめ

特定技能ビザ申請は、外国人材の受け入れを成功させるための重要なプロセスです。本記事では、申請に必要な書類から手続きの流れ、注意点、費用と期間、さらに2025年の最新制度変更まで、企業の人事担当者が知っておくべき実務的な情報を包括的に解説いたしました。
申請の成功には、正確な書類準備と適切な支援体制の整備が不可欠です。特に、雇用契約の適正性、支援計画の具体性、各分野の特別要件への対応が審査のポイントとなります。また、2025年の制度変更により、手数料の改定や届出制度の見直しが実施されており、企業は新しい要件への対応が必要となっています。
複雑な制度要件や頻繁な制度変更への対応は、自社の力だけで対応するのは困難な場合も多くあります。専門家の活用や登録支援機関との連携により、確実で効率的な外国人材受け入れを実現することをおすすめします。適切な準備と支援体制により、外国人材は企業の貴重な戦力として長期的に活躍してくれるでしょう。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。