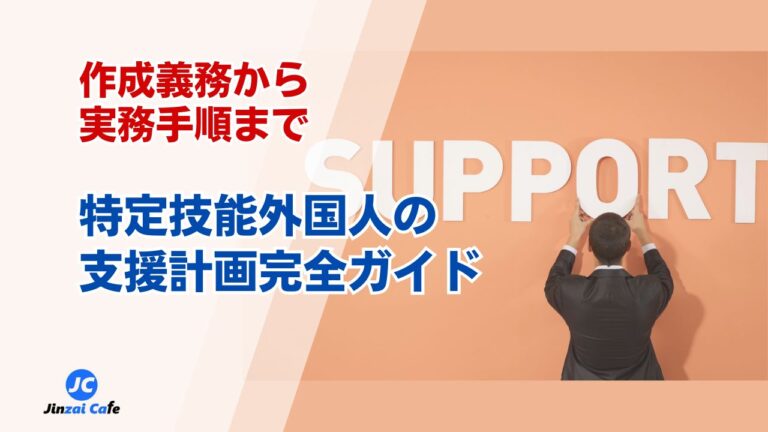特定技能外国人を雇用する際、企業には「支援計画」の作成が法律で義務付けられています。この支援計画は、外国人材が日本で安心して働き、生活できるようサポートする具体的な内容を定めたものです。
しかし、初めて特定技能外国人を受け入れる企業の人事担当者にとって、何をどのように計画すればよいのか、どこまで詳細に記載する必要があるのか判断に迷うケースは少なくありません。特に、建設分野や製造業など、外国人材の採用を検討している企業がまず取り組むべきことは、支援計画の概要を正しく理解することです。
本記事では、支援計画の法的根拠から必須となる10項目の詳細、実際の作成手順、そして計画実施後の変更・報告義務まで、人事担当者が押さえるべき実務知識を体系的に解説します。加えて、よくある質問への回答や、他の企業の事例も紹介していきます。
特定技能外国人の支援計画とは何か

支援計画は、特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する企業が必ず作成しなければならない法定書類です。この計画には、外国人が日本での日常生活や仕事に円滑に適応できるよう、企業が提供する具体的な支援内容を記載します。
出入国在留管理庁への在留資格申請時に提出が求められ、計画の適切性が審査されるため、実現可能で具体的な内容を盛り込む必要があります。そのため、計画書の作成段階から、実施体制や費用面についても十分に検討しておくことが重要です。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(11ページ)
支援計画の法的根拠と義務
支援計画の作成義務は、出入国管理及び難民認定法に基づく「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」によって規定されています。
この省令では、受入れ企業(特定技能所属機関)が外国人に対して実施すべき支援の内容と基準が明確に定められております。支援計画を作成せずに特定技能外国人を雇用することはできず、また計画内容が不適切と判断された場合は在留資格の許可が下りません。
さらに、計画を作成しても実際に支援を実施しなかった場合、在留資格の取消しや今後の受入れ停止といった行政処分の対象となる可能性があります。労働基準法や他の労働関連法規の遵守も求められるため、法令違反がないよう注意が必要です。
参考:E-GOV法令検索 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
特定技能1号における支援の位置づけ
特定技能の在留資格には1号と2号がありますが、支援計画の作成が義務付けられているのは特定技能1号のみとなっています。これは、特定技能1号が「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人を対象としており、日本での生活や就労が初めてというケースが多いためです。
一方、特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人が対象で、すでに日本での生活基盤が確立していると想定されるため支援義務はありません。つまり、支援計画は外国人材の日本社会への定着を促進し、安定的な雇用関係を構築するための制度的な仕組みといえます。なお、在留カードの交付を受けた後も、継続的な支援が求められる点に留意が必要です。
支援計画と支援委託の関係性
企業は支援計画に記載した支援を自社で実施することが原則ですが、登録支援機関に支援の全部または一部を委託することも認められています。登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された支援の専門機関であり、支援実施に必要な体制や経験を備えています。
自社で支援を行う場合は、過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があることや、支援責任者・支援担当者を選任することなど、一定の要件を満たす必要があります。
一方、登録支援機関に全部委託する場合は、これらの要件が免除されるため、初めて特定技能外国人を受け入れる企業や支援体制の構築が難しい中小企業では、委託を選択するケースが一般的です。詳細については、各登録支援機関のページで確認できる一覧情報も参考になります。
参考:出入国在留管理庁 登録支援機関(Registered Support Organization)
日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れを検討する企業が急速に増加しています。2019年に創設された特定技能制度は、人材確保が困難な16分野において、一定の専門性と技能を有する外国人を即戦力として雇用できる[…]
支援計画に含めるべき10項目の詳細

支援計画には、法令で定められた10項目の義務的支援を必ず含める必要があります。これらの支援は、外国人が入国する前の段階から、日本での生活が始まった後の継続的なサポートまで、時系列に沿って体系的に設計されています。
各項目には具体的な実施方法や頻度の基準が設けられており、計画書にはこれらを明確に記載しなければなりません。中でも、外国人が社会生活を円滑に送れるよう、日常的な助言や質問への対応体制を整えることが重要です。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(12ページ)
各支援項目の具体的内容と実施基準
10項目の支援には、それぞれ具体的な実施基準が定められています。以下の表で各項目の詳細を整理します。
| 支援項目 | 実施タイミング | 具体的内容 | 実施基準 |
|---|---|---|---|
| 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、入国前 |
| 対面またはテレビ電話で3時間以上、母国語で実施 |
| 出入国時の送迎 | 入国時・帰国時 |
| 本人負担なしで実施 |
| 住居確保・生活契約支援 | 入国直後 |
| 必要に応じて通訳を配置 |
| 生活オリエンテーション | 入国後遅滞なく |
| 8時間以上、母国語で実施 |
| 公的手続き同行 | 必要時 |
| 本人の求めに応じて実施 |
| 日本語学習機会の提供 | 継続的 |
| 入学案内や自主学習支援を含む |
| 相談・苦情対応 | 継続的 |
| 平日・休日を問わず対応可能な体制 |
| 日本人との交流促進 | 継続的 |
| 定期的な機会の提供 |
| 転職支援 | 雇用契約解除時 |
| 本人都合・会社都合(人員整理含む)を問わず実施 |
| 定期的な面談 | 3か月に1回以上 |
| 対面で母国語により実施 |
※横スクロールできます→
義務的支援と任意的支援の違い
義務的支援とは、上記の表で示した法令で実施が必須とされている10項目の支援を指します。これらは在留資格の許可要件となっており、計画書への記載と実際の履行が求められます。
一方、任意的支援は法令で義務付けられていないものの、外国人の生活向上や職場定着のために企業が独自に提供する支援です。任意的支援の例として、以下のようなものがあります。
- 日本語教材の無償提供や日本語学習費用の補助
- 業務に関連する資格試験の取得支援や受験費用の負担
- 家族の呼び寄せに関するサポートや手続き案内
- 社内イベントや懇親会への参加促進
- 通勤用の自転車や交通費の支給
- 健康診断の追加実施や医療機関への同行サービス
- 母国の文化行事や祝日への配慮
義務的支援を適切に実施することが在留資格許可の前提条件となるため、まずは10項目の確実な履行体制を整えることが重要です。任意的支援は、義務的支援の基盤が整った上で、企業の状況に応じて追加することが望ましいといえます。簡単に実施できる任意的支援から始めることで、外国人材との信頼関係を構築しやすくなります。
支援項目ごとの頻度と記録方法
各支援項目の実施後は、実施日時、実施内容、対応者、外国人の反応などを詳細に記録し、書類として保管する義務があります。
特に定期面談については、3か月ごとに実施した記録を出入国在留管理庁への定期報告時に提出する必要があるため、面談記録票の作成が不可欠です。記録には、面談実施日、面談場所、面談時間、使用言語、面談内容(労働時間、賃金支払状況、健康状態、困りごとの有無など)を具体的に記載しなければなりません。
また、相談・苦情対応についても、相談内容と対応結果を記録し、適切に対処したことを証明できるようにしておく必要があります。これらの記録は、在留資格更新時の審査や行政機関による実地調査の際に確認される重要な証拠書類となります。
特定技能外国人を受け入れる際、企業には様々な支援義務が課せられています。その中でも最初に実施すべきなのが「事前ガイダンス」です。採用活動を経て、入国前に労働条件や生活情報を十分に説明することで、外国人材の不安や悩みを解消し、スムーズな受入れ[…]
特定技能外国人労働者を採用する際、多くの企業が「生活オリエンテーション」という言葉を耳にするでしょう。しかし、具体的に何を伝えればいいのか、どのように実施すればよいのか、悩まれる人事担当者の方は少なくありません。生活オリエンテーショ[…]
支援計画の作成手順とポイント

支援計画の作成は、特定技能外国人の在留資格申請に必要な重要プロセスです。計画書は出入国在留管理庁が定める様式に従って作成し、具体的かつ実現可能な支援内容を記載しなければなりません。
初めて作成する担当者でも迷わず進められるよう、準備から提出までの手順を段階的に解説します。許可申請の際には、支援計画書と併せて他の必要書類も準備しておくことが求められます。
作成前の準備と必要書類
支援計画を作成する前に、まず雇用する外国人との雇用契約を締結し、契約内容を明確にしておく必要があります。雇用契約書には、業務内容、勤務地、労働時間、賃金、休日などの労働条件を日本人と同等以上の水準で記載しましょう。
次に、支援を自社で実施するか登録支援機関に委託するかを決定し、自社実施の場合は支援責任者と支援担当者を選任することになります。支援責任者は、過去2年以内に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を持つ者、または外国人の生活支援に関する知識を有する者でなければなりません。
また、外国人が使用する言語に対応できる通訳人の確保も事前に行っておくべきでしょう。これらの準備が整った段階で、計画書の作成に着手できます。
計画書の記載項目と書き方
支援計画書は、出入国在留管理庁が公開している「参考様式第1-17号」を使用して作成します。計画書には、受入れ企業の基本情報(名称、所在地、代表者氏名)、支援対象となる外国人の情報(氏名、国籍、在留資格、従事する業務内容)、そして10項目の義務的支援それぞれについて具体的な実施方法を記載します。
各支援項目の記載では、以下のポイントを押さえることが重要です。
| 支援項目 | 記載すべき具体的内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンス |
|
| 出入国時の送迎 |
|
| 住居確保支援 |
|
| 生活オリエンテーション |
|
| 日本語学習機会 |
|
| 相談・苦情対応 |
|
| 定期面談 |
|
記載内容は抽象的な表現を避け、「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」実施するのかを明確に示すことが審査通過のポイントとなります。
審査で指摘されやすい注意点
支援計画の審査では、実現可能性と具体性が重視されるため、曖昧な記載は避けなければなりません。よくある指摘事項として、以下のような点が挙げられます。
- 支援の実施方法の曖昧さと具体性の欠如
- 使用言語の明記不足や対応可能言語の不明確さ
- 支援責任者・支援担当者の法定要件不適合
- 通訳人の確保方法や配置体制の不明確さ
- 「適切に対応」「必要に応じて支援」などの抽象的表現の多用
- 事業所の所在地や事業内容の記載不足
特に抽象的な表現は、具体的な実施方法に書き換えることが求められます。また、登録支援機関に委託する場合でも、委託契約書の添付が必要であり、委託する支援項目と自社で実施する項目を明確に区別して記載しなければなりません。
さらに、支援に要する費用を外国人本人に負担させることは原則として認められないため、費用負担についても計画書に明記しておくべきです。
特定技能外国人の受け入れを検討する際、多くの企業が最初に直面するのが「実際にどれくらいの費用がかかるのか」という疑問です。人材紹介会社への手数料、登録支援機関への委託費用など、さまざまな費用項目が存在し、その全体像を把握することは難しいもの[…]
支援実施体制の構築方法

支援計画を作成した後は、計画に記載した支援を確実に実施できる体制を整える必要があります。企業の規模や外国人受入れの経験、利用可能なリソースによって、最適な体制は異なるため、自社の状況を踏まえた判断が求められるでしょう。
ここでは、自社実施と外部委託の比較、必要な人員要件、そして効果的な体制構築の事例を紹介していきます。
自社実施と登録支援機関への委託の比較
支援を自社で実施する場合と登録支援機関に委託する場合では、それぞれにメリットとデメリットがあります。以下の表で両者を比較し、判断材料を整理しましょう。
| 比較項目 | 自社実施 | 登録支援機関への委託 |
|---|---|---|
| 費用 | 人件費や通訳費用のみ (月額3〜5万円程度) | 委託料 (月額2〜4万円程度) |
| 要件 | 過去2年間の受入れ実績または同等の経験 | 受入れ実績不要 |
| 人員配置 | 支援責任者・支援担当者の選任が必須 | 人員配置要件の免除 |
| 通訳対応 | 母国語対応可能な通訳人の確保 | 多言語対応サービスの提供 |
| 柔軟性 | 自社状況に応じた柔軟な支援 | 標準的な支援内容 |
| 負担 | 支援業務が社内負担 | 支援業務負担の軽減 |
| リスク | 支援不備の直接的リスク | 登録支援機関による責任分担 |
※横スクロールできます→
初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、支援体制の構築が難しい中小企業では、登録支援機関への全部委託を選択するケースが一般的です。一方、すでに技能実習生の受入れ実績があり、外国人対応のノウハウを持つ企業では、自社実施を選択することでコストを抑えられる可能性があります。
支援責任者と支援担当者の要件
自社で支援を実施する場合、支援責任者と支援担当者を選任しなければなりません。支援責任者は、支援計画の実施状況を管理し、支援担当者への指示や外部機関との調整を行う役割を担います。
支援責任者の要件として、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験、または外国人の生活支援に関する知識を有していることが求められます。具体的には、技能実習の監理団体や登録支援機関での勤務経験、行政機関での外国人相談窓口の担当経験などが該当するケースです。
支援担当者は、実際に外国人と接して日常的な支援を提供する役割であり、支援責任者の指示のもとで業務を遂行していきます。支援担当者には特定の資格要件はありませんが、外国人とのコミュニケーション能力や文化的な理解があることが望ましいでしょう。
効果的な支援体制の事例とパターン
効果的な支援体制を構築するには、企業の規模や受入れ人数に応じたパターンを選択することが重要です。以下の表で、企業規模別の推奨体制を整理しました。
| 企業規模 | 受入れ人数 | 推奨体制パターン | 体制の特徴 |
|---|---|---|---|
| 小規模企業 | 1〜3名 | 部分委託型 | 人事担当者が支援責任者を兼任し、専門的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など)を登録支援機関に委託 |
| 中規模企業 | 4〜10名 | 自社中心型 | 専任の支援責任者を配置し、母国語対応可能な通訳スタッフを確保した上で、大部分の支援を自社で実施 |
| 大規模企業 | 11名以上 | 専門部署設置型 | 外国人材の受入れ部署を設置し、複数の支援担当者を配置してきめ細かい支援を提供 |
※横スクロールできます→
いずれのパターンでも、緊急時の連絡体制や休日・夜間の相談対応をどう確保するかが重要なポイントとなるため、外部の通訳サービスや相談窓口との連携も検討すべきです。
外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]
支援計画の変更と報告義務

支援計画は一度作成したら終わりではなく、状況の変化に応じた変更手続きや、定期的な報告義務が発生します。これらの手続きを怠ると、在留資格の取消しや今後の受入れ停止といった行政処分のリスクがあるため、適切な管理が不可欠です。
ここでは、変更が必要になる具体的なケースと手続き方法、報告義務の種類と内容について詳しく解説していきます。
変更が必要になるケースと手続き
支援計画の変更が必要になるケースは、大きく分けて以下のような状況が該当します。
- 受入れ企業の名称、所在地、代表者が変更になった場合
- 外国人の勤務地や従事する業務内容が変更になった場合
- 支援責任者や支援担当者が交代した場合
- 登録支援機関への委託を開始または終了する場合
- 支援の実施方法や内容を大幅に変更する場合
これらの変更が発生した際は、変更後14日以内に出入国在留管理庁へ「支援計画変更届出書」を提出しなければなりません。届出書には、変更前と変更後の内容を明記し、変更を証明する書類(登記事項証明書、委託契約書など)を添付する必要があります。
特に登録支援機関との委託契約を変更する場合は、新たな委託契約書の写しと、登録支援機関の登録証明書の提出が求められます。変更届出を怠った場合、支援計画違反とみなされ、行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、変更が発生した時点で速やかに手続きを行うことが重要です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
定期報告と随時報告の区別
支援計画に関する報告義務には、定期報告と随時報告の2種類があります。定期報告は、2025年4月1日から年1回(4月1日から翌年3月31日まで)に出入国在留管理庁へ提出する「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」です。
この報告には以下の項目を記載しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期面談の実施記録 | 実施日時、面談内容、確認事項 |
| 支援の実施状況 | 各支援項目の実施日、実施内容 |
| 外国人の労働状況 | 勤務時間、賃金支払状況、業務内容 |
| 外国人の生活状況 | 住居、健康状態、日本語学習の進捗 |
| 相談・苦情の内容と対応結果 | 相談・苦情の内容、対応結果 |
報告期限は、対象年度終了後の翌年4月1日から5月31日までとなっています。なお、2025年1月分から3月分については、従来の四半期報告制度により4月15日までに提出する必要があります。
一方、随時報告は、特定の事象が発生した際に速やかに届け出る義務です。随時報告が必要となる主なケースは以下の通りです。いずれも14日以内の届出が必要です。
- 外国人が行方不明になった場合
- 外国人が死亡した場合
- 外国人が労働関係法令違反の被害を受けた場合
- 雇用契約を解除した場合
- 支援計画に従った支援を実施できなかった場合
これらの報告を怠ると、受入れ企業としての信頼性が損なわれ、今後の外国人受入れに影響を及ぼす可能性があります。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度における運用改善について
出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
出入国在留管理庁 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
出入国在留管理庁 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
支援実施状況の記録と保管義務
支援計画に基づいて実施したすべての支援について、詳細な記録を作成し、保管する義務があります。記録すべき項目には、支援の実施日時、実施場所、実施者、支援内容、外国人の反応や状況、使用した言語などが含まれます。
特に定期面談については、面談記録票を作成し、面談で確認した労働時間、賃金支払状況、健康状態、困りごとの有無とその対応内容を具体的に記載しなければなりません。
これらの記録は、在留資格更新時の審査や出入国在留管理庁による実地調査の際に確認される重要な証拠書類です。記録の保管期間は、特定技能雇用契約終了日から1年以上と定められており、記録の保管形態は紙媒体でも電子データでも構いませんが、必要時に速やかに提出できる状態にしておくことが求められます。
また、相談・苦情対応の記録については、相談者のプライバシーに配慮しつつ、相談内容と対応結果を詳細に残しておくことが重要です。適切な支援を実施している証拠として、これらの記録が重要な役割を果たします。
まとめ|特定技能外国人の支援計画作成で押さえるべきこと

特定技能外国人を雇用する際の支援計画は、単なる書類作成ではなく、外国人材が日本で安心して働き、生活するための具体的な行動指針となるものです。本記事では、支援計画の法的根拠から10項目の義務的支援の詳細、作成手順、実施体制の構築、そして変更・報告義務まで、人事担当者が押さえるべき実務知識を体系的に解説してきました。
支援計画の作成で最も重要なポイントは、実現可能で具体的な内容を記載することです。抽象的な表現を避け、「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」支援を実施するのかを明確にすることで、審査を通過しやすくなります。また、計画作成後も定期的な報告や記録の保管といった継続的な管理が求められるため、社内の体制整備と業務フローの確立が欠かせません。
自社で支援を実施するか登録支援機関に委託するかの判断は、企業の規模や受入れ実績、利用可能なリソースを総合的に考慮して決定しましょう。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、登録支援機関への委託から始め、ノウハウが蓄積された段階で自社実施に切り替えるという段階的なアプローチも有効です。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。