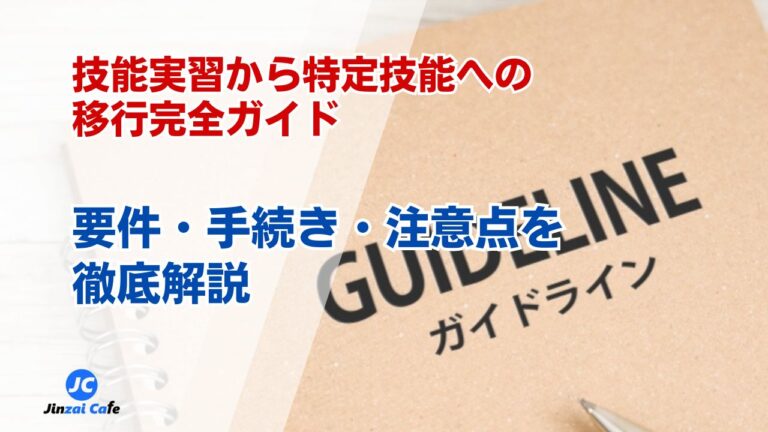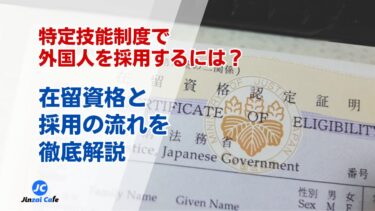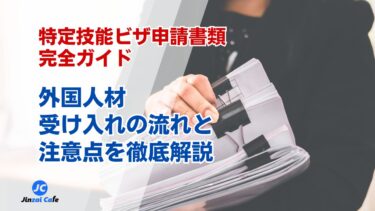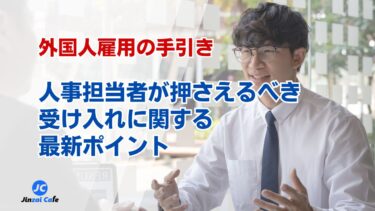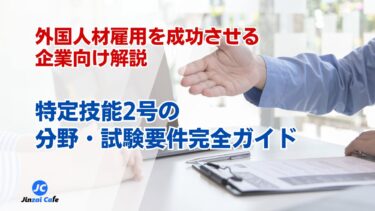外国人材の雇用を進める企業にとって、技能実習生から特定技能への移行は重要な課題です。技能実習制度で培った技能と経験を持つ外国人材、いわゆる外国人労働者を、より長期的に戦略的に雇用することで、人手不足の解決と企業の成長につなげることができます。
とはいえ、技能実習から特定技能への移行には複雑な手続きや要件が多くあります。そのため、非常にたくさんの企業が「どのような手順で進めればよいのか」「どんな書類や資料が必要なのか」「注意すべきポイントは何か」といった疑問を抱えています。適切な準備と理解なしに進めると、手続きの遅延や不許可につながるリスクもあり、移行が困難になるケースも少なくありません。
本記事では、技能実習から特定技能への移行について、企業の人事担当者が知っておくべき要件や手続きの流れ、実務上の注意点を詳しく解説します。以下の目次に沿って解説を進めますので、この記事をご覧になることで、スムーズな移行手続きを実現し、優秀な外国人材を長期雇用できるようになります。
技能実習と特定技能制度の違いとは
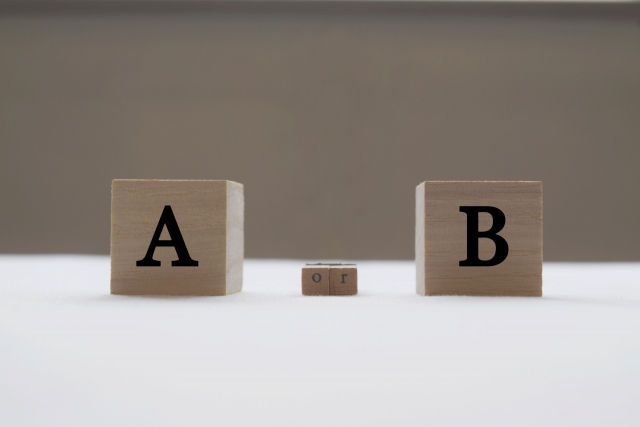
技能実習から特定技能への移行を理解するには、まず両制度の相違点を正確に把握することが重要です。ここではこの2つの制度について、いくつかの点で比較します。この2つの制度は、目的や在留期間、業務内容などがそれぞれ異なり、国際協力と人材育成を目的とする技能実習制度に対し、特定技能制度は人手不足分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。そのため、在留期間や業務内容、受け入れ機関の要件等、様々な面で大きな違いがあります。
参考:
厚生労働省 外国人技能実習制度について
出入国在留管理庁 特定技能運用要領
制度の目的と基本的な仕組み
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を通じた国際協力を主目的としており、外国人技能実習生が日本で技能を修得し、母国の発展に貢献することを想定しています。一方、特定技能制度は深刻な人手不足に対応するという理由から、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力として受け入れるという目的があります。
技能実習では監理団体を介した受け入れが原則ですが、特定技能では企業による直接雇用が認められており、より柔軟な雇用が可能になる点が大きな違いです。受け入れ分野についても、技能実習の対象となる業種は約90職種に対し、特定技能は現在16分野と対象範囲が異なります。これには、造船・舶用工業、自動車整備、航空、外食業なども含まれます。
参考:
厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
出入国在留管理庁 特定技能制度分野別情報
在留期間と更新可能性の比較
技能実習の在留期間は最長5年間であり、原則として更新はできません。技能実習2号や3号にはそれぞれ2年の期間が設定されています。一方、特定技能1号の場合、在留できる期間が最長5年と定められていますが、1年・6か月または4か月ごとの更新ができ、合計で最長5年間の滞在が認められます。さらに、特定技能2号へステップアップできれば、在留期間に上限はなくなります。家族の帯同もできるようになり、国内での長期的な生活設計が可能です。技能実習の全課程を終えた後、特定技能へ在留資格、通称ビザを切り替える場合、通算の在留期間は最長10年間となり、企業にとっては長期的な人材戦略を立てやすくなります。
業務内容と技能レベルの要求水準
技能実習では段階的な技能修得が重視され、各段階で技能検定の受検が義務付けられています。業務内容は技能実習計画に基づいて厳格に管理され、計画外の業務に従事させることはできません。特定技能という枠組みにおいては、技能実習の時よりも広範囲の業務に携われるため、即戦力としての活用が前提となります。相当程度の知識・経験が求められ、業務内容もより幅広く柔軟な対応ができます。優れた成績で技能実習2号を完了した外国人が同一分野へ進む場合、技能試験の受験は不要となり、日本語の試験で基準をクリアすれば特定技能の資格を得られます。この優遇措置により、技能実習で培った技術や経験を活かして、より高度な業務を担当することが可能になります。
近年、日本では多くの産業分野で慢性的な人手不足が深刻な状況となっており、とりわけ介護・建設・農業・外食産業・製造業などの現場では、必要な人材を確保できないことが経営上のリスクとなっています。少子高齢化による労働人口の減少が背景にあることは言[…]
特定技能への移行が可能な要件と条件

上記の制度の違いを踏まえ、特定技能への移行には、明確な要件と条件が定められています。単に技能実習を修了しただけでは移行できず、技能実習の修了状況とは別に、対象分野の適合性、日本語能力など複数の要件を満たす必要があります。企業は事前にこれらの要件を十分に確認し、移行の可能性を適切に判断することが重要です。
技能実習2号・3号の良好な修了要件
特定技能の資格を得るには、技能実習の2号もしくは3号の課程を「良好な成績」で終えていることが最も重要です。「良好な修了」と認められるためには、技能実習計画通りに実習を終え、さらに技能検定3級か、同等のレベルとされる技能実習評価試験に合格している必要があります。また、素行が良好であること、技能実習中に法令違反や重大な問題行為がないことも条件です。これらの条件をすべて満たした外国人のみが、移行の申請が可能となります。技能実習1号の課程を終えただけでは移行の対象とならないため、少なくとも技能実習2号までを完了し、その認定を得なければなりません。申請時には、出入国在留管理庁に対して、良好に修了した事実を明らかにするための修了証明書や評価調書を提出する必要があります。
対象分野の対応関係と制限事項
技能実習から特定技能への切り替えは、双方の職務内容に関連性が認められる分野間に限定されています。例えば、建設分野で技能実習の課程を修了した人材は、特定技能の建設分野へ、また介護分野の技能実習を終えた場合は、特定技能の介護分野へステータスを変更できます。また、一部の分野では年間の受け入れ人数に制限があることにも注意が必要です。同分野であっても、企業の状況によって受け入れの可否が異なる場合があります。
製造業関連では「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「素形材産業」といった特定技能の対象分野が存在し、農業分野では「農業」、漁業分野では「漁業」の特定技能分野への移行ができます。飲食料品製造業、ビルクリーニング、宿泊業についても対応関係が明確に定められており、対応する分野の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
参考:厚生労働省 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について
日本語能力と技能試験の免除条件
優れた状態で技能実習2号もしくは3号を終えた外国人が特定技能に移行する場合、同一分野への移行なら技能試験の受験義務はありません。しかし、日本語のスキルに関しては原則として、日本語能力を測る試験である日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書を取得する必要があります。介護分野では、他の分野よりも日本語スキルの要求水準が高く設定されており、加えて介護日本語評価試験にも合格する必要があります。
技能実習3号を修了し、かつ技能検定2級などに合格しているケースでは、日本語試験の受験が不要となる場合もあります。企業は雇用予定の外国人材がどの試験の免除対象になるかを事前に確認し、必要に応じて日本語学習のサポートを提供することが重要です。
外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]
移行手続きの流れと必要書類
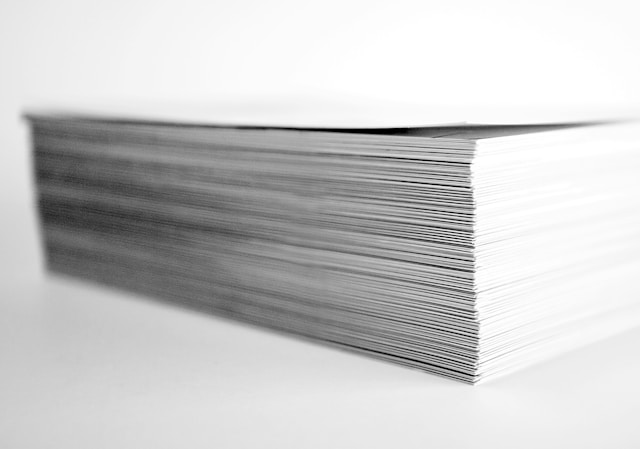
技能実習から特定技能への移行手続きは、法的には在留資格変更許可申請として行われます。手続きには非常に多い書類や資料が必要で、準備期間も相当程度必要になるため、計画的な進行が重要です。次のステップに進む前に、企業は外国人材と連携して、必要書類の準備から申請、許可まで一連の流れを適切に管理する必要があります。
在留資格変更許可申請の基本的な流れ
特定技能への移行は、出入国在留管理庁に対して在留資格変更許可申請を行うことから始まります。まず、雇用契約を締結した上で、特定技能雇用契約書を作成し、続いて「1号特定技能外国人支援計画」という書類を作成します。申請書類の準備が完了したら、外国人本人または企業の担当者が、必要書類を持って出入国在留管理庁に申請を行います。審査には費用もかかり、期間は通常1か月から3か月程度かかるため、技能実習の在留期間満了前に余裕を持って申請することが重要です。
審査中に在留期間が満了する場合は、特例措置により「特定活動」の在留資格で審査結果が出るまで在留が認められます。許可が下りた場合は、新たな在留カードが交付され、特定技能での就労ができます。不許可の場合は、その理由を確認して再申請を検討するか、一度帰国するなどの他の方法を検討する必要があります。
企業側で準備すべき主要書類
雇用主となる企業や会社が準備すべき書類には様々な種類があり、多岐にわたります。特定技能雇用契約書、雇用条件書、賃金台帳の写し、特定技能所属機関概要書などの他、「1号特定技能外国人支援計画書」の作成も必須です。支援の実施を登録支援機関へ委託する際には、その委託契約書の写しも提出書類に含まれます。財政状況を証明する資料として、直近年度の決算書類や法人税確定申告書の写しも必要です。受け入れ分野によっては、業界特有の許可証や届出書の写しが求められる例もあります。
建設分野では建設業許可証、介護分野では介護保険法に基づく指定書等、事業に関連する許可証の提出が必要になります。必要書類の一覧は、公式サイトで表形式で確認すると分かりやすいでしょう。出入国在留管理庁の公式サイトでは、これらの申請書式を提供しており、ダウンロードして使用できます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能制度における運用改善について
外国人本人が用意する書類と注意点
外国人本人が準備する書類には、パスポートの写し、在留カードの写し、在留資格変更許可申請書、証明写真などの基本書類に加え、技能実習修了証明書や技能実習評価調書が含まれます。日本語能力試験の合格証明書など自身の日本語スキルを証明する書類も必要です。
書類を紛失して「あれはどこに?」と探すことのないよう、ファイルでまとめて管理することがおすすめです。翻訳が必要な場合は、適切な翻訳者に署名をしてもらう必要があります。また、本国の家族状況を証明する書類が求められる場合もあるため、事前に本国から取り寄せておくことが重要です。健康診断書は、指定の期間以内に受診したものが有効です。
人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]
移行時の注意点とよくある課題

技能実習から特定技能への移行では、多くの企業が共通の課題に直面します。特に、手続きの複雑さ、申請タイミングの調整、書類の不備といった点が、つまずきやすいポイントです。それぞれの制度の特徴を理解し、メリットだけでなくデメリットも把握した上で、事前にこれらの注意点を把握し、適切な対策を講じることで、スムーズな移行を実現することができます。
在留期間満了との時期調整
技能実習の在留期間満了前に特定技能への移行手続きを完了させることは、最も重要な注意点の1つです。在留資格変更許可申請の審査には通常1か月から3か月程度の時間を要するため、遅くとも在留期間満了の3か月前には申請を行う必要があります。現在の在留期間を常に把握し、移行を希望する者については早期に手続きを開始することが重要です。
また、技能検定の受検時期や合格発表のタイミングも考慮する必要があります。計画的なスケジュール管理により、外国人材の不安を軽減し、企業の事業継続性も確保することができます。
雇用条件の変更と待遇改善
特定技能への移行に伴い、雇用条件の見直しと改善が必要になる場合があります。特定技能外国人へ支払う報酬額は、同じ業務を担当する日本人従業員と同等か、それ以上の水準であることが求められます。また、特定技能では転職ができるため、優秀な人材を自社で確保し続けるには、より魅力的な雇用条件の提示が重要です。住居の提供、福利厚生の充実、キャリアアップの機会創出など、包括的な待遇改善を検討する必要があります。
支援体制の構築と登録支援機関の活用
企業は、特定技能外国人が日本で安心して働いていけるよう、法律で定められた支援を行う義務があり、そのための適切な支援体制を構築する必要があります。支援内容には、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応など10項目の支援が含まれます。
企業が自社で全ての支援を行うこともできますが、専門的な知識と経験が必要なため、支援業務を外部に委託するという形も考えられます。その委託先として、多様なサービスを提供する登録支援機関を検討することがおすすめです。委託先として信頼できる機関を選ぶには、実績、サポート内容、費用などを多角的に判断することが求められます。
近年、日本の労働市場では人手不足が深刻化しており、特に介護、建設、サービス業などでは慢性的な人材不足が課題となっています。こうした状況の中で注目されているのが、海外からの労働者の活用です。多様な文化や価値観を持つ[…]
移行成功のためのメリットと企業への効果

技能実習から特定技能への移行は、企業にとって多くのメリットをもたらします。即戦力人材の確保、長期雇用の実現、コスト削減など、戦略的な人材活用ができます。これらのメリットを最大化するには、移行プロセスを適切に管理し、外国人材のポテンシャルを十分に活用することが重要です。
即戦力人材として長期雇用の実現
技能実習の課程を終えた外国人材は、日本の職場環境に順応済みであり、一定レベルの技能と日本語能力を持つ即戦力と見なせます。特定技能への移行により、最長5年間(技能実習期間と合わせて最長10年間)の長期雇用ができ、企業は安定した労働力を確保できます。職場の同僚や作業手順に既に慣れ親しんでいるため、生産性の維持・向上が期待できます。
採用コストの削減と効率的な人材確保
新規に外国人材を採用する場合、多くのコストが発生します。技能実習から特定技能への移行では、これらの採用コストを大幅に削減できます。また、既に企業の業務内容や企業文化を理解している人材であるため、採用におけるミスマッチのリスクも低くなります。海外からの新規採用では、入国手続きや住居確保、生活基盤の整備など多くの準備が必要ですが、移行の場合はこれらの手間も不要です。これは大きなメリットと言えます。
技能レベル向上と生産性の最大化
特定技能制度においては、技能実習よりも幅広い業務への従事が認められており、外国人材のスキルアップと生産性向上が期待できます。技能実習で培った基礎技能を土台として、より高度で複雑な業務にチャレンジする機会を提供することで、個人の成長と企業の生産性向上を同時に実現できます。日本人従業員との協働により、多様性のある職場環境を構築でき、新しいアイデアや改善提案も期待できます。
まとめ:移行成功がもたらす価値

技能実習から特定技能への移行は、企業にとって即戦力人材を長期的に確保する絶好の機会です。技能実習2号または3号を良好に修了した外国人材は、既に一定の技能と日本語能力を身につけており、特定技能制度を活用することで最長10年間の雇用ができます。
移行を成功させるには、制度の違いを正確に理解し、要件確認から手続き、支援体制の構築まで計画的に進めることが重要です。特に、在留期間満了との時期調整、適切な書類準備、雇用条件の見直しなどは、企業が特に注意すべきポイントです。登録支援機関の活用により、専門的な支援を効率的に提供することもできます。
移行により企業は採用コストの削減、即戦力人材の確保、生産性の向上といった多くのメリットを享受できます。一方で、外国人材にとっても長期的なキャリア形成と安定した職業生活が実現できるため、双方にとってWin-Winの関係を構築できます。
人手不足が深刻化する中、技能実習修了者の特定技能への移行は、企業の持続的成長を支える重要な人材戦略の1つです。適切な準備と支援により、優秀な外国人材との長期的なパートナーシップを築き、企業の競争力強化を実現してください。
外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材を紹介しており各種メディアでも取り上げられています。